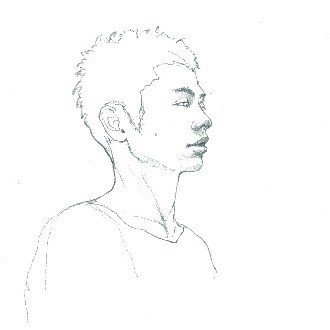今年読んだベスト本9冊
今年読んだ本は全部で70冊(読んだけど記録に留めるに値しないものは記録していない)。書物としての質、個人的に楽しく読めたかどうか、洞察が得られたかという観点から評価をしているのだけど、全てが五つ星だったものだけを紹介する。
(タイトルが英語のものは英語で読んでいます)
Daron Acemoglu & James A. Robinson、''Why Nations Fail''
(邦題:国家はなぜ衰退するのか)
文明が発達し、人間の力が増えた現代において、個人の創意工夫や努力を誘発させる社会機構は強烈な経済成長の武器となるというのが本書の主張(昔は地理的要因のほうが強かったのかもしれない)。どんな人でも頑張れば政治的に強いポジションを得ることができたり、経済的に成功を収められるような社会は強いパフォーマンスを達成する。
社会機構が豊かな国と貧しい国を決めるというのが著者らの主張だった。個別の技術や武力ではなく、インセンティブが最も強いパフォーマンス決定要因になる。著者らの主張に対しては「他の要因もある」との批判もあるが、経済学者らは基本的に物事を捨象して最も強く影響を与える要因だけを取り出す人々なので、それは批判として的を射ていないだろう。(というより、著者らは本書で片っ端から他の論者に喧嘩を売っているので、反論も多かったのなろう)
上野千鶴子、''近代家族の成立と終焉(新版)''
1990年代前半に書かれた論文が大部分を占めているが、その主張は今でもほとんど色あせていない。それは著者の洞察力もさることながら、日本におけるジェンダー非対称が改善してこなかったことにも理由があるのだろう。
特に印象に残っている論文の一つは、「家族、積みすぎた方舟」だった。この論文はアメリカの法学者・政治哲学者であるファインマンの議論を紹介しながら進む。その主張は、フェミニズムのみならず社会運動全体について自分がなんとなく感じていたことを言語化してくれた。
「法は、支配的な文化的、社会的イデオロギーを反映したより大きな規範的体型のもとに編み込まれ、それによって制約を受けている。」・・・したがって法は「社会変革の主要な触媒や文化の変化にとって強力な道具になりえない」(本書77ページ)
だからこそ、社会を変えたいと願うのであれば、単に法律を変えるだけでなく、その法を作り出している社会の規範体型を扱わないといけない。
たとえば、「機会平等」のもとで女性が男性と「公正な競争」に参加することを是とする主張を、ファインマンは「古典的主張」(褒めていない)とよぶ。そもそもの競争のルールが男性を標準として作られているので、そこで競争を勝ち抜こうとする女性は、男性化せざるを得ない。そして、もともと存在している競争社会に潜むジェンダーバイアスを見えなくさせてしまう。
この点については個人的にも思うところがある。多くの企業において、人事制度は、出産や養育・介護を負担せず、ひたすら働く人間を前提につくられている。少なくとも、家庭に時間を割く人々は出世しにくい。そして、そのルールの下で出世した女性は、そのルールを否定せず、男性的な強者の論理を振りかざすようになる。例えば、「女性だからって不平等にさらされたことはない。上に行けないのは努力が足りないからだ」といった風に。なお、これは女性に限らず、「マイノリティ成功者」にはびこる根深い問題だと個人的には思っている。
また、日本男性は世界で三番目に家事に時間を割かない(韓国はワースト1位)。共働き世帯でも同じことが起きている。男性が家事を行う時間が少ない国と、男女の賃金ギャップは明確に相関している。企業の人事制度が変わらず、男性のほうが往々にして多くの賃金を稼ぐ現状においては、「合理的な」意思決定として、家事や介護・養育が女性に寄せされるようになる。
こういった非対称の状況において、法律だけを平等主義にしても、望んだ結果が得られない。変えるべき本丸は法律とは違うところにある。
ただし、ファインマン(と著者)は決して法律を変えるための運動が無駄と言っているわけではない。法自体には象徴的な役割があるし、人々の生活を実際に変えるものでもあるので、そのためだけにでも闘う価値がある。要は、法改正が全ての変化を成就させるものではないと知った上で変化に挑むべきである、ということなのだろう。
もう一つ、本書において最初から最後まで通奏低音として流れているのは家族とは何か、という問いだ。そもそも明治より前においては家の定義は様々だった。父系の長子相続の家族というのは武士階級のみの話で、それ以外の人々は多様な世帯構成のもとに暮らしていた。母系相続や末子相続などもあった(モンゴル帝国も末子相続)。現在の家父長制は日本の伝統でもなんでもなく、国民国家が成立する過程においてつくられた発明品だった。
家父長制は父を絶対的な権力者として家に君臨させる制度であり、それに背く人々を容赦なく罰する。多くのシングルマザーとその子どもが陥っている苦境、婚外子が受けないといけない差別は、この家制度を外れた人間に対する懲罰である。
著者は30年前にこの近代家族は終焉に向かっていると喝破した。当時にはその徴候程度しか見られなかった。しかし今は離婚も増え、婚外子も増えていくなかで、「普通の家族」の輪郭はぼやけてきている。その慧眼には敬服させられる。
映画「万引き家族」は、まさに本書の冒頭の論文で指摘されていた多様な家族観を描いたものだった。この映画のヒットも、そういった背景があってのことなのではないかと個人的には思っている。
Rutger Bregman、"Humankind: A Hopeful History" (おそらく翻訳なし)
性善説についての本は性悪説同様に古今東西ずっと書かれてきている訳だけど、現代の性善説についての本では特に白眉。基本的な主張は次のもの。
・人間は本質的に利他的である。サルと人間の知能はSocial Learning以外では大差がない。人間だけが赤面するが、赤面というのは相手の感情を読み取ろうとする人間の特質から来ている。また、人間は珍しく白目がある動物で、それは視線を把握しやすくしている。
・近年における、人間の利己主義についての研究の多くはでっち上げ。スタンフォードの監獄実験、スタンレー・ミルグラムの電気実験、ジャレドダイアモンドのイースター島の描写などはでっち上げられたもの(ところで著者はジャレド・ダイアモンドに大変手厳しい。彼は地理学者であって歴史学者ではないと何度も書いている)。
・人間が持つエンパシーは実は諸刃の剣でもある。愛情をもたらすオキシトシンは単に愛情を感じさせるだけでなく、仲間でない人間に対する敵対心も駆り立てる(親クマが攻撃的になるのに似ているのか)。虐殺やテロの多くが愛国心や同胞愛などからやってくるのには理由がある。
・現代社会における権力構造は権力者を孤独にさせる。結果として、権力者はごく一部の「身内」を大切にして、その他の人たちを信頼しない施策を打ちがちになる。そしてそれは自己充足的な予言になる。人間は信頼されていないと感じるとパフォーマンスが落ちるし、だからこそ「悪いこと」をしやすくなる。(著者は若干共産主義に好意的なようなのだけど、なぜかマルクスの人間疎外論については言及していない)
・現代社会において人が利他主義を信じない理由の一つが、文脈を完全に排除したニュースの存在にあると著者は指摘している。ニュースは例外的な出来事だけを取り扱うもので、そればかりを見ていると世界はひどい場所だと感じがちだけど、実際はそうでもない(このあたりはFactfulnessでも指摘されている内容だね)
Richard Rumelt 、''Good Strategy / Bad Strategy''(邦題:良い戦略、悪い戦略)
僕の戦略についての考え方をようやく確定させてくれた一冊。
戦略コンセプトは、次の3つを同時に満たすものである。
・マクロ環境変化から生じる機会を捉える
・自分たちのアドバンテージ(強みとはちょっと違う)を活かす
・同業他社の動きを読んで出し抜く
その戦略コンセプトは、組織が現在直面している課題群(企業の場合、基本的に競争に負けること)の根本要因に対する対策となる。このコンセプトを中心として、すべての組織行動・リソース配分を首尾一貫させる。
戦略が間違っていることよりも、無いことのほうが問題である。間違っていたら直せばいいが、無いと何も起きないから。
Peter Frankopan、''The Silk Road'' (邦題:シルクロード全史)
今年読んだ本のなかでも、インサイトとしては極めて高い。特に面白かった内容としては以下。
・グローバリゼーションは今に始まったことではなく、移動手段が限られていた2000年前から世界は一つだった。シルクロードは東西の文明をつなぐ経路であり、プラットフォームだった。だからこそ、この場所に最も古い文明が存在したし(メソポタミア)、ペルシャは世界の文化の中心だった。ギリシャ文明があった時代をとってみても、この時期のペルシャはギリシャより遥かに豊かな国だった。
・ローマ帝国が拡大できたのも、エジプトを押さえることができて、肥沃な土地を手に入れられたから。
・ペルシャで最も評価の高い王であるDarius the Greatからはじまり、大帝国は極めて寛容だった。一番大切なのは安定と安心であり、少数民族や少数派に対しては極めて寛容だった。
・もう一つの大帝国拡大の教訓は、「Expansion without defence was useless」。これは今の仕事でも全く同じことが言えるな。。。
・プラットフォームの地位は商取引における摩擦が小さいほど強くなる。だからこそ、航海技術の発達にともない、ヴァスコ・ダ・ガマが開拓したヨーロッパ➖インド航路は極めて大きな意味を持った。陸路であると、国をまたぐ度に通行手数料が必要であるのに対して、航路ではそれが存在しなくなる。大航海時代に派遣が海に近い国に移っていったのは極めて興味深い。
・場所柄常に戦乱に見舞われたし、技術や製品の他にも、思想、宗教、病原菌などありとあらゆるものがこの地を通って流れていった。例えばインドのMahabharataやRamayanaはギリシャ神話の影響を受けて作られたもの。仏教もエジプトまで流れていった。
・当時の支配者たちにとって、宗教への投資はプロパガンダ投資でもあり、戦略上正しい宗教をピックアップする必要があった。自国の慣習、敵国ではやっている宗教など、判断軸は色々あった。
・ムハンマドは優秀な指導者であるとともに、運が良かった。当時、シルクロードを通じてキリスト教が世界に伝播していたこと(旧約聖書まではイスラム教もキリスト教も同じ&当時でいうとキリスト教徒はヨーロッパよりアジアにもっと多くいた)、ペルシャ帝国が弱りきっていたことなどが大きい。いいタイミングで新興宗教を始めたこと、そして、中心地を戦乱に巻き込まれやすいエルサレムでなく、慣習的に受け入れられやすいメッカに置いたことも賢かった。なお、初期においては、イスラムの主なサポーターはキリスト教徒とユダヤ教徒たちだった。
・スラブ系の人たちの多くが戦乱に巻き込まれ奴隷となった。Slaveの語源はスラブ。
・ギリシャの文明がペルシャの翻訳運動を通じて保存されたおかげで、ルネサンスは起きた。ちなみに、イタリア以外のヨーロッパ主要国は、ルネサンス(=再興)を名乗る歴史的な資格を持っていない。というのも、彼らは歴史的にギリシャ文明との歴史的連続性を持っていないため。
・モンゴル大帝国のもとで物流が更に加速されるとともに、ペストがユーラシア全体にやっていた。そして、そのペストが人口減をもたらし、労働力が減った社会における一般平民の社会的地位向上をもたらし、それがヨーロッパの勃興をもたらした、というのはなんともいえない歴史の不思議を感じさせる。また、モンゴル帝国がもたらした世界の安定は、ヨーロッパの後の拡大の土台となった。
・イギリスが19世紀から強くなった理由は、国が端っこだったため戦乱に巻き込まれにくく、軍事支出を節約できたこと、そのタイミングで人口が大きく増えたこと、勃興していたポルトガルやスペインに対抗するために、ヨーロッパ諸国ではなくオスマン帝国と同盟を結んだこと、など戦略的に優れたいたこと、など。消耗しないポジション取りは秀逸だった。
・いま世界で起きている中東と中央アジアの不安定は、この地域の再興と再安定のためのプロセスであると著者は考えている。そして、おそらく、そのプロセスを主導するのは一帯一路を進めている中国。
宇野重規、''民主主義とはなにか''
読み始めた瞬間に襟を正した。民主主義について考えたい人が日本語の文献にあたるのなら、まずこの本を読めばいいのではないか。過去の歴史から始まり現代にまで射程に収めた民主主義論。
A1:民主主義は多数決だ。より多くの人々が賛成したのだから、反対した人も従ってもらう必要がある
A2:民主主義の下、すべての人は平等だ。多数派によって抑圧されないように、少数派の意見を尊重しなければならない
・・・
A1は正しいが、それはA2の条件を満たす限りにおいてである、というのが答えになるでしょう。
B1:民主主義国家とは、公正な選挙が行われている国を意味する。選挙を通じて国民の代表者を選ぶのが民主主義だ
B2:民主主義とは、自分たちの社会の課題を自分たちで解決していくことだ。選挙だけが民主主義ではない
・・・
近代だけをみればB1はそれなりに正しいのですが、古代以来の民主主義の姿に立ち戻るB2の立場からすれば、どうしても不満が残ります。・・・B1とB2の関係を、対抗的でありつつも相互補完的に捉えるのが、妥当ではないでしょうか。
C1:民主主義とは国の制度のことだ。国民が主権者であり、その国民の意思を政治に適切に反映させる具体的な仕組みが民主主義だ
C2:民主主義とは理念だ。平等な人々がともに生きていく社会をつくっていくための、終わることのない過程が民主主義だ
・・・
C1とC2の両側面があることを前提に、両者を不断に結びつけていくことこそが、重要だといえるでしょう。
"IPCC reasons for concern regarding climate change risks"
Natureに掲載された気候変動についてのサーベイ論文。サーベイ論文を一生懸命読むのが、素人がその領域について知るのに一番いい。
気候変動がもたらす5つのReasons for Concernと、それに加えて気候変動の速度、海水の酸化、水位の上昇がもたらすリスクシナリオについてまとめられている。文字数は小さいものの、8ページの論文で引用文献が104。読んでて分からないコンセプトがある度に英文のWikipediaを訪問してたら、読むのにだいぶ時間がかかったが、これを押さえるだけで、気候変動についての見方が大きく変わった。
Kentaro Toyama、''Geek Heresy: Rescuing Social Change from the Cult of Technology''
我が意を得たり、と思った一冊。テック系起業家たちが「テクノロジーが全てを救う」と意気揚々と途上国にでかけていき大失敗していることから、皆学ぶべきだ。なんで30年くらい同じ失敗が続いているのか僕は不思議に思っているのだけれども。冒頭のビル・ゲイツの引用文が秀逸で、「効率的なオペレーションにテクノロジーを適用したら効率性は向上するが、非効率なオペレーションにテクノロジーを適用したら非効率性が増す」というのは全ての世界に共通のこと。途上国の事業についても、いいソリューションというのは最低限のテクノロジーとアナログな解である程度効果がでるものであり、それを作ってからテクノロジーを実装していくべきである。
Kenneth Pyle、''Japan in the American Century''(邦題:アメリカの世紀と日本)
日本の現代史、特に太平洋戦争から戦後にかけての本については、アメリカ人研究者が書いた本のほうが読み応えがあるものが多い。若干客観的に見られるということもさておき、日本の戦後はアメリカによって形作られたものであるし、資料へのアクセスがしやすいとういのも一因なのだろう。
Japan in the Americal Century(日本語タイトルはいかにも日本での読者向けに翻訳された感がある)は、ジョン・ダワーのEmbracing Defeat(敗北を抱きしめて)に次ぐ、個人的には当たりの本だった。
20世紀の初頭において、日本とアメリカは世界における新興勢力だった。どちらも19世紀から急速に力をつけ、20世紀には欧州列強に並ぶ勢力を持つようになった。19世紀におけるイギリスがそうであったように、海に囲まれ、列強らの争いに巻き込まれにくかったというのも大きい。
新興勢力は人間でいうと思春期の青年に似ている。野望と愛国的熱狂に満ち、自分たちの権勢を世界に広げようと躍起であり、国際秩序を作り変えようと企て、軍備を拡大する。世界最大の経済大国になったアメリカと、日露戦争で勝利した日本はまさにそんな状態だった。アメリカは20世紀はアメリカの世紀になると確信していたし、日本は自分たちが指導民族として欧米からアジアを奪取しようと考えていた。
両者とも欧州のような外交経験に長けているわけではなく、老獪な振る舞いはできなかった。そしてそのことが、日米を避けがたい正面対立に向かわせることにつながる。一部の外交通の山本五十六など、幹部の諫言を聞かずに実施された国際連盟脱退や日独伊三国同盟、そしてそれに続く真珠湾攻撃は、国内で反日感情が高まりつつあった米国を、史上まれに見る無条件降伏を求めさせるに至る。
クラウゼヴィッツが説くように、戦争は外交の延長線上にある手段であり武力なしに解決できない状況を打破するものである。目的はあくまで外交上の目的を達成することであり、無条件降伏を求めることの実利的な意義は極めて低い。無条件降伏が求められたからこそ、日本は徹底抗戦し、沖縄、広島、長崎、その他地域で多くの人々が死ぬことになった。ナチスドイツと違い、日本に対して無条件降伏を求めたことの妥当性は今も論争の対象となってる。
アメリカは無条件降伏を受け入れた日本を徹底的に改造しようとした。日本を占領し、軍備を一生不可能にする憲法を打ち立て、教育システムを入れ替えて民主主義をつくること、財閥解体などに取り組んだ。アメリカのイデオロギーを世界に輸出することを本気で信じていたようにもみえる。
当時のアメリカ人の日本に対する理解は、統治者としては絶望的に低かった。統治は統治対象の性格を理解することなしに成立しない(なお、統治下手は日本もそうだったけれども)。また、民主主義は国民自身の手によって達成されない限り根付かない。後に起きた安保闘争も、政治に影響を及ぼした国民的な異議申し立てではあるが、その目的は反戦であり民主主義ではなかった。結果として、日本の民主主義はアジアのその他の国の民主主義と同様、欧米における民主主義とは別物になっている(良いかどうかはさておき)。
朝鮮戦争が始まり冷戦が始まるなかで、この方針は一気に急転換する。日本を再軍備させるための圧力をかけ、企業への経済・技術支援も惜しまなかった。アメリカのおかげで日本は早くからGATTやOECDに早期に入ることができた。
しかし、日本再軍備の企ては極めて有能な政治家である(と僕は思う)吉田茂によって阻止される。吉田はアメリカに押し付けられた憲法を逆手に取り、また冷戦に突入するアメリカが日本の協力を必要としていた事実を利用し、日本が再軍備することを避け、安全保障をアメリカに負担させ、自国のリソースを経済成長だけに集中させることに成功した。戦後における日本の発展は、アメリカの目論見をうまく利用した吉田茂の功績によるところが大きい。この本を通じて、僕は戦後で最も偉大な日本の政治家は吉田茂であると思うようになった。
アメリカがA級戦犯であった岸信介をサポートし、彼が首相になったところで、国民の戦争へのトラウマは極めて強く、後戻りすることはできなかった。安倍政権による憲法解釈の変更により、近年になってようやく日米同盟はアメリカが半世紀以上前から望んでいたものになった。
20世紀は、多くの国がアメリカの指導原理である自由と民主主義を信奉し、アメリカの同盟国となることで経済・安全保障上の支援を得るというモデルだった。20世紀を通じてアメリカは世界唯一の超大国であり、多くの国が朝貢した。そして、アメリカの指導のもと、国連、世界銀行、IMFなどの国際機関が作られていった。
そのアメリカの時代はもう黄昏を迎えつつある。21世紀においては、まずは中国、そしてインドが世界の大国となる。両者は日米とは違い覇権国家として長い歴史を持っているが、それでも成長における混乱は避けがたいのだろう。世界が一つの方向性に収斂しない可能性が極めて高くなった。そんな中で日本の外交的な立場も大きく変わらざるを得ない。"
(おまけ)
Steve McCurry、''The Iconic Photographs''
展示とかが全部なくなって気が狂いそうになっていた時期に救われた写真集。Steve McCurryは大好きな写真家のひとりで、僕が途上国で撮る写真は間違いなく彼の影響を受けている。撮る相手一人ひとりにきちんと許可を得て、相手の事情をすべてちゃんと聞いた上で撮っている写真たち。巻末には一つ一つの背景が書かれていて、こういう姿勢も含めて勉強になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?