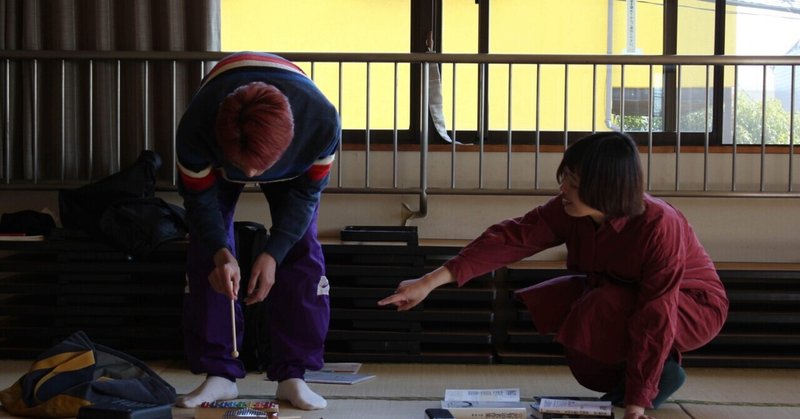
あそぼ!っていえたあの頃
旅するたたき場メンバー、神保治暉です。演劇の演出をメインに、劇作や俳優、作曲などいろいろとやっています。クリエイターの集まり「エリア51」、劇団「じおらま」もやっています。AOI Pro.から映像や音楽などのお仕事をいただいたりもしています。
「旅するたたき場」は自分にとってどんな場所なのか、ここでどんなことをしたいのか、書いていきます。まだ書き途中ですが、気づきがあるたびに書き替えていこうと思っているので、ひとまず公開します。

線がある
子供の頃、ぼくは誰かに遊びをさせるのが好きだった。アニメに登場する魔法の道具を段ボールで似せていくつもつくり、それを友達に渡して鬼ごっこのような遊びをした。ぼくは埼玉県春日部市が出身で、そこは、ずっとそこで暮らしてきた地元の人たちのコミュニティが息づくいい町だった。母と父は、外からやってきた人たちだった。コミュニティというのは、たとえば消防団とか、サッカーや野球のクラブチームだったりした。ぼくはそういったところに混ざっていかなかった。いけなかったのか、母や父がそうさせたのかは、今となってはわからない。
どうやってそこの同級生たちと仲良くなっていったのかは覚えていないけれど、段ボールのおもちゃや、オリジナルのカードゲームなどを手作りしてみんなに渡し、遊んでいたことをよく覚えている。球技やスポーツが苦手で、ドッヂボールをすれば、相手を倒すことができないので最後まで生き残ってしまい、ぼくだけが内野に残ると、敵チームは勝利を確信してボールを片付けにいく。そのうち、ぼくは外交といって、いざというときに自分の一機を味方に譲って外野に出るためにボールを避けて生き残るというやり方を見つけた。すると、ありがたがられたのだった。ぼくは相手にボールを当てられないので、外野に出たら内野に復帰することはほぼない。外野と内野の間には、石灰で白線が引かれていた。さわるとかぶれる線。

線がぼやける
ぼくたちはいつだってこの「線」に翻弄されて生きているのではないだろうか。ヨソとウチの線、国と国の線、自分と他者の線。線は、あった方がいい時と、ないほうがいい時があって、よくわからない。ただ社会に出て、ぼくこの「線」をよりくっきりハッキリと見えるようになっていった。そしてこの線は「見えにくくなること」はあっても「なくなることはない」ことも学んでいった。しかしときに、この「線」はグニャリと形を変える瞬間もあった。それはいつも、とても不思議な体験である。その多くは演劇と呼ばれるものによって生まれる体験であった。舞台と客席の線のことだ。
舞台と客席の間には、非常にハッキリとはよくわからない線がある。ぼくはこの線について考えることで、ヨソとウチの線、国と国の線、自分と他者の線のような「ハッキリとよくわからない、さわるとかぶれる線」とうまく付き合っていく方法を学んでいけるんじゃないかという気がしている。
線がグニャリと形を変えるということは、つまり、線より「こっち」と線より「あっち」が、これまでハッキリしていたはずなのにハッキリしなくなるということだ。あるいは、どこまでが「こっち」でどこまでが「あっち」なのかがわからなくなるということだ。たとえば、舞台を見るとき、はじめは客席側に緊張感があって、舞台と客席の間にはピンと張られた見えない壁のようなものを感じる。が、物語が盛り上がったり、俳優のふとした仕草にスッと惹きつけられると、さっきまでハッキリと「こっち」と「あっち」が分かれていたのが、自分も「あっち」にいるかのような感覚に陥ったり、逆に俳優が「こっち」に来てふれてきているような感覚を体験したりする。
こういうことは、実は実生活でも起こっているとぼくは思う。初めて会った人と、酒を酌み交わしたり共通の趣味の話題で盛り上がったりすることで距離が近く感じられたり、逆に、ちょっとした裏切りによって、これまで寄せていた親近感がなくなり、ピンと張られた壁を感じたりもする。じつは線は、絶え間なく形を変えている。これが時々、本人も気が付かないうちに線の向こうに行っていたり、こっち側に受け入れていたりすることもある。これらを仮に「線がぼやける」現象だと仮定する。ぼくは旅するたたき場で、「線がぼやける」ような体験をつくっていきたい。

別の遊び
ぼくたちは旅をするとき、いつだってヨソモノである。外野の人間である。外野の人間は内野に入ろうとするとき、敵陣の相手を倒さなければならない。ぼくはそうすることができなかった。そんなとき、やっぱりあの「線」が憎かった。線がグニャリと形を変えて、ときに内野に、ときに外野にいるということができたらよかったのに、と思う。それはきっと、ヨソとウチの線、国と国の線、自分と他者の線、あらゆる線において同様のことが言えるのではないか。
線の上をボールが飛び交う。摩擦が起こる。どこまでいっても、線は続いている。どこにいっても、線がある。その線のまわりでは、敵をなぎ倒して勝ち抜く人もいる。よけ続けて生き残る人もいる。一機を引き換えに外野に出ることを選ぶ人もいる。試合が終わると、バドミントンか何かを持った別のグループがやってきて、ドッヂコートだったそこで遊ぶ。すると線がいつの間にかぼやけていて、ドッヂコートは失われ、さっきまで外野と内野で争っていた僕たちは、けろっとした顔で宮沢賢治の「風の又三郎」などを回し読みして遊んでいる。「別の遊び」が「線」をぼやかすのだ。
舞台芸術は、よほど意識しなければ創作過程から「遊び」が失われていく構造を持っているとぼくは感じる。それは私たち一人一人が、この国の教育や社会風潮の中で「遊び」から遠ざけられつつあることと無縁ではないだろう。旅するたたき場のアクティビティには、舞台芸術のあり方そのものに変化をもたらす可能性も秘められている。

暮らす
「遊び」は、もっと掘り下げると、すなわち「暮らし」そのもののことだったりもする。暮らしから自然と生まれた遊びこそが、本当の意味で遊びたりうるのだ。ぼくがつくったカードゲームは、どこぞの営業マンが売り込んできたものとは違って、日常の延長で、ぼくたちならではの遊びから生まれたからこそ、友達はそれを受け入れてくれたのだ。つまり、ぼくたちは旅先で何か発表ごとをしようとなったとき、それは必ず営業マンの持ち込んだ遊びになってしまう。これをぼくたちは、「旅先で暮らしを共にした人たちとつくっていく」ことで本当の遊びの復権を試みる。本当の遊びが実現したとき、そこは劇場や舞台ではなく、もはや広場へと変わる。旅するたたき場がつくる作品は、この「広場」のことなのである。
車ひとつで持ち運べるだけの物を持って行き、そこで暮らし、広場を一緒につくる。そしてその広場を、誰もが遊びに参加できるものにする。
そのためにできることならなんでもする。工作もするし、演奏もするし、朗読も演技もダンスもする。初めてのことにもトライする。これを演劇と呼ぶのか、ワークショップと呼ぶのか、レクチャーパフォーマンス、参加型鑑賞、パフォーミングアーツ、なんと呼ぶのかはわからない。でも、まだこの世界に存在しないアクティビティであることは確かだ。

ひとことめは「あそぼ!」だった
ぼくたちの、「線」を超えてやってきて「線をぼやかそうとトライする姿」を見て、旅先の人々はどんなことを感じるだろう。何度も尋ねる。いつかの未来で、旅するたたき場が来る!じゃあ遊びに行こうかな!と子供や友達を連れてきてくれると嬉しい。
大人も子供も、属性やアイデンティティに関わらず、あそぼ!っていえたあの頃に戻れるような場所にしたい。そこでぼくは、いろんな人と遊んでみたい。
「対話」の重要性があちこちで求められている。でも、どんな対話にもひとことめが必要だ。ぼくが旅するたたき場で投げるひとことめは「あそぼ!」というボールだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
