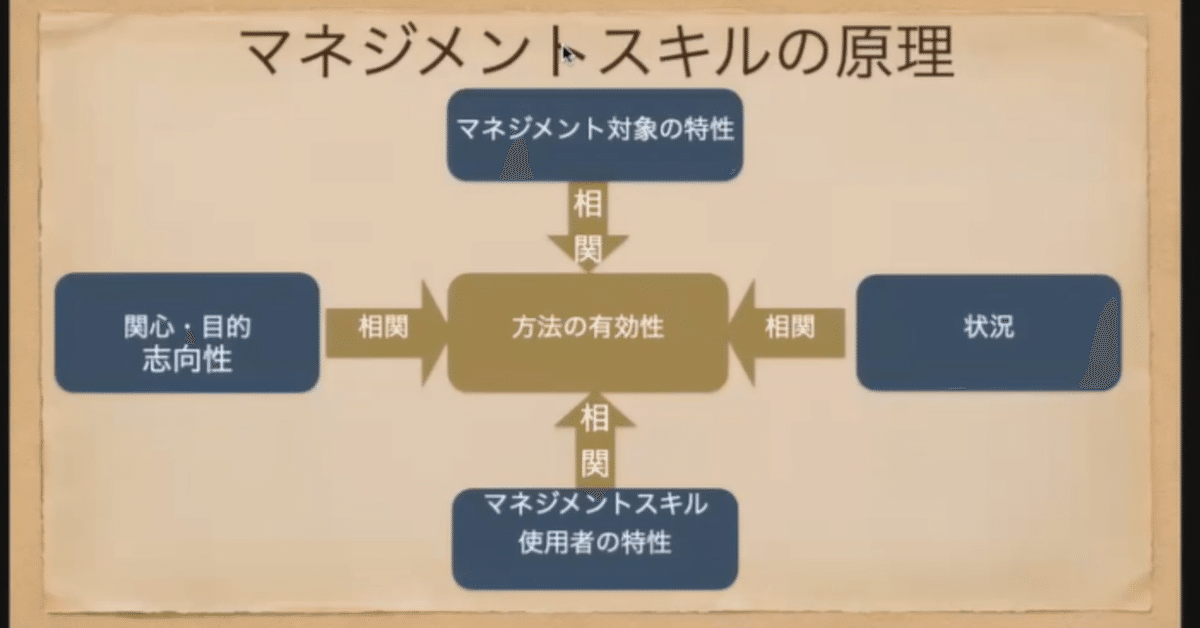
エッセンシャル・マネジメント・スクールと私
2005年 西條剛央著『構造構成主義とは何か ― 次世代人間科学の原理』が北大路書房から出版されました。
2007年 東洋大学での日本心理学会で「構造構成主義とは何か」のワークショップに参加したことで、私は構造構成主義の存在を知りました。信念対立の解消の理論だと理解しました。
2011年 ふんばろう東日本
2015年 いいチームを作りましょう 〜ソーシャルと成果を両立させる金融とボランティア組織の共通本質から学ぶ〜
西條剛央氏と新井和宏氏の出版記念講演会
2017年 エッセンシャル・マネジメント・スクール(オンラインサロン)が開校されました。
2019年 エッセンシャル・マネジメント・スクール0期が開校されました。
リアル会場が主でzoomや録画によるMBAL(movie based active learning)が採用されましたが、始めの頃はハイブリッド・オンラインに様々なトラブルが起こり、手探りで進みましたが、参加者は全てのことにワクワクしていました。
私は臨床検査技師として大きな病院で長く働いていたので心身の健康に関心があり、そのため、組織の健康にも関心を持っています。
その年に1期基礎コースと1期特論(アドバンスコース)が開講され、1期基礎コースで中井信之さんと共にFA(Facilitating Assistant)しました。
また、田口ランディさんのクリエイティブ・ライティングに参加しました。
2020年 2期の時にはハイブリッド・オンライン・インターンとしてチームFの福島毅さんの元で学びながら参加しました。コロナウイルスの蔓延のため2期の途中である2月半ばから参加者は全てzoomからとなり、配信チームのみ会場で配信と収録を行いました。
2020年4月から一部分お手伝いしつつ参加したコースです。
2020.04 本間正人「エッセンシャル・コーチング」
2020.06 EMS3期
2020.10 池田清彦「池田清彦原論」
2020.12 EMS4期
2021.04 ASE(art science entertainment)コース
小橋賢児(DON’T STOP)
澤田智洋(マイノリティ・デザイン)
岡本佳美(オタクと推し)
西村雄一(サッカー審判)
中津川浩章(フリーダ・カーロ)
田上陽一(ANIMENTINE)
2021.06 EMS5期
2021.07 HAPPY BIRTYDAY, EVERYDAY!(宮本亞門)
2021.12 EMS6期
ASEコースで岡本佳美さんがEMSに繰り返し参加する理由は「消化不良と余白」であり「EMSは永遠のβ版」と話されていました。生物が好きな私はいのちに置き換えて考えてしまいますが、生きている個体も永遠のβ版のようと思います。心身は常に変化しています。
地球46億年の歴史の中で最初のいのちらしきものが誕生したのは38億年前、真核細胞の単細胞生物の誕生は21億年前と考えられています。多細胞生物の誕生は10~14億年前とされていますので、多細胞生物になるのには長い時間がかかっています。
多細胞生物では同じ遺伝子を持っている細胞が、卵からの発生の過程でお互いの関係性から遺伝情報の一部のみを働かせて組織のひとつになりいのちを形成しています。
身体の中では様々な組織がお互いにホルモンなどで連絡を取り合って、いのちの維持のために働いています。脳が指令を出しているのは一部です。
一人一人が別々の会社のようなものだ考えてみると、人と人との交流は困難があって当然です。自分のことさえわかっていないかもしれないです。常にチャレンジと失敗と成功を繰り返しているのが生きているという事です。
それぞれの物語を聴き合うのは大切で、「私はあなたの行動をみてこう感じました」と伝える時、「こういう場にしたいと思っています」という理想と現実を添えるといいというのは納得できました。
失敗を話すとみんなも話してくれる、そういう余裕のある場がいいですね。
「自分がわかっている」と思い過ぎずに素直さを保つのも大切だと思いました。焦りがあると思い込みで動いて調和を乱してしまいます。
永遠のβ版であることを思うと、プロセスを共有するのは重要です。不確定のことでもふわーっと伝えてあるとメンバーは勝手に一生懸命考えてくれる。
結論を固定して話し始めない。そうすると創造的な場になり、スパイシーな意見がどんどん出る。
どのような場も自分のバージョンアップのためにあると思えます。
「重力バランスを均す」というのもいのちの自然のように思いました。
ひとりひとりの影響力は惑星の重力のようだと考えると、それぞれの重力を感じ取る力が大切になります。
自分を掌握しているときは素直でごきげんでいられて、そうすると場を掌握できて対立を解消できるように思えます。
また、小さな声には耳を傾けるけれど大声を張り上げると去っていくというのも興味深いです。声ではなく息を伝える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
