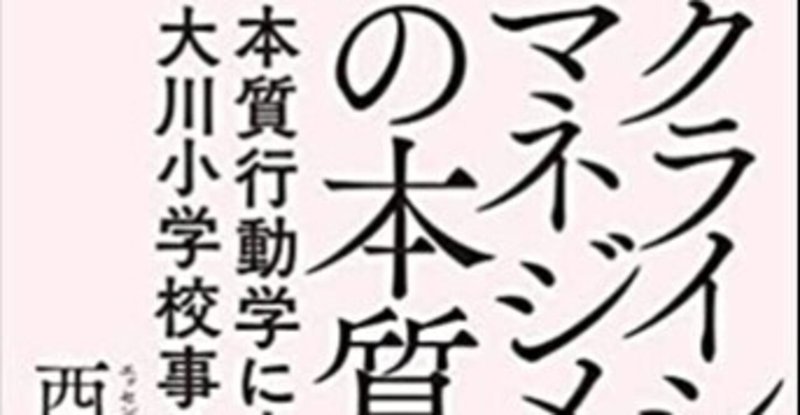
クライシスマネジメントの本質
クライシスマネジメントの本質
本質行動学による3.11大川小学校事故の研究 2021.2 西條剛央
第1部は本質行動学による大川小学校事故の研究―質的研究法SCQRMによる科学的構造化と提言、です。
「大川小学校の研究は、資料、アンケート、インタビュー、現地調査のいずれの観点からも困難を極める状況にあった。
亡くなった人を傷つけないための配慮や忖度から生じた虚偽が含まれていたためである。」と書かれています。
インタビュー結果は全て文字に起こしてテクストデータとしてまとめ、文字数は約35万字ほどとなりました。
SCQRM(構造構成主義的質的研究法)という方法論に依拠して構造化が行なわれました。SCQRMは断片的な情報からでも現象を丁寧に構造化することによって、科学的な研究を可能とする方法です。
63の概念から、52の小カテゴリー[]、10の中カテゴリー《》、5つの大カテゴリー【】が生成されました。
大カテゴリーは14時46分から津波に飲まれる15時35分から36分までの3つのフェイズ、そして【事故の背景要因】と【大川小学校固有の要因】の5つです。
質的研究法に依拠して、この時間にあったことが構造化できました。
第2部は大川小学校事故の「事後対応」マネジメントの研究―遺族たちはなぜ、司法による真相解明を求めざるをえなかったのか、です。
この中でいちばん教頭の無念さが伝わるのは「超正常性バイアス」が成り立っていたことです。
なぜ教頭は山に避難させたいと思っていたにもかかわらず意思決定ができなかったのか?
「正常性バイアス」・・・たぶん大丈夫と思う気持ち
「経験の逆作用」・・・一度も津波被害にあっていない 2度の津波警報の空振り
「逆淘汰」・・・津波への危機感をリアリティをもって感じた人は既に高台に避難していた
「他の脅威への危機感」・・・余震が続き山や道路が危ないと思う気持ち
「同調性バイアス」・・・たぶん大丈夫だと思う気持ちへの同調
この5つを掛け合わせた「超正常性バイアス」といった状態になりました。
また、ここでは「第三者検証委員会」の失敗から司法へ向かわざるを得なかった親たちの気持ちが溢れて何度読んでも泣いてしまいます。
その気持ちの集積により10年をかけてこの本が完成しました。
第3部 クライシスマネジメントの本質―組織、教育、社会の不条理に対抗する本質行動学の視座、です。
・意思が未来を切り拓き、未来が過去を意味づける
・正解がないものに対して、学校はエネルギーを割けていない現状がある
・真のクライシスマネジメントには、空間的、時間的に拡張して考えることができる思考力と想像力が必要となる
防災の目的はハッピーエンドでなければならない
敏郎氏の言葉です。
「恐怖だけではダメだと思うんですよね。津波は怖いけれども、普段は恵みの自然です。だから、それと向き合って、付き合って、津波がこないから大丈夫ではなくて、津波がきても大丈夫という未来まで想定しきる。防災は恐怖ではなく希望であるべきです」
第3部まで読み全体を通して感じたことは「構造構成主義的質的研究法」と西條剛央さんと佐藤敏郎さんの思いが幹となり、関わった多くの方々が根となり土となり、枝となり葉となり日の光となりこの本という実になったと思いました。そしてこの本の内容は、あちこちで読む防災として未来を拓いていくことと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
