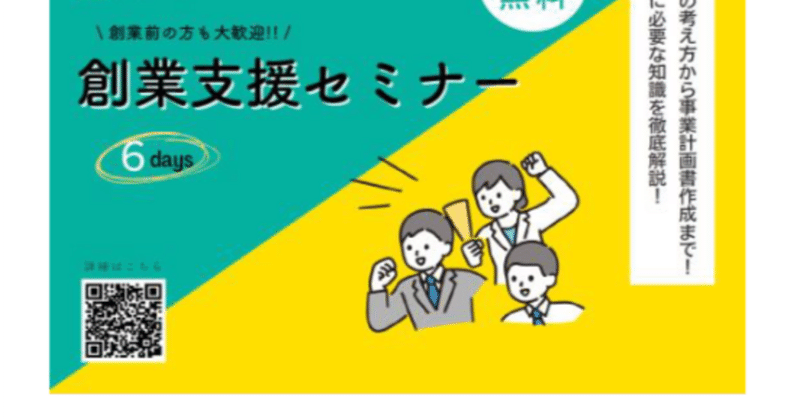
宇治市の産業支援策を視察しました。
京都府宇治市の産業支援策を視察させていただきました。ご協力いただきました宇治市産業振興課、同市議会事務局の関係者のみなさま、心から御礼申し上げます(上の写真は宇治市HPより)。
宇治市の人口は、176210人(5年3月1日)、面積は67.55平方キロメートル。京都駅から宇治駅は、約13キロです。
宇治市は、産業戦略を2019年3月に策定しています。自市の産業戦略を策定するというのは極めてまれですし、産業戦略策定会議を2018年7月から、19年1月まで開催し、会議録を公開しており、これも珍しい。会議録は要旨ですが、かなり議論が広範にわたっており、方向も多岐に及んでいますが(すいません)、大変貴重な資料となっています。そしてこの会議の委員の多くを市外から迎えています。具体的には、同志社大学や龍谷大学の先生や、京都の経済界の方などです。これも珍しい。また、同戦略についても、2022年3月には、改訂版を策定しています。
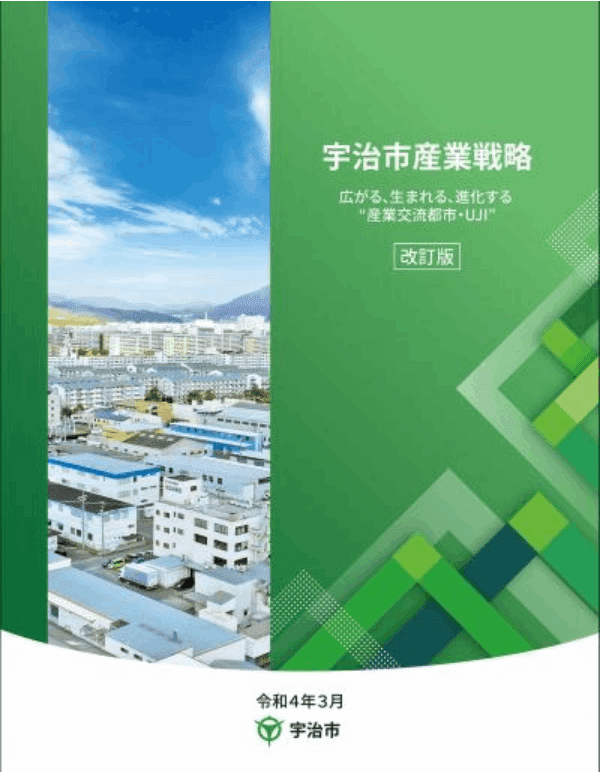
視察の最後に、レクチャーしてくださいましたHさんにうかがったところ、他市をモデルにしておらず、いかに、戦略策定会議の議論を整えていくか、政策に落とし込んでいくか、に注力したとのことです。これを聞いたとき、自らを創り上げていく(クリエイトの)姿勢の力強さを感じ、少々、驚嘆しました。戦略の内発的発展といいましょうか。
それでは、宇治市が取り組んできた産業戦略策定と実際の施策の中身をみてみましょう!
1 産業戦略の特長と策定後のフォローアップ
宇治市では、産業戦略の主要産業について、観光業ではなく、製造業を位置付けました。これは、市内の従業者数(民営)での構成比が20.6%、市内生産額の構成比が20.9%、移出入額額が123億円の移入、でそれぞれ他業種に比べトップであることに注目したからです。
次に、商工会議所との協力です。一般に、商工会議所は、商業会議所ともいわれ、商業者中心の運営のところが多いようですが、製造業への支援を強化しようと、市が一体となって、事業者支援を行う産業交流拠点宇治NEXTを2019年6月に立ち上げました。https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/index-2.html

宇治NEXTは、宇治市産業会館において、市と商工会議所が協同で運営しています。成長支援と産業交流は、3階の市の産業振興課が、中小企業相談は、2階の商工会議所が、それぞれ行っています。1階は、「うじらぼ」というコワーキング、イベント、製品展示のスペースと、展示会、講演会など向けの多目的ホールに分かれています。
宇治NEXTは、企業立地、設備投資、販路開拓などの支援策をまとめた産業支援ガイドブック(20P)をつくり、市内事業者の訪問時に手渡しています。以降、製造業への支援に注力しています。

2 誘致する業種やそのための条件整備等の継続調査の状況
宇治市内では、既存の事業者の中でも、土地が手狭になったりしていましたが、市内に転地、立地する余裕のある土地がありませんでした。
そこで市は、市内安田町に産業用地を確保することにしました。

具体的には、2022年5月に策定した、都市計画マスタープランに、産業立地検討エリアを3か所明記し、そのうち小倉地域を優先的に検討することにしました。将来、13の企業が立地する予定であり、総面積16ヘクタールのうち半分を物流企業が、残り半分を12の製造業企業が進出します。
なお、当該エリアは、農振農用地(第1種農地)であるため、規制解除が必要で、地域未来投資促進法による手続きを経ることによって解除が可能となりました。
3 市内外の企業や事業所、関係団体、人材等との連携強化の状況
まず、製造業支援では、宇治NEXTによる市内企業訪問を精力的に実施しました。産業戦略では、支援者数の目標が150とされています。令和4年には、183社を訪問し、381件の支援を行いました。上記産業支援ガイドブックを手渡し、支援施策を紹介し、業況の確認をします。お困りごとの御用聞きうかがいや関係構築といった狙いもあります。要望などで受けた内容は、資金繰りや補助金に関するものが多かったそうです。市の支援策のブラッシュアップの参考にしたとのことです。
令和4年3月には、東京ビッグサイトで開催された機械要素技術展に、市内製造業6社とともに、宇治NEXTブースを合同出展しました。次回は、6年6月を予定しています。
宇治市の特長ですが、ベンチャー企業育成工場(VIF)というものがあります。Hさんから聞いた時、「えっ?」と驚きましたが、これは、2001年に閉鎖された日産の車体工場の跡地に、民間の事業所用地とともにつくられた市の施設です。

VIFの入居企業は現在8社なのですが、そのうち3社が大学発のベンチャーとなっています。民間では、車載用ペロブスカイト太陽電池をつくっている会社が入居しています(トヨタと協力開発)。入居企業については、京都リサーチパーク(研究開発、ベンチャー支援が主事業、大阪ガス系)に支援を委託し、インキュベーションマネージャーが資金調達や市内外企業とのマッチング支援を行っています。
宇治NEXTによる市内の事業者支援としては、宇治NEXTの1階、産業交流拠点うじらぼで異業種交流会を精力的に実施しています。令和4年度の利用者数は827人で、業種別では、専門技術サービスが28%、年代別では20~30代、職種別では個人事業種が50%とそれぞれトップとなっています。
また、地域の金融機関と連携した事業を展開しています。京都信用金庫とは、京都市内河原町御池にある同金庫の多目的コラボ施設「クエスチョン」と宇治の魅力フェスを共催で、2022年7月に、開催しました。
京都信用保証協会とは、地域クラウド交流会(ちいクラ)を、2017年より、これまで4回開催しています。これはもともと関東でサイボウズという会社が行っていたものですが、近畿では珍しく、経済産業省近畿経済産業局との共催で行っています。第1回のプレゼンテーターは5人で、参加者は227人でした。

同協会とは、円滑な事業承継とアトツギコミュニティ形成などを目指して事業承継支援として、「アトツギらぼ」というセミナーを行っています。通常、事業承継支援というと、現業の方への支援が多いのですが、ここでは、後継者、後継者候補への支援を行っています。令和4年の参加者は39名、業種は製造業、卸小売業、建設業などで、ポジションとしては、後継者として入社済みという方が25名強以上という内訳でした。この取組は、反響が大きく、日経グローカル紙や、2023年度版中小企業白書などにも取り上げられました。

参加者の学びたいこと、知りたいことのアンケートでは、組織活性化やリーダーシップ、財務・税務が上位となっています。参加者が今後、事業承継支援について期待することのアンケートでは、経営力育成の勉強会や一般セミナーが上位になっています。アトツギ支援としては、3年度は、発掘、4年度はコミュ二ティづくり、5年度は組織開発・人材育成(新規事業)、6年度は新規事業というテーマで行っていく流れとなっています。
4 設備投資やDXの推進
改訂版の産業戦略には、「生産性の向上や付加価値の増加に対する支援」を位置付けました。具体的には、4年度補正予算で、先端設備等導入支援補助金を創設し、5年度当初予算にも計上、5年度補正予算でさらに拡充しています。

DXの推進については、事業者ごとにまちまちの状況で、補助金の説明や専門家の派遣を検討しています。デジタル人材の獲得では、京都市内での合同企業説明会にエントリーし、取組んでいます。
ここまでHさんのお話を聞いてきて、タイムアップとなりましたが、Hさん曰く、冒頭に書いた通り、産業戦略策定会議(現在は産業振興会議)の意見をいかに具体化させるかに注力してきた。私が質問した「外部の影響」としては、京都府のバックアップがある、とのこと。2018より府職員の出向を受け入れてできた府とのパイプが大きいとのことでした。都道府県の役割は、各地さまざまですが、京都府の施策には注目したいと思います。
なお、今後は、経済産業省が進める地域一体型オープンファクトリーにもエントリーする計画とのことでした。
「製造業主力」と聞いたときには、ずいぶん時代のはやりと同じではない、と思いました。ただ、上に書いた宇治市の取組は、正攻法をどしどし展開している、そして結果を出している、その秘訣は、産業戦略策定会議であり、現在の産業振興会議だと思うのです。議論の内幕についてはここでは触れませんが、今、見ても、議論をし、それを残し、公開している。そのことが今の政策につながっているのかな、と思います。会議の議論に興味がある方は、下のURLみてみてくださいね!
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/6532.html
,
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
