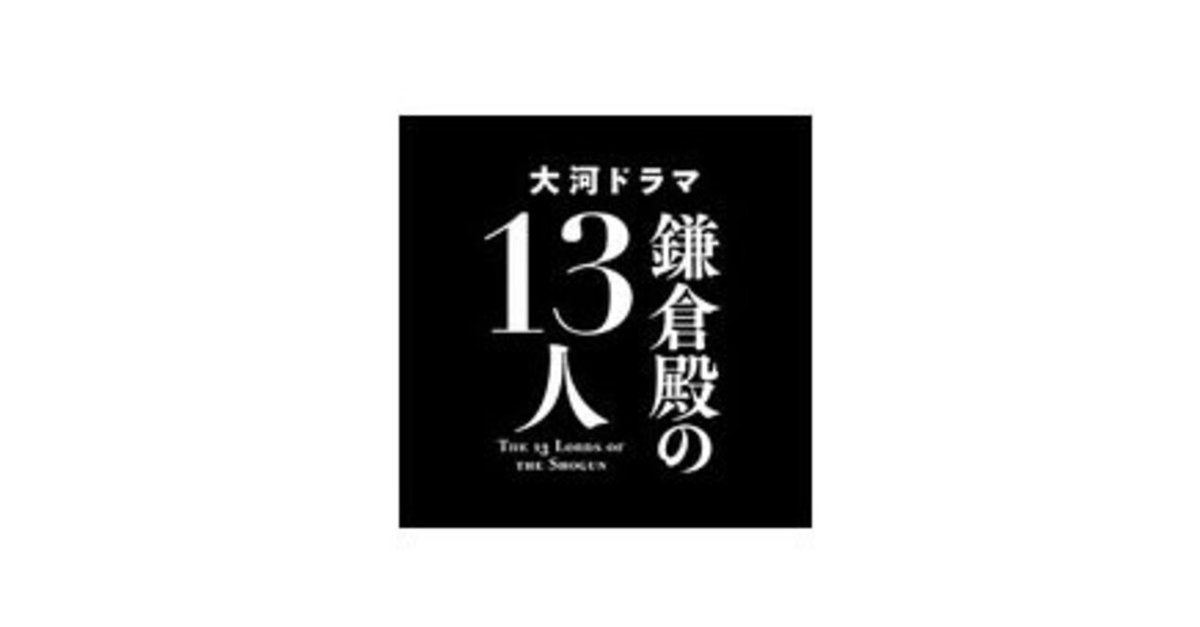
畠山重忠の乱(2/2)乱とその後
■元久2年(1205年)
4月11日 御家人が鎌倉に集まる。
5月 3日 鎌倉に集まった御家人、解散させられる。
6月19日 畠山重忠、菅谷館を出発。鎌倉に向う。
6月20日 畠山重保、稲毛重成に招かれ、鎌倉に着く。
6月21日 北条時政、畠山重忠親子を誅することを謀る。
6月22日 畠山重保、由比ヶ浜で、畠山重忠、二俣川で討たれる。
後の第7代執権・北条政村(北条義時と伊賀の方の子)、生誕。
北条①時政─②義時┬③泰時─時氏┬④経時
│ └⑤時頼─⑧時宗
├重時─⑥長時
└⑦政村
6月23日 稲毛重成と榛谷重朝、三浦義村に討たれる。
7月 8日 北条政子、畠山重忠の所領を分け与える。
閏7月19日 北条時政&牧の方夫妻、追放される。
7月20日 北条義時、第2代執権となる。
7月26日 平賀朝雅、京都で討たれる。
■承元4年(1210年)
5月14日 畠山重忠の後妻(娘?)、畠山重忠旧領を安堵される。
【登場人物(元久2年(1205年)での数え年)】
・北条時政(67) :平氏。鎌倉幕府初代執権。武蔵守代行。
・牧の方 (44) :藤原姓牧氏。北条時政後室(年の差婚)。
・平賀朝雅(23) :武蔵守。京都守護。妻は北条時政&牧の方の娘。
・稲毛重成(不詳):秩父平氏。妻は北条時政の娘。出家して隠居。
・畠山重忠(42) :秩父平氏。妻は北条時政の娘。留守所惣検校職。
・畠山重保(不詳):畠山重忠と北条時政の娘の子。
・北条政子(48) :北条時政の子。
・北条義時(43) :北条時政の子。
北条四郎時政┬長男・三郎宗時 (片岡愛之助):母・伊東祐親の娘
(坂東彌十郎) ├長女・政子=源頼朝室 (小池栄子) :母・伊東祐親の娘
├次男・江間小四郎義時 (小栗旬) :母・伊東祐親の娘
├次女・実衣=阿野全成室(宮澤エマ) :母・伊東祐親の娘
├三女・ちえ=畠山重忠室(福田愛依) :母・足立遠元の娘
├四女・あき=稲毛重成室(尾碕真花) :母・足立遠元の娘
├三男・五郎時連→時房 (瀬戸康史) :母・足立遠元の娘
├五女・きく=平賀朝雅室(八木莉可子):母・牧宗親の妹
└四男・遠江左馬助政範 (中川翼) :母・牧宗親の妹
【畠山重忠の乱(元久2年(1205年)6月22日)の背景 】
①畠山重忠&重保父子 vs 北条時政&牧の方&平賀朝雅の対立
②北条政子&義時姉弟 vs 北条時政&牧の方&平賀朝雅の対立
--------------------------------------------------------------------------------------
1.平賀朝雅の讒訴
■元久2年(1205年)
4月11日 御家人が鎌倉に集まる。
5月 3日 鎌倉に集まった御家人、解散させられる。
6月19日 畠山重忠、菅谷館を出発。鎌倉に向う。
6月20日 畠山重保、稲毛重成に招かれ、鎌倉に着く。
6月21日 北条時政、畠山重忠親子を誅することを謀る。
6月22日 畠山重保、由比ヶ浜、畠山重忠、二俣川で討たれる。
元久2年(1205年)4月11日、「鎌倉に御家人たちが集まり、武装している」と噂が広がり、「戦が始まるのでは?」と鎌倉中が騒然とした。
隠居していた稲毛重成(妻は北条時政の娘。妻が亡くなり、出家して隠居。妻の供養にと川に橋を架けた。その橋の落成式の帰路、源頼朝は落馬して死亡した)が舅・北条時政に呼ばれ、郎党を引き連れて鎌倉へやってきた。「何か起こるのではないか(今度は源実朝が毒を盛られ、落馬して死ぬのか?)」との噂(憶測)が流れたが、何事も無く、集まった御家人は、5月3日には帰国し始めた。
──この「いざ!鎌倉」は何だったのか?
──なぜ隠居している稲毛重成を呼んだのか?
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)4月11日」条
元久二年四月大十一日戊戌。鎌倉中不靜。「近國之輩群參、被整兵具」之由、有其聞。又、稻毛三郎重成入道、日來者蟄居武藏國、近曾依遠州招請、引從類參上。人恠之、旁有説等云々。
(元久2年(1205年)4月11日。鎌倉中が騒々しい。「近国の御家人が群れ集まり、武器を準備している」と噂が流れている。また、稲毛重成は、武蔵国稲毛庄で蟄居していたが、舅・北条時政に呼ばれて、従者を連れて参上した。人々は、これを怪しみ、噂が広まった。)
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)5月3日」条
元久二年五月小三日庚申。世上物忩、頗靜謐。群參御家人、依仰、大半及歸國云々。
(元久2年(1205年)5月3日。世間の騒ぎがすっかり静まった。集まって来ていた御家人達は、命令により、大半が帰国したという。)
6月21日、平賀朝雅は、「去年、畠山重保に悪口を言われた」と、牧の方に讒訴した。牧の方は考えた上で、これを夫・北条時政に訴えた。武蔵国を掌握しようとしていた北条時政は、「チャンス到来!」と思い、「既に稲毛重成を通して鎌倉に来るように伝えてある畠山重忠&重保親子を反逆罪で討とう」と考え、北条義時と北条時房に相談すると、「畠山重忠は忠臣であり、謀反など起こすがはずがない。討ったら後悔する」と反対されたので、北条時政はその場を去った。すると、牧の方の兄・牧宗親の子・大岡時親(一説に牧の方は牧宗親の妹ではなく娘で、大岡時親は兄)がやって来て、「存繼母阿黨、爲被處吾於讒者歟」(承諾しなかったのは、「継母(牧の方)は、平賀朝雅の阿党(一味)だ」として、私(牧の方)を讒者(嘘つき)にするためか=私が実母ではなく、継母だから言うことを聞かないのか)と牧の方の言葉を伝えると、北条義時は「此上者、可在賢慮」(この上は、賢慮あるべし=しかたないので、討伐軍を召集しますが、必ず討てる作戦を考えましょう)と答えたという。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)6月21日」条
元久二年六月小廿一日丁未。晴。牧御方、請朝雅(去年爲畠山六郎被惡口)之讒訴、被欝陶之間、「可誅重忠父子」之由、内々有計議。
先遠州被仰此事、於相州并式部丞時房主等。兩客被申云「重忠治承四年以來、專忠直間、右大將軍、依鑒其志給、「可奉護後胤」之旨、被遣慇懃御詞者也。就中雖候于金吾將軍御方、能員合戰之時、參御方抽其忠、是併重御父子礼之故也。(重忠者、遠州聟也。)而今、以何憤可企叛逆哉。若、被弃度々勳功、被加楚忽誅戮者、定可及後悔。糺犯否之眞僞之後、有其沙汰、不可停滯歟」云々。遠州、重不出詞兮、被起座、相州又退出給。
備前守時親、爲牧御方之使、追參相州御亭、申云。「重忠謀叛事、已發覺。仍爲君爲世、漏申事由於遠州之處、今貴殿被申之趣、偏相代重忠、欲被宥彼奸曲。是、存繼母阿黨、爲被處吾於讒者歟」云々。相州、「此上者、可在賢慮」之由、被申之云々。
(元久2年(1205年)6月21日。晴れ。牧の方は、娘婿・平賀朝雅の「去年、畠山重保に悪口を言われた」という讒訴を受けて、悩み、夫・北条時政に「畠山重忠&重保親子を誅殺しよう」と密かに相談した。
北条時政は、まず、北条義時と北条時房にこの事を話して意見を聞いた。2人が言うには「畠山重忠は、治承4年以来の忠臣で、源頼朝はその志を理解し「(源頼家など)私の後胤を守って下さい」と、丁寧な言葉をかけた者である。特に源頼家の味方であるにもかかわらず、(比企能員が北条時政を討とうとした)「比企の乱」では、(比企能員側の源頼家につかず)我々北条氏の味方について忠を示したのは、(北条時政と親子であることの)礼を重んじたからである。(畠山重忠は北条時政の婿である。)なのに今、何を怒って反逆を企てるのか。もし、たびたびの勲功を捨てて、そこつ(粗忽/楚忽)に誅殺すれば、定めし後悔する。事の真偽をきちんと調べた後、沙汰を下しても、停滞とは言えないのではないか」と。北条時政は重ねて言葉を出せず、席を立ち、退出した。
牧宗親の子・大岡時親が、牧の方の使者として、北條義時の屋敷へ追って参じて言った(牧の方の言葉を伝えた)。「畠山重忠の謀反は既に発覚している。それで主君・源頼家や国のために、北条時政に相談したのに、あなたの申されようは、まるで畠山重忠になり代わって謀反をごまかしたいようだ。これは、「継母(牧の方)は、平賀朝雅の阿党(仲間)だ」として、私(牧の方)を讒者(嘘つき)にするためか」と。北条義時は「では、熟慮しましょう」と答えたという。)
2.畠山重保の死(由比ヶ浜)
翌・元久2年(1205年)6月22日早朝、鎌倉は大きな騒ぎとなり、軍兵が謀反人を誅するべく由比ヶ浜へ先を争って走った。同じ秩父氏の稲毛重成に招かれて鎌倉にいた畠山重保も、稲毛重成に「謀反人を誅するべく由比ヶ浜へ」と聞き、郎党3人と共に由比ヶ浜へ駆けつけると、北条時政に命じられた三浦義村(祖父・三浦義明は、畠山重忠に攻められて自害)が、佐久間太郎らに畠山重保を取り囲ませた。自分が謀反人とされていることに気づいた畠山重保は、驚きながらも奮戦したが、多勢(30人)に無勢(4人)で勝ち目は無く、郎党共々誅殺された。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)6月22日」条(前)
元久二年六月小廿二日戊申。快晴。寅尅、鎌倉中驚遽、軍兵竸走、于由比濱之邊。「可被誅謀叛之輩」云々。依之畠山六郎重保。具郎從三人、向其所之間、三浦平六兵衛尉義村、奉仰、以佐久滿太郎等、相圍重保之處、雖諍雌雄。不能破多勢。主從共被誅云々。
(元久2年(1205年)6月21日。晴れ。寅の刻(午前4時頃)、鎌倉中が騒がしくなり、軍兵が由比ヶ浜の辺りに競うように走って行った。「謀反人を誅すべし」と言う。これにより、畠山重保は、3人の従者を連れて、由比ヶ浜へ向かったところ、三浦義村が、北條時政に命じられて、佐久満家盛に畠山重保を取り囲ませたところ、雌雄を争うことになったが、多勢を破ることはできず、(畠山重保は、)従者と共に誅殺されたという。)
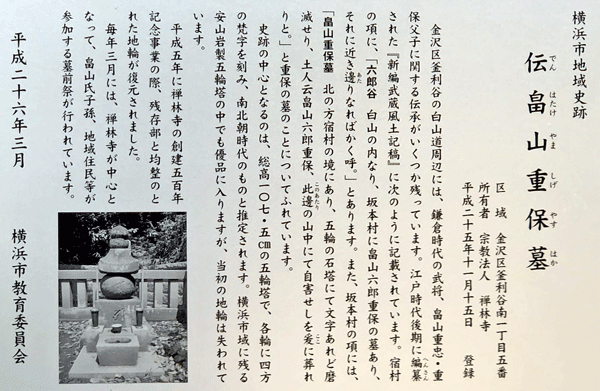
一説に、畠山重保は、鎌倉・由比ヶ浜で討たれたのではなく、「六郎谷」(神奈川県横浜市金沢区釜利谷)で自害したという。「白山道六郎ヶ谷公園」裏に「畠山六郎重保公廟所」がある。
■「伝畠山重保墓」(現地案内板)
金沢区釜利谷の白山道周辺には、鎌倉時代の武将、畠山重忠・重保父子に関する伝承がいくつか残っています。江戸時代後期に編纂された『新編武蔵風土記稿』に次のように記載されています。宿村の項に、「六郎谷 白山の内なり、坂本村に畠山六郎重保の墓あり、それに近き邊りなればかく呼。」とあります。また、坂本村の項には、「畠山重保墓 北の方宿村の境にあり、五輪の石塔にて文字あれど磨滅せり、土人云畠山六郎重保、此邊の山中にて自害せしを爰に葬れりと。」と重保の墓のことについてふれています。
史跡の中心となるのは、総高107.5cmの五輪塔で、各輪に四方の梵字を刻み、南北朝時代のものと推定されます。横浜市域に残る安山岩製五輪塔の中でも優品に入りますが、当初の地輪は失われています。
平成五年に禅林寺の創建五百年記念事業の際、残存部と均整の取れた地輪が復元されました。
毎年三月には、禅林寺が中心となって、畠山氏子孫、地域住民等が参加する墓前祭が行われています。
平成二十六年三月 横浜市教育委員会
※「重保の墓が地域文化財に」
https://www.townnews.co.jp/0110/2013/11/28/214240.html
3.畠山重忠の死(「二俣川の戦い」)
畠山重保の場合は、だまし討ちであり、寝起きである。鎌倉の屋敷から少人数で駆けつけることが想像され、三浦一族だけで30人集めれば討てる。
畠山重忠の場合は、倒幕のために大軍を率いてくるであろうし、畠山重忠は強いので、大軍を用意しなければ対抗できない。実際、北条時政は、山に連なり、野に満ちる程の大軍(1万騎以上)を集めたので、三善善信に「御所の守りが手薄になった」と注意されている。御所に400人の守護兵を残して幕府軍(討伐軍)が出陣した。大手の大将軍は、北条時政の次男・北条義時、挟み撃ちにするための搦め手・関戸(東京都多摩市関戸)の大将軍は、北条時政の三男・北条時房と和田義盛であった。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)6月22日」条(中)
又、「畠山次郎重忠參上」之由、風聞之間、「於路次可誅」之由、有其沙汰、相州已下被進發、軍兵悉以從之。仍少祗候于御所中之輩。于時、問注所入道善信、相談于廣元朝臣云。「朱雀院御時、將門起於東國、雖隔數日之行程、於洛陽猶有如固關之搆。上東、上西兩門(元土門也)始被建扉。矧重忠已莅來近所歟。盍廻用意哉」云々。依之、遠州候御前給、召上四百人之壯士、被固御所之四面。次、軍兵等進發。
大手大將軍、相州也。先陣、葛西兵衛尉淸重。後陣、堺平次兵衛尉常秀、大須賀四郎胤信、國分五郎胤通、相馬五郎義胤、東平太重胤也。其外、足利三郎義氏、小山左衛門尉朝政、三浦兵衛尉義村、同九郎胤義、長沼五郎宗政、結城七郎朝光、宇都宮弥三郎頼綱、筑後左衛門尉知重、安達藤九郎右衛門尉景盛、中條藤右衛門尉家長、同苅田平右衛門尉義季、狩野介入道、宇佐美右衛門尉祐茂、波多野小次郎忠綱、松田次郎有經、土屋弥三郎宗光、河越次郎重時、同三郎重員、江戸太郎忠重、澁河武者所、小野寺太郎秀通、下河邊庄司行平、薗田七郎、并、大井、品河、春日部、潮田、鹿嶋、小栗、行方之輩、兒玉、横山、金子、村山黨者共、皆揚鞭。
關戸大將軍、式部丞時房、和田左衛門尉義盛也。前後軍兵、如雲霞兮、列山滿野。
(また、「畠山重忠が鎌倉へ向かっている」という噂が流れたので、「途中で誅殺しよう」と決まり、北条義時以下が出発し、軍兵は皆従った。それで、御所を守護する兵が少なくなってしまった。その時、問注所の三善善信が、大江広元に相談して言った。「朱雀天皇の御世(930-946)、平将門が関東で反乱「平将門の乱」を起こした時(939年)、関東から京都まで数日かかる程離れているのに、京都ではより固い関をと、上東門と上西門に(元は土門だったが)初めて扉をつけた。畠山重忠はすぐ近い所まで来ているというではないか。何か用意が必要であろう」と。それで北条時政が御前に来て、400人の兵士を集め、御所の四方を守らせた。それから軍隊は出発した。
大手の大将軍は北条義時である。先陣は葛西清重、後陣は堺常秀、大須賀胤信、国分胤通、相馬義胤、東重胤(といった千葉一族)である。他に足利義氏、小山朝政、三浦義村、三浦胤義、長沼宗政、結城朝光、宇都宮頼綱、八田知重、安達景盛、中条家長、苅田義季、狩野介入道、宇佐美祐茂、波多野忠綱、松田有経、土屋宗光、川越重時、川越重員、江戸忠重、渋川武者所、小野寺秀通、下河辺行平、薗田七郎、それに大井氏、品川氏、春日部氏、潮田氏、鹿島氏、小栗氏、行方氏や、児玉党、横山党、金子党、村山党(といった武蔵七党)も皆、鞭を上げて出発しました。
関戸(東京都多摩市関戸)の大将軍は北条時房と和田義盛で、前後の軍兵は、雲霞の如く山に連なり、野に満ちていた。)
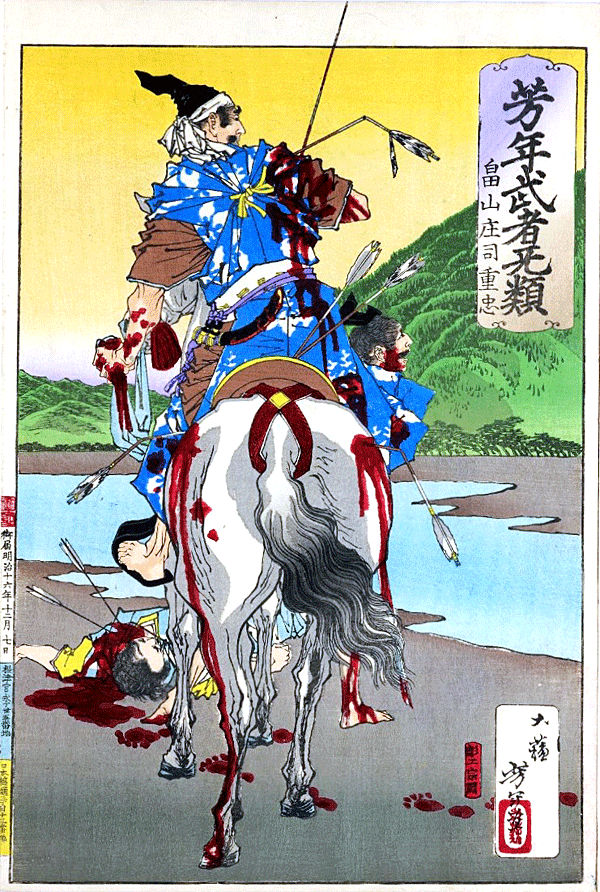
桓武天皇…平武綱┬秩父重綱┬秩父重弘┬畠山重能─畠山重忠──┬畠山重保
│ │ └小山田有重┬稲毛重成 └井田重政
│ │ └榛谷重朝─榛谷重季
│ └河越重隆─河越能隆─河越重頼─河越重房
└河崎基家─河崎基家─渋谷重国─渋谷高重
畠山重能┬畠山重忠【討死・享年42】┬重保【由比ヶ浜で討死・享年不明】
├長野三郎重清:信濃国 ├重秀【自害・享年23】
├渋江六郎重宗:奥州 ├井田重政
├蓬莱三郎経重 ├重慶(恵空→証性。享年77)
└深妙(大友能直正室) ├円耀(別当)
├貞嶽夫人(島津忠久室)
└足利義純室
※畠山重忠の前室は足立遠元の娘で、後室は北条時政の娘である。畠山重忠の死後、重忠旧領と「畠山」の名跡は、通説では、足利義純が未亡人(畠山重忠の後室)と結婚して継承したとするが、『佐野本系図』では、足利義純の妻は、畠山重忠の娘(畠山重保の異母妹)だとする。
足利義純の子・泰国が「畠山」を名乗り、室町幕府の管領家に繋がる。
--------------------------------------------------------------------------------------
畠山重忠は、「鎌倉内に兵起あり」(鎌倉に異変あり。至急参上されたし)という稲毛重成からの手紙を受け取り、6月19日に菅谷館(埼玉県比企郡嵐山町菅谷)を出発した。畠山重忠の弟・長野重清は信濃国、渋江重宗は奥州へ行っており、畠山重忠が率いていたのは、二男・畠山重秀、郎党・本田近常、乳母父・榛沢成清以下134騎に過ぎなかった。
6月22日午の刻(正午頃)、畠山重忠は、武蔵国と相模国の国境付近の二俣川(神奈川県横浜市旭区)付近まで来た時、今朝、長男・畠山重保が殺されたことや、幕府軍(討伐軍)が牧ヶ原(現・万騎が原)に大挙しているとの報を受け、騙されたことを知るが、退くことなく、鶴ヶ峰(神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰)に布陣した。
家臣の本田近常と榛沢成清が「多勢(1万騎以上)に無勢(134騎)。勝つ見込みは無い。ここは一旦、菅谷館に退いて、軍勢を集めてから戦いましょう」と進言したが、畠山重忠は「梶原景時は、立派な武士であったが、深夜に屋敷を抜け出て京都に向かう途中で殺された。そのため、「命を惜しんで逃げたのではないか」「公家との倒幕計画があったのではないか」などと憶測されて名を汚した。これを「後車之誡」(こうしゃのいましめ。(「先に通った車がひっくり返ったのを見て、同じようにひっくり返らないように注意せよ」の意から)先人の失敗に学び、戒めにすること。出典は『漢書』「賈誼伝」。「前車の覆るは後車の戒め」「覆車之戒」とも)にすべきである。今、菅谷館に退く途中で討たれたら、「命を惜しんで逃げたのではないか」「謀反の計画があったのではないか」などと憶測されかねない」と退けた。
そこへ旧友・安達景盛の主従7騎が先陣を切って突入し、激戦の火蓋が切られた。戦いは4時間あまり続いたが、畠山重忠に弓の達人・愛甲季隆の放った矢が当たり、首を取られると、次男・畠山重秀以下が自害したので、戦いは終わった。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)6月22日」条(後)
午尅、各於武藏國二俣河、相逢于重忠。々々去十九日出小衾郡菅屋舘、今着此澤也。折節、舎弟・長野三郎重淸在信濃國、同弟・六郎重宗在奥州、然間、相從之輩、二男・小次郎重秀、郎從・本田次郎近常、榛澤六郎成淸已下百三十四騎。陣于鶴峯之麓。而「重保今朝蒙誅之上、軍兵又襲來」之由、於此所聞之、近常、成淸等云。「如聞者、討手不知幾千万騎。吾衆更難敵件威勢。早退歸于本所、相待討手、可遂合戰」云々。重忠云。「其儀不可然。忘家、忘親者、將軍本意也。随而重保被誅之後、不能顧本所。去正治之比、景時辞一宮舘、於途中伏誅。似惜暫時之命、且又兼、似有陰謀企。可耻賢察歟。尤可存『後車之誡』」云々。
爰襲來軍兵等、各懸意於先陣、欲貽譽於後代。其中、安達藤九郎右衛門尉景盛、引卒野田与一、加世次郎、飽間太郎、鶴見平次、玉村太郎、与藤次等畢。主從七騎進先登。取弓挾鏑。重忠見之、「此金吾者、弓馬放遊舊友也。抜万人赴一陣、何不感之哉。重秀對于彼。可輕命」之由、加下知。仍挑戰及數反。加治次郎宗季已下多以爲重忠被誅。凡弓箭之戰、刀劔之諍、雖移尅、無其勝負之處、及申斜、愛甲三郎季隆之所發箭、中重忠(年四十二)之身。季隆即取彼首、献相州之陣。而之後、小次郎重秀(年廿三。母右衛門尉遠元女)并、郎從等自殺之間、縡屬無爲。
今日未尅、相州室(伊賀守朝光女)男子平産(左京兆是也)。
(午の刻(正午頃)、武蔵国二俣川(神奈川県横浜市旭区)で幕府軍(討伐軍)は畠山重忠と出遭った。畠山重忠は6月19日に武蔵国男衾郡(埼玉県比企郡嵐山町菅谷)の菅谷館を出て、今の沢に着いた。ちょうど、弟の長野重清は信濃国にいて、もう一人の弟の渋江重宗は陸奥国にいた。それで従っているのは、次男・畠山重秀と郎従の本田近常、榛沢成清以下の134騎で、鶴ヶ峰(神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰)の麓に陣を敷いた。ところが、「長男・畠山重保が、今朝、誅殺された上に、軍兵が襲来してきている」と、この場所で聞いた。きました。本田近常と榛沢成清が言った。「聞くところによれば、討手は幾千万騎とも知れない。我々は、威勢に対抗し難い。早く本拠地・菅谷館に引き上げ、討手を待って合戦しましょう」と。重忠が言うには、「それは適切ではない。家を忘れ、親しい者を忘れるのが将軍の本意である。したがって、長男・畠山重保が誅殺された後に、本拠地を顧みることは出来ない。去る正治の頃( 正治2年(1200年)1月)、梶原景時が一宮館(神奈川県高座郡寒川町一之宮)を出て、都へ上がる途中で誅殺されたは、暫しの命を惜しんだかのようであった。かつまた、兼ねてから陰謀を企んでいたかのようであった。そのように推察されるのは恥ずべきだ。まことに「後車之誡」(反面教師)にするべきである」と。
この時、襲来した軍兵たちは、それぞれが一番槍を目指し、その名誉を後代に残そうと願っていた。その中でも安達景盛は、野田与一、加世次郎、飽間太郎、鶴見平次、玉村太郎、与藤次を引き連れ、主従7騎で先陣をきって突進し、弓を取り、鏑矢を取って手に挟んだ。畠山重忠はそれを見て、「この安達景盛は、私の「弓馬の友」である。誰よりも早く、一番に来た。感動せずにはいられない。畠山重秀よ、安達景盛と命賭で戦ってこい」と命じた。それで2人の戦いは何度も行われ、加治宗季以下、多くが畠山重忠に討たれた。弓での戦いも、刀での争いも、時が経っても勝負がつかなかったが、申の斜め(午後の4時半頃)になって、愛甲季隆の射った矢が畠山重忠(年は42歳)の体に当った。愛甲季隆は、畠山重忠の首をとり、北条義時の本陣に届けた。その後、畠山重秀(年は23歳。母は足立遠元の娘〕と郎党らが自殺したので、戦いは終わった。
今日、未の刻(午前10時頃)、北条義時室(伊賀守朝光の娘)が男の子(後の北条政村)を産んだ。
「二俣川古戦場」周辺(鶴ヶ峰)には、「首塚」「硯石水」「六ッ塚」「駕籠塚」「首洗いの井戸」など、畠山重忠関連史跡が多くある。
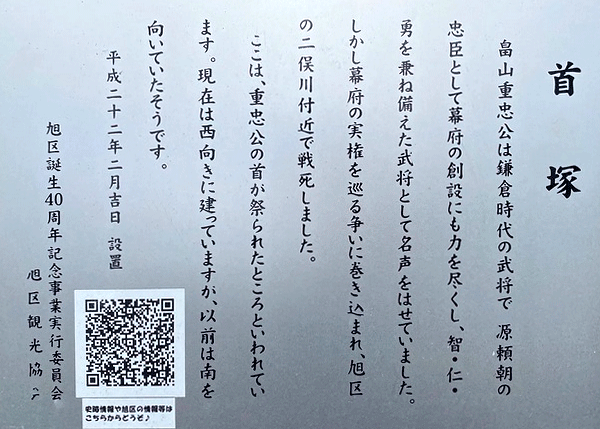
■相良氏の活躍
相良氏は藤原南家乙麻呂流で、本貫地は、遠江国榛原郡相良庄(静岡県牧之原市)である。
「二俣川の戦い」において、相良長頼は、幕府軍(討伐軍)として畠山重忠を攻め、その抜群の戦功により、平家没官領である球磨郡人吉庄(熊本県人吉市)の地頭職に補任された。(多良木庄(上球磨)の相良氏を「上相良氏」、人吉庄(下球磨)の相良氏を「下相良氏」、相良荘に残った相良氏を「遠江相良氏」と呼ぶ。)
この「二俣川の戦い」での相良長頼の活躍は『求麻外史』に詳しい。
■『求麻外史』
元久二年乙丑夏六月、遠江守北条時政、譛畠山次郎重忠、征夷大将軍・源実朝、遣兵討重忠。
二十二日、公、従相模守北条義時等諸将、東下。重忠迎戦於武蔵二俣川。公、先登中槍傷額。神気不撓、猶能健闘。殆危者敷、従兵捉其鎧袖而止之。公、踊躍進。鎧袖中断。遂深入獲首数級。時、人、称之「相良之袖切鎧」(注記略)。重忠及子弟、皆、敗死。
七月二十五日、以軍功、幕府賜下文(北条時政花押)、補人吉荘地頭職(注記略)。
(元久二年(1205年)夏6月、北条時政は、畠山重忠について讒言し、源実朝に畠山重忠討伐軍を派遣させた。
6月22日、相良長頼公は、北条義時など諸将に従い、東国へ下った。畠山重忠は武蔵国の二俣川で幕府軍を迎え、戦った。相良長頼公は、先陣をきって突進し、槍があたって額に傷を負った。しかし、闘志は消えず、なおも良く健闘した。危なっかしいので、従兵が相良長頼公の鎧の袖をつかんで止めたが、相良長頼公は突進し、鎧の袖はちぎれた。遂に敵陣深く入り、数個の首をとった。時に人は、これを「相良の袖切鎧」と呼んだ。畠山重忠とその一族は、皆、敗れ死んだ。
7月25日、相良長頼公は、その軍功により、幕府から(北条時政の花押がある)下知文を賜り、人吉荘の地頭職に補任された。)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/766604/25
・袖切鎧胴絵図
・覚(袖切鎧并綱切太刀由緒書下書)
・吉田幸平「肥後人吉相良家袖切之鎧残欠小札考」
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/7952056
https://chunichisyuppan.shop-pro.jp/?pid=116205916
・「相良長頼の武功」
https://kuma.atukan.com/rekisi/bukou.html
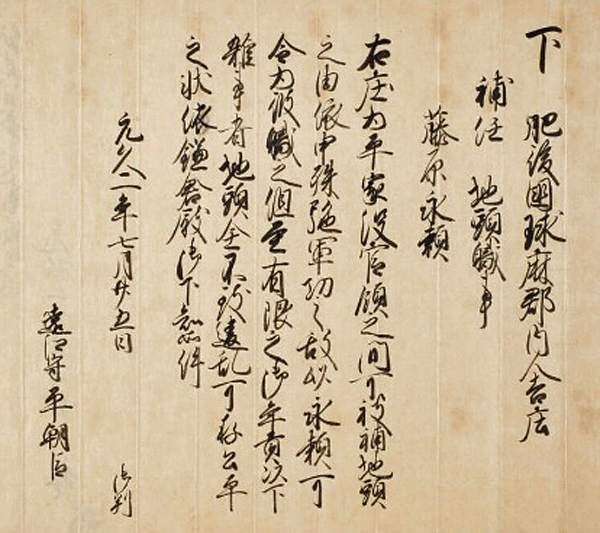
■元久2年(1205年)7月25日付相良永頼宛北条時政単署下知状(案文)
下 肥後国球麻郡内人吉庄
補任 地頭職事
藤原永頼
右庄為平家没官領之間、可被補地頭之由依申、殊施軍功之故、以永頼、可令為彼職之。但至有限之御年貢以下雑事者、地頭全不被違乱、可存公平之状、依鎌倉殿御下知如件。
元久二年七月廿五日 御判
遠江守平朝臣
(下す。 肥後国球磨郡内人吉庄
補任す。 地頭職の事
藤原永頼
右の庄、平家没官領たるの間、地頭に補せらるべきの由申すに依り、殊に軍功を施すの故、永頼を以て、彼の職となさしむべし。但し、有限の御年貢以下雑事に至りては、地頭全く違乱致さず、公平を存ずべきの状、鎌倉殿の御下知に依り、件の如し。
元久2年7月25日 御判
遠江守平朝臣)
https://dcollections.lib.keio.ac.jp/en/sagara/001-004
4.「二俣川の戦い」後
翌6月23日、鎌倉に引き上げてきた北条義時は、合戦の様子を聞いた父・北条時政に対し、「畠山重忠一族は全国に散らばっていて、畠山重忠軍は小勢であり、畠山重忠の謀反は虚報。畠山重忠は無実であった。畠山重忠の首を見ると涙を禁じ得なかった」と述べた。北条時政は黙って引き下がった。
この日の夕方、鎌倉で兄・稲毛重成と弟・榛谷重朝が畠山重忠を陥れた首謀者として三浦義村らによって斬殺された。北条時政がこの2人に罪をなすりつけて事態(無実の者を反逆者として討ったこと)の収拾を図ったのであろう。
小山田別当有重┬稲毛三郎重成┬小沢次郎重正
│ ├女子(宇都宮頼綱室)
│ └女子(綾小路師季(源師季)室)
└榛谷四郎重朝┬榛谷太郎重季
├榛谷次郎秀重
└榛谷三郎実重
※渡辺真治「榛谷重朝の基礎的研究 ―『吾妻鏡』を中心に―」
https://archives.pref.kanagawa.jp/www/contents/1556078596951/simple/kiyou707.pdf
※讃岐国阿野(あや)郡南川東村(香川県仲多度郡まんのう町川東)の讃岐国最大の庄屋・稲毛家の後裔など、現在、香川県には稲毛さんが約400人いるが、これは、稲毛一族の大半が讃岐国阿野郡、鵜足(うた)郡へ落ち延びたからだという。
綾小路師季(源師季)と稲毛重成の娘の間の女の子(2歳)は、北条政子が猶子として、稲毛重成の遺領である武蔵国小沢郷(神奈川県川崎市多摩区)を与えた。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)6月23日」条
元久二年六月小廿三日己酉。晴。未尅、相州已下被歸參于鎌倉。遠州被尋申戰塲事。相州被申云、「重忠弟、親類、大略以在他所。相從于戰塲之者、僅百餘輩也。然者、企謀叛事、已爲虚誕。若依讒訴。逢誅戮歟。太以不便。斬首持來于陣頭、見之、不忘年來合眼之眤、悲涙難禁」云々。遠州無被仰之旨云々。
酉尅、鎌倉中又騒動。是三浦平六兵衛尉義村、重廻思慮、於經師谷口、謀兮討榛谷四郎重朝、同嫡男・太郎重季、次郎季重等也。稻毛入道爲大河戸三郎被誅。子息小澤次郎重政者。宇佐美与一誅之。今度合戰之起。偏在彼重成法師之謀曲。所謂右衛門權佐朝雅。於畠山次郎有遺恨之間。彼一族巧反逆之由。頻依讒申于牧御方(遠州室)。遠州潜被示合此事於稻毛之間。稻毛變親族之好。當時鎌倉中有兵起之由。就消息テ。重忠於途中逢不意之横死。人以莫不悲歎云々。
(元久2年(1205年)6月23日。晴れ。未の刻(午後2時頃)北条義時以下、鎌倉へ帰ってきた。北条時政殿は合戦の事を尋ねた。北条義時が言うには「畠山重忠の弟や親類の大半は他の場所にいた。畠山重忠に従って戦場に来たのは、百余騎であった。であるから、謀反を企てたというのは、既に嘘であったことは明らかである。もしかして、讒訴によって征伐されたのか。非常に気の毒である。陣頭に切り取られた首を持ってきて、これを見た時、年来、目を合わせてきた仲を忘れられず、悲しみの涙を止められなかった」と。北条時政は何も言わなかった。
酉の刻(午後6時頃)、鎌倉で(昨日の由比ヶ浜での騒動に続けて)また騒動があった。三浦義村は重ねて思慮を巡らし、なお良く考え直して、経師ヶ谷(きょうじがやつ。石井山長勝寺の東側の谷)口(神奈川県鎌倉市材木座)で、策を弄して榛谷重朝と長男・重季、次男・秀重を討った。稲毛重成は大河戸三郎行元に討たれ、稲毛重成の子・小沢重政は宇佐美与一が討った。今度の合戦の原因は、全て稲毛重成の謀(はかりごと)だとして処理された。ようするに、平賀朝雅が、(口論したのは畠山重保だが)畠山重忠に恨みがあり、「畠山重忠一族が反逆を企んでいる」と、しきりに牧の方(北条時政の妻)に讒言したので、北条時政は、内緒で娘婿・稲毛重成と示し合わせ、稲毛重成は親戚の好(よしみ)を捨て、「鎌倉内に兵起あり」と手紙を出したので、畠山重忠は(鎌倉への)途中で、思いもよらず死ぬ事になってしまった。(畠山重忠の死を)悲しまない人はいなかったという。)
7月8日、将軍・源実朝に代わり、執権・北条時政が行うはずの畠山一族の遺領の分配を北条政子が行ったと『吾妻鏡』にある。とはいえ、上掲「相良長頼宛下知状」は北条時政が発行している。この時期、北条政子の名で発行された文書は発見されていない。遺領の分配を将軍・源実朝に代わり、北条政子が行い、源実朝の下知として北条時政が発行したのであろう。
■『吾妻鏡』「元久2年(1205年)7月8日」条
元久二年七月大八日癸亥。以畠山次郎重忠餘黨等所領、賜勳功之輩。尼御臺所御計也。將軍家、御幼稚之間、如此云々。
(元久2年(1205年)7月8日。畠山重忠余党の領地を、手柄を立てた人に褒美として与えた。これは、北条政子の裁量である。将軍実朝様が幼稚(子供)の間は、尼將軍が裁量するとのことである。)
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
