
岡本綺堂『修禅寺物語』
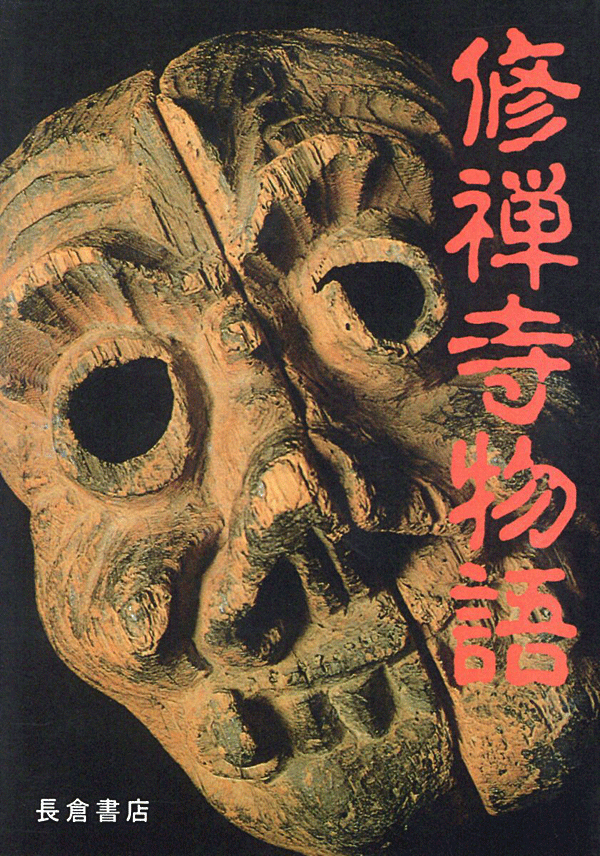
■岡本綺堂『修禅寺物語』
伊豆の修禅寺に頼家の面というあり。作人も知れず。由来もしれず。木彫の仮面にて、年を経たるまま面目分明ならねど、いわゆる古色蒼然たるもの、観来たって一種の詩趣をおぼゆ。当時を追懐してこの稿成る。
岡本綺堂は修禅寺で、鎌倉幕府2代将軍・源頼家の顔とされる割れた面(長倉書店版『修禅寺物語』の表紙の面)を見て、『修禅寺物語』という戯曲(1幕3場)を書いた。1911年(明治44年)1月に『文芸倶楽部』に発表。同年5月、明治座で2世 市川左団次らにより初演。
《登場人物》
面作師(おもてつくりし) 夜叉王(やしゃおう)
夜叉王の娘 桂(かつら)
鎌倉幕府2代将軍 源左金吾(げんざきんご)頼家
《あらすじ》
修禅寺村(現・修善寺)に幽閉された源頼家は、夜叉王に「形見として、自分そっくりな面をうて」と命じるが、いつまでたっても納品されない。しびれを切らした源頼家が夜叉王の家を訪ねると、桂が面を見せた。夜叉王は「死相が出ているので納品できない」と言うが、見事な出来栄えに満足した源頼家は、面を持ち帰り、その夜、夜襲に遭って亡くなった。これを聞いた夜叉王は、面に死相が現れたのは、自分が未熟なためではなく、死相をも表す神の域に達したからだと、喜び、笑った。
江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎は、
「己六才より物の形状を写の癖ありて、半百の此より数々画図を顕すといへども、七十年前描く所は実に取るに足ものなし。七十三才にして稍禽獣虫魚の骨格、草木の出生を悟し得たり。故に八十歳にしては益ゝ進み、九十歳にて猶其奥意を極め、一百歳にして正に神妙ならん歟。百有十歳にしては一点一格にして生るがごとくならん。願くは長寿の君子、予が言の妄ならざるを見たまふべし」
(私は、6才から物の形を写す癖があり、50才の頃より数々の絵を発表したが、70才以前に描いた絵には取るに足ものがない。73才で鳥獣虫魚の骨格や草木の出生を悟り得た。それで、80才にしてますます進み、90才でその奥意を極め、100才になれば、神の域に達しているのではなかろうか。110才になれば、絵の一点一格が生きているように見えるであろう。願わくば長寿の神よ、私の言葉が妄言ではないことを見ていて下さい)
と言っているが、夜叉王の技は神の域に達したようである。
この『修禅寺物語』は、本人そっくりな面がうてても、「死相が出ている」と、割っては、納得がいく面が出来るまで彫り続けるという「職人気質」の話とされるが、エンディングはさらに壮絶である。
夜叉王 幾たび打ち直してもこの面に、死相のありありと見えたるは、われ拙きにあらず。鈍きにあらず。源氏の将軍頼家卿がかく相成るべき御運とは、今という今、はじめて覚った。神ならでは知ろしめされぬ人の運命、まずわが作にあらわれしは、自然の感応、自然の妙、技芸神に入るとはこのことよ。伊豆の夜叉王、われながらあっぱれ天下一じゃのう。(快げに笑う)
かつら (おなじく笑う)わたしもあっぱれお局様じゃ。死んでも思いおくことない。ちっとも早う上様のおあとを慕うて、冥土のおん供……。
夜叉王 やれ、娘。わかき女子が断末魔の面、後の手本に写しておきたい。苦痛を堪えてしばらく待て。春彦、筆と紙を……。
春彦 はっ。
(春彦は細工場に走り入りて、筆と紙などを持ち来たる。夜叉王は筆を執る。)
夜叉王 娘、顔をみせい。
かつら あい。
(桂は春彦夫婦に扶けられて這いよる。夜叉王は筆を執りて、その顔を模写せんとす。僧は口のうちにて念仏す。)
桂は瀕死の状態であった。源頼家を逃がすために、夜叉王がうった源頼家の面を被って逃げたが、追いつかれて斬られたのだという。
春彦 して、この体は……。
かつら 上様お風呂を召さるる折から、鎌倉勢が不意の夜討ち……。味方は小人数、必死にたたかう。女でこそあれこの桂も、御奉公はじめの御奉公納めに、この面をつけてお身がわりと、早速の分別……。月の暗きを幸いに打物とって庭におり立ち、「左金吾頼家これにあり」と、呼ばわり呼ばわり走せ出づれば、むらがる敵は夜目遠目に、「まことの上様ぞ」と心得て、「うち洩らさじ」と追っかくる。
「源頼家が死んだ」と聞いて、悲しむ前に「神の域に達した」と喜んで笑い、瀕死の娘を見て「しっかりしろ」と言って介抱するのではなく「苦痛にもだえる若い女性の顔を描いておこう」と紙と筆を持って来させる夜叉王は、まさに「夜叉(鬼神)の王」であった。
芥川龍之介『地獄変』の良秀は、「地獄変」(「地獄変相図」の略。地獄を描いた絵)の屏風を献上した翌日に自殺したが、この夜叉王は生き続けそうである。

2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で使われた面は、源頼家というより、猿だな。
※岡本綺堂『修禅寺物語』(青空文庫)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/1312_23045.html
ポートレート界隈では、「本人の写真なら、子供でもシャッターを押すだけで撮れる。プロが撮った写真は、『本人以上に本人な写真』だ」と言われている。私も、「過去のプロの絵師は、みんな神の域に達しており、本人以上に本人な肖像画を描ける」と信じ、織田信長の肖像画を見ては「神経質な人であろう」と思う。
そういえば、先日(8月9日)、「熱唱!ミリオンシンガー」という物まね番組があった。審査員は5人。「本人と全く同じ」と思えば100点、「本人を超えた」と感じた場合は101点をつけ、合計501点以上取れば100万円もらえるというシステムであった。
──ミリオンシンガー(100万円もらえる素人)は出ないだろうな。
と思った。100点をつければ、プロの歌手に「あなたと同レベルの素人がいます」と宣言することになるし、101点をつけてば、「あなた以上の素人がいます」と宣言することになる。同じ業界にいれば、そのプロの歌手に会うこともあるわけで・・・私が審査員なら100点以上はつけられない。
「物まね」に「歌まね」というジャンルがあってもいいが、普通は振りや歌い方を誇張して笑わせる「お笑い」の1ジャンルであるような気もする。「物まね」を絵にたとえれば、「肖像画」ではなく、「似顔絵」では?
※日テレ「熱唱!ミリオンシンガー」 「本人超え」で賞金100万円に物議 「本家に失礼すぎる」
https://news.yahoo.co.jp/articles/cff856414cd0d91fd55b0149dd0a5523389b4831
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
