
「富士川の戦い」の実際
1.『吾妻鏡』の記述
■『吾妻鏡』治承4年(1180年)10月19日条
治承四年十月小廿日己亥。武衛令到駿河國賀嶋給。又、左少將惟盛、薩摩守忠度、參河守知度等、陣于富士河西岸。
而及半更、武田太郎信義、廻兵畧、潜襲件陣後面之處、所集于富士沼之水鳥等群立、其羽音偏成軍勢之粧。依之、平氏等驚騒。爰、次將・上總介忠淸等相談云。「東國之士卒、悉属前武衛。吾等憖出洛陽、於途中、已難遁圍。速令歸洛、可搆謀於外」云々。羽林已下任其詞、不待天曙、俄以歸洛畢。
治承4年(1180年)10月20日。源頼朝は、駿河国賀島(静岡県富士市加島)に到着した。また、平維盛、平忠度、平知度等は、富士川の西岸に陣を敷いた。
しかし、夜半になって、武田信義が兵略(作戦)をめぐらし、ひそかに平家の陣の背後を襲ったところ、富士沼(浮島沼、浮島が原)に集まっていた水鳥が群れをなして飛び立ち、その羽音は、軍隊の粧(よそおい、様子)にそっくりであった。これにより、平家軍は驚き、騒いだ。この時、次将(副沼)・上総忠清(藤原忠清、伊藤忠清とも)などが相談して言った。「東国の兵隊は全て源頼朝に属していおり、我々平家は無理を押して京都を出て、(鎌倉を攻める)途中で既に囲まれて逃げられなくなっている。ここは速やかに京都へ戻り、他の謀(作戦)を考えた方が良い」と。平知盛以下はこの上総忠清の言葉に従い、夜明けを待たずに、すぐに京都へ帰った。
2.公家の日記
(1)公家・九条兼実の日記『玉葉』
■治承4年(1180年)11月5日条
五日癸丑。晴。伝へ聞く。前将軍宗盛、「遷都有るべき」の由、禅門に示す云々。承引せずの間、口論に及び、人を以て耳を驚かす云々。
又、伝へ聞く。追討使等、今日晩景に及び、京に入る。知度、先づ入る。僅に廿余騎。維盛追って入る。又、十騎に過ぎずと云々。
先に去月十六日、駿河国高橋の宿に着く。是れより先、彼の国の目代及び有勢武勇の輩、三千余騎、甲斐の武田城に寄する間、皆悉く伐ち取られ了んぬ。目代以下八十余人、頸を切り、路頭に懸くと云々。
同十七日朝、武田方より使者を以て(消息を相副ふ)維盛館に送る。その状に云はく、「年来見参の志有りと雖も、今に未だその思ひを遂げず、幸に宣旨の使として、御下向あり。須らく参上すべしと雖も、程遠く(一日を隔つと云々)、路峻しく、輙く参り難し。又、渡御煩ひあるべし。仍て浮島原(甲斐と駿河の間の広野と云々)に於て、相互に行き向ひ、見参を遂げんと欲す」と云々。忠清これを見て大に怒り、使者二人頸を切り了んぬ。
同十八日、富士川辺に仮屋を構へ、明暁十九日攻め寄すべき支度なり。而る間、官軍の勢を計る処、彼れ是れ相並び四千余騎、平定陣を作り議定已に了り、各休息の間、官兵の方数百騎、忽に以て降り落ち、敵軍の城に向ひ了んぬ。拘留するに力無く、残る所の勢、僅に一、二千騎に及ばず。武田方、四万余と云々。敵対に及ぶべからざるに依り、竊に以て引き退く。これ則ち忠清の謀略也。維盛に於ては、敢へて引き退くべき心無しと云々。而るに忠清、次第の理を立て、再三教訓し、士卒の輩、多く以て之に同ず。仍て黙止するに能はず。京洛に赴きしより以来、軍兵の気力、併せ以て衰損し、適(たまたま)残る所の輩、過半逐電す。凡そ事の次第、直也事に非(あら)ずと云々。今日勢多に着き、先づ使者(馬允満季)を以て子細を禅門に示す。禅門大に怒りて云はく、「追討使を承りたるの日、命を君に奉り了んぬ。縦ひ骸を敵軍に曝すと雖も豈恥とせん哉。未だ追討使を承りたるの勇士、徒らに帰路に赴く事を聞かず。若し京洛に入れば、誰人か眼を合はすべき哉。不覚の恥を家に貽(のこ)し、尾籠(おこ)の名を世に留むる歟。早く路より趾を暗くすべきなり。更に京に入るべからず」と云々。然れども竊かに洛に入り、検非違使忠綱の宅に寄宿すと云々。知度に於ては、先づ以て洛に入り、禅門の八条家に在りと云々。大略、伝説を以て之を記す。定めて遺漏有る歟。但し、是れ、軍陣に供奉する輩の説也。子細多しと雖も、短毫に及び難きもの也。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/228
(2)公家・吉田経房の日記『吉記』
■治承4年(1180年)11月2日条「追討使帰洛之由風聞事」
追討使の事、閭巷の説縦横す。但し、或る者云はく、権亮(注:平維盛)駿河国に下着の節、一国の勢二千余騎(目代(注:橘遠茂)を棟梁と為す)を以て甲州に寄せしむる処、皆率い入る後、路を塞ぎ、樹下巌腹に歩兵を隠し置き、皆悉く之を射取らしむ。異様の下人少々の外、敢へて帰る者なし。其の後、謀反の輩(頼朝歟、武田歟)牒状を送る。其の状、詳しく聞かず。件の子細糺問の後、首を切らしむ(殺害之条有不甘心之輩等)。其の後、頼朝襲来の由、風聞す。彼等の勢、巨万。追討使の勢、敵対すべからず。仍て引き返さんと欲する間、手越宿において、館失火出で来(扈従の者の中、坂東の輩等、之を放つと云々)、上下魂を失ふ間、或は甲冑を棄て、或は乗馬を知らず、逃げ帰り了んぬ。是れ、則ち、東国の勢、江州より皆悉く付くべき由、兼ねて支度する処、敢へて付かず。或は、その身、参ると雖も、伴類、眷属、猶伴はず。或は形勢に随ひ、逆徒に随ふ等、弥(いよいよ)官軍弱しと見ゆる由、各(おのおの)逐電し、これ残す所、京下りの輩纔(わず)か也。世を以て「逐帰」(注:「退帰」の誤り?)と称す由、古今追討使を遣はす時、未だ此の例を聞かず。尤も悲しむべき事也。但し今度の事、只事に非ず。依て由無く委(くわ)しく記さず。又、定説を知り尋ぬべし。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1236604/82
(3)公家・中山忠親の日記『山槐記』
■治承4年(1180年)11月6日条
或る者云ふ。追討使・右少将維盛朝臣、今暁、旧都六波羅に入る。九月十八日、駿河国に着く。同じき十九日、頼朝の党、不志河(注:富士川)に営し、使を送る。其の状知らず。維盛朝臣、為す所を忠景(注:伊藤忠清)に問ふ。忠景曰く、「兵法、使者を斬らず。然れども、此の条、私合戦の時の事也。今、追討使として返答及ぶべきかな。先づ彼方(かなた)の子細を問ひて首を斬るべし」と。維盛朝臣、此の言に従ひ、痛め問はしむ。使者、云ふ。「軍兵数万有り。敢へて敵対を為すべからず」と。者聞きて此の後、首を斬りて了んぬ。或は、「此の事難し」と云云。「官兵、纔(わず)かに千余騎。更に合戦に為すべからず。兼ねて又、諸国の兵士、内心、皆、頼朝に在り。官兵、互ひに異心を恐れ、暫く逗留せば、後陣を塞ぎ囲まんと欲す」と云々。忠景等、此の事を聞き、戦はんと欲する心無きの間、宿の傍らの池の鳥数万、俄に飛び去る。其の羽音、雷を成す。官兵、皆、軍兵の寄せ来たると疑ひ、夜中に引き退く。上下競ひ走る。宿の座(注:「屋」の誤り)形、中将の雑具等を自焼す。忠度、知度、此の事を知らず。追って退帰す。忠景、伊勢国、京師へ向かひ、維盛朝臣、京に入る。近州野路に着く時、五、六十騎有りと云々。此の事、或は之を感ず。兵法、「引き退く事に随ふ難無し」の故也。或は又、之を謗る。近日、門々戸々虚言甚だ多し。此の事、定めて、少実歟。然れども閭巷の説、聞き随ふに、粗注に及ぶ。後日、頭弁(経房)示送して曰く、「東国追討の事、平中納言(頼盛)、平宰相教盛、下向すべきの由、沙汰有ると雖も、先づ伊勢守清綱、定安、海道より下向すべし」と云々。又、「鎮西の武士、船より遣はすべし」と云々。薩摩守忠度朝臣、参川守知度、筑前守貞俊、大夫尉忠綱を参河国に留め、右少将維盛朝臣、近江国に在るの由、聞こゆる所也。新都、歎息の気あり。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2568337/17
3.『平家物語』の記述
去程に右兵衛佐殿謀反のよし、風聞ありしかば、福原には公卿僉議(くぎやうせんぎ)有て、「今一日も勢(せい)の付かぬさきに、急ぎ討手を下さるべしとて大将軍に小松権亮少将維盛、副将軍には薩摩守忠度、侍大将には上総守忠清を先手として、都合三万余騎、治承四年九月十八日、新都を立って、明日十九日には旧都に著(ちゃく)し、同じき廿日、東国へこそ赴かれけれ。大将軍権亮少将維盛は生年二十三容儀帯佩絵に画くとも筆も及び難し。重代の着背長唐皮といふ鎧をば唐櫃に入れて舁かせらる。路中は赤地の錦の直垂に萌黄威の鎧着て連銭葦毛なる馬に金覆輪の鞍を置いて乗り給へり。副将軍薩摩守忠度は紺地錦の直垂に黒糸威の鎧着て黒き馬の太う逞しきに沃懸地の鞍を置いて乗り給へり。馬鞍鎧甲弓矢太刀刀に至るまで光輝くほどに出で立たれたればめでたかりし見物なり。中にも副将軍薩摩守忠度は年比或る宮腹の女房の許へ通はれけるがある時おはしたりけるにこの女房の局に止事なき女房客人に来たつて小夜も漸う更けゆくまで帰り給はず。忠度軒端に休らひ扇を荒く使はれければかの女房の声と思しくて「野もせにすだく虫の音よ」と優に口遊み給へば扇を使ひ止みてぞ帰られけ。その後またおはしたりける夜いつぞや何とて扇をば使ひ止めしぞやと問はれければいざ かしがましなど聞え候ひしほどにさてこそ扇をば使ひ止みて候ひしかとぞ申されける。その後この女房薩摩守の許へ小袖を一重遣はすとて千里の名残の惜しさに一首の歌を書き添へて送られける。
あづま路の草葉をわけん袖よりもたたぬたもとの露ぞこぼるる
薩摩守の返事に
わかれぢをなにかなげかんこえてゆく関もむかしのあととおもへば
「関も昔の跡」と詠める事は先祖平将軍貞盛将門追討の為に吾妻へ下向したりし事を思ひ出でて詠みたりけるにやいと優しうぞ聞えし。昔は朝敵を平らげんとて外土へ向かふ将軍はまづ参内して節刀を賜はる。宸儀南殿に出御して近衛階下に陣を引き内弁外弁の公卿参列して中儀の節会を行はる。大将軍副将軍各礼儀を正しうしてこれを賜はる承平天慶の蹤跡も年久しうなつて准らへ難しとて今度は讃岐守平正盛が前対馬守源義親追討の為に出雲国へ下向せし例とて鈴ばかり賜はつて皮袋に入れて雑色が首に懸けさせてぞ下られける。古朝敵を滅ぼさんとて都を出づる将軍は三つの存知あり。節刀を賜はる日家を忘れ出づる時妻子を忘れ戦場にして敵に戦ふ時身を忘る。されば今の平氏の大将軍維盛忠度も定めてかやうの事をば存知せられたりけんあはれなりし事共なり。各九重の都を立つて千里の東海へ赴かれける。平らかに帰り上らん事もまことに危ふきなれば或いは野原の露に宿を借り或いは高峰の苔に旅寝をし山を越え河を重ね日数経れば、十月十六日には、駿河国清見関にぞ着き給ふ。都をば三万余騎で出でたれども路次の兵(つわもの)付き副(そい)て、七万余騎とぞ聞へし。前陣(せんぢん)は蒲原富士川に進み、後陣はいまだ手越宇津の屋に支へたり。大将軍権亮少将維盛、侍大将上総守忠清を召して維盛が存知には足柄の山うち越え広みに出でて勝負をせんと逸られけれども上総守申しけるは福原を御立ち候ひし時入道殿仰せには「軍をば忠清に任せさせ給へ」とこそ仰せ候ひつれ伊豆駿河の勢の参るべきだにも未だ見え候はず御方の御勢は七万余騎とは申せども国々の駆武者馬も人も皆疲れ果て候ふ。関東は草も木も皆兵衛佐に従ひ付いて候ふなれば何十万騎か候ふらん。ただ富士川を前に当てて御方の御勢を待たせ給ふべうもや候ふらん。と申しければ力及ばで揺らへたり。さるほどに兵衛佐頼朝鎌倉を立つて足柄の山うち越えて木瀬川にこそ着き給へ 。甲斐信濃の源氏ども馳せ来たつて一つになる駿河国浮島原にて勢揃へあり。都合その勢二十万騎とぞ聞えし。常陸源氏佐竹太郎の雑色の主の使に文持て京へ上りけるを平家の方の侍大将上総守忠清この文を奪ひ取つて見るに女房の許への文なり。苦しかるまじとて取らせけり。「さて、当時鎌倉に源氏の勢はいかほどあるとか聞く」と問ひければ 、「下臈は四五百千までこそ物の数をば知つて候へ。それより上は知らぬ候ふ。四五百千より多いやらう少ないやらうは知り候はず。凡そ八日九日の道にはたと続いて野も山も海も河も武者で候ふ。昨日木瀬川で人の申し候ひつるは源氏の御勢二十万騎とこそ申候ひつれ」と申しければ上総守、あな心憂や、大将軍の御心の延びさせ給ひたるほど口惜しかりける事はなし。今一日も先に討手を下させ給ひたらば大庭兄弟、畠山が一族などか参らで候ふべき。これらだに参り候はば、「伊豆、駿河の勢は皆従ひ付くべかりつるものを」と後悔すれどもかひぞなき。
大将軍維盛、東国の案内者とて長井斎藤別当実盛を召して、「汝程の強弓の精兵、東八箇国にいかほどあるぞ」と問ひ給へば、斎藤別当、嘲笑ひて 「君は実盛を大箭(や)と思し召され候ふにこそ僅かに十三束を仕り候へ。実盛程射候ふ者は八箇国に幾らも候ふ。大箭と申す条者、十五束に劣って引くは候はず。弓の強さも健(したた)かなる者の五、六人して張り候ふ 。かやうの精兵共が射候へば鎧の二、三両は容易(たやすく)かけず射徹(とを)し候ふ。大名と申す条に者は、五百騎に劣って持つは候はず。馬に乗って落つる道を知らず。悪所を馳すれども馬を倒さず。軍は又、親も討たれよ子も討たれよ死ぬれば乗り越へ乗り越へ戦ひ候ふ。西国の軍(いくさ)と申すは、惣(すべ)て其の儀は候はず。親討たれぬれば、引き退き、仏事孝養(けうやう)し忌(い)み明(あ)きて、寄せ子討たれぬれば、其の愁歎(しうたん)とて寄せ候はず。兵糧米、尽きぬれば、春は田作り、秋は刈り収めて寄せ、夏は熱しと厭(いと)ひ、冬は寒しと嫌ひ候ふ。東国の軍は、凡(すべ)て、其の儀は候はず。其の上、甲斐、信濃の源氏等、案内は知りたり。富士の裾より搦手にや廻り候はんずらん。かやうに申せば大将軍の御心を臆させ参らせんとて申すとや思し召され候ふらん。其の儀では候はず。(その故は、今度の軍に命生きて二度都へ参るべしとも存じ候はず。)但し軍は勢の多少にはより申さず。大将軍の謀(はかりごと)によるとこそ申し伝へて候へ 」と申しければ、是れを聞く兵共、皆、ふるひ慄(わなゝ)き敢(あへ)りたり。
去る程に、同じき二十四日の卯の刻、富士川にて源平の矢合せとぞ定めける。二十三日の夜に入って平家の兵ども、源氏の陣を見渡せば、伊豆、駿河の人民、百姓等が、軍に恐れて、或は、野に入り、山に隠れ、或は、舟に取り乗って海河に漂(うか)びたるが、営みの火の見へけるを、「あな夥(おびただ)し」と、「源氏の陣の遠火の多さよ。実に野も山も海も河も皆武者にて有りける。いかがせん」とぞあきれける。
其の夜の夜半計、富士の沼に幾等も有りける水鳥どもが何にかは驚きたりけん、一度にばっと立ちける羽音の雷(いかづち)、大風などの様に聞へければ、平家の兵ども、「源氏の大勢の向かふたるは、昨日、斎藤別当が申しつる様に、甲斐、信濃の源氏等、富士の裾野より搦手へ廻り候ふらん。敵、何十万か有るやらん。取り籠められては叶ふまじ。爰をば落ちて、尾張河洲俣を防げや 」とて、取る物も取り敢へず、「我先に」「我先に」とぞ落ち行きける。余りに周章(あは)て騒いで、弓取る者は矢を知らず、矢取る者は弓を知らず 。我が馬には人に乗り、人の馬には我れ乗り、繋ぎたる馬に騎(の)って馳すれば、株(くひ)を繞(めぐ)る事、限りなし。其の辺近き宿々より遊君遊女ども召し集め、遊び酒盛りしけるが、或は、頭(かしら)を蹴破られ、或は、腰踏み折られて喚(おめ)き叫ぶ事、夥し。
同じき二十四日の卯の刻に、源氏二十万騎、富士川に押し寄せて天も響き大地も𩖢(ゆら)ぐ計りに鬨をぞ三箇度作りける 。平家の方にはしずまり返って音もせず。人を入れて見せければ、「皆、落ちて候」と申す。或は敵の忘れたる鎧取って参る者もあり、或は、平家の捨て置きたる大幕取って帰る者もあり。「凡そ平家の陣には、蠅だにも翔(かけ)り候わず」と申。兵衛佐殿、急ぎ馬より降り、甲を脱ぎ、手水(ちょうず)、鵜飼(うがい)をして王城の方を伏し拝み、「これ、全く頼朝が私の高名に非(あら)ず。偏へに八幡大菩薩の御計らひ也」とぞ宣(のたま)ひける。「軈(やが)て打ち取る所なれば」とて、駿河国をば一条次郎忠頼、遠江国をば安田三郎義定に預けらる。「猶も続いて責むべかりしかども、後ろの覚束なし」とて、駿河国より鎌倉へぞ帰られける。
落首に、
富士川の瀬々の岩こす水よりも はやくも落つる伊勢平氏哉
4.「富士川の戦い」の実際
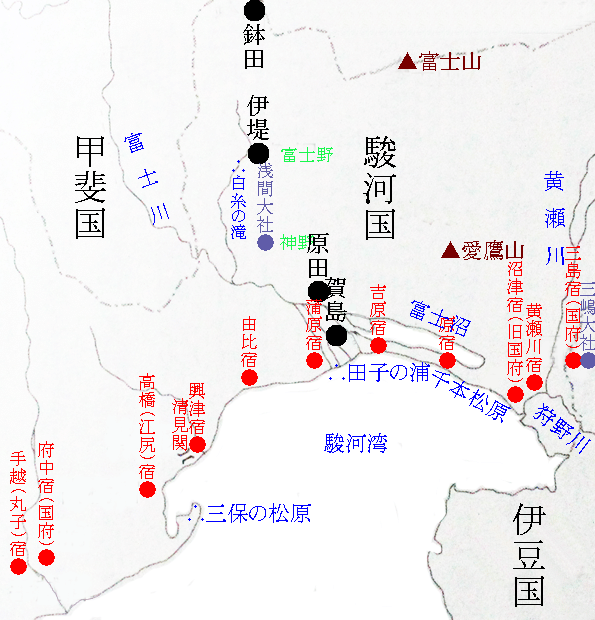
(1)「富士川の戦い」の本質と戦場
「富士川の戦い」は、「南進してきた武田軍(甲斐源氏)と東進してきた平家軍の戦い」であって、「西進してきた源頼朝軍(河内源氏)と平家軍のとの戦い」ではない。
・源頼朝は、北条時政の正室・牧の方の本拠地(静岡県沼津市大岡牧)がある黄瀬川宿(黄瀬川と狩野川の合流点の西部。現在の静岡県沼津市大岡)にいて、武田軍の後方支援をした。また、和田隊は賀島庄(静岡県富士市加島)まで進軍した。
・平維盛は高橋宿(静岡県静岡市清水区高橋)にいて、賀島庄まで進軍したのは先発隊だという。
戦場は「富士川」ではなく、江戸時代の「東海道53次・吉原宿」の北の「富士沼」(「浮島沼」とも。『義経記』では「浮島が原」)の西端である。
■『義経記』
武蔵國足立郡、こかは口に著き給ふ。御曹司の御勢は、八十五騎にぞなりにける。板橋に馳せ付きて、「兵衛佐殿は」と問ひ給へば、「一昨日、是を立たせ給ひて候」と申す。武蔵の國府の六所の町に著いて、「佐殿は」と仰せければ、「一昨日、通らせ給ひて候。相模の平塚に」とぞ申しける。平塚に著いて聞き給へば、「早、足柄を越え給ひぬ」とぞ聞えける。いとど心許なくて、駒を早めて打ち給ひける程に、足柄山打ち越えて、伊豆の國府に著き給ふ。「佐殿は、昨日、此処を立ち給ひて、駿河國千本の松原、浮島が原に」と申しければ、「さては程近し」とて、駒を早めてぞ急がれける。 九郎御曹司、浮島が原に著き給ひ、兵衛佐殿の陣の前、三町許り引退いて陣を取り、暫く息をぞ休められける。
戦場は「浮島が原」(狭義では江戸時代の「東海道53次・原宿」のことだとされるが、一般には沼津宿~原宿~吉原宿~蒲原宿を「浮島が原」という)の西端である。(現在、戦場と富士川は遠く離れているが、当時の富士川は大きく東へ蛇行しており、「戦場は、当時の富士川の河口」と言えなくもない。)
なお、『義経記』の「駿河國千本の松原」は、静岡県沼津市の狩野川河口から、富士市の田子の浦港の間(約10km)の駿河湾岸(正式名称「富士海岸」、通称「千本浜」)に沿って続いている「千本松原」のことである。
【余談】「日本武尊が乗った船が焼津(後の益津)に着岸すると、駿河国造が来て、『沼にいる怪物を倒して欲しい』と嘘を言って安倍の麻機沼に連れ出し、野火で攻めたが、草薙剣で難を逃れ、国造を討ち取った」とされるが、嘘である。天武天皇は、駿河国を駿河国と伊豆国に分け、駿河国の国府を安倍、伊豆国の国府を三島に置いた。分割前の駿河国の国府は沼津であり、「日本武尊が乗った船は浮島が原に着岸した」とする『平家物語』の記述が正しいと思われる。野火で攻められた沼の位置は、駿河国説と相武国(相模国)説があり、日本武尊を野火で攻めたのは相武国造だという。多分、日本武尊が野火で攻められたのは、駿河国と相武国(正確には、当時、相模国の西部に存在した磯長国(師長国))の国境の芦ノ湖であったので、駿河国説と相武国説が生まれたのであろう。日本武尊を野火で攻めたのは、磯長国造であり、日本武尊に討ち取られ、妻・弟橘姫の父・穂積忍山宿禰が磯長国造に就任している。

※地図:『静岡県の歴史散歩』(山川出版社)
▲戦場の詳細な位置は不明だが、合戦関連の伝承地はある。
※「源頼朝の伝説」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kyouiku/c0403/fmervo0000011miw.html
・平家越(富士市新橋町):平家軍が敗走した場所
https://hellonavi.jp/detail/page/detail/1147
・横割八幡宮(富士市横割2丁目):源頼朝が戦勝祈願をした神社
・日吉神社(富士市鮫島):道先案内・鮫島宗家の氏神社
・和田神社(富士市今泉上和田):和田義盛の陣地
・呼子坂(富士市宇東川西町):呼子を吹いて兵を集めた場所
・鎧ヶ淵(富士市原田の鎧ヶ淵親水池公園):源頼朝が身体を洗った淵
■今泉上和田の「和田神社」(和田義盛の陣地)現地案内板
和田神社(義盛さん) 富士市今泉上和田1379
祭神 和田義盛
合祀 大山津見命、建速須佐之男命
創建 年月不明
祭日 毎年5月3日
由緒 治承4年(1180年)10月 富士南麓の加島平野に源平の大合戦が展開されようとしたとき、源氏の大軍は、今泉・原田の高台を中心に依田橋・鈴川・鮫島あたり一帯に陣を布いた。
勢子村(今泉村)付近の守りを頼朝から命じられた和田義盛は、東泉院付近に本陣をおき、南側を流れる川に逆茂木をしかけて厳重に警備した。そのため、のちにその川を和田川と呼び、陣を布いた所を和田城、その付近の土地を「和田」と呼んだ。そして土地の人々は和田義盛をこの土地の守護神として神社を建てた。
(2)平家軍の戦闘形態
平家軍は、
①家人:現地の豪族。前衛部隊。
②駆り武者:強制的に動員された追討部隊。
から成る。
駆り武者(追討軍)は諸国の国衙を通じて召集した臨時戦闘員で、人数が多いが寄せ集めの兵で、(飢饉による兵糧不足もあって)士気が低く、「富士川の戦い」の前に敵前逃亡した兵も、源頼朝側に寝返った兵もいたという。(平家軍は7~8万人であったが、富士川に詰めたのは4000人。それが水鳥の音がした時には1000~2000人に減っていたという。)
「鉢田合戦」で家人が負けた時点で、「富士川の戦い」の勝敗は決まったといえよう。
(3)「鉢田合戦」→「富士川の戦い」
9月21日 追討軍、福原を出発。(『玉葉』)
9月23日 追討軍、京都六波羅に到着。
9月29日 追討軍、京都六波羅を出発・(『玉葉』)
10月13日 追討軍(平維盛)、駿河国手越宿に到着。(『吾妻鏡』)
10月14日 駿河目代と甲斐武田軍の「鉢田合戦」。(『吾妻鏡』)
10月16日 源頼朝、鎌倉を出発。(『吾妻鏡』)
平維盛、高橋宿に到着。(『玉葉』)
10月17日 武田信義、平維盛に書状。平維盛、使者を斬る。(『玉葉』)
10月18日 源頼朝、駿河国黄瀬川宿に到着。(『吾妻鏡』)
追討軍4000余騎、富士川の河辺に仮屋を構える。(『玉葉』)
追討軍、兵が減ったので伊藤忠清の策で退却決定。(『玉葉』)
10月20日 源頼朝、賀島まで進軍。「富士川の戦い」。(『吾妻鏡』)
10月21日 坂東武者たちは源頼朝の上洛を止める。(『吾妻鏡』)
11月5日 使者を送ると、平清盛は怒り、帰洛を不許可。(『玉葉』)
追討軍(平知度20騎、平維盛10騎)、密かに帰洛。(『玉葉』)
11月6日 平維盛、朝、六波羅に入る。(『山槐記』)
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
