
『和田合戦記』を読んでみよう。
この土日は『和田合戦記』を読んでみよう。
読めない字がたくさんあるけど、気にしない。まずはとばし読みして、土日にきちんと翻刻&現代語訳をする。ただし、需要があればだが。時間は貴重だ。需要がなければ、他の事に当てる。
※『和田合戦記』:『吾妻鏡』をもとに「和田合戦」について書かれた軍記物。全11章。全46ページ。
1.序

夫、覆てかくす事なきは天の道也。裁く倦事なきは地の徳なり。故に君は臣を㯢て其賞罸を正くし、臣はきみをうやまいて、其忠節をいたす。是にしたがふ時は、上下和睦し、これにそむくものは、子孫、長久なくす。茲に、実朝の代にあたつて、和田左衛門義盛が一類、めつぼうせし由、来をくはしく尋ぬるに、子息・和田四郎義直、同・六郎義重、同・平太胤長が和泉小次郎親平が謀逆にくみせしゆへなり。
その濫觴をもとむれば、建暦三年如月中旬のころかとに、鎌倉兵乱起るのよし、諸国に風聞するゆへに、近国遠国の御家人等、鎌倉にはせ集る事、いく千万といふかずをしらず。然所に、和田左衛門義盛は、かのしろ上総国伊糺日(純か?)の庄に在けるが、此事を聞よりも汗馬を馳て御所に入、実朝に対面つかまつり、其次而に日比の労功を申し立、其上、子息・義直、義重が御勘気の事を許申しければ、将軍、沙汰をへられず、父が毎度の勲功につのり、罪をゆるされ除けり。義盛、めんぼくをほどこし、御所を退出したりけり。
【現代語訳】それ、覆い隠す事が無いのが(「天網恢恢疎にして漏らさず」。全てはまるっとお見通しなのが)天道である。倦む裁判沙汰が無いのは地(為政者、君主)の徳である。ゆえに、為政者(君主)は家臣を選んで正しく賞や罰を与え、家臣は君主(主君)を敬って忠誠を尽くせば、主従関係が上手くいく。
※「君は国を憂へ、臣は家を忘る。君臣合体、上下和睦するものなり」(『古今著聞集』)
この理に背いた者の子孫は絶える。
源実朝が将軍であった時代、和田義盛の一族が滅亡した。その理由を詳しく尋ねると、和田義盛の子・和田義直、子・和田義重、甥・和田胤長が、泉親平(親衡)の(主君・源実朝への)反逆に与したからだという。
その濫觴(らんしょう。事の始まり)を求めれば、建暦3年(1213年)2月中旬の頃かと思うが(注:反乱の発覚は2月15日)、「鎌倉で兵乱が起こる」と諸国に噂が広まったので、近国、遠国の御家人等が、鎌倉にはせ参じ、その数は幾千万人にのぼったという。そんな折に、和田義盛は、彼の領地・上総国夷隅郡の伊北庄にいたが、この事(2人の息子と1人の甥が反逆罪で逮捕されたこと)を聞き、馬に鞭打って(鎌倉に向かい、3月8日に鎌倉に着くと)大倉御所に入り、源実朝に対面した。その場を借りて、自分の日頃の功績を述べ、次に子・和田義直&義重の赦免を願うと、将軍・源実朝は、審議不要とし(不起訴とし)、父・和田義盛の常日頃の勲功をかんがみて、2人の子の罪を許して釈放した。和田義盛は、面目を保って、大倉御所から退出した。
2.和田胤長、御赦免ならず。
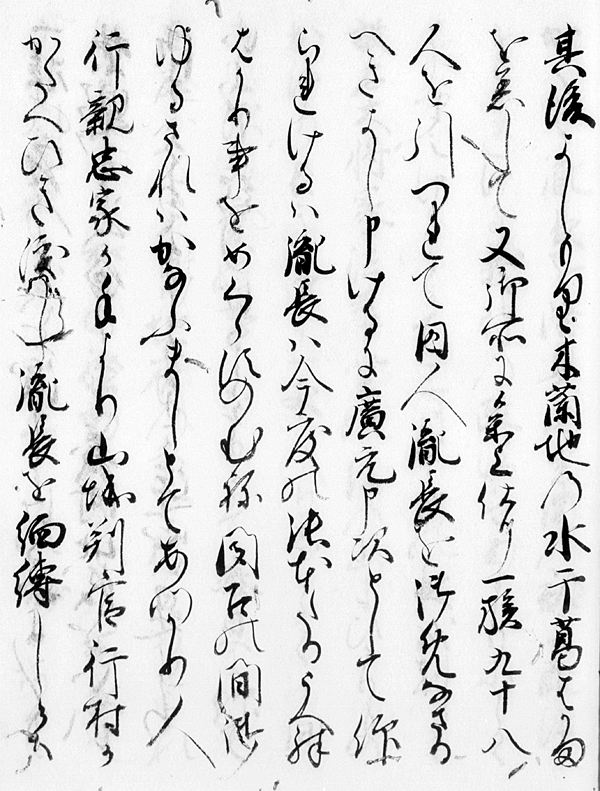
其後よしもり、本蘭地の水干、葛はまを着して、又、御所に而奉つり一族九十八人を引つれて、囚人・胤長を御免なさるべきよし、申しけるに、広元、申し次として、仰られけるは、「胤長は、今度の張本たるうへ、殊はかり事をめぐらすのむね、聞召間、御、ゆるされはかなふまじき」とて、あづかり人・行親、忠家が手より、山城判官行村がかたへひき渡し、胤長を面縛して、一族の座のまへを渡しける。「いよいよ禁遇(あつを)くはへべし」と、義時、此ををいひつたへけり。よしもりが逆心は是よりいよいよ起りけるとぞ。
【現代語訳】その後、和田義盛は、本蘭地の水干に葛袴を着て、(次の日も)また、大倉御所へ、一族98人を連れて行き、まだ釈放されていない甥の和田胤長を釈放して下さい」と申し出ると、大江広元が、(将軍・源実朝からの)申し次ぎとして、「(将軍・源実朝が)仰せられるには、和田胤長は、今回の件の張本人である上に、殊に謀(はかりごと)を廻らしたと聞いているので、許すことはできない」と言い、預かり人の金窪行親と安東忠家から、山城判官・二階堂行村へ渡され、和田胤長を縛り、一速が列座している前を(これ見よがしに)歩かせた。「もっと責めよ」と、北条義時が(将軍・源実朝の言葉を)伝えたので、和田胤長の逆心は、この件により、ますます強まったという。
3.鎌倉に怪事あり。

かくて胤長を陸奥国岩瀬の郡に配流、をくれける。義時の政法は、あまりにからくに■しける。
かくて3月10日の夜、戌刻に、故・右大将家法華堂の後の山にひかりのかげの長き事一丈ばかり、しばらくが間、きし。
次、天変(へん)の事なりとて、泰貞に仰て南庭にて、天曹(ちう)地府の祭をおこなはせられける。是に和田の騒動起るべき前表也。
かくて胤長屋敷地、えがらの前にありけるを、義盛、五条のつぼねに近よりて申し上けるは、一族の領家、故・右大将家のとも地、他人に仰られず、拝領すべきと訴申しければ、則、たまはりてんけり。よしもり。是にて暫時、喜悦のまゆをひらきける。
【現代語訳】こうして和田胤長を陸奥国岩瀬郡に配流された。北条義時の政治手法は(翻刻ミスか、以下意味不明。「情け無用で厳しく裁いた」か?)。
こうして3月10日の夜、午後8時頃、亡き右大将・源頼朝の家(大倉御所)の北の法華堂(頼朝廟)の裏山に光る物(火の玉)、光の尾の長さ約1丈(3m)が、しばらくの間、来た。
次に3月16日、これは天変地異(の予兆)だとして、安倍泰貞に命じて大倉御所の南庭にて、天曹地府祭(てんちゅうちふさい)を執行させた。これは、和田の騒動「和田合戦」が起る前触れであった。
こうして(和田胤長が配流されたので)和田胤長の屋敷は、荏柄天神の前にあったが、和田義盛が、五条局に近づいて、「一族の領家(甥・和田胤長の屋敷)は、亡き右大将・源頼朝家(大倉御所)の東隣にあるが、他人(和田一族以外の人物)に与えず、私に与えて下さい」と訴えたところ、与えられた。それで、和田義盛は、しばらくの間、喜びの眉を開いた(不安や悩みごとが解消して喜んだ。嬉しさのあまり顔がほころんだ)。
【解説】 『吾妻鏡』の
3月10日条に「戌尅、故右大將家法花堂の後山に光物有り。長さ一丈許り。遠近を照らし暫く消え不と云々」(戌の刻(午後8時頃)、亡き源頼朝の霊廟「法華堂」の背後の山に光る物が出現した。長さは1丈(3m)ほどで、遠近を照らし、しばらくはて消えなかったという)、
3月16日条に「天變の事に依て、御所に於て御祈等を行は被る。不動供は隆宣法橋。天曹地府祭は、大夫泰貞南庭に於て之を行う。橘三藏人惟廣御使と爲し、其の所へ向うと云々」(天変地異が起こるのを恐れて、御所で祈祷が行われた。「不動供」(願い事を成就する妨げや困難を焼き尽くしていただいこうと、不動明王像の前で護摩を焚く「護摩供」)は隆宣法橋、「天曹地府祭」は大夫・安倍泰貞が南庭で行った。橘三蔵人惟広が代参としてその場所へ向かったという」とある。
戦死者の霊といえば、無数の源氏蛍に平家蛍である。「源頼朝の霊廟の背後の大きな火の玉」といえば、流れ星であろうが、源頼朝の霊とも考えられる。「この後、和田合戦が起こる」と知らせたのであろうか?
6日後に仏式の不動供と、陰陽道の天曹地府祭が「天変の事によって」行われた。「天曹地府祭(てんちゅうちふさい/てんそうちふさい)」は、陰陽道で、戦死者の冥福を願って冥官に祈祷をささげる儀式で、「六道冥官祭」ともいう。戦死者・・・「泉親衡の乱」の戦死者のことか?
「泉親衡の乱」は、事前に露見したので、戦いといっても、荏柄天神下で和田胤長が暴れたのと、筋替橋で泉親衡が暴れたくらいで、「合戦」というより「逮捕劇」であるが、死者は出ている。

4.和田義盛への使者
■(茲?)所に胤長が屋敷をば相模守申しうけ、前の給人、義盛が代官・久野屋の弥次郎を追出して、金窪兵衛尉行親、忠家に給りけり。義盛、欝陶(うつちう)をふくむといへども、鼠と虎のごとくなれば、子細を申すに及ばず。先の日、胤長を面縛(めんはく)せしより、ことごとく、お仕をやめけるに、件の屋(をく)地を給はりて、いささかうらみを散(さん)をしに、今又何の事ともなくかへられぬる無念さに、いよいよ逆心起りける。
かくてよしもり、年来帰依(きゑ)の僧・尊道房といひけるもの、伊勢の国の者なるが、なにのゆへなく追放しけるこそふしぎなれ。外には追いだすと彼房して内には為祈祷、太神宮へまいらせけるとぞ聞えける。これよりして、世上弥もの忩(さわが)しくぞなりにける。
然処に、義盛が逆心の実否を尋られむがために、宮内兵部少輔公氏を将軍の御使として、かれが宅へつかはされけるに、よしもり、寝殿より侍に来り、造り合のはしなき所をとびこゆるに、義盛が着りたりける烏帽子、公民が前におちたりける。其躰、ひとへに人の首を伐(きる)に似たりける。公氏、おもひけるは、此人、もし逆心を企ば、誅戮(ちうりく)に伏すべき前表なりとおもひける。よしもり、御返事申していふ様は、右大将家の時よりも随分忠節とはげます。然ゆへに、抽賞涯分にこえ遣わるに、逆心の企なしと申しける。いひ畢(をはり)る。保忠、義秀等勇士列座して兵具を調置にける。
【現代語訳】ここに和田胤長の屋敷を北条義時が拝領し、北条義時は、前に和田義盛から与えられた代官・久野谷弥次郎を追い出して、金窪行親と安東忠家に与えた。和田義盛は憤慨したが、和田義盛と北条義時とでは、鼠と虎くらいの差があったので、文句は言えなかった。先日、甥・和田胤長が赦免されず、縛られて以降、ずっと仕事を休んでいたが、和田胤長の屋敷を拝領して、少しだけ恨みが消えたが、今回、何の断りも無く、北条義時の物に変えられた無念さにより、ますます逆心が強まった。
こうして和田義盛は、年来帰依していた僧の尊道房(そんどうぼう)という伊勢国の者を、何の理由も無く追放したのは不思議である。外部の人間には「追い出した」としておいて、実は祈祷をさせるため伊勢神宮へ行かせたらしいと噂になった。この時から、世間はいよいよ物騒がしくなった。
この時、和田義盛の逆心があるかないか確かめるために、宮内公氏を将軍・源実朝の御使者として、和田義盛の屋敷に遣わせると、和田義盛は、寝殿から侍詰所へ来るのに、建物と建物の間の橋が渡されていない場所を飛び越えた。その時、和田義盛が被っていた烏帽子が宮内公氏の前へ落ちた。その様子が、まるで人間の首を伐るのに似ていた。宮内公氏が思ったのは、「これは、この人がもし反逆したら誅殺される予兆である」と。和田義盛の返事は「源頼朝の時から十分に忠誠を尽くしてきた。であるから、褒美は分相応以上にいただいており、反逆の企てなど無い」と言った。この時、古郡保忠や朝比奈義秀らの勇士が列座して、兵具を(身につけてはいないものの)整えて置いていた。
5.使者の報告

公氏、御所にかへりて、事の躰を申しける。そのまはに義時、在鎌倉の御家人を御所に皆々集られける。扨、是日のくれほどに、又、刑部丞忠季を御使として、義盛がもとへつかはさる。申していはく、世をはかるべき其聞えあり。おどろき思召所なり。先蜂起をやめ恩儀を待べしとの事也。よしもり御返奉申していはく、上に対して全なにの恨もなく、相模守のしわざ、傍若無人の振舞也。子細を尋と。
【現代語訳】宮内公氏は、大倉御所に帰って、事の様子を(源実朝に)申し上げた。その間に北条義時は、鎌倉に住んでいる御家人を皆、大倉御所に集めた。さて、この日の夕暮れ時に、(源実朝は)また、若狭忠季(津々見忠季)を使者として、和田義盛のもとに遣わした。使者が言う(源実朝の言葉を伝言する)には、「世を謀る(反乱を起こす)と聞いている。驚いている。先ずは蜂起をやめ、恩儀(鎌倉殿の裁決)を待ちなさい」と。和田義盛が返答するには「鎌倉殿に対しては、全く何の恨みもないが、北条義時の所業は傍若無人(人前を憚らず勝手気ままに振舞うこと)である。(何の説明も無く、和田胤長の屋敷を奪った)子細(理由)を尋ねたい」と。
6.和田義盛挙兵

同き年五月始の比かと、筑後の左衛門尉守が家は義盛がとなりなるが、よしもりが舘に、軍兵、競あつまる音を聞、使をつかはして、事のよしを広元に告ければ、大膳大夫、御所にはしり奉り、朝重の注進を申し上げる。
さて、三浦平六左衛門尉義村、 同弟・胤義等、御所に奉りて申しけるは、われわれども、始めのほどは、義盛と一味して、北門を警固すべきと同心の起請文をかきけれども、我曩祖・三浦の平太郎、八幡殿につき奉り、武衡、家衡を誅せしより恩祿をはむこと人にこへたり。今、親類のすゝめによりて、累代の主君を射たてまつらば、天のせめ、の
【現代語訳】同年(注:建暦3年(1213年))の5月の始めの頃かと思うが(注:5月2日)、左衛門尉筑後守(注:八田知家(右衛門尉、筑後守)か、その子・八田朝重(知重とも。左衛門尉、紀伊守))の屋敷は、和田義盛の屋敷の隣であるが、和田義盛の屋敷に、軍兵が、競い合うように急いぎ集まる音を聞き、使者を遣わして、状況を大江広元に報告したので、大膳大夫・大江広元は、大倉御所へ走って行き、八田朝重の注進(ちゅうしん。事件を急いで目上の人に報告すること)を(源実朝に)申し上げた。
さて、三浦義村、 弟・三浦胤義等が、御所に参上して言うには、「我々は、初めは和田義盛と一味同心して、『(大倉御所の)北門を警固する』という起請文を書いたが、我らの曩祖(始祖)・三浦平太郎為継は、八幡太郎源義家に従ってきた。奥州で清原武衡、家衡を征伐してから、源氏の恩恵を人一倍受けて来た。今、縁故で親戚(和田氏)について、先祖代々の主君(源氏)に矢を射れば(戦を挑めば)、天の責めからは逃れられない。さっさと先約を翻して、北条義時の屋敷に
7.
8.
其中
9.
10.
かりける所に
11.
義時、かり屋を由比の浦の汀にかまへ、死骸どもを実検
代とすべし、すべし。(了)
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
