
『泉親衡物語』を読んでみた。
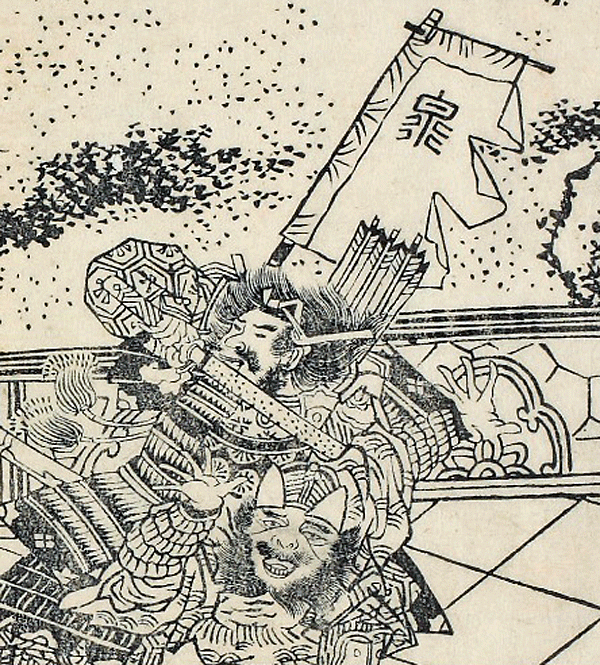
泉氏は、源為公を祖とする信濃源氏で、信濃国小県郡小泉荘(現・長野県上田市)を本拠として、「小泉」ではなく「泉」と名乗り、子孫は、信濃国飯山(現・長野県飯山市)を拠点として栄えた。
源経基┬嫡男・源満仲
└五男・源満快─満国─為満─為公─□─□─□─泉快衡─公衡┬小二郎親衡
(この3代不詳) ├四郎俊衡
├五郎頼衡
└六郎公信
泉二郎公衡─泉小二郎親衡(親平)─泉孫太郎満衡の3代(3人)は実在の人物であるが、信濃源氏の泉氏と同族であるか(泉公衡と源為公が系図でどう繋がるのか)は微妙である。
そもそも泉親衡は、小泉荘ではなく、信濃国東筑摩郡中山村泉(長野県松本市中山の和泉地区)の生まれとされ、現地の泉親衡伝説では「神童」「朝比奈義秀と双肩の怪力」等、調べていくと「足柄山の金太郎」を思い出した。
ということは、昨日の記事に書いた。
★「泉親衡の乱」
学者は、『吾妻鏡』の「信濃國住人泉小次郎親平」(建暦3年2月16日条)に注目し、「泉親衡は信濃国小県郡(上田市)に住んでいた。信濃国は、木曽義仲が支配していたが、討たれると、比企能員が支配したが、討たれた。信濃国の比企能員の家臣だった人を中心に声をかけた鎌倉襲撃が「泉親衡の乱」だ」とするが、私は、「泉親衡は信濃国東筑摩郡(松本市)出身で、相模国(横浜市)に住んでいた。相模国(西相模)の鎌倉幕府に不満を持つ人中心に声をかけた鎌倉襲撃が「泉親衡の乱」だ」と考えている。
『泉親衡物語』(全5巻。全15章)を読んでみた。
『和田合戦記』(全1巻。全11章)に比べるとかなり長い。
「私、読むのは早いので、大丈夫かと」(by 城塚翡翠)
司馬遼太郎氏のような速読は出来ないけどね。泉親衡のような膂力も無い。
──調べていくと「足柄山の金太郎」を思い出した。
ようするに、泉小二郎親衡伝承&伝説と泉小太郎伝説が混同されている。(泉小二郎親衡=金太郎、泉小太郎=龍の子太郎のイメージ。)
A.泉小二郎親衡伝承&伝説の例
※金峯山牛伏寺(長野県松本市内田)
・泉親衡の愛刀(泉親衡が使っていた刀だというが、長さが5尺(150cm)と長い。実際に泉親衡が使っていたのか、泉親衡が奉納したのかは不明であるが、新刀ではなく、古い時代の刀で、「こんなに長くて重い刀は、泉親衡のような力持ちでないと振り回せない」とは思う。)
http://www.gofukuji.or.jp/
B.泉小二郎親衡伝承&伝説と泉小太郎伝説の混同例
※鉢伏山(長野県岡谷市、松本市、岡谷市と境を接している標高1929mの筑摩山地の山)
・泉親衡が「権現人倫」(人の形をした神)として現れ、松本平の湖水を善光寺平に押しやったという。(善光寺平はよく水害にみまわれたが、善光寺自体は断層で押し上げられた扇状地にあったので、水害は受けなかった。)史実は「地頭として治水工事を行った」ということだというが、これは泉小太郎の話だと思うぞ。
※犀乗沢
・泉小二郎親衡は、犀に乗って「地頭として山間部を開拓した」というが、これは、泉小太郎は、母・犀龍に乗って、山岳部を切り開いたという伝説との混同である。
なお、泉小太郎は泉小二郎親衡の兄なのかとも思ったが、時代が大きく異なっていた。
・「泉小太郎」
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kids/menu03/minwat01.html
C.泉小太郎伝説
・泉小太郎伝説①
http://www.anc-tv.ne.jp/~loschild/tishitsu/kotarou1.htm
・泉小太郎伝説②
http://www.anc-tv.ne.jp/~loschild/tishitsu/kotarou2.htm
・泉小太郎伝説③
http://www.anc-tv.ne.jp/~loschild/tishitsu/kotarou3.htm
。泉小太郎伝説④
http://www.anc-tv.ne.jp/~loschild/tishitsu/kotarou4.htm
・泉小太郎伝説⑤
http://www.anc-tv.ne.jp/~loschild/tishitsu/kotarou5.htm
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
