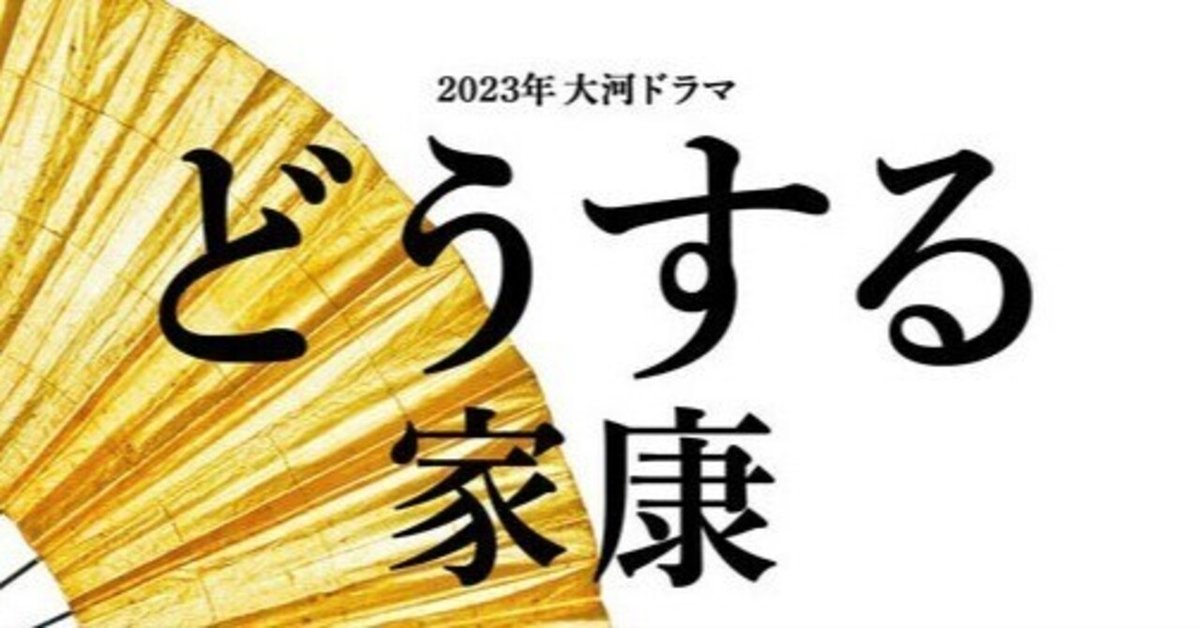
「六度半の槍」の本多忠真
本多平八郎忠豊(?-1545)┬平八郎忠高(1526?-1549)─平八郎忠勝
└肥後守忠真(1531?-1573)─菊丸
「徳川殿の16人」ではないが、「徳川16神将」は個性派揃いである。
名槍「蜻蛉切」を操る槍の達人「徳川四天王」本多忠勝(1548-1610)の父・本多忠高は、安城合戦で討死し、若干2歳の鍋之助(後の本多忠勝)は、叔父である槍の達人・本多忠真が引き取って育てた。
『鎌倉殿の13人』『どうする家康』と見て思うのは、
「脚本が分かりやすい。史実と違うけど」
ですね。『どうする家康』の本多忠勝は、
「俺の祖父・本多忠豊は、主君であるお前の祖父・松平清康のために死んだ。俺の父・本多忠高は、主君であるお前の父・松平広忠のために死んだ。俺は生まれてから、お前を主君と仰ぎ、お前のために死ぬと決めていた。でも、こんなに不甲斐ない人物だったとは。俺はお前を主君と認めない」
と言っていて、非常に分かりやすい。ただ間違っている。祖父・本多忠豊は、安城合戦で、松平広忠の身代わりとなって死んだのである。なお、本多忠豊と本多忠高の墓は、妙源寺(愛知県岡崎市大和町)にある。
本多忠勝の初陣は永禄3年の「桶狭間の戦い」、
初首は翌・永禄4年の「鳥屋根城(登屋ヶ根城)攻め」である。
「桶狭間の戦い」の前哨戦「神君大高城兵糧入れ」に伴う「鷲津砦攻め」で、初陣の本多忠勝が、織田方の武将・山崎多十郎に討ち取られそうになった時、本多忠真は槍を投げつけて窮地を救っている。
「鳥屋根城(登屋ヶ根城)攻め」では、本多忠真が槍で敵兵を刺して本多忠勝を招き、「この者の首を取ればよい」とアシストしたが、本多忠勝は、
「我、何ぞ人の力を借りて、以て武功を立てんや」
と言って自ら敵陣に駆け入り、初首をあげたという。
『どうなる家康』の本多忠真は「松平家のために代々身を捧げてきた本多家の武将。叔父として忠勝に武芸を徹底的にたたき込み、最強武士に育てた。昼間から徳利を片手に酒を飲み、酔っているのか正気なのかわからないが、戦場ではスイッチが入ったように体が動く」人物だと設定されている。
本多忠真が呑ん兵衛(酒豪)かどうかは知らないが、本多忠勝の息子・本多忠朝は呑ん兵衛として知られる。慶長19年(1614年)の「大坂冬の陣」の時、酒を飲んでいて不覚をとったのを徳川家康に咎められたので、翌年の「大坂夏の陣」では、名誉挽回のため、毛利勝永軍に正面から突入し、奮戦するも戦死した。死に臨んで深く酒弊を悔い、
「酒のために身を誤る者を助けん」
と誓って瞑目したと伝えられ、今では「酒封じの神」「禁酒の神」として、崇められている。
演じているのは波岡一喜さんである。Vシネマの任侠物のイメージが強いが、徳川家康ゆかりの静岡県浜松市を舞台として書道部の女子高生の活躍を描いた浜松・浜名湖地域振興映画製作プロジェクト『青い青い空』では、書道部顧問を演じている。
・原題は『書道♡ガールズ 青い青い空』であったが、後発の日本テレビ『書道ガールズ!! わたしたちの甲子園』が先に公開されてしまったためにタイトル変更を余儀なくされた。
・監督は大林信彦監督の弟子・太田隆文監督だけあって、随所に大林信彦監督風のカットが織り込まれている。
・映画は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場する「第3村」のモデル地の1つとなった天竜浜名湖鉄道・天竜二俣駅での出会いから始まる。
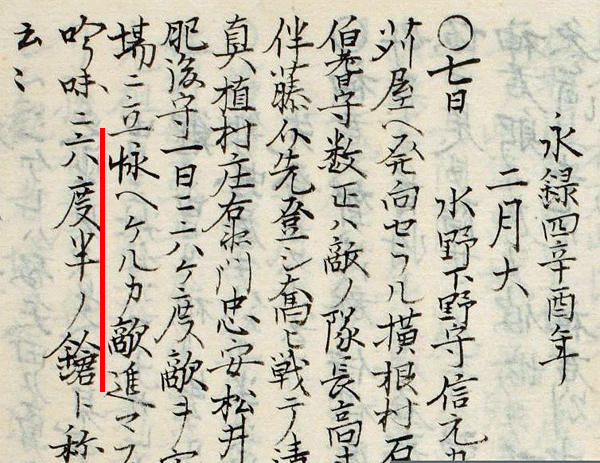
本多忠真といえば、「三方ヶ原の戦い」で殿(しんがり)戦での壮絶死で有名であるが、犀が崖の「表忠彰義之碑」には、永禄4年2月7日の「石ヶ瀬川の戦い」(水野信元と今川方の松平元康(後の徳川家康)の戦い)での活躍「6度半の槍」についても触れられている。
「石ヶ瀬川の戦い」において、本多忠真は、槍を持って敵と戦うが、負傷してしまう。再び槍を持って敵と戦うが、また負傷してしまう。それでも、槍を持って敵と戦うが、また負傷してしまう。・・・これを6度繰り返し、誰もが「もう無理だろ」と思ったが、彼は立ち上がって戦おうとした。しかし、敵は彼の気迫に負け、誰も槍を合わせようとしなかった。この武勇を称えて「6度半の槍」という。
肥後守、一日に六度、敵を突き崩し、疵を蒙る。七度目に槍傷に立ち怺(こら)へけるが、敵進まずして、槍を接(まじは)へざれども、参河武士の吟味に「六度半の槍」と称美し、世に其の驍勇を讃嘆すと云々。
1つの戦いで6箇所以上の槍傷が出来たのであろうが、彼の弟子・本多忠勝は、「生涯戦うこと57度。されど、かすり傷一つ無し」であった。
■「表忠彰義之碑」(犀が崖)
この碑は、本多肥後守忠真の忠義を称えて、第17代本多子爵により明治24年に建立されました。
本多忠真は、徳川草創期を支えた徳川四天王の一人である本多忠勝の叔父にあたる武将です。
本多忠真は、三方原の戦いで武田軍に大敗した徳川軍の中にあって、撤退に際し殿を買って出ました。
道の左右に旗指物を突き刺し、「ここから後ろへは一歩も引かぬ」と言って、武田勢の中に刀一本で斬り込み、39歳をもってこの地で討ち死にしたと伝えられています。
忠真の子、菊丸は父の命により家康を援護し浜松城に無事退却しましたが、父の最後を前にし友が次々と死んでゆくのを見た彼は無常を感じ、父の遺骸を三河に葬ったあと出家の道を歩むことになりました。
この碑には本多家が代々松平家・徳川家に仕えたこと、本多忠真が数々の戦で功績を残したことが記されています。
また、碑の題字「表忠彰義之碑」は、徳川家16代家達公によって書かれています。
■きのさん「犀ヶ崖の「肥後守本多君戦歿地の碑」を読み解く」
https://blog.goo.ne.jp/kinosan1/e/5e9d4eb7092cb06e017cfec6a2e18b39
https://blog.goo.ne.jp/kinosan1/e/da6dd6da95765c198e2fe0b27ffd4065
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
