
式内・石徳高神社(伊豆国田方郡)
『延喜式』「式内帳」伊豆国田方郡(24座(大1座 小23座)) 石徳高神社
『伊豆國三ヶ郡神明帳』田方郡24所 従四位上 にゐのゝ明神
論社①:守山八幡宮(静岡県伊豆の国市寺家) 御祭神:大山祇神
論社②:豆塚神社 (静岡県伊豆の国市北江間) 御祭神:石徳高命
論社③:多賀神社 (静岡県三島市谷田) 御祭神:伊弉諾尊
論社④:岩徳高神社(静岡県伊豆市徳永) 御祭神:大山祇神
古代、江間郷は1つの郷で、南江間の雄徳山(大男山) の山頂に鎮守社(式内・石徳高(い わとくたか)神社)があった。石徳高命とは、三島大神(大山祇神)の別称だという。
その後、守山にぶつかって東麓を流れていた狩野川の流路が西麓に変わり、江間郷と北条郷に分断したので、鎮守・石徳高神社は、それぞれの郷に建てられた。
北条郷=四条郷(上条、下条、中条、南条)の総鎮守・石徳高神社(御祭神:大山祇神)は、延喜7年(907年)に源頼義が豊前国宇佐神宮から八幡神(譽田別命)を勧請して「守山総社八幡」「伊豆国総社八幡」と称し、石徳高神は三島大神として相殿に祀られた。
江間郷(北江間、南江間)の総鎮守・石徳高神社(御祭神:石徳高命)は、現在の珍野(新野(にゐの)→新野(しんの)→珍野(ちんの)と転訛)に建てられ、「新野明神」(『伊豆國三ヶ郡神明帳』)と称したが、江間郷を領した北条義時が豆塚に遷座し、「豆塚大明神」と称して崇敬した。

■守山八幡宮(現地由緒書)
当社の創建は大化3年(647年)御祭神は大山祇神で延喜式内石徳高神社である。
延喜7年(907年)源頼義豊前国宇佐より八幡神を勧請して以来伊豆国総社八幡と 称す。
治承4年(1180年)源頼朝此所に源家再興を祈願社兵を挙げて山木館に上る火煙を望見すと。
頼朝神威を畏み社殿を造営し心願成就の社なり。
■守山八幡宮境内「史蹟 源頼朝挙兵之碑」碑文
源頼朝治承4年(1180)8月15日守山八幡宮に平家追討を祈願して挙兵。夜陰、源氏重忠の軍兵数十騎、山木判官平兼隆を襲い討つ。其の間、頼朝遥かに山木館の火煙を望み悲願の達成を悦ぶ。蓋し鎌倉幕府草創の礎はここに於て成ると。故に記して建碑の所以とする。
正しくは「守山八幡宮に待機していた源頼朝は、山木館から火炎があがらないので、業を煮やして山木館に向けて出陣した」という。
■『吾妻鏡』「以仁王の令旨」
治承四年四月小廿七日壬申。高倉宮令旨。今日到着于前武衛將軍伊豆國北條舘。八條院藏人行家所持來也。武衛裝束水干。先奉遥拝男山方之後。謹令披閲之給。
(治承4年(1180年)4月27日、高倉宮(以仁王)の令旨が、今日、前武衛将軍(源頼朝)がいる伊豆国の北条館に届いた。八条院蔵人・源行家が持ってきた。源頼朝様は水干を着て、まず京都府八幡市八幡高坊の男山八幡宮(現・石清水八幡宮)の方を拝み、次に謹んでこれを開いた。)
男山は石清水八幡宮の旧称「男山八幡宮」だというが、正確な方向が分かるだろうか? 大男山(雄徳山。おとく→おとこ)の石徳高神社、もしくは「男山」ではなく「守山」で、守山八幡宮ではないか?
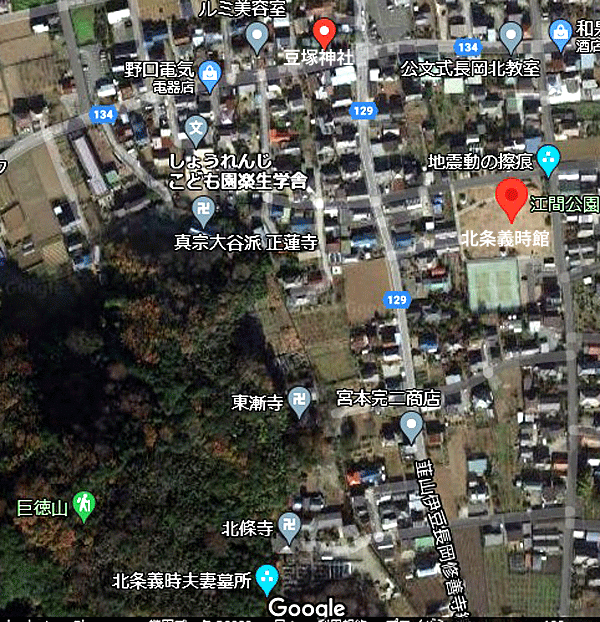
■豆塚神社(現地由緒書)
鎮座地 伊豆長岡町北江間小字町屋
御祭神 石徳高命
例祭日 4月3日
由 緒
創建の年代は詳でないが明細帳に依れば大明神と書いた古額あり、又文明4年と記した神器あり。昔は雄徳山大男山に鎮座せしを幾度か遷祀し江間小四郎平義時は崇敬厚く現地豆塚に遷し大明神と稱せり。明治6年9月郷社に定められ大祭には県よりの奉幣便により神事を行う。往時は江間郷北條郷は一郷にて狩野川の流れが中間を流れる様になり、總鎮守を江間郷に北條郷は守山の地に遷し祀った。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
