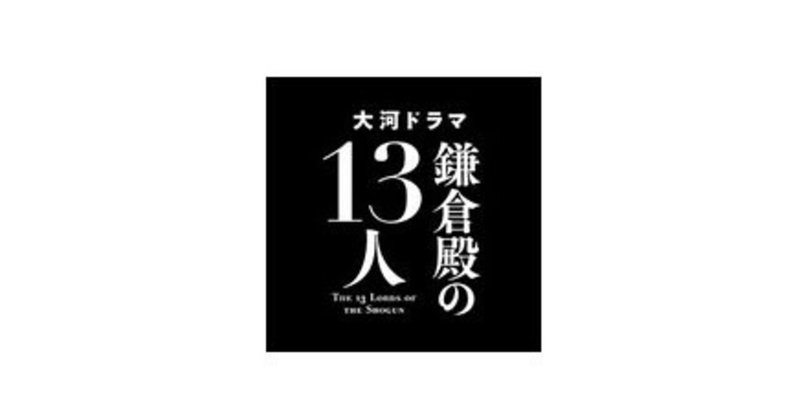
「泉親衡の乱」

▲安念法師、荏柄胤長が亭に密謀を語る図
建暦3年(1213年)、「泉親衡の乱」の首謀者・泉親衡(信濃源氏)は、源頼家の遺児・千寿丸(後の栄実)を鎌倉殿に擁立して執権・北条義時を討ち取ろうと図り、泉親衡の郎党・青栗七郎の弟・阿静坊安念(安念法師)を北条氏に批判的な御家人に遣わし、挙兵への協力を求めていた。

▲安念法師、面縛せらるる図
建保元年(1213年)2月15日、阿静坊安念(安念法師)は、千葉成胤を反乱に誘うが、忠臣・千葉成胤に捕縛され、北条義時に差し出された。
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(冒頭部分)
建暦三年十二月六日に改元あり。建保元年とぞ號しける。
然るに、今年二月十五日、千葉介成胤が手に、一人の法師を召捕りて、相摸守にぞ參せける。是、叛逆の中使(ちうし)なり。信濃國の住人、靑栗(あをぐり)七郎が弟・阿靜房安念といふ者なり。諸方に廻りて、一味同心の輩を相語ふ。運命の極る所、天理に叶はざる故にやありけん、千葉介が家に入來り、かうかうと語りければ、成胤は、當家忠直の道を守り、即ち召捕て參せたり。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186667/213
阿静坊安念(安念法師)の自白により、泉親衡に与みした武士は、張本(中心人物)130人余、伴類(張本の家来)200人余にのぼったことが分かった。その中には、和田義盛の子である和田義直、和田義重、甥の和田(荏柄)胤長がいた。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)2月16日条)
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
相摸守、軈(やが)て、山城判官行村に仰せて糺問し、金窪(かなくぼの)兵衞尉行親を相副へて聞かしめられたりければ、安念法師一々に白狀して、謀叛の同類をさし申す。一村(いちむらの)小次郎、籠山(こみやまの)次郎、宿屋(しゆくやの)次郎、上田原(うへだはらの)三父子、園田七郎、狩野(かのゝ)小太郎、澁河(しぶかはの)刑部六郎、磯野(いそのゝ)小三郎、栗澤(くりざはの)太郎父子、木曾、瀧口、奥田、臼井等(ら)、殊更、和田義盛が子息四郎義直、五郎義重、一族、是(これ)に與(くみ)す。張本百三十餘人、伴類百人に及ぶといひければ、國々の守護人に仰せて、「召進ずべし」と下知せらる。この事の起(おこり)を尋ぬるに、泉小次郎親平と云ふもの、賴家卿の御子・千壽丸とておはしけるを、大將に取立てて、北條家を亡(ほろぼ)さんと相謀り、安念法師に廻文(くわいぶん)を持たせて、潛に諸國の武士を語(かたら)ふに與力(よりき)同心、既に多し。

▲荏柄胤長、必死の勇を現す図
翌日(2月16日)、十数人が捕縛された。
この時、弓の名手・荏柄平太胤長(和田胤長)は、大倉御所の鬼門守護・荏柄天神社(神奈川県鎌倉市二階堂)下の屋敷前で戦った。
※荏柄天神社:京都の「北野天満宮」、福岡の「太宰府天満宮」と共に「日本三天神」の一社。

▲親平、祐友、建橋に戦ふ図
泉親衡(親平)は、郎党の青栗四郎、保科次郎、籠山次郎、市村近村、粟沢太郎らと共に「鎌倉十橋」の違橋(たがえばし。建橋、筋替橋。大倉御所の南西)に潜伏していることが分かり、捕縛の使者・工藤十郎祐友と合戦に及び、工藤十郎祐友を倒した。泉親衡は、戦いの最中に戦線離脱した。船を背負い、水路や陸路を使って逃げ回り、行方不明となったので逮捕できなかった。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)3月2日条)
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
「親平は建橋(たてばし)といふ所に隱れ居る」と申しければ、工藤十郎を遣して召て參るべき由、仰せ付もる。工藤は家子郎從二十餘人を倶して建橋に行き向ひ、案内しければ、親平、異なる氣色もなく工藤を呼入れて首打落し、其間に親平が郎從三十餘人、打ちて出でつゝ、工藤が郎従、一人も殘らず打殺して、親平は行方なく落失せけり。
瑶光山最明寺(埼玉県川越市小ヶ谷町)の縁起によれば、泉親衡は、千寿丸と共に当地に落ち延びて出家し、「静海」と名乗り、文永2年(1265年)5月19日に88歳で没したという。
※泉中央公園(神奈川県横浜市泉区)には、泉親衡の関東での居館と伝わる城跡「泉小次郎親衡館」が残り、この泉中央公園の池は、この池水で泉親衡が馬を洗っていたとされ、「馬洗いの池」と呼ばれている。
・「長福寺と伝 泉小次郎館跡」
https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/shokai/rekishi/ayumi/imamukashi/2-shoshi/kaihatsu/9-cyoufuku.html
逮捕されたのは、次の13人(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)2月16日条)。
①一村小次郎近村
②籠山次郎
③宿屋次郎
④⑤⑥上田原平三父子3人
⑦薗田七郎成朝
⑧狩野小太郎
⑨和田四郎左衛門尉義直
⑩和田六郎兵衛尉義重
⑪渋河刑部六郎兼守
⑫和田平太胤長
⑬磯野小三郎

▲和田義盛、三浦一党を率いて御所へ推参の図

この時、和田義盛は、自領の上総国夷隅郡伊北荘(伊隅荘(いすみのしょう)の北部を伊北荘(千葉県夷隅郡大多喜町)、南部を伊南荘という)に行っており、鎌倉を留守にしていたが、知らせを聞いて、すぐに大倉御所に参上した。
結果、和田義盛の子の和田義直と和田義重は許された。
・和田義盛のこれまでの功績
・阿静坊安念(安念法師)の自白により、事前に防げたこと
・北条義時の命を狙っていたが、源実朝の命は狙っていなかったこと
等々が考慮されての判決だという。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)3月8日条)
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
和田左衞門尉義盛は、上總國伊北莊(いぎたのしやう)にありけるが、この事を聞きて急ぎ走參(はせさん)じ、御所に伺候して對面を遂げ奉る。今度、二人の子息等召誡(めしいまし)めらるゝ事を大に歎き申しければ、數年勲功の忠節に優(いう)じて、子息四郎義直、五郎義重が罪名を除きて、許し下されたり。羲盛、「老後の眉目(びもく)、之に如(しか)ず」と喜び奉りて、退出す。
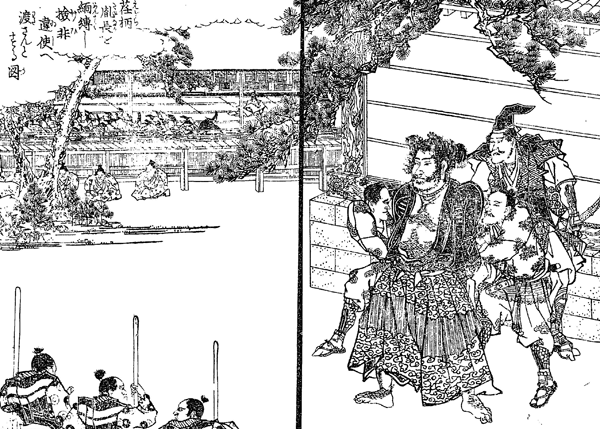
▲荏柄胤長を面縛し、検非違使へ渡さんとする図
翌日、許されなかった和田義盛の甥の和田胤長は、和田一族98人の前を、後ろ手に縛られて通り、侍所の二階堂行村に引き渡された。和田一族は恥をかいた。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)3月9日条)

▲古郡保忠。荏柄胤長を励ます図
※古郡保忠:古郡氏は、「武蔵七党」の一つ「横山党」の一族とされる。横山党の祖・横山義孝の孫・横山忠重が、甲斐国都留郡古郡(山梨県上野原市上野原)を本拠にしたことから「古郡(ふるごおり)」を名乗ったとされる。
「和田合戦」では、古郡保忠は、和田方で出陣し、和田軍の敗北を聞き、古郡保忠&経忠兄弟は自領の「板東山波加利之東競石郷二木」(坂東山(笹子峠)、甲斐国都留郡波加利荘(山梨県大月市初狩)の東の競石郷二木(きそいいしごうにっき)で自害した。こうして横山党と共に古郡氏も滅亡した。
※『甲斐国志』「坂東山」:建保五年五月四日、古郷左衛門兄弟於甲斐国坂東山波加利之東競石郷二木自殺矣(東艦)みさか かた山 つるばんとう(曽我物語)鎌倉へ出仕の道すじを云う趣なり。或いは篠山即ち坂東山なりと云々。

▲尼公、簾を捲しめ胤長を糺し玉ふ図

▲「荏柄平太縄付き問答」
(荏柄平太胤長(市川団十郎)&政子尼公(沢村田之助))
尼御台・北条政子が、直々に荏柄平太胤長(和田胤長)を尋問した。
「多くの共犯者を集めた」
として許されず、陸奥国岩瀬(福島県岩瀬郡)へ流罪となった。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)3月17日条)
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
翌日、又、義盛、その一族九十八人を引卒して、御所の南庭に列坐し、「迚(さても)の御恩に、囚人の内和田平太胤長を許し給はるべし」と申す。「平太は謀叛人の張本なれば、叶ふべからず」とて、高手小手に縛搦(しばりから)め、一族共の坐したる前を引渡し、判官行村に仰せて、陸奥國岩瀨の郡(こほり)に流罪せらる。
■講談『鎌倉星月夜』「荏柄平太縄付き問答」序文
茲に及んで荏柄氏、北条が専横を悪(にく)み、反って謀反に陥り、実朝公が御前に於いて姦佞の曲者を罵詈讒謗なし、義時をして慙懼汗流せしめ、尼公をして又半言隻句なからしめたるがごときは、沛然として雨を下し、陰然として雲を起こし、龍起こり、虎嘯くかと怪しまる。是ぞ有名なる荏柄平太縄付問答なり。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/889571

▲荏柄平太胤長、配所、奥州へ送らるる図
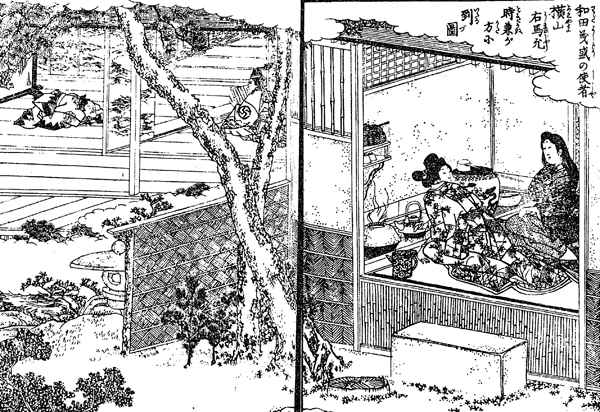
▲和田義盛の使者、横山右馬允時兼が方に到る図
和田義盛は、横山時兼に味方になるよう求めた。(和田義盛は、横山時兼に決行の日は5月3日だと告げたので、横山時兼が応援に来たのは5月3日であるが、事が露見したので、和田義盛は決行を早め、合戦は5月2日の夕方から始まっていた。)

▲和田義盛、五条の局に就いて願ひを達する図
流罪となった荏柄平太胤長(和田胤長)の荏柄天神社の屋敷は、没収された。一等地であるので、欲しい者が多かった。和田義盛が五条局に「和田胤長の屋敷は私に」と願うと聞き届けられた。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)3月25日条)
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
平太が家は荏柄(えがら)の天神の前にあり。御所の東の隣たるに依て、近習の侍、望み申す人多し。義盛、即ち五條局とて、近く召使はるゝ女房に屬(しよく)して、言上しけるやう、「故右大將家の御時より、義盛が一族の所領の地としては、他人、更に住居すべからず。只今、闕所(けつしよ)に及ぶ條、是非なし。せめて彼が屋形をば申受け奉らん」と望み申す。實朝卿、御許容ありけるが、忽に變改(へんがい)して、相摸守義時に賜る。

▲金窪行近、荏柄の宿地に来たり、勤番を追ひ出だす図
没収された和田胤長の屋敷は、和田義盛が拝領することとなったが、突如、北条義時の預かりとなり、旧・和田胤長屋敷にいた和田義盛の家人(勤番)は、北条義時の家人によって追い出された(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)4月2日条)ため、面目を潰された和田義盛は、北条義時を打倒する意思を固め、「和田合戦」となった。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)5月2日条)
このように、「和田合戦」の原因を作った「泉親衡の乱
」は、「和田合戦の前哨戦」の呼ばれている。
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
和田が代官久野谷(ひさのやの)彌次郎を追出し、行親、忠家、分(わけ)取りて移住みけり。義盛、大に怒て曰く、「この屋形を申受けて少の怨をも散ぜんと思ひし所に、忽に變改して義時に賜る事、重々以て口惜き事なり。此上は生きて世にありて何を面目とすべき。皆、北條が所屬なれば、思ひ知らせばべらんものを」とて、頓(やが)て叛逆を企てけり。
--------------------------------------------------------------------------------------
杉本義宗──┬和田左衛門尉義盛(67)┬長男・和田常盛(42)─和田朝盛
├和田義茂(落馬) ├次男・和田義氏(40)─和田重盛
├和田義胤 ├三男・朝夷奈三郎義秀(38)
├和田義長─和田胤長 ├四男・和田四郎左衛門尉義直(37)
└和田宗実─藤原秀宗 ├五男・和田五郎兵衛尉義重(34)
├六男・和田六郎兵衛尉義信(28)
├七男・和田七郎秀盛(15)
├八男・杉浦八郎義国
├長女
└次女

▲和田義直、馬を馳せて、朝盛を逐ふ図
源実朝とは和歌を通して仲が良かった和田朝盛(和田義盛の孫。父・和田常盛は和田義盛の嫡男)は、祖父・和田義盛の謀反の意思を知り、「祖父に付かないのは「不孝」、将軍・源実朝に付かないのは「不忠」」として、どちらに付こうか悩み、4月15日、下した判断は「出家して京都に向かう」であった。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)4月15日条)
「嫡男なのに、武勇に優れているのに、戦わないとは、情け無し」と怒った和田義盛は、和田義直に追わせた。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)4月16日条)

▲和田義盛、怒りて朝盛入道を折檻の図
和田義直は、朝盛入道に駿河国手越(静岡県静岡市手越)で追いつき、連れ戻した。(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)4月18日条)
一方、北条義時も、勘当した次男・北条朝時を呼び戻した。

▲宮内兵衛尉公民、義盛が亭へ御使ひを勤むる図
「朝盛入道を連れ戻した」ということが広く知られると、「和田義盛に謀反の意思あり」と察した源実朝は、和田義盛邸へ宮内公民を派遣して和田義盛に自重を促した。宮内公民は、迎えに出てきた和田義盛の烏帽子が落ちたのが首が落ちたように見え、「戦になれば和田義盛は負ける」と予感したという。
続けて源実朝は、和田義盛邸へ今度は若狭忠季を派遣したが、和田義盛は「いきり立つ若い衆をもう引き止められない」と言い(『吾妻鏡』建暦3年(1213年)4月27日条)、予定よりも1日早い建暦3年(1213年)5月2日、「和田合戦」が勃発した。
■『鎌倉北条九代記』「千葉介阿靜房安念を召捕る 付 謀叛人白状 竝 和田義盛叛逆滅亡」(部分)
和田新兵衞尉朝盛は、義盛が孫なり。將軍家の近習として等倫(とうりん)の寵恩、之に越る人なし。近比、父祖一黨して怨を含み、出仕を留めて、叛逆を企てはべる。是に與すれば、君を射奉るの科(とが)あり。與せざれば、父祖の孝道に叛く事を思ひて、淨遍僧都に謁して、發心出家の身となり、實阿彌陀佛と名を付きて、京都に上りける所に、義盛、聞付けて、四郎左衞門義直を追手に遣はす。駿河國手越にて追付き、引返しはべり。この事、隱なかりしかば、將軍家より宮内兵衞尉公氏を遣し、樣々宥め仰せらるれども、用ひず。
--------------------------------------------------------------------------------------

泉親衡
泉の親衡は、信州の人なり。源満仲の後なり。強力、勇気、万人に傑出す。建暦癸の酉に陰謀露顕して、当与十余人、つゐに囚虜となる。工藤の某、親衡が隠れたる所を探して、是を捕らえんと欲す。親衡、工藤を殺して去る。遂に所在を失す。世に伝ふ。「親衡、大船を負ふて水陸を上下す」と。
※源満仲の後裔ではなく、源満快の後裔。
※泉親衡に与みした武士が「張本(中心人物)130余人、伴類(張本の家人)200余人の330余人」と言われても、信じがたい数であるが、「関係者10余人(13人)が逮捕」というのは、あり得ると思う。
「泉親衡の乱」の首謀者は、泉親衡(いずみちかひら。「親平」とも表記。通称:小次郎。治承2年(1178年)-文永2年(1265年)5月19日?)である。
泉氏は、源為公を祖とする信濃源氏で、信濃国小県郡小泉荘(現・長野県上田市)を本拠として、「小泉」ではなく「泉」と名乗り、子孫は、信濃国飯山(現・長野県飯山市)を拠点として栄えた。
源経基┬嫡男・源満仲
└五男・源満快─満国─為満─為公─□─□─□─泉快衡─公衡┬小二郎親衡
(この3代不詳) ├四郎俊衡
├五郎頼衡
└六郎公信
泉二郎公衡─泉小二郎親衡(親平)─泉孫太郎満衡の3代(3人)は実在の人物であるが、信濃源氏の泉氏と同族であるか(泉公衡と源為公がどう繋がるのか)は微妙である。
そもそも泉親衡は、小泉荘ではなく、信濃国東筑摩郡中山村泉(長野県松本市中山の和泉地区)の生まれとされ、現地の泉親衡伝説では「神童」「朝比奈義秀と双肩の怪力」等、調べていくと「足柄山の金太郎」を思い出した。
※参考記事「『吾妻鏡』に見る建暦1212~1213年 」
https://note.com/sz2020/n/n2dc4314df1ca
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
