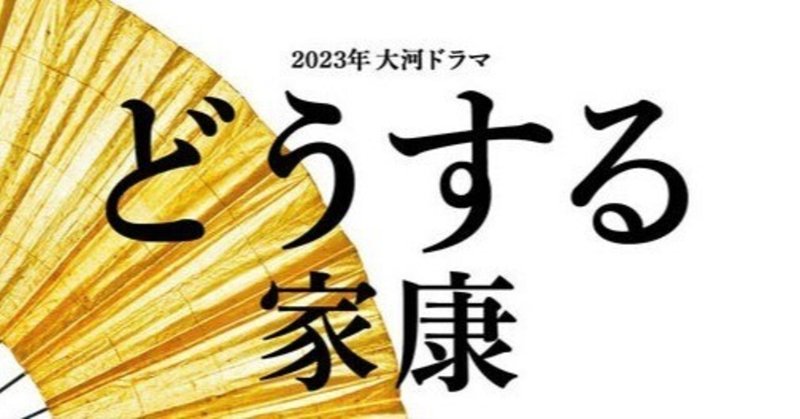
第8回「三河一揆でどうする!」(復習)
永禄3年(1560年)5月19日 「桶狭間の戦い」(岡崎城へ帰還)
永禄4年(1561年)4月11日 「牛久保城攻め」(今川氏から独立)
永禄5年(1562年)1月15日 「清須同盟」(織田信長と和睦)
永禄5年(1562年)2月4日 「上ノ郷城攻め」(人質交換)
永禄5年(1562年)2月24日 「元康」から「家康」に改名(翌年説あり)
永禄5年(1562年)6月 上ノ郷城に久松長家、於大の方等入城
永禄6年(1563年)5月 「神君一宮後詰」(永禄7年説あり)
永禄6年(1563年)6月 上野城の酒井忠尚が挙兵
永禄6年(1563年)7月6日 「元康」から「家康」に改名(昨年説あり)
永禄6年(1563年)10月 寺部城の小笠原広重&東条城の吉良義昭が挙兵
永禄6年(1563年)10月 「三河一向一揆」勃発
永禄7年(1564年)2月 「三河一向一揆」終結
永禄9年(1566年)5月 「三河国平定」(牛久保の牧野氏が従属)
永禄9年(1566年)12月29日「松平」から「徳川」に改姓。三河守叙任。

『鎌倉殿の13人』の参考書は、鎌倉幕府公式史書『吾妻鏡』であり、
『どうする家康』の参考書は、江戸幕府公式史書『徳川実紀』である。
その『徳川実紀』には次のようにある。
君ことし御名を家康とあらため給ふ。(永禄四年十月の御書に「元康」とあそさばされ。五年八月一日の御書には「家康」とみゆ。)
六年には信長の息女をもて若君に進らせんとの議定まりぬ。信長かくむすぼふれたる御中とならせたまへば、今川方にはこれを憤り、所々のたゝかひやむ時なしといへども。今川方いつも敗北して勝事を得ず。
此ほど小坂井、牛窪辺の新塞に粮米をこめ置るゝに、御家人等、佐崎の上宮寺の籾をむげにとり入たるより、一向専修の門徒等、俄に蜂起する事ありしに、譜第の御家人等、これにくみするもの少からず。國中騒擾せしかば、君御みづからせめうたせたまふ事度々にして、明る七年にいたり門徒等勢をとろへて、御家人どもゝ罪をくひ帰順しければ、一人もつみなひ給はず、有しながらにめしつかはる。
このさわぎに時を得て、吉良義昭、荒川頼持、松平三蔵信次、松平監物家次、松平七郎昌久等、又、反逆して、をのが城に立こもりしかど、かたはし攻おとされき。されども、吉田城には、今川氏真より小原肥前守鎮実をこめ置て、岡崎の虚をうかがへば、是にそなへられんがため、岡崎よりも喜見寺、糟塚等に寨をかまへさせたまふ。
君ことし御名を家康とあらため給ふ。
「元康」から「家康」に改名した時期には、
・説①:永禄5年(1562年)2月24日説(『徳川実紀』『伊束法師物語 』)
・説②:永禄6年(1563年)7月6日説(『家忠日記』『武徳編年集成』)
がある。
江戸幕府公式史書『徳川実紀』は、「永禄4年10月の文書に「元康」、永禄5年8月1日の文書には「家康」とある」として、説①を支持する。
現在の歴史学者は「永禄6年6月付の松平直勝に上野砦を申し付ける判物に「元康」、永禄6年10月24日付の松平亀千代(後の家忠)宛の幡豆砦の忠節で知行を与えるとする判物に「家康」とある」として、説②を支持する。
徳川家康の文書には偽文書が多いので、注意を要する。
小坂井、牛窪辺の新塞に粮米をこめ置るゝに、御家人等、佐崎の上宮寺の籾をむげにとり入たるより、一向専修の門徒等、俄に蜂起する事ありしに、譜第の御家人等、これにくみするもの少からず。(中略)このさわぎに時を得て、吉良義昭、荒川頼持、松平三蔵信次、松平監物家次、松平七郎昌久等、又、反逆して、をのが城に立こもりしかど、かたはし攻おとされき。
「三河一向一揆」の発端については、
・説①:松平家康の家臣が寺の穀物を奪った。(寺内町へ侵入):通説
・説②:松平家康が本願寺教団の市場(水運、商業圏)へ介入:新説
・説③:今川氏真の要請:異説
がある。
通説は「不入権の侵害」であり、江戸幕府公式史書『徳川実紀』も、「小坂井、牛窪辺の新塞に粮米をこめ置るゝに、御家人等、佐崎の上宮寺の籾をむげにとり入たる」(東三河の小坂井、牛久保(共に愛知県豊川市)に新しく築いた要塞(砦)に兵糧米を入れるために、上宮寺(愛知県岡崎市上佐々木町)の籾を無下に奪って砦に入れた)と説①を支持する。
松平家康には兵糧米が無かったようである。同盟を組む織田信長は裕福で、松平家康は貧乏──この差は領内の良田の広さにもよるが、商業活動にもよる。織田信長は、熱田神宮のある熱田港と、津島神社のある津島港を押さえていた。西三河の港町には一向寺院があり、松平家康は、若気の至りもあって、一向寺院との付き合い方を間違えたといえよう(説②)。
松平家康の譜代の家臣の内、一向宗の門徒が一揆側につき、反松平家康の国衆(吉良義昭、荒川頼持、松平信次、松平家次、松平昌久等)も蜂起したので、「三河一向一揆」は「家康三大危機」の1つにあげられる。一向宗の寺や反松平家康の国衆のバックには今川氏真がいたという(説3)。
されども、吉田城には、今川氏真より小原肥前守鎮実をこめ置て、岡崎の虚をうかがへば、是にそなへられんがため、岡崎よりも喜見寺、糟塚等に寨をかまへさせたまふ。
西三河の反乱分子を一掃し、西三河を統一した松平家康の次の課題は、東三河へ攻め込んで、三河国を統一することにあった。
今川氏真は、東三河の吉田城に小原鎮実を入れ、松平家康は、「吉田城攻め」の拠点として、喜見寺(愛知県豊橋市花園町)、糟塚(愛知県豊川市小坂井町樫王)等に砦を築いた。
※「吉田城攻め」では、糟塚砦からさらに吉田城に近い聖眼寺(愛知県豊橋市下地町)に本陣を移すと、住職は、牧野氏が聖眼寺太子堂に奉納した2本の金扇の1本を献上すると、松平家康は馬印(この記事のタイトルの背景)に採用した。(松平家康は吉田城を攻め落とせなかったが、聖眼寺の住職が仲介人となり、和解が成立し、今川軍は吉田城を出て、松平軍が入った。)
この牧野氏が降参して三河国の平定となるが、それはまだ先(2年後の永禄9年(1566年)5月)のことである。(「三河国平定」後、松平家康は「松平」から「徳川」に改姓し、朝廷から三河守に任じられた。)
劇中偈文
『どうする家康』は全48回であろうか?
今回は8回。もう1/6が終わった。
残り40回もあると考えるか、5/6しかないと考えるか?
★今後の『どうする家康』
・第9回「守るべきもの」
・第10回「側室をどうする」
・第11回「信玄との密約」
・第12回「氏真」
※ノベライズの2巻は3/17発売。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
