
『義経記』に見る『勧進帳』の原型
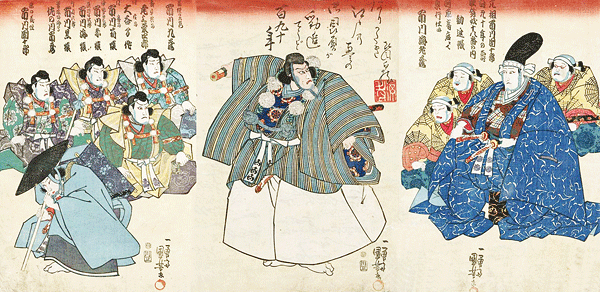
1.『勧進帳』とは?
■『歌舞伎事典』「勧進帳」
歌舞伎十八番【かぶきじゅうはちばん】の一つ。
兄源頼朝【みなもとのよりとも】との仲が悪くなった源義経【みなもとのよしつね】は、武蔵坊弁慶【むさしぼうべんけい】らわずかな家来とともに、京都から平泉【ひらいずみ】(岩手県)の藤原氏【ふじわらし】のもとへと向かいます。頼朝は平泉までの道すじに多くの関所を作らせ、義経をとらえようとします。『勧進帳』は、義経たちが加賀国【かがのくに】の安宅【あたか】の関所(石川県)を通過する時の様子を歌舞伎にしたものです。義経一行は山伏【やまぶし】に変装して関所を通過しようとします。ところが関所を守る富樫左衛門【とがしさえもん】は、義経たちが山伏に変装しているという情報を知っていたので、一行を怪【あや】しんで通しません。そこで弁慶は、何も書いていない巻物を勧進帳と見せかけて読み上げます。勧進帳とは、お寺に寄付を募【つの】るお願いが書いてある巻物です。いったんは本物の山伏一行だと信じて関を通した富樫ですが、中に義経に似た者がいる、と家来が訴【うった】えたため、呼び止めます。変装がばれないようにするために、弁慶は持っていたつえで義経を激しく叩【たた】きます。それを見た富樫は、その弁慶の痛切な思いに共感して関所を通すのでした。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic/entry.php?entryid=1091
2.『義経記』に見る『勧進帳』の原型
『義経記』には、「安宅の関」での武蔵坊弁慶と富樫左衛門とのやりとりは載っていませんが、似た話は登場します。(「安宅の関」は存在しなかったのか、安宅の渡りを越えたとだけあります。)
①三口の関(愛発の関)での関守とのやりとり
②平泉寺の僧と弁慶のやりとり
③三口の関(愛発の関)の井上左衛門
④富樫城の富樫泰家と武蔵坊弁慶
⑤如意の渡しの渡し守・平権守と弁慶のやりとり
⑥直江津の笈改め
①三口の関(愛発の関)での関守とのやりとり
山伏の一行を源義経一行だと思った関守たちは、相談し、「もし、源義経でなければ、無罪の山伏を殺すことになる。ここは1つ試してみよう。『関手(関所を通る通行税)を払え』と言ってみよう。羽黒山伏が関手を払ったことはない。本物なら断り、偽者なら払うはず」と考えたが、武蔵坊弁慶は、「そんな命令は聞いたことがない」と断った。関守が「判断できないので、関東に人を送って指示を仰ぐ。返事が来るまで関屋に留め置く」言うと、武蔵坊弁慶は「ラッキー! 関所の兵糧米で腹を満たせるぞ!」と言って、関屋に入ってくつろいだ(今で言えば、無銭飲食をした人が警察に逮捕されて、「ラッキー! これで三食昼寝付きの刑務所に入られるぞ。餓死しなくて済む」と喜ぶようなものか)ので、関守たちは、「これは源義経一行ではないな。さっさと通してしまおう」と、関戸を開いた。
②平泉寺の僧と弁慶のやりとり
源義経は、「回り道になるが、なんとしても平泉寺(福井県勝山市平泉寺町平泉寺にある平泉寺白山神社)へ行きたい」と言った。従者たちは納得できなかったが、「主人の命ならば仕方ない」と、平泉寺を参拝した。僧たちは、山伏を見て源義経だと思ったが、武蔵坊弁慶の機転で回避した。
③三口の関(愛発の関)の井上左衛門
街道を歩いていると、こうから三口の関(愛発の関)の責任者・井上左衛門がやってきたので、源義経は、「仕方ない」と、刀の柄に手を掛け、郷御前の後ろに隠れ、笠で顔を隠してすれ違おうとしたが、突風が吹いて笠が持ち上げられ、井上左衛門に顔を見られてしまった。
井上左衛門は馬から下り、挨拶をすると、源義経を見送り、源義経の背中が見えなくなってから、馬に乗って愛発関へ向かった。
その日、細呂木(福井県あわら市細呂木)に着いた井上左衛門は、家臣たちを呼び、
「さっきの山伏を誰と思う? あれこそ鎌倉殿(源頼朝)の弟・判官殿(源義経)ぞ。山伏に姿を変えておられるとは不憫でならない。もしあそこで討っていたならば、我が一門は千年万年安泰であったろうか? あまりにお痛わしく思って何事もなく通したのだ」
と言うと、家臣たちは、「主人は情けも慈悲も深い人だ」と頼もしく思ったという。
④富樫城の富樫泰家と武蔵坊弁慶
武蔵坊弁慶は、先手必勝と思ったのか、富樫城の城主・富樫泰家(『勧進帳』の富樫左衛門)に会いに行き、「焼失した東大寺再建の勧進(寄付募集)の山伏でございます」と言うと、富樫介は、「よくぞ参られた」と言って勧進すると、武蔵坊弁慶を馬に乗せ、宮腰まで見送った。
⑤如意の渡しの渡し守・平権守と弁慶のやりとり
如意の渡し(富山県高岡市伏木)を渡ろうとすると、渡し守・平権守(へいごんのかみ)が怪しみ「近くに越中国の守護所(富山県高岡市伏木古国府)があり、守護(比企朝宗?)がいるので、知らせる」という。武蔵坊弁慶が、「どの山伏が源義経だと思うのだ?」と言うと、源義経を指差したので、武蔵坊弁慶は、「お前のせいで渡れぬ」と源義経を背負って浜へ行くと、砂の上に投げ棄てて、腰にあった扇を抜いて、手加減することなく、続け打ち続けたので、平権守はこれを見て、「羽黒山伏ほどに情けのない者はいない。あの者も源義経ではない」と言い、渡らせてもらえた。その後、武蔵坊弁慶は泣きながら源義経にわびた。
⑥直江津の笈改め
越後国の守護は鎌倉に上っていて不在であったので、「山伏が着いた」と聞いた代官が人を集め、源義経一行が居る直江津花園の観音堂を200人余りで取り囲んだ。従者は托鉢に出ており、源義経がただ1人だけが残っていたので、騒ぎを聞きつけて、武蔵坊弁慶が戻ってきた。
代官は、「この山伏が源義経かどうか確かめたいので、笈(荷物入れて背負う竹製の箱)の中身を確かめたい」というので、武蔵坊弁慶は、手に取った笈を投げ出した。それは、たまたま源義経の笈で、中からは日用品が出てきた。次に投げ出したのは、片岡常春の笈であった。中には武具が入っていたが、暗い上に、きつく縛ってあったので、代官が解けずにいると、武蔵坊弁慶は、「その笈には権現が入っておられるぞ。罰が当たるぞ」と脅して開けさせなかった。
⑦念珠の関
念珠の関(山形県鶴岡市鼠ヶ関)の関守が厳しく、通ることができないように思えたので、武蔵坊弁慶が策を講じ、源義経を下種山伏に見たて笈を背負わせ、武蔵坊弁慶は、「歩めや法師」と叱り付け、強く鞭打ちながら進んだので、関守たちはこれを見て、止めることなく木戸を開けて通した。
念珠ヶ関跡に「勧進帳乃本家」の標柱、鼠ヶ関マリーナの道路向かいに『源義経』の著者である直木賞作家・村上元三の「源義経上陸の地」碑が立っている。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
