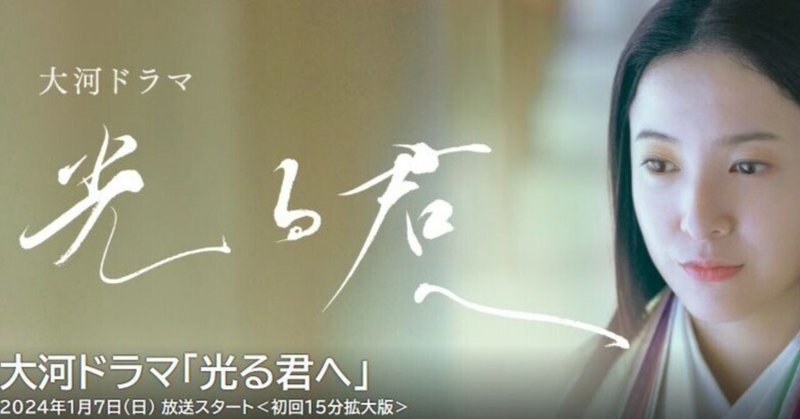
『光る君へ』(第6回)「詩会」とは

詩会(しかい)〘名〙 詩、特に漢詩を詠んで鑑賞する会。【勉強会】
※起源は菅原道真の私塾だという。
詩宴(しえん)〘名〙 詩を詠む席。詩を詠みあう宴。【宴会】
公宴(こうえん)〘名〙 天皇主催の詩宴。⇔密宴【宴会】
内宴(ないえん/だいえん)〘名〙 正月子の日の天皇主催の詩宴。
・題者:お題を献上する人。
・序者:序文を献上する人。
・講師:添削する人。
宇多天皇の意向に沿いながら、年中行事の変革に寄与したのが菅原道真である。寛平期 に始まった九月尽日と八月十五夜の宴にそれを見ることができる。この二つの宴は、すで に菅家廊下で開いていた詩宴を宮廷に持ち込んでいる。官人養成のために菅原氏が経営し ていたこの塾は、門下生が日頃の研鑽の成果を発揮するために、この日に催していた。八 月十五夜の詩は、中唐の詩人白居易とその仲間がはじめて詠んだようである。白詩享受が 盛んな風潮の中、その詩趣を認めた是善・道真父子が私塾に採り入れたのであった。とこ ろが、是善が元慶四年八月三十日に薨じた。以後八月は家忌の月となるため、停廃しなけ ればならない。これに対応するべく道真は、白居易独自の詠作と言うべき三月尽日の惜春 の詩情を応用して、九月尽日における惜秋の風趣を生み出し、私塾での詩宴の題材とした のであった。やがて道真が宇多天皇の側近として重用されるに及んで、この菅家の二行事 は、宮廷の詩宴に採り入れられるに到る。一私塾で催していた九月尽日と八月十五夜の詩宴が、宮廷に持ち込まれるような事態は極めて稀であり、それだけに道真の果たした役割 は大きかったと言えよう。また、行事を創始する契機となった、白詩の及ぼした文学・文化 への絶大な影響力にも着目する必要がある。 菅家廊下は是善の時代には開いており、八月十五夜の詩宴は催されていた。したがって 新たな年中行事の端緒は是善の頃には萌していたのである。とかく道真に耳目が集まるのであるが、是善の働きは、宮廷での九月尽日と八月十五夜の宴を検討する上では見逃すべ きではない。道真はこの父の足跡を継承するとともに、進展させたと言えよう(以上「1 菅原氏と年中行事―寒食・八月十五夜・九月尽―」「2 是善から道真へ―菅原氏の年中行 事―」「4 菅原道真と九月尽日の宴」)
寛平期には、正月十五日・三月三日……などの行事と食との関連について、宇多天皇が 関心を向けている。従前の年中行事ではあまり見られない傾向である。これは中国の宮廷 で給せられていた節食に倣おうとしたためであろうと思われる。ただそれだけでもなく、 日本の民間での食を持ち込んだと思しきところもあり、その食の背景や経緯は単純ではな い。道真は、正月の子の日における羹を食べる風習が、どういう所から始まったかについ て言及しており、宇多天皇と同様に目を向けている。このような動きが宮廷行事に新しさ を加えるきっかけとなったようである(「3 寛平期の年中行事の一面」)。 菅原氏やその一員である道真は、中国文学・文化を学んで、その成果をもとに年中行事 を取り入れて新たな行事を生み出した。そしてその行事を定着させ、やがて宮廷行事にま で展開させる。その後、その行事は長く引き継がれ、文学作品にも描かれた。なお、中国 文学とりわけ白居易の詩文は、平安朝年中行事の形成に当たって重要な役割を果たしてい る。それは、菅家一門の熱心な学習の成果であり、当時の文人のほとんどが、白詩を摂取 するという背景があったためであろう。その上で、道真らの行事が受け入れられたという 側面もあったのである。
※9月9日の「詩宴」は、費用の関係で「詩会」となったが、一条天皇の御世、詩宴に戻っている。
■『日本紀略』に見る一条天皇御世の詩会/詩宴の一部
○十日己巳詩宴。題云「雨夜紗燈」。
〇九日乙卯。重陽宴。題云「秋露如珠」。某日。天皇幸朱雀院。命詩宴。題云「林池秋景」。
○廿八日丁丑。仁王會。日。冷泉太上天皇詩宴。題云「隔花遙勸酒」。同日。公宴。詩題云「春色雨中盡」。
〇十四日癸卯。天皇行幸攝政(經)東三條第。命行詩宴。題云「葉飛水面紅」。又、召ニ擬文章生。奉試賦詩。題云「池岸菊猶鮮」。
〇九日辛未。重陽宴。天皇出御南殿。詩宴。題云「菊是爲仙草」。
○卅日己酉。禁闡命詩宴。題云「送秋筆硯中」。
○十七日庚申。禁闡初命詩宴。題云「鷲雀相賀」。
〇二日乙巳。東宮第一孫王敦明讀書始。參議式部大輔菅原朝臣輔正奉授御註孝經。無尙復。有詩宴。序者式部權大輔大江朝臣匡衡。
〇九日庚申。今夜。於殿上守庚申。御書所學生給祿。詩宴。題云「再吹菊花酒」。
〇三日辛亥。御燈。今日。於御書所有詩會。題云「花貌年々同」。序者匡衡。
○七日癸丑。御書所詩會。題云「織女雲爲衣」。
○廿五日辛卯。於一條院皇居命詩宴。題云「所貴是賢才」。公卿以下屬文之輩多獻詩。題者權中納言忠輔卿。序者文章博士大江以言。講師東宮学士大江匡衡。又、有音楽。
https://dl.ndl.go.jp/pid/991095/1/540
詩題は「酒」──お題が1つの単語ということは、和歌の「題詠」では普通ですが、詩会や詩宴では聞いたこと無いなぁ。たとえば実際に9月9日の「菊の節句」(重陽)に開かれた詩会/詩宴の詩題は「菊」でも「菊花」でもなく、「秋露如珠」「菊是爲仙草」「再吹菊花酒」であり、「秋露如珠」であれば、菊の葉の露が不老長寿の薬であった故事を知っていないと詠めない。
九月九日の宴すなわち重陽節会を挙げてみたい(「4 重陽節会の変遷― 節会の詔勅・奏類をめぐって―」)。天武天皇の十四年にこの宴を催した後長く途絶し、桓 武天皇の代にまで下って再興の機運が醸成され、九月九日およびその前後に遊猟や小宴を 行っていた。そして、平城天皇の大同二年に到って、九月九日は、「菊花の豊楽聞こし食す」 日であると、詔に明言して観射・宴等を催す。宴の復活である。その後、嵯峨天皇の弘仁 三年になって節会となり、儀式としての格を上げる。ところがこの節会は、国庫を圧迫す る要因の一つとの理由で、しばらく停止される。ただし詩会のみの宴は行っている。やが て淳和天皇の天長八年までにはもとの節会にもどっていた。これ以後も消長をくり返しな がら、文字どおり公宴として重んじられ開催されたのである。そして、その後も公宴とし てつづいて行くこととなる。
テーマが具体的に絞られると、参加者は(韻字は指定されるものの)詠みやすく、講師は優劣をつけやすいけど、範囲が狭いと、それ以外の事が書けず、その人の本心は掴みにくくなるので、藤原道隆は、和歌の題詠のように「酒」と一文字にしたのでしょうか。
「詩宴」として、少しお酒を飲んでから「憂政醉吟」(政治を憂い、酒を飲んで漢詩を詠む)でもいいと思うけど。
私は、以前の記事で、『光る君へ』(第6回)「二人の才女」の「詩会」について、「韻を踏んでいない藤原公任の0点の詩、というか、もはや詩ではない文字列が高く評価されたのはおかしい」と述べ、今回、「詩題が一文字なことは無いない」と批判しました。実は、『光る君へ』は、根本的に史実に反しています。「これを言っちゃあ、おしまいよ」というのは、詩会/詩宴で読む漢詩は七言絶句(7語✖4句)ではなく、七言律詩(7語✖8句)と決められており、日本独自のルールもありました。
ようするに、実際行われた自分の作った詩を発表する「詩会」とは違い、好きな詩を挙げる会なので、「漢詩の会」としたのでしょうね。当時は「詩」といえば「漢詩」のことでしたので、「詩の会」でいいんですけどね。
※以下は藤原道長の邸宅で開催された詩宴の実際です。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
