
第15回の再放送を観た。
それは恐ろしい怪談、いや、会談であった。
・源頼朝 :鎌倉殿
・北条義時:源頼朝の側近(源頼朝の正室の弟)
・大江広元:源頼朝のブレーン
・比企能員:源頼朝の側近(源頼朝の長男の乳母夫)
・安達盛長:源頼朝の従者(源頼朝の乳母・比企尼が派遣)
比企能員(一覧表を手渡しながら)「今度(こたび)の乱に加わった者達で御座います」
源頼朝(一覧表を見て)「こんなにおるのか」
北条義時「皆、これまでの武功、並々ならぬ者達で御座います。寛大なお裁きをお願いいたします」
安達盛長「御台所からも、同様のお言葉をいただいております」
比企能員「奴等は御所に攻め寄せるつもりだったのだぞ。厳罰に処さねば示しが付きません」
北条義時「考えがあります。平家を倒した暁には、その所領を御家人達に分配すると約束なさるのです。皆、我先にと戦に向うはず」
安達盛長「なるほど。御家人の気持ちは、御家人が一番分かっておるということですな」
源頼朝 「合点がいった。ここは小四郎の言う通りにしよう」
北条義時「ありがとうございます」
大江広元「しかしながら、やはり御家人達が何一つお咎め無しというのでは、示しが付きません」
源頼朝 「それもそうだ」
大江広元「この際、誰かひとりに見せしめとして罪を負わせるというのはいかがでしょう」
源頼朝 「誰かに死んでもらうと」
北条義時「お待ち下さい。ひとりを選んで首を刎ねるなど、馬鹿げております」
安達盛長「ここは、何卒、慈悲のお心を。さすれば、鎌倉殿の懐の深さに、皆、心を打たれまする」
比企能員「ひとりぐらいなら、いいのではないか」
大江広元「謀反など二度とあってはならぬ。次こそは皆で殺し合いになるやもしれません。見せしめは必要です」
北条義時「必要ありませぬ」
源頼朝 「しかし、誰にする?」
大江広元「それは鎌倉殿がお決めになられては」
源頼朝 「やはり、あの男しかおらんだろう」
大江広元「上総介広常殿」
北条義時「上総介殿は、我等に頼まれて企みに加わったのです。責めを負わせるとはおかしゅう御座います」
大江広元「上総介殿でよいかと」
北条義時「本気で申されてるのですか? まさか…初めからそのおつもりだったのですか? こうなることを見越して」
大江広元「最も頼りになる者は、最も恐ろしい」
北条義時「ご存知だったのですか?」
源頼朝 「この鎌倉で、わしの知らない事は無い。広元から逐一聞いておった。上総介広常――いずれなんとかせねばならぬと思っておった。その矢先にこの一件が持ち上がってな。最初に思いついたのは、おぬしであったな」
大江広元「鎌倉殿でございます」
源頼朝 「ふふっ、わしであったのぉ」
大江広元「敢えて謀反に加担させ、責めを負わせる。見事な策にございます」
源頼朝 「これだけ大きな企てがあったのだぞ。上総介の命と引き換えに、皆を許そうと言っておるのだ」
北条義時「承服できません!」
源頼朝(一覧表をに示して)「では誰ならいいのか申してみよ。この中で死んで構わぬ御家人をここで挙げてみよ!」
以上、この首脳会談で、北条義時の「平家を倒した暁には、その所領を御家人達に分配すると約束する」という提案は通ったが、「上総広常はもちろん、誰も殺害しないで欲しい」という意見は却下されたのである。会談の大勢は「誰かを見せしめにする」に決まり、三浦義村が指摘したように、「北条義時も、実衣などと同様、大事件なのに誰も罰せられないのはおかしいと納得した」ようだ。それでも、「自分が策に参加するよう促した上総広常を殺すのは心苦しい」としたが、策を協賛した時点で、北条義時は「源頼朝に似てきた」(三浦義村談)と言える。
源頼朝の「ふふっ、わしであった」という台詞を聞いて、源頼朝が大江広元に「わしが考えたって、ばらしちゃだめだろ」と言っているように聞えて、「大江広元の策ではなく、源頼朝の策だったのか」と驚愕した。確かに史実は「上総広常が殺された時、大江広元は京都にいて鎌倉にはいなかった」のであるから、大江広元の策とは考えられない。
見直すと、源頼朝の「ふふっ、わしであった」という台詞は、「えっ?お前が考えたことをわしが考えたこと(わしの手柄)にしちゃっていいの?」と言ってるようにも聞えるが、それだと大江広元が「敢えて謀反に加担させ、責めを負わせる。見事な策にございます」と自画自賛することはないと思う。源頼朝が考え、大江広元が絶賛して支持したと考える方が自然であろう。「源頼朝と大江広元で、どちらが悪賢いか」と考えた時、ドラマ的には「源頼朝の方が凄い」とした方がいいのでは? 上に立つ者は、いい面でも、悪い面でも、下の者より凄くあって欲しいと思う。(心のバランスを測る天秤があるとして、いい面が大きければ大きい程、悪い面も大きくないと精神が崩れると思う。)
最近、思うのは、
「時代考証の3人の仕事って何?」
である。

第13回。
金目鯛が登場した。平安時代の人には未知の食材である。金目鯛の初見は明治時代だと思われる。
以前、小和田先生が時代考証の時、鍋料理のシーンで「この時代に白菜はない」と諌言されたという話を思い出した。白菜の初見は、明治8年(1875年)の博覧会に於ける清(中国)からの出品物であり、日清戦争の時に種を持ち帰って、全国に広まったとされる戦国時代には無かった野菜である。
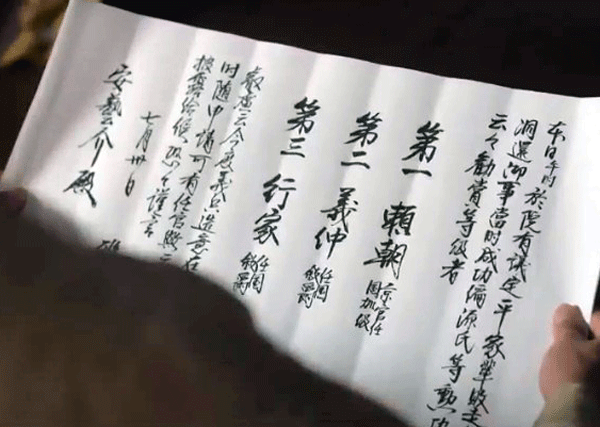

第14回。
論功行賞の文書が、本人(鎌倉殿)宛ではなく、「安芸介殿」宛である。
「三善康信から源頼朝宛の連絡便」という設定でも良かったと思う。
源義経の腰越状は、本人(鎌倉殿)宛では読まれないとして、「進上因幡前司殿」(大江広元)宛に送られた。アイドルへの手紙を、本人宛ではなく、所属事務所に送るようなものか(違うだろ;)。
日付は寿永2年(1183年)7月30日。安芸介・大江広元は、
・寿永2年(1183年)4月9日、従五位上に昇叙。
・元暦元年(1184年)、鎌倉に下向。9月17日、因幡守に任官。
であり、寿永2年7月30日には京都にいて、従五位上である。
・従五位上:大国守
・従五位下:上国守(因幡守など)
・正六位上
・正六位下:大国介、中国守
・従六位上:上国介(安芸介など)
・従六位下:下国守
宛先が書かれていない「寿永2年10月宣旨」の発給月日は、10月4日ではなく、10月14日である。
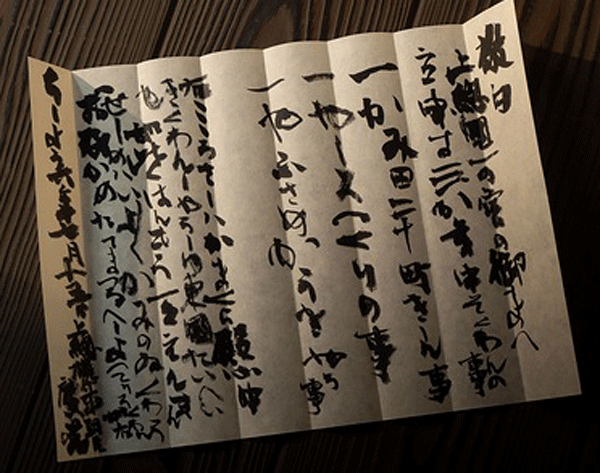
第15回。
上総国一宮・玉前神社の境内に、この願文を刻んだ石碑がある。有名な願文なのに、なぜ文面まで子供レベルに変えたのか理解できない。字が子供の字であっても、文章は大人の文章のはずである。
発給文書は右筆が書くが、署名と花押は本人が書く。本文が子供の字であっても、書き慣れた署名と花押は上手いはずである。
願文は玉前神社に奉納した鎧から見つかったが、ドラマでは屋敷にあった鎧から見つかったと変更された。なぜ? そもそも、願文って、神社に奉納するものであって・・・。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
