
内藤信成
1.松平広忠の子供たち
徳川家康の実父・松平広忠(1526-1549)の子の数は、
・一男一女(『武徳大成記』)
・二男二女(『参松伝』)
・二男三女(『改正三河後風土記』『徳川実紀』)
・三男三女(『御九族記』)
とバラバラです。
■江戸幕府公式文書『徳川実紀』
広忠卿の御子は、竹千代君の外に、男子君一人、女君三人おはしたり。御男子は家元、後に康元、生涯足なえて世に出で人にも交り給はず、後に「正光院」とをくりまいらす。
女君は、多刧姫と申し、桜井の松平与一忠政に嫁せられ、後に、その弟・与一郞忠吉にあはせ給ひ、其後、また、保科弾正忠光に降嫁せらる。(『藩翰譜』に正光に降嫁ありし烈祖の御妹は、伝通院殿、久松がもとにて設け給へる所といふは誤なり。)その次は市場殿とて、荒川甲斐守頼持(又、義虎)に嫁し給ひ、後に、筒井紀伊守政行にとつぎ給ふ。その次は矢田姫と申、長沢の源七郞康忠に嫁したまひき。
広忠卿には、この後、田原の城主・戸田弾正少弼康光の女をむかへ給ひしかど、この御腹には御子もましまさず。
福釜の甚三郞信乗が子・兵庫頭親良といへるも、桑谷の右京大夫忠政といへるも、内藤豊前守信成といへるも、実はこの卿の御子 なりしともつたへたり。
実際は次の六男二女?
正室・於大の方(水野忠政の娘)との間に生まれた子
・徳川家康 1543-1616
継室・真喜の方(戸田康光の娘)との間に生まれた子
・市場殿 ?-1593(一説に平原正次の娘との間に生まれた子)
側室・於久の方(大給松平2代乗正の娘)との間に生まれた子
・松平忠政 1541-1599
・樵暗恵最 1543-1567:松平乗勝の子・松平清成?
側室・平原正次の娘との間に生まれた子
・矢田姫 1547-1603
母不明
・内藤信成 1545-1612(母:於大の方の侍女?)
・松平親良 1545-1623(母:於大の方とも、於大の方の侍女とも)
・松平家元 1548-1603(母:御湯殿方女中?):架空の人物?
★於大の方妊娠説:松平広忠が於大の方と離婚し、刈谷へ帰したのは天文13年(1544年)のことで、於大の方が久松俊勝と再婚したのは天文16年(1547年)である。3年間、於大の方がどこで何をしていたかというと、「椎の木屋敷」(愛知県刈谷市銀座6丁目)で暮らしていたというが、「椎の木屋敷」に入る前、なぜか酒井正親の屋敷に滞在しており、ここで松平広忠の子を出産したという説がある。
また、滞在したのは酒井屋敷ではなく、松平信乗(西福釜松平氏)の屋敷であり、生まれた子が松平親良(天文14年(1545年)3月2日生まれ)だとも。
--------------------------------------------------------------------------------------
今回取り上げる内藤信成は、父母ともに不明ですが、父は松平広忠、母は於大の方の侍女であろうと考えられています。いずれにせよ、容姿が徳川家康そっくりだったそうです。
また、徳川家康は、安寧寺の住職・清庵和尚に内藤信成を「三男」と紹介していますので、徳川家康の頭の中は、
・長男(1543年生まれ):徳川家康(母:正室・於大の方)
・二男(1543年生まれ):樵暗恵最(母:側室・於久の方)
・三男(1545年生まれ):内藤信成(母:於大の方の侍女?)
だったのでしょう。樵暗恵最は、徳川家康と同じ日の同じ時間に生まれており、一説に於大の方が生んだ双子で、於久の方に預けたとか。というのも、於久の方が天文10年(1541年)には40歳前後だったとする記録があり、於久の方を当時15歳の松平広忠の側室とはするのは不自然であり、松平忠政と樵暗恵最の2人は、於久の方と松平広忠の子ではないとする説もあります。特に樵暗恵最は、於大の方が生んだ双子だと考えられています。
内藤信成は天文14年5月5日生まれであるので、刈谷へ天文13年に返された於大の方の子であれば、於大の方は妊娠中に返されたことになる。とはいえ、於大の方が生んだのは松平親良であり、内藤信成は、於大の方と結婚している間(しかも妊娠中)に、於大の方の侍女に手を付けて出来た子であるとされ、松平広忠は、於大の方や水野氏に申し訳なく思い、我が子とは承認しなかった(侍女には手を付けなかったと主張した)という。
2.内藤信成の生涯
(1)内藤信成の出自
内藤信成は、天文14年(1545年)5月5日に生まれました。
父母は誰なのか分かっていません。
父親
説①松平広忠
説②島田景信→内藤清長の養子
母親
説①於大の方の侍女(小野次郎右衛門の娘)
説②於大の方の侍女(内藤清長の娘)
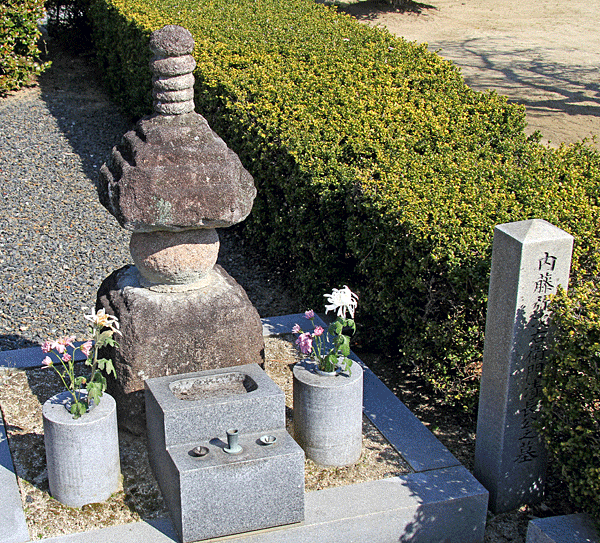
内藤信成の出自については、「松平広忠が於大の方の侍女(内藤清長の娘)に手を付け、妊娠したまま矢作の島田景信(土岐島田氏)と結婚させ(「拝領妻」)、子・信成が生まれると、「松平広忠の子・信成をどう扱うか」と会議が開かれ、嫡男のいない内藤清長の嫡養子とすることに決められた。しかし、翌年(天文15年)、内藤清長に長男・内藤家長が生まれたので、内藤信成は、家督を義弟・内藤家長に譲り、自分は新たな内藤家(信成系内藤家)を興した」という説が有力です。(上の写真は「内藤弥次右衛門清長公之墓」)
■新井白石『藩翰譜』
豊前守藤原信成は(初三左衛門と申せしなり)弥二右衛門清長が二男、実は参河国の住人嶋田の何某が子、清長取りて子とせしと申なり。信成が母は、岡崎贈大納言家の寵女にて懐妊せしを、嶋田久左衛門景信に給ひ、三月を過て信成をうむ。是れ天正十四年の事なり。清長、岡崎殿の御子と知てければ、むつきの内より取りて養ひ、弘治三年、信成十三歳の時、徳川殿に見参させければ、御身近く召仕れ、三左衛門信成と召されき。正しく徳川殿同父異母の御弟なりと云ふ。
──弘治三年、信成十三歳の時、徳川殿に見参
弘治3年(1557年)、内藤信成(13歳)は、松平元信(後の徳川家康)に謁見しました。あまりにも顔が似ているので、お互い驚いたそうです。
この時、「元信」の「信」の1字を与えられて「信成」と名乗り、松平元信の近侍となって駿府人質屋敷で暮らしました。(「成」は、「内藤正成」の「成」という。)
※松平元信:「元」は今川義元の「元」であるが、「信」は織田信長、武田信玄に通じるとして、尊敬する祖父・松平清康の「康」を使って「元康」に改名した。後に今川氏を離れて「元」を捨て、源義家の「家」をとって「家康」と改名した。
(2)初陣
弘治4年(1558年)2月5日(2月28日に「永禄」に改元したので、2月5日は永禄元年ではなく弘治4年)の松平元信の初陣「寺部城(愛知県豊田市寺部町)攻め」には随従しなませんでしたが、続く「西広瀬城(愛知県豊田市西広瀬町)攻め」には随従しました。これが初陣です。
初陣以降、「小牧・長久手の戦い」の時は清州城の留守居役、「上杉征伐」「関ケ原の戦い」の時は沼津城と興国寺城の留守居役を命じられて参陣できませんでしたが、これら以外の戦いでは、参陣し、ほぼ全ての戦いで武功をあげました。
(3)安寧寺

徳川家康に、「聞法の師」と仰がれた安寧寺中興開山・清庵宗徹(静岡県浜松市西区村櫛町出身)は、井伊家の軍師と言われる龍潭寺(静岡県浜松市北区引佐町井伊谷)の南渓瑞聞の弟子とも、善水寺(静岡県浜松市西区伊左地町)の幢宗和尚の弟子(『善水寺過去帳』)ともいわれています。
徳川家康は、清庵和尚に学ぶと同時に、内藤信成を預けて、学ばせたといいます。
「清庵和尚は、東照神君(旧記に家康公と称し奉る)御帰依にて、国家の事、大小となく、毎時の吉凶を為され、問ひ玉ふには、必ず清庵に請け玉ふ、云々」(『安寧寺旧記』)
清庵和尚は、徳川家康に、仏法だけではなく、兵法も教えたとされ、軍師としてか、陣僧としてか、しばしば参陣したそうで、「三方ヶ原の戦い」の時の「布橋」の策(陣幕を橋のように犀ヶ崖に架けて武田軍を落とす作戦)を考えたのは、清庵和尚だとされています。

また、逃げてきた徳川家康を「音無坂」を経て、浜名湖を舟で渡し、実家のある村櫛に落ち延びさせたとも伝えられています。通説は「徳川家康は三方ヶ原から直接、浜松城へ戻った」ですが、浜松には「○○で1泊し、翌日、浜松城へ戻った」とする伝承が複数有り、「翌日帰城」が史実だとしても、1泊した場所を決められません。もっともらしいのが、徳川家康の感状が残っている伊場の庄屋ですが、徳川家康文書には偽文書が多いので、鑑定待ちですね。(偽文書が多いのは、徳川家康も自覚していて、花押を頻繁に変えています。おかげで、花押を見るだけで、書かれた年がだいたい分かります。)
安寧寺(臨済宗妙心寺派)は、内藤信成の子孫からの寄付(祠堂銭)を使って金貸し業を行い、裕福だったそうですが、明治5年(1872年)の放火で、山門、通用門、土蔵以外は焼失してしまいました。ただ、本堂の寺宝は、全て持ち出しせました。特に重さ28貫500目(107kg)の清庵和尚坐像を、村一番の力持ち・楠野吾三郎が抱えて持ち出したことは語りぐさとなっています。また、焼け残った江戸時代の山門は、大正12年(1923年)、建仁寺(京都市東山区小松町)に移築され、「望闕楼」と呼ばれています。
安寧寺には、清庵和尚坐像以外に、徳川家康公坐像、於大の方坐像、内藤信成の位牌、徳川将軍歴代の位牌があります。雪舟の名画などの寺宝もあったそうですが、昭和13年(1938年)に全て盗まれ、犯人は逮捕されたものの、売られた後で、寺宝はまだ寺には戻ってきていません。
なお、よく似た名の内藤信成開基の護国山安泰寺は、新潟県村上市塩町のお寺です。
(4)人食い馬のエピソード
内藤信成が若い頃、人食い馬を素手で生け捕りにしようとするも叶わず、食われそうになったので、仕方なく脇差で馬の喉笛を斬ったそうです。
この時、内藤信成は、「他人の馬を殺してしまった」と切腹しようとしましましたが、周囲の人が制止し、徳川家康は、この話を聞いて、「普通の馬では無く、人を食べるような馬なのだから仕方がない」と許したので、人々は徳川家康の名裁きに感心したそうです。(『甲陽軍鑑』)
■新井白石『藩翰譜』
信成若かりし時、或人の馬の勝れて力あつて、あたりを払ひ、人を喰ふが、放れ出て走り来り。信成に行きあひ、人の如くに立て、信成を無手と抱きて、ひたぐひに喰ふ。信成、さるしたゝか者にて、「いかにも組み伏てくれん」と思ひけれども、叶ふべからず。既に喰殺されんとする時に至りて、是非なく、差添刀引抜き、馬の喉ぶえかき切て捨つ。
信成、辛き命生きけれど、馬にあうて、力及ばで切たるを口をしき事に思ひ、且は「人の馬殺しければ、腹切ん」とするを、人々押止む。徳川殿、聞召し、「尋常の馬牛の頭斬りつたるなどとは品大きに変れり。何か苦しき。自害に及ぶべからず」と制し給ひしを、隣国の人、伝へ聞て、御裁断の程を感ぜしといふ事、『甲陽軍鑑』に出づ。
(5)義弟・内藤家長
内藤家では、内藤正成(内藤信成の父・内藤清長の弟・内藤忠郷の次男。享禄元年(1528年)生まれ)が「徳川十六神将」、内藤信成と内藤家長(内藤信成の義弟)が「徳川二十八神将」にランクインしています。
永禄12年(1568年)1月22日の夜、天王山の掛川古城に陣取っていた徳川家康は、今川氏真と朝比奈泰朝が籠もる掛川城を攻めました。この時、内藤信成は、鉄砲で左股を討たれました。動けない内藤信成に迫り来る敵を、弓の名手で「無双の弓手」と称えられた内藤家長が射殺し、岡田甚左衛門が助け出したそうです。徳川家康は、成瀬国次を使者として、武勇を褒めると共に、怪我の具合を確かめさせたそうです。
■『寛政重修諸家譜』「内藤信成」
12年、今川氏真が家人・朝比奈備中守泰能がこもるところの遠江国掛川城を攻たまふのとき、敵兵、城外に出で、防ぎ戦ふといへども、しばしば敗走し、味方、進みて天王山に陣す。信成、敵城に近寄て、挑み戦ふのとき、城中より放つところの鉄砲、信成が左の股にあたる。このとき、敵兵3人、すゝみ来りて、信成をうたんとしてあやうかりしば、弥次右衛門家長、弓をもつて敵を射、また、家臣・岡田甚左衛門某、馳来りて、敵を追しりぞけ、遂に命を全うすることを得たり。のち、成瀬藤八国次をもつて、其功を感賞したまひ、且、其疵を問せたまふ。
内藤家長は、「関ケ原の戦い」の前哨戦である「伏見城の戦い」で亡くなっています。偶然でしょうが、内藤信成の領地・長浜にある真言宗大谷派の「長浜別院」こと無礙智山大通寺(滋賀県長浜市元浜町)には、伏見城の遺構(本堂(阿弥陀堂、伏見城の殿舎)と大広間(附玄関)。共に国指定重要文化財)が移築されています。
(6)一言坂の戦い
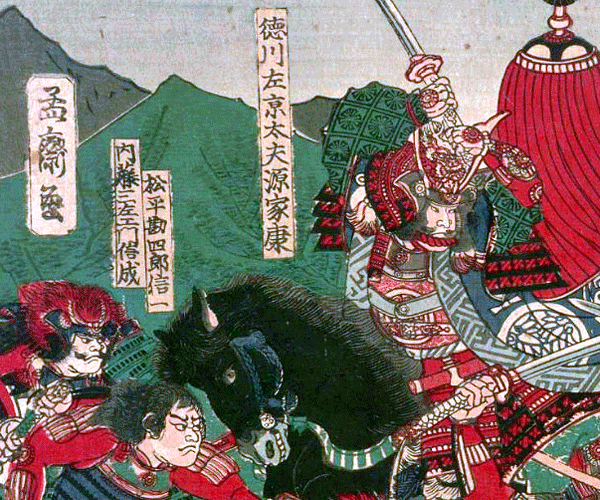
「三方ヶ原の戦い」(1573年)の前、「久野城(静岡県袋井市鷲巣)が武田信玄に攻められている」と聞いた徳川家康は、本多忠勝と内藤信成を大斥候(1000人の偵察隊)として送り、自分自身も3000人の兵を率いて出陣したそうです。本多忠勝と内藤信成が「徳川軍8000人のうち、ここにいるのは半分の4000人。敵は多数。勝ち目が無いので、一旦、退却しましょう」と報告したので、退却することにしました。天竜川を渡る手前で追いつかれ、図らずも戦いとなったのが、「三方ヶ原の戦い」の前哨戦となった「一言坂の戦い」です。なお、この戦いでは、殿(しんがり)を務めた本多忠勝が名を挙げました。
その後の「二俣城救援」では先鋒を務めて、敵(武田軍)の物見(偵察兵)を射殺しました。続く「三方ヶ原の戦い」では、殿(しんがり)を申し出ています。
■『寛政重修諸家譜』「内藤信成」
3年10月、武田信玄、遠江国に兵を進め、多々羅、飯田の両城を抜。よりて浜松より4000余騎、三野川に出張し、すでに先軍、一兵坂にをいて武田が兵と接戦すときに信成がいはく、「我兵8000のうち、こゝに出るもの半なり。武田が大兵に敵がたし。強て一戦をとげば、味方、利を失ふべし。速に兵をおさめむ事を欲といへども、其一人の力に及ばず」とて、本多平八郎忠勝、大久保七郎右衛門忠世等と議す。二将、これを「しかり」として、相ともに後殿となり、奮戦し、つゐに兵を引あげ、浜松にかへる。東照宮、信成等が勇戦を賞せらる。
(7)長篠の戦い
天正3年(1575年)5月21日の「長篠の戦い」の時、織田信長が内藤信成を遠くから見て、「誠に先駈(さきがけ)の猛将、奇異の勇士なり」と賞賛し、「近くでよく顔を見たい」と呼び出しました。面頬(マスク)を取った顔は、徳川家康にそっくりだったので、織田信長は驚かれたことでしょう。(『寛政重修諸家譜』に「御紋置たる朱塗の御頬当を賜ふ」とあります。なお、村上市郷土資料館「おしゃぎり会館」(新潟県村上市三之町)に展示されている面頬は、三つ葉葵の紋が消えていますが、徳川家康から拝領した面頬である可能性が高いとのことです。)
■『寛政重修諸家譜』「内藤信成」
天正3年5月、「長篠の役」に、大久保忠世、治右衛門忠佐等とともに御先手の侍大将をうけたまはりて、勝頼が兵2000余騎に備へ、進み戦ふ。信成、鉄炮の士卒等に下知をつたへて曰く、「敵、今、馬を馳せて、直に来る。其鋒、甚鋭し。溝塹を前に隔て、5歩、10歩に引請て、能ためて放つべし」と。士卒等、指揮にしたがひてこれを射るに、敵兵、300人ばかり、声に応じて倒る。其余の兵、魂をうばはれ、隊伍を乱して敗走す。特に信成、金の軍配団扇に七曜を黒く点せる指物を用ふ。織田右府、これを見て、其名を東照宮にとはる。「これは、内藤三左衛門」とこたへたまふ。右府のいはく、「誠に先駈の猛将、奇異の勇士なり。彼が面頬をぬがしめ、能其の面を知む」。則、信成をして面頬をとらしめ、右府にまみえしめたまふ。東照宮も其軍功を賞せられ、「感状をあたへらるべし」といへども、「信成が武勇はこれに限らざれば、今更感状をあたふべきにもあらず」とのたまふ。
(8)小田原征伐
天正18年(1590年)4月、「小田原征伐」の時、豊臣秀吉は、内藤信成の「武備」を感じ、接見を許し、陣羽織と青江の刀(備中青江派作の日本刀)を自ら与えました。
また、徳川家康の書状を持って、使者として伊豆韮山城城代・北条氏規に会い、降参を勧めました。徳川家康の駿府人質時代、内藤信成も人質屋敷で共に暮らしています。『武徳編年集成』によれば、徳川家康の人質屋敷の隣が北条氏規の人質屋敷だったそうなので、内藤信成と北条氏規は顔見知りだと思われます。
■『寛政重修諸家譜』「内藤信成」
18年4月、小田原陣のとき、信成、領地より馳来るの処、太閤、これを見て、其武備を感じ、拝謁をゆるされ、着料の陣羽織及び青江の刀を手づからあたへらる。
(9)長浜
慶長11年(1606年)、「上方筋の警衛と北陸から京都へ向かう道の監視に」と近江国4万石に移封され、廃城となっていた長浜城を徳川家康からいただいた銀5000枚を使って改修し、居城としました。(「天下普請」(江戸幕府が全国の諸大名に命令して行わせた土木工事)ではなく、美濃、飛騨、近江国の3ヶ国での改修工事でした。)
これまでの居城だった駿府城には、徳川家康が入り、「駿府の大御所」として、大御所政治を始めました。
長浜というと、浅井長政、豊臣秀吉、石田三成って感じですけど、内藤信成も頭に入れておこう。
■『徳川実紀』
内藤豊前守信成、駿府を転じて、江州長浜の旧城をたまひ、城廓修造の料として銀五千枚を下され、美濃、飛騨、近江の役夫をして営築せしめらる。
そのとき、「汝にこの地を給ふ事は、上方筋警衛、かつ、北越より京摂(きょうと)の要路たれば、それを監せしめられん為なり」と仰せ下さる。
内藤信成の人生は戦い漬けでしたが、どうも本人がそれを望んでいたようです。自分の出自を恨み、「自分の居場所は戦場(いくさば)にしかない」として、怒りの矛先を戦(いくさ)に向けていたのかもしれません。徳川家康の弟なのに、ちやほやされることは無く、周囲の人々には「顔がそっくり」と好奇の目で見られました。
養子ですから領地はありません。しかし、新たな内藤家(信成系内藤家)を興し、4万石の大名になったのですから、大したものです。
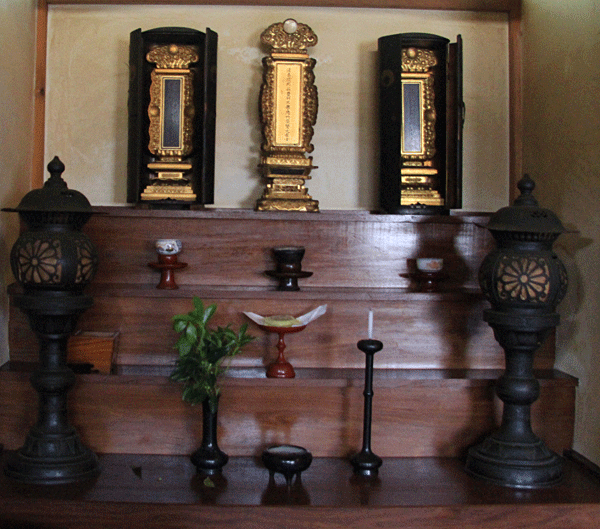
慶長17年(1612年)7月24日、長浜城において68歳で病没。法名「法善院殿陽竹宗賢大居士」。今は神となって藤基神社(新潟県村上市三之町)に祀られています。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
