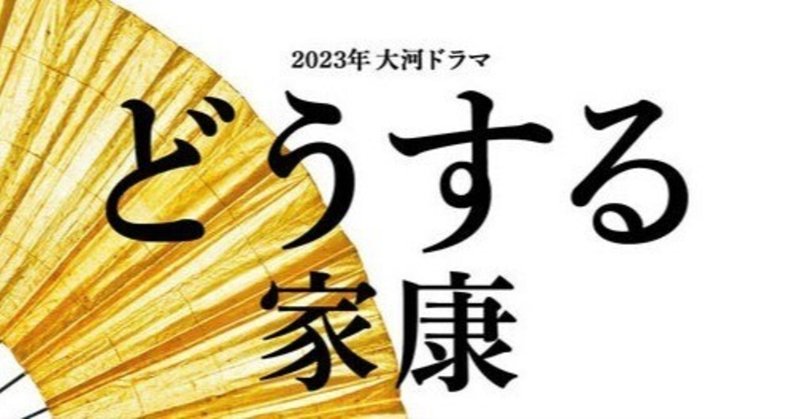
瀬名姫(築山殿)に関する本
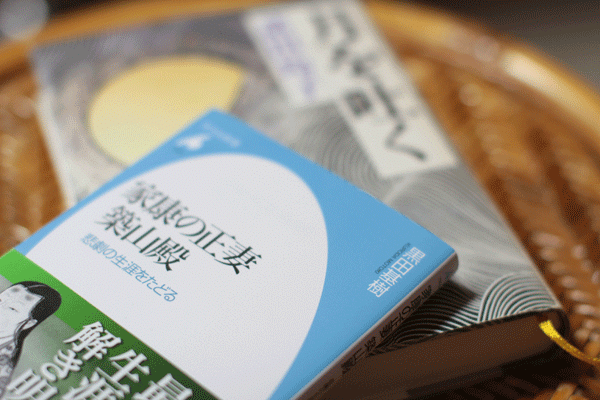
【古文書】
『築山御殿御伝記』
『御前谷由緒』
『西来院由緒口上書』
『西来院廟堂記』
【研究書】
久野仙雨『築山御前紅涙史』(私家本)
昭和3年に築山御前350回忌を執行した西来院29世・戸田義参『築山御前考』
小山正 『戦国哀史 築山御前』(私家本)1958
関口正八&柳史朗『築山御前考 徳川家康の正室』→『夕顔記』1979所収
冨永公文『築山殿と徳川家康 徳川氏の謎と伝説』(トレンドライフ)2009
黒田基樹『家康の正妻 築山殿』(平凡社新書)2022
【小説】
榊山潤 『築山殿行状』(文祥社)1958
阿井景子『築山殿無残』(平凡社)1983
諸田玲子『月を吐く』(集英社)2001
森清英 『家康の夫人築山殿秘録』(新風舎文庫)2004
【その他】
歌舞伎『築山殿始末』(1953)→TV『家康無情』1963/『築山殿始末』1966
浜松市広沢町の西来院は藤棚と築山御前の廟で知られている。寺院内に一歩踏み入ると、ここが市内かと思われるほどに閑寂である。
墓地にはうっそうと茂った古木が群生していて、四百年前の面影を残しているように思われる。その墓地の奥に、築山御前の霊を祀る「月窟廟」がひっそりとしたたたずまいを見せている。昭和五十二年に荒れ果てた廟を悲しんだ一婦人の浄財寄進により復元されたものという。まだ木肌は新しく、往時を伝えるよすがとてないものゝ、質素な中にも気品を漂わせる入母屋造りの建築である。ただし、夫君を祀る日光霊廟の、あの華麗さとは較ぶべきもない。
築山殿、幼名は瀬名、嫁して駿河御前、後、岡崎城内へ移ってからは築山御前と呼ばれた。当時今川家の人質となっていた後の家康と結婚し、長男信康、続いて長女亀姫を駿河の地で儲ける。
江戸中期の郷土雑録「曳馬拾遺」によると、若き日の築山殿は「そのかたち人にこえていとめでたく みやひやかなる御よそほひおわしましければ…」と記され、西来院に残されている画像からも、気品のある美人であったことがうかがわれる。
駿河における家康夫婦は二児に恵まれ、一応人並に幸せであったと云えるのではなかろうか。家康の人質生活がそのまゝ続いたら、いささか権高い妻に時として嫌気がさすことはあっても、二人にとっては平凡な月日が流れたであろう。然し、戦国の世は激動する。
今川義元が上洛を決意し、数え年十九歳の家康も先陣を承って、兵を大高城に進めたが、大将義元は織田信長に桶狭間で討たれ、今川勢は総崩れとなった中で、家康は岡崎城に入り、長い辛苦の年月に終止符を打ち、岡崎党が夢に見た独立を果すこととなる。築山殿母子は岡崎城に迎えられた。
築山殿にとって岡崎は決して安息の地ではなかった。九才になったばかりの息子信康に信長の長女徳姫を嫁に迎えねばならぬことになった。築山殿にとって信長は主家今川の憎き仇敵である。誇り高き築山殿にとっては耐えられぬ屈辱であったろう。而も、自れの哀しみや憤りを訴えるべき夫・家康は元亀元年(一五七〇年)浜松城へ移ってしまう。
この頃から岡崎城内には家康の生母於大の方が夫と共に住い、女三代にわたる三つ巴の争いが城中に渦巻くことになる。然し、この陰湿な争いは徳姫から父信長に送られた訴状によって悲惨な終止符が打たれてしまう。母築山殿が信康に申し勧めて甲州と内通をしたことを中心に十一ケ条にわたって述べられ、今から思うと、それほど騒ぎ立てることのない、いわば嫁の愚痴ともとれるものである。その嫁の愚痴を信長は政治的に利用した。信長の断は「信康に死を賜う」ことであった。
自れの蒔いた種が元で、今度は息子まで仇敵によって殺されねばならぬとは。築山殿の心中はどんなであったろう。
やがて、天正七年(一五七九年)初秋の頃家康に召されて、築山殿は浜松の地に向かう。
築山殿とて戦国の女性である。既に心は定まっていたであろう。
私は築山殿柊焉の地を訪れた。この地は「御せん谷」で、「曳馬拾遺」によれば、「此谷は今みつ山の北にある谷なり」と記され、小薮が群生していた所から「小薮の里」とも呼ばれていたという。今は市の医療センターの高層ビルが建ち、駐車場が設けられ、往時の面影は全く見られない。築山御殿伝記によると、「御膚には皆紅のしんい、その上に黄のしまぎぬ、なお白絹の衣のうちかけ、香をたいた」晴れ着姿で「石川義房・岡本時仲、野中重政及び多くの侍女を従え給い」三ケ日から浜名湖を渡り、川を漕いで佐鳴湖へ出、この御せん谷目指してやってきた。岸辺には一行を待ち受ける浜松からの使者がいた。岸辺に一歩を印した時、使者の口から「君命により築山殿に死を賜う」と告げられたのである。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
