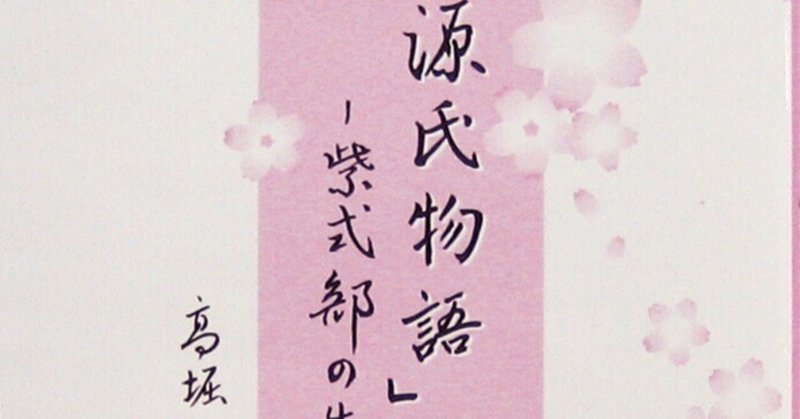
第82回 高松方・顕信(あきのぶ)の出家
道長が三条帝を苦手にしていた理由の一つに、三条帝が道長の父兼家によく似ていた事だと言われます。三条帝にしてみれば兼家は祖父ですから隔世遺伝で似ていて当たり前なのですが。
道長は若い頃、乱暴狼藉をしていてよく喧嘩していました。その度に兼家から怒られてあわや絶縁という所までいきました。三条帝を見るたびにその事を思い出したのでしょうか?
道長の息子たちはほとんど大人しいのですが、一人四男の能信(高松方)が乱暴したり強姦まがいの事を手伝ったりと道長からよく謹慎を喰らっていたみたいです。
三条帝が大嘗会(だいじょうえ:即位してすぐの新嘗祭)をする予定にしていた秋、三条帝の父・冷泉上皇が62歳で崩御され、翌年に延期となりました。しかし人々の反応は冷たく、「折悪しく亡くなられたことよ」という感じでした(『大鏡』)まあ香子も世評を見て『源氏の物語』に不義で生まれる天皇という設定にしたのでしょうが。
翌寛弘9(長和と改元:1012)年正月16日、とんでもない事が起こりました。道長の三男・顕信(19歳)が突如比叡山に出奔したのです。
高松方に生まれて、前途を悲観したのかどうか。出奔はあるといえばありますが、今を時めく道長の御曹司でそういう子が出るというのは京の人々にとって驚きでした。
前述の能信(18歳)などは「日頃から高松方を差別するからだ」とでも思っていたでしょうか。
4月になって道長は叡山に向かいますが、途中で僧兵たちから石を投げられ、這う這うの体で帰ってきます。仏教勢力の強さを香子も感じました。
『源氏の物語』では、真面目一徹と思われた夕霧が、柏木の未亡人女二宮を世話している内に恋心が芽生え、古妻雲居の雁が怒って実家に帰ってしまうという一幕があります。
「男はそういうものよ」という香子の声が聞こえてきそうです。
紫の上はまたしみじみと感じ入ります。「しっかりした実家があるからそういう事ができるのだ。私には帰る実家もない・・・」と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
