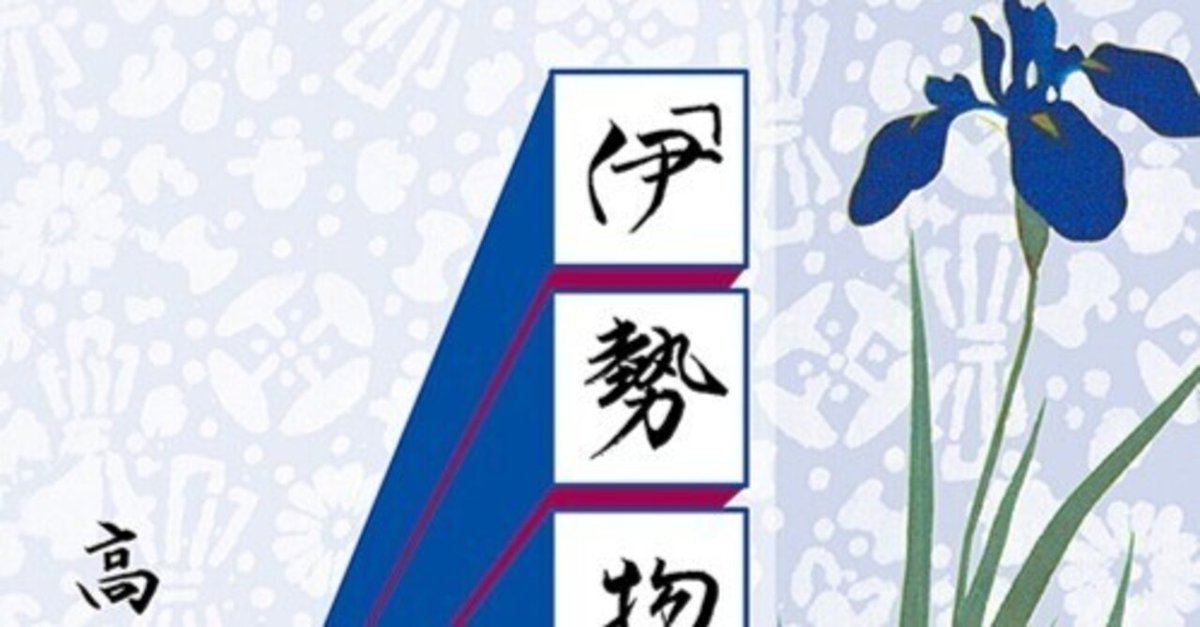
第81回 道真「このたびは幣もとりあへず手向(たむけ)山」
宇多天皇が醍醐天皇に譲位した寛平9(897)年7月、入内を巡ってトラブルが起こります。
摂関家の若き当主である藤原時平(27歳)は醍醐天皇(13歳)の元へ、妹・穏子(12歳)を入内させようとします。摂関家の姫が一番に入内するのは当然の事でした。
しかし思わぬ所からストップが入ります。それは宇多上皇の母后・班子女王(65歳)が娘の為子内親王(年齢不明)を先に入内する事を希望しその通りになったのです。穏子は4年後の道真左遷(901年)まで待たされる事になります。そして時平一派はこれも道真の妨害だと思い込み恨むのでした。
翌年2月、在原業平の長男棟梁(むねやな)が49歳で亡くなり、娘二人がなぜか中納言国経(基経の異母兄・71歳)に養われる事になり長女はやがて妻になります。その女性は後年、時平に奪われてしまいます。(谷崎潤一郎氏の『少将滋幹の母』に詳しいです)国経は廃后となった高子の大夫を長年務め、対立した基経とは違って懇意だった様です。そのせいか業平の息子・棟梁とも親しかったのでしょうか・
そして10月、譲位の打ち上げ旅行なのでしょうか、宇多上皇が、道真以下群臣100名ほどを伴って季節も良く、12日間の吉野旅行に行きます。
もちろん宇多上皇派ばかりを伴ったものでした。そこで道真は旅に必要な幣(ぬさ:神々に捧げるもの)を忘れたのですがすかさず有名な歌を詠みます。
「このたび(度と旅をかける)はぬさもとりあへず手向山 紅葉の錦 神のまにまに」
今回、幣を忘れてしまったのですが、その代わりこの紅葉の素晴らしい景色を神に捧げます。という意味ですが色々な解釈がありますが、別に景色は道真の私有物ではないのに、それを捧げますというのは、道真絶頂の心境を詠んだものだというものもあります。皆さんはどう思われますか?(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
