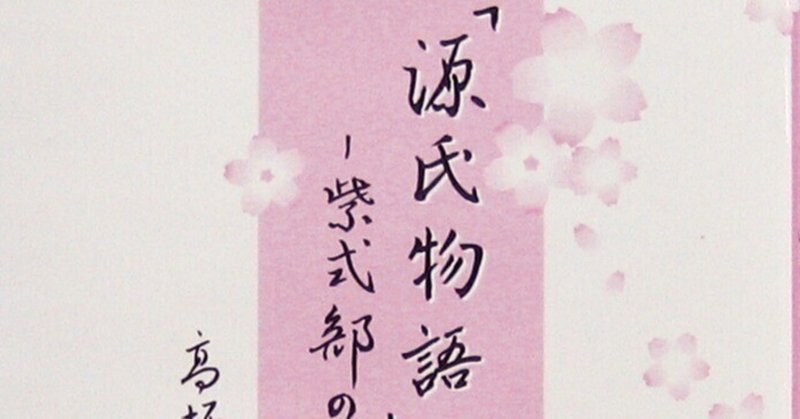
第93回 この世をば
小一条院が寛子の婿になった2カ月後の寛仁2(1018)年正月3日、後一条天皇(敦成親王)は11歳で元服しました。父の一条天皇も11歳で元服し、その年に定子が入内し、中宮となっています。
正月7日、皇太后彰子は、前年遵子が亡くなったため、空位となった太皇太后に昇格します。
そして3月、倫子が産んだ三番目の姫、威子が女御として入内します。威子は天皇の叔母であり20歳と9歳も上ですが、小柄なのでよく似合ったといいます。
4月には、三条天皇の時に消失した内裏が新造されます。
そして10月16日、中宮だった次女妍子が皇太后、そして威子が中宮になるのでした。道長の倫子方の娘が3人とも后になったのです。
高松方の能信は、「うちの寛子は即位の見込みのない小一条院の妃だったのに」と内心不服です。
そして10月22日、三人の后が道長の土御門邸に行啓します。
天皇は外孫、東宮も外孫。そして「一家三后」-一つの家が三人も后が出るのは前代未聞です。宴で道長は嬉しさの余り、自画自賛の歌を詠みます。
「この世をば我が世とぞ思ふ 望月のかけたる事もなしと思へば」
これは実資の『小右記』に記録されています。実資は返歌を求められましたが、辞退し、そこに居る全員で三度復唱したということです。
まさに道長の絶頂の時だったでしょう。
11月には倫子方の4番目の姫、嬉子(12歳)が尚侍となり、東宮妃への準備を始めます。「一家四后」も夢ではありません。
しかしその直後、彰子を驚愕が襲います。20歳の敦康親王が病に臥し、危篤となったのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
