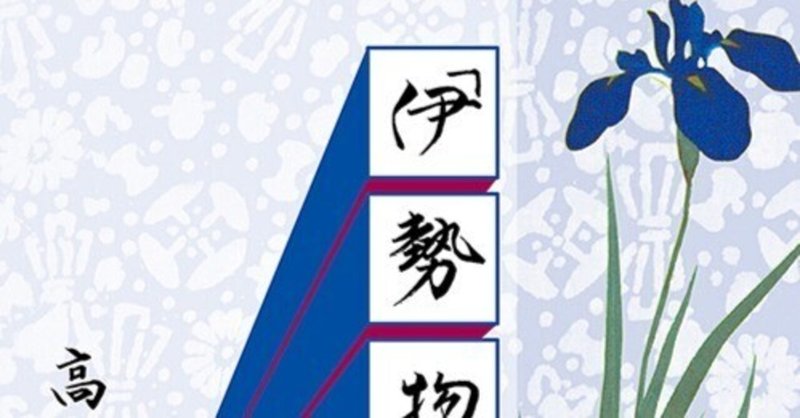
第100回 忠平の最後の仕上げ
宇多法皇崩御の後、9歳の朱雀天皇の摂政として揺るぎ無き地位に就いた忠平でしたが、まだ地固めをいろいろとしていました。
翌承平2(932)年、亡き惟喬親王の子、兼覧(かねみ)王が亡くなり、お金に困っている遺族に対して、忠平はその一等地の屋敷を買い上げ、長男の実頼に与えました。惟喬親王が小野に住む、小野宮と呼ばれていたので、実頼の家系は「小野宮家」とか「小野宮流」と呼ばれる事になります。
翌年2月、凡庸な次兄・仲平が59歳で、忠平から20年遅れで右大臣となりました。「咲くべき花は咲きにけり」と周囲は喜んでいましたが、忠平にとってこの5つ上の兄は問題ではありませんでした。ターゲットは、亡き時平の長男保忠(やすただ)です。
忠平の妹である皇太后穏子は、いまだに長兄時平の恩が忘れられず、ゆくゆくは保忠に政権を譲ってくれるよう、それとなく忠平に頼んでいました。
表面上、善人の忠平は微笑んでいましたが、何とかしなければならないと思っていました。
手は打っていました。保忠は男子に恵まれず、忠平の長男・実頼と保忠の妹を結婚させて、その間に生まれた次男の頼忠を保忠の養子としていたのです。これなら保忠の財産は頼忠のものになります。(頼忠の子としては公任[きんとう]が有名です)
承平6(936)年7月、47歳の保忠は病になりました。そして祈祷の僧たちが読経の中で、保忠の役職である「宮比羅(くびら)大将」の「くびら」をわざと大きな声で言ったのです。道真怨霊に怯える保忠は「縊(くび)る」と思い込んで絶命してしまいました。
忠平はまたも源光失踪事件と同じく尻尾を出しません。しかし私は忠平の影を感じます。
時平の次男顕忠は怨霊を怖れて邸内に閉じこもっており、三男の敦忠は恋に悩んで、男系はやがて絶えてしまいました。
忠平は完全に摂関家を乗っ取って満足で、時平の家系は歴史から消えた様に見えました。
しかしどっこい、時平の末娘が敦実(あつみ:醍醐天皇の同母弟)親王の妃となって、源雅実を産み、雅実の娘倫子は道長の妻となって、その長男頼通は摂政・関白となり、長女彰子は一条天皇の中宮となって、その系統は現在まで繋がっています。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
