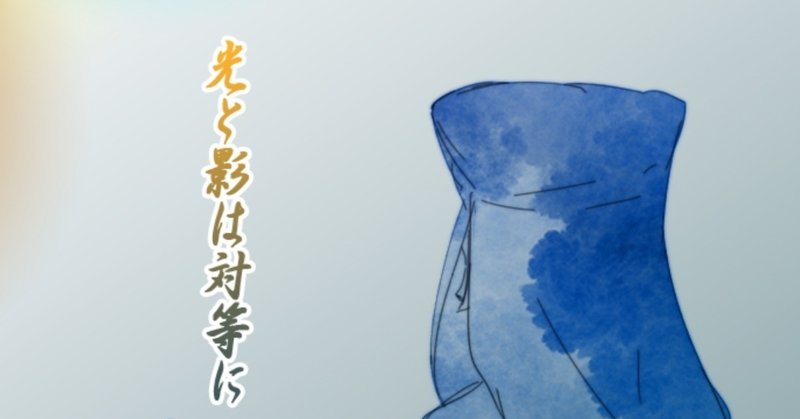
光と影は対等に
緊張した。
「トサキントっていうんだね、この子」
こんな感覚いつぶりだろうかと思う位に。
「釣ったら係の人に見せると良いんだっけ。探してこようかな」
あまり失礼のないように、敬語で、話を…したつもりだった。
違和感。
なんだろうか。勉強不足か…。分からないことがあるともやもやする。
「………あの」
当たり障りのないやり取りをして一瞬目線を逸らしたが、聞きたいことがあって顔を向ける。
彼は釣ったトサキントを、釣り竿と一緒に先へと行ってしまったようで、少し先の波打ち際を歩いていた。
その後ろを慌ててついていく彼のパートナーのダンゴロは、波に巻き込まれないようにと彼を追いかけていくのとで大変そうに見えた。
その様子をぼんやりと眺めるしかできなかった。
ついて行こうにもまだポケモンを釣り上げてもいないしなと海に視線を返す。
青々とした穏やかで広い海だったが、青衣の自分は濁っていた。
「…」
憧れている人物に会えたというのに、この感動が酷く申し訳ない気持ちになる理由を解説してくれるものなんて、ない。
「俺は…向いてないな」
釣り竿に反応がないまま時間が過ぎていくことに、ここまで影の薄いこともあるのかと考えながら釣り竿を固定し、青衣の内にしまっていた扇を取り出す。
模様の無い真っ白のそれを暇つぶしに固定した釣り竿の先端に乗せる。
扇の的が出来上がる。少し離れた場所に行き、その辺に転がっている石を手に取った。
「カーゲ!」
カゲボウズのすすは扇と石を持つ自分を交互に見て、応援してくれているのかふよふよと笑っている。
「…」
一つ。二つ。
石を投げてみるも当たらずに波の中へと消えていく。
これが"扇の的"の伝説なら、自分は切腹しなければならなかったなとため息。
そもそも、石ではなく弓矢で射貫く話なのだが。
「自分の名を射貫くには、覚悟が足りない…か」
もう一度石を投げようとした時、ふっと釣り竿に乗せた扇が落ちてしまった。
風でも吹いたか、と思ったがどうやら違うらしく。
「カゲっ!!」
すすが慌てて釣り竿の先端が揺れているのを目で教えてきた。
放置した方が良い結果が得られるのなら、最初から自分は。
「要らないんだよな」
釣り竿を掴み、慎重に糸を巻きとりつつ、最後は思い切り引っ張りあげる。
丸々とした黒い物体が海水から飛び出て宙ぶらりんとなる。
所々に赤っぽいピンクの突起があり、それと同じ色の瞳と目が合った。
ヌルヌルしてそうなその全身を目の前に、空白の間。
「………どうも」
あまり馴染みのないポケモンで何と無く挨拶をしてしまったが、とりあえずこのまま持っていこう。
そういえば、同室のパートナーに同じポケモンがいたなと思い出す。
ナマコブシ…だったか。でも色が違うのはどちらかが色違いの希少種か。
後で聞いてみるかと海に落ちた扇を拾ってきたすすと共に、その場を後にした。
――――――――――
三日目の夜。
今日は花火大会があるのだったか。
なんだかんだもう三日目で今日の演奏会が最後にもなる。
闇に溶けた黒衣の自分は始まりを告げる一発目の大輪の花を見送った。
輝かしい彩で空を飾っていくそれは、眩しかった。
でも、それ以上の感情が湧いてこない。
何故だろうか。いや、知ってはいる。認めたくはないだけで。
「…」
すすは横でキラキラと落ちていく花弁がこっちまで届かないかとそわそわしている。
無邪気でお気に入りのお花をいつの間にかつけて、この合宿が楽しくて仕方がないようで。
そんな様子が少し羨ましいとも見える。
――純粋で素直な気持ちが、自分から欠けている。
いつからかは分からない。分からないが、その気持ちを思い出したのも事実で。
彼――フィンと出会えて感動した。感動して、それで、お話もできて。
もう少しお話をしたいこともあったが、大勢の合宿参加者から一人を見つけるのは難しくて。
おかしな話だ。舞台に上がる芸能人で、一般のそれとは違うオーラは少なからず持っていそうなものなのに見つけられない。
忍者の話をしたが、まさか目指して…。役作り…。
表情にあまり浮かびはしない内心でもやもやしつつ、適当にその辺の草原に仰向けに寝転がって空を眺めた。すすが腹の辺りにちょこんと乗っかり同じく空を眺める。
大きな音がしているはずなのにとても静かに感じた。
数分の間そのまま眺めていると、不意に自分の足に衝撃があった。
痛いまではいかないが、何か固いものに当たった感触。
上体を起こして確認してみれば、そこにはダンゴロがいた。
「…(あれ、このダンゴロ)」
躓かせてしまい大丈夫かとそっと撫でると、驚いたのかびくりとしてプルプルしていた。
「カゲ~♪」
すすがダンゴロの隣に移動し、話しかけている。
ではこの子は…。
「お隣、良いかな?」
花火の打ちあがる合間から聞こえたのはフィンの声。
驚いて振り返り返答する前に、静かに隣に座ってきたのは釣りをした際に出会った彼だった。
「花火、綺麗だね」
「ぇ…あ、そうですね…」
花火を綺麗だと言っている彼は目を閉じている。
「あの後、君は何か釣れたかい?」
「一応…ナマコブシっていうのが釣れましたね」
「それは良かった」
会話が続いているようで続かない。自分で途切れさせているせいでもある。
遠慮しているといえば聞こえはいいかもしれないが、単に光に踏み込むのがダメな気がして。
「………あの」
「ん?」
「こんな機会、滅多にないので…お話しても良いですか」
「いいよ」
本当は聞きたいことがたくさんあった。些細なことから難しいことまで。
でも今一番話したいことはそのどれでもないと全て捨て、口から自然と零れるものを投げかけた。
「役者と素の違いは、知っている…つもりです。だから、俺が知っているフィンさんとここで出会ったディムナさんが全く違うのも分かってます」
「そっかー」
「…憧れる気持ちは変わらないんですが、その、違和感があって」
「違和感かい?」
あの時とは違って頭巾の布は垂れ下がったままである。
「…距離を感じるんです。当たり前なんですけど。あって当然ではあるんですが…」
光と影とは距離があるものだと思っていた時がある。
でも違う。光があるから影ができ、影があるから光ができると教えてくれたのは誰だったか。
「舞台での表裏一体…。ましてや同じ年齢の奴が、素のあなたにこうやって敬語で話して、距離を感じないわけないよなと…俺が、そう思ってしまって」
失礼に失礼を重ねているかもしれない。
舞台に立つ役者を知っている自分は、裏方を雑用にでもするかのような人も居て、なるべく波風を立てないようにするのも賢い生き方だとも教わった。
『脇役よりも位が低いんだから、ちゃんと役に立てるようにしろよ。あ、役にはならないかあはは』
直接自分が言われた言葉ではないが、耳にしたことがある罵詈雑言が蘇る。
誰も、何も、あまりの言葉に返せずにその役者には幻滅した。
色んな人間がいる。役者は"役"で、素は"人"だ。
それを混同して夢を見過ぎるのは良くない。相手にも自分にもダメージを与える手段となる。
「俺は夢を見ていたい側ではあります」
夢とは現実があってこそ成り立つもの。これも表裏一体の一つ。
「…」
静かに息を吸う。
俺だって今は舞台仕事をしているわけではないんだ。
顔に垂れる布を捲って、彼を見かけた時の勢いをまたここに。
「ディムナ、俺は合宿中は対等が良い。呼び捨てて呼んでほしい」
丁度打ち上げられた花の音で掻き消されてたら、なんて考えないことにした。
合宿中なんて、もうじき終わると言うのに馬鹿かもしれないと、後から振り返るのに時間は掛からなかった。
――――――――――
母親が俺にくれた芸名がある。
もし、舞台上で活躍することがあれば使ってほしいと贈られた名前。
『朔日(ついたち)』
語源は様々あるようだが、母が込めた思いはこうらしい。
元は月立ちという言葉からきている説がある。
"月立ち"の立ちは出現する、現れるといった意味。
月の満ち欠けで月日を数える際の、新月が表れる最初の日にあたる。
『新しく活躍するあなたが現れる度、色んな素敵な表現で満たしていけますように』
最期の贈り物は筆談で、とても優しい字だった。
空に浮かぶ月が次に新月になるときには、日進月歩の如く少しでも多く成長できれば月もまた満ちるだろうか。
思い出に応えるには、もう少し時間が掛かるかも…しれない。
なんて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
