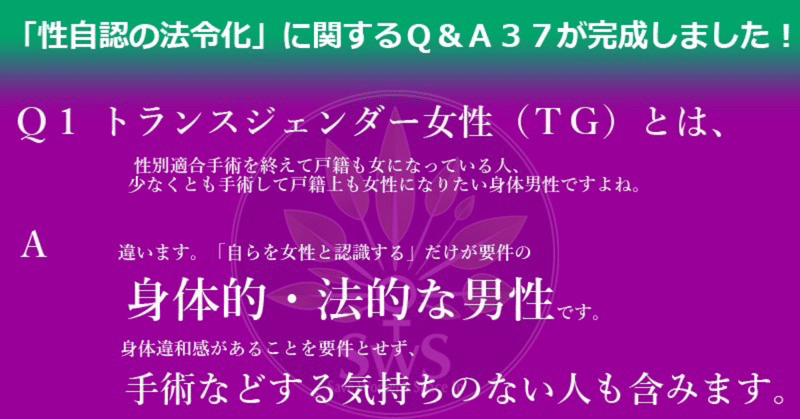
「性自認の法令化」に関するQ&A37が完成しました!(2023年2月)
2021年9月以来、修正しつつアップしてきた「性自認 ― 意外に誤解されていること ―25の Q&A」を、大幅に追加修正したものです。どうぞ入手して拡げて下さい。なお、上記の旧データは削除し、今回の最新版に上書きしました。
人に伝える場合には、言葉だけでは難しいものです。討論ではしっかりと論理と裏付けが必要であり、それを示さないで言葉の応酬だけして分かってもらうことはまずありません。
PDFをダウンロードされるか、パンフ「女性スペースの安心安全を」と同様に、無償で計20部の限り郵送できますので、希望される方はsave@womens-space.jpまで、送り先をご連絡ください。
(※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません)
広く伝えるためもっと多数をという方も、どうぞご連絡ください。
その際カンパを頂ければ、なおありがたいです。以下がカンパ振込先の口座情報になりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
↓
埼玉りそな銀行 ふじみ野支店 普通 口座番号0852451 女性スペースを守る会ーLGBT法案における「性自認」に対し慎重な議論を求める会ー
⭕️「性自認の法令化」に関する―Q&A37
2023.2.11 弁護士 滝本太郎
(意外に誤解されていること25 初出2022.4.6の修正更新)
Q1 トランスジェンダー女性(TG)とは、性別適合手術を終えて戸籍も女になっている人、少なくとも手術して戸籍上も女性になりたい身体男性ですよね。
A 違います。「自らを女性と認識する」だけが要件の身体的・法的な男性です。身体違和感があることを要件とせず、手術などする気持ちのない人も含みます。
ですから「トランス女性」と表現した方がより正確です。
なお、旧来は性別適合手術などした元々は男性だった女性を指すことがあり、今もその意味なのだとの誤解が一部にあるようです。
Q2 「トランスジェンダー女性」の定義を教えて下さい。
A それが定まっていないのです。「トランス女性は女性だ」というスローガンを言う人の中
でも明確にできていないのです。具体的には、
TS 身体違和がきつく性別適合手術も視野に入れる「TSトランスセクシャル(≒性別不合≒性同一性障害)」
TG 身体違和でなく性別違和であるといい、手術などする気持ちのない「狭義のTGトランスジェンダー」のほか、
TV 性別違和がないが、異性装などしている「TVトランスヴェスタイト(≒クロスドレッサー)」まで含めている人もいます。
国連の人権委員会では、往々にしてTVまで含めて話されており、またトランスジェンダーの法令化について推進論者である弁護士の中には「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられた出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」とする方もいます。「ジェンダー表現」とは表現の面でどの性別なのかの趣旨なのですから、TVまで含めておられましょう。
ですが、性表現はあくまで外部的なものですから、TVに「性自認」の食い違いがあることにはならないものですよね。
Q3 身体違和はないが性別違和があるという狭義のTG「トランスジェンダー」という意味が、どうにも分からないのですが。
A はい、性別は頭の中ではなく、身体についている、排泄は体からする、スポーツは体でする、性行為も体でするのですから、身体に違和はないが性別に違和があるという趣旨は、私も納得できないままです。ただそのような訴えがあることは確かです。
Q4 日本の法令化で議論されているのは、TVトランスヴェスタイトまでも含まないということですね。
A はい、そのとおりです、野党提出のLGBT法案は「自己の性別についての認識」に食い違いある場合を議論しており、TVは含まれません。自民党が2021年に提出しなかった理解増進法案も同様でしょう。
それを巧妙に、TVまでも含んで対象だと言おうとするならば、偽りの運動となってしまいます。もちろん、TVの人に対しても揶揄したり仕事上の差別などしてはいけませんが、「性自認」の法令化の問題とは別のことでしょう。
日本の法令化で議論されるべき「トランス女性」とは、TSと狭義のTGを含んでの「自己の性別についての認識が、生まれながらの生物学的・身体的性別と食い違う人を言う」とすべきでしょう。
制度を論議するときの定義は、明確にしなければ議論にならないと思われます。
Q5 TVトランスヴェスタイトの人が、性別に違和ある狭義のTGや、身体違和がきついTSと誤解されてしまうこと、また逆はあり得ないのですか。
A その点が心配です。「性別の認識」など外見的・客観的には分からないことだからです。もともと、性自認の権利を謳った日本学術会議の提言作成に至った陳述人三橋順子氏は、著書では「女装家」から出発したとし「性別越境者」としています。そして2020年9月6日には「性自認は基本『自称』なんだよ」とまでツイートしています。
TVの人も、またそうでなく怪しげな目的で異性装する人が、外見的・客観的にTSや狭義のTGと区別することができず、TSや狭義のTGだと見せることも可能であることが、大きな問題です。
Q6 日本のメディアでは、最終的に性別適合手術をするような人が多く紹介されていますが、あれは、正確ではないのですか。
A はい、メディアが誤導していると言うほかないでしょう。身体違和があり手術を望むトランスセクシャル(TS)の人の例だけを紹介して、「トランス女性」と報道していることが多いのです。このため「トランス女性」はみな身体違和がつらいのだとの誤解が、拡がっています。
Q7 トランス女性(TSと狭義のTG)の性的指向(性愛の対象)は男性ですよね?
A 違います。それはまた別のこと、性的指向は色々です。2021.9.24関東弁護士会連合会の報告によれば、東京都内の某精神科クリニックの受診者の自己申告によるとしつつ、性的指向がなし9%、両性23%、女性16%、男性45%、わからない7%です。
つまり、(性的指向が男性に向いている)ゲイの人の一部が、トランス女性だというものではないのです。なお、トランス男性(体は女性)の性的指向は、女性91%です。
Q8 LGBT法案のT「性自認」のところは、2003年「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の延長線上のものですよね。
A 違います。性同一性障害GIDとは、先のトランスセクシャル(TS)を医学的見地から言ったもので、2022年からは「性別不合」とも言います。
定義は、第2条にあり「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している者」です。
一方、野党LGBT法案も、理解増進法案も、「性別についての認識」などといったことそれ自体を尊重するという新しいものです。異質であり、延長線上のものではありません。
ただ、身体違和感を持つが、未成年や健康上の理由で手術できない人も含むので、その限られた範囲では延長線上のものとも言えましょう。
Q9 野党LGBT法案は「差別禁止」と明確にし、色んな機関も作ろうというもののようですが、どのようなことをもって「差別がある」と言うのですか。
A 実はそれが明確にされていないのです。揶揄したり、仕事上で差別したり、住宅の賃貸借で差別したりすることは誰しも「差別」、それも不合理なものと考えましょうが、女子トイレに入りにくいという苦情も出てその解決のためともされており、女子トイレに入りにくいことを差別、としている模様です。
とすると、女湯はどうか、更衣室はどうか、病院では、性犯罪被害者の相談や支援の場では、刑務所では、女子スポーツ選手権では、女子大学では、女子高校ではどうか、様々な女性枠には入れるのか、統計はどう考えるのか等々の疑問が、湧いてきます。
そのうち、どれをもって「差別」とするのか議論しておかなければなりません。これこれの差別があるから何とかしようというところから始めるべきなのに、推進論者の中でも議論されている様子が見えません。おおよそ一致しているのは、公衆の女子トイレに入りにくいのは差別だ、女性が排除しているという文脈の限りです。
「差別」は不合理なものが許されません。視力が悪すぎれば自動車運転免許は取れませんが、これは合理的な差別です。女湯だけでなく、女子トイレは、男性器ある人の性犯罪が圧倒的だから一律に入れないものとして成立しました。そこに入れないのは、合理的差別ではないか、いやただの区別ではないか、などの議論が必要です。
どのようなことをもって「差別がある」と言うのか、示されていないのです。
Q10 女子トイレが問題のようですが、2003年「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」で性別変更などした方々の意見はどうなのですか。
A 「日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会」は、2019年2月20日付の手術要件の撤廃についての「更なる議論が必要」との意見表明の中で、女性専用エリアの女性の安心・安全な環境を考慮すべきことを理由としており、手術前に女性専用エリアに入れるのはまずいと考えておられます。
「日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会」 2019年2月20日付意見表明
「3.権利を侵害されることになる側(特に女性)への配慮が必要
手術を必要としないとなると、男性器を持った女性、女性器をもった男性が存在することになります。世の中にはトイレ、更衣室、浴場、病室、矯正施設など男女別の施設がいくつもありますが、これらの施設が男女別になっていることには意味があります。特に、性的被害を受ける可能性が高い女性にとっては「安心・安全な環境を提供する」という意味合いがあります。 しかし、手術を必要とせずに戸籍の性別変更ができるとなると、男性器をもった人、しかも場合によっては女性を妊娠させる能力を持った人がこうした女性専用の施設に入場してくることになります。世の中に女装した人の痴漢行為や盗撮などの性犯罪が多く存在する昨今、これで本当に女性の安心・安全な環境を提供することができるのでしょうか。」
Q11 LGBT法案も理解増進法案も理念法だから、トランス女性が女性専用スペースに入ることが公認されて良いかなど、成立した後に議論して決めれば良いのでは?
A それがそうではないんです。一部のトランス女性やその支援者は、これが成立すると「トランスジェンダー女性は女性だ」とのスローガンのとおりとなり、女子トイレに入ることが公認されたことになる、としています。
日本学術会議の2017.10と2020.9の提言も、関東弁護士会連合会の2021.9の大会宣言もその趣旨が記載されています。またLGBT法案を提案した議員は、記者に「いかにも男の格好では入らない」という言い方ですが、女性の格好でトイレに入ると説明し「公認」する姿勢です。そして、女湯や女子スポーツについてまで入れると言う論者がいます。
そのために今、議論して、明確に定めなければならないのです。
Q12 女性専用エリアにトランス女性が入れると公認されても、その他の男性は今までどおり、入りにくいままですよね。
A その保障は一切ありません。単に女装が好きな男性(TV)はもちろん、どの男性も「女性らしい」装いをすれば入りやすくなります。
すでに、外観からしか分からないから「女性らしい」かどうかによると明言する論者、言い換えれば上手に女装すれば入れることになる意見もあります。それで良いのでしょうか。
Q13 女性専用エリアに、男性器を持つ人すべてが入れないと決めても、入り口で確認はできないから、いろいろ言う意味がないのではないですか。
A 違います。もちろん確認は人権上して良いものでも、できるものでもありません。しかし、そのような「建前・ルール」を維持しておくことで入りにくくさせ、通報しやすく、また警察も「自分は尊重されるトランスジェンダー女性だ、女性だ」と言われても、何らひるまずに対処できます。
すでに欧米では「性自認で法的性別が変更できる国」も多々あり、パスポートや日本の在留カードでは「女性」だが男性器ある人がいます。温泉地などでいつトラブルになってもおかしくありません。日本では既にレズビアンバーで外国人「レズビアン」というトランス女性が入場を求めてトラブルになり、その後トランス女性を断れなくなっています(2019年4月Gold Finger事件)。
Q14 トランス女性が、あやしい目的のために女性専用エリアに入ることはないですよね。
A そうとは言い切れません。トランス女性の中にも、性的指向は女性に向いている方がもち
ろんいます。通例の男性同様に、中にはあやうい方もいましょう。これは残念ながら当然の
ことです。こう述べることは差別でも何でもありません。「性犯罪をした人はトランス女性
ではない」という説明をする人が時にありますが、それはご都合主義に過ぎましょう。
Q15 女性も、金銭目的の盗撮などあやしい目的のために女性専用エリアに入ることはあるから、男性器を持つ人が入れないとする意味はないのでは。
A 女性専用エリアは、性犯罪のほとんどが男性によるものなので、男性は比較して危険な属性を持つという考えのもとに、女性のために確立されたスぺースです。強制わいせつ事件の被害者の圧倒的多数は女性で、加害者の圧倒的多数は男です。多くの男性には失礼でしょうが常識でしょう。
一部ふらちな女性がいても、男性器ある人が入れないままとする意義は大きいでしょう。
Q16 性的指向が女性であるトランス女性から「性的な対象として見られるのがまずい」と言うならば、レズビアンからそう見られるのもまずくないですか。
A どうでしょうか。体格・筋肉も自らより一般に大きく、男性器もあるトランス女性(生物学的男性)からのそう見られる場合の恐怖感と、レズビアンから見られる場合とは、質的にまったく違うのではないでしょうか。
Q17 トランスジェンダー女性で、従来、公衆の女子トイレに入れていた人まで入れなくなるというのは、酷です。
A 多くの女性は「分るよ」とも言うが、確かに従前、不自然でなく排泄目的では入れてきた人には恐縮します。だがそれは「黙認していた・させていた」ものでした。それが「公認」されると、どの人も入りやすくなるので、明確に言わなければならなくなりました。この際、しっかりとした解決が必要だと思われます。
Q18 女性スペースにトランスジェンダー女性が入れないというのは、南アフリカのアパルトヘイトなどについて、1980年代「治安が悪くなる」とか「危うい人が入ってくる」恐れがあるから廃止はまずいとも言われた、それと同じ論理ではないですか。
A アパルトヘイトは弱者側である黒人を差別するため、白人優位の維持のためにあり、これを廃止したくなかったのは白人側でした。
一方、女性専用エリアは男性に比較して弱者である女性の安全性等を確保するために女性のためにできたものです。維持したいのは女性側であり、決定的に違いましょう。
Q19 時に「女性自認者」「自認女性」とか「身体男性」「身体女性」という言葉が使われますが、嫌がられる時もあるから差別用語ではないのですか。
A 先に述べた通り「トランス女性」の定義は曖昧ですから、むしろ制度やシステム、ルールについて議論する場合は「女性自認者」などの方が適切ではないでしょうか。また論点である「男性器があるまま」と言うよりも「身体男性」と言う方が生々しくないのではと感じられます。
Q20 「男は女トイレに入ってならない」と法律にはあるだろうから、ここで焦る必要はないのではないですか。
A その法律はないんです。労働安全衛生規則第628条等に男女トイレは分けろとの規則があるだけです。また管理者の意思により被害届出をもらい建造物侵入罪になることがありました。
しかし、性自認が法令に導入されると、建造物侵入罪が不成立となる「正当理由」として「トランス女性だ、公認されている」が主張され、怪しげなことをしていると思っても通報しにくく、警察もひるむだろうと思われます。
Q21 「トランスジェンダー男性」の方は、身体的には女性ですが、男の格好をしていて、体格が良くなり、ひげが生えていても、女子トイレに入れと言うのですか。
A それは違います。女性の性犯罪は男性に比較してとても少なく、また男性は女性より一般に体格がよいので、男性は違和こそ感じても危険性が増すこともありません。また身体的に女性である以上は女子トイレに入ることも自由でしょう。
トランス女性とトランス男性とで対応の違いがあることになりますが、合理的な差別として許されましょう。
Q22 女湯のことですが、政治家によっては、トランス女性はほとんど女湯に入ることなど求めていない、丸裸になる場所ではトラブルになり易いからそんなことはない、また銭湯の組合で規制されているなどと言っています。論点ではないのでは。
A 一部でもそれを主張する人がいることにこそ注意すべきでしょう。信頼性あるトランス女性ばかり考えるのでは、「世の中にはホント色々な人がいる」ことを前提に定められなければならない法制定の議論として正しくないです。実際、女湯に入ったことを誇るように報告している方もいます。また、銭湯の組合規則は銭湯の限りですし、男女別とあるだけですから、新法の解釈として「女性として遇せよ」となれば維持できるか疑問となります。
時速30㎞制限の道路だが違反している自動車が多いことがあります。しかしルールはルールとして維持されます。特定の人を救済するための法律ではなく、ルールだからです。
「女性という自認」という曖昧かつ主観的な要件で「トランス女性は女性だ」とされてしまっては、女湯も問題となります。女性が不安に思うのは当然です。
Q23 女装して危うい目的で入ってくる男性が増える可能性があっても、それはトランス女性の責任ではないのだから、理由にしていいはずがありません。
A そうでしょうか。女性スペースは、性犯罪の圧倒的多数が男性によることから、無防備な場所での安全のためにできました。男性でそんなことをするのはごく一部で、他の男性には責任がないけれども、できたのです。そして、トランス女性は身体的には男性です。
その論拠ならば、男の中で性犯罪をする人も一部なのですから、そもそも公衆トイレも温泉・銭湯も男女で分けなくて良いということになってしまいます。
Q24 「トランス女性は女性」なのに「女子トイレに入れない」というのはマジョリティーである女性の横暴で、差別ではないのですか。
A 「トランス女性は女性だ」はスローガンでしょうに「真理」のごとく言う人がいて面食らいます。身体は男性、日本の現行法でも男性なのですから。
実は、性別セックス男性の中の、「性の多様性」としてある一つの類型として、マジョリティーである通例の男性の中のマイノリティーの課題ではないでしょうか。
それを、女子トイレに入れるようにすることで解決するのは筋違いだと思われます。女性の方がトランス女性より数が多くとも、女子トイレの中にあっては体格的な違いからして女性の方がマイノリティーでもあります。
「性別も多様性がある」などと言っていながら、突然「女性だ」と白黒の発想になってもおり、矛盾しています。
Q25 公衆用の女子トイレについて、どんな解決方法が提案されていますか。
A 解決方法としては、すべてオールジェンダー、つまりトイレの男女別をなくしてしまうとの考えがありますが、適切ではないでしょう。それは昔懐かしき「共同便所」であって女性の安心安全を確保できないのですから。
すべてを個室にしようという声がありますが、個数を確保できる施設はそうないとみられますし、その入り口までは男女ともになのですから連れ込まれたらかえって危険です。
多目的トイレ・誰でもトイレを拡充していく方法もありますが、日本全国で数百万あるだろうトイレの中で、実施できるのはかなり限られると言う外ありません。
むしろ、女子トイレはそのままに、男子トイレの構造を変えつつ、もともとの共用トイレに戻し、そう表示するのが現実的かつ適切だと思われます。男性は女性が入ってきても違和感はありこそすれ恐怖感はないのですから、甘受するしかないのと思えます。トランス女性、トランス男性も入りやすくなります。
これは男性への不合理な差別でもありません。女性こそがもっとも性犯罪におびえているのですから。
Q26 「セルフID」つまり性自認で性別変更ができることになるという批判がありますが、野党LGBT法案は、そうする法律なのですか。
A いえ、野党法案もそうは書いていません。性自認に食い違いがあることにつき尊重せよ、差別解消せよとあるものです。
ですが、様々な場面で「女性として遇せよ」という趣旨だと読む運動があるので、女性の安心安全を害する混乱が予想されますし、続いて欧米のように法的性別を変更できる制度にすすむ蓋然性があるのです。
Q27 欧米の「セルフID」は、どうなっているのですか。混乱はあるのですか。
A 「性自認」で法的性別も変えられるところに至っている国、つまり「セルフID」になっている国があります。性別不合の診断がいらないどころか、裁判所は関与しない、またドイツなどは1年を経過すればまた変更できることになっています。日本ではメディア報道もなく知られていなさすぎです。これにより、女子スポーツ選手権や、病院、シェルター、刑務所、いわゆる女性枠や統計に関して、混乱が続いています。
米国の大学女子水泳選手権では2022年、男性器あるままのトランス女性が女性として出場し記録を塗り替えてしまいました。女子アスリートとしては冗談ではないところでしょう。これを受け、国際水泳連盟では2022年6月トランス女性の参加資格を大きく制約しました。女子ラグビーも対処しました。
ですが他の競技団体ではまだ明確な姿勢になっていません。なお、「トランス男性」は男性ホルモンの投与がドーピング扱いとなり、どちらの選手権にも出られなくなります。女性スポーツの公平性が害され、このままでは崩壊していきましょう。
Q28 2021年5月自民党が結局は出さなかった「理解増進法案」は、適切でしょうか。
A 理解増進法では、「性自認」の定義として「自己の性別の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度にかかる意識を言う」としていますが、「性自認」の概念をいれる以上は同様の不安があります。何が「許されない差別」になのかも不明確です。
何より、条文の中で、「トランス女性」が女性スペース、女子スポーツその他で「女性として遇せよ」とされる趣旨の法律ではない、と読める工夫が必要でしょう。
Q29 ひょっとして、日本にもパスポート上「女性」とある男性器ある人が来ているのですか。
A はい、温泉などのトラブルが心配です。すでに日本でも2019年、トランス女性の外国人
男性が「女性だ」としてレズビアンの集まりに参加しようとしての混乱が起こっています。
「T=性自認」の尊重により、性的少数者Lレズビアンの法益が危機に瀕しているのです。
Q30 考えてみれば、2003年特例法の「手術要件」を削除してしまえば、家庭裁判所の許可は必要ですが、「セルフID」と同じことになりませんか。
A はい、その点が心配されます。この手術要件については、現在、最高裁判所の大法廷で審理されています。性別適合手術をしなければ、性別変更ができないというのは人権侵害だとの主張です。
ですが、この法律は身体違和がきつい人について性別適合手術を公認し、その生活の便宜のために後に法的性別を変更できるとしたものです。希望しない人に手術せよというのではありません。たしかに、男性器あるままの「女性」はあり得ないという考えに基づきますが、それが国民の意思と乖離(かいり)しているのか、また国民の意思と合致しているのかが、課題です。
当事者団体からは、先に述べた「日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会」の意見表明のほか、「性別不合当事者の会」でも手術要件の削除に反対しています。その2022年1月の政党あて要請文には
「身分証明書の記載と身体的状況が一致しない状況は、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も大きく失われると思います。」「私たちにとって、手術要件は決して『過酷な条件』ではなく、それこそ『身を守る盾』だとさえ感じています。」
とまで書かれてあります。それでも、性別不合(性同一性障害)の診断がしっかりとされていれば、身体違和がきつい人以外は含まれないので「セルフID」と同じにはならないとも言えます。しかし、診断は一日でとれてしまい、手術を勧められたという実態報告が相次いでおり、信頼性が低くなってきています。
手術要件を外せば「セルフID」とほとんど同じだという外ないでしょう。
Q31 多方面で、いろいろ議論をして決めていかなければならないと思いますが、トランス女性について「女性として遇せよ」さらに「性別変更を」とする人との間で、面談や文章の上での意見交換はないのですか。
A 意見交換自体が「差別だ」と拒絶されてしまうのです。「トランス女性は女性だ」という論者は、欧米から始まりました。日本でもこの考えを述べ、マスメディアや知識人女性らに、女性に比較して少数であるトランス女性への理解を求めます。「女性特権がある」という言葉さえあります。そこで訴え、イメージされるのは信頼と同情できるトランス女性ばかり。そしてその人権保障のために、男性器あるまま「女性として遇せよ」「性別変更を」を承諾させていきます。
疑義を呈する人に対しては、「差別者だ」「トランスヘイト」と言うばかりで、議論を拒否します。疑義を呈する方との討論に末端の推進論者がたまたま参加すると、その方が推進論者から批判されます。少しでも理解を示す人がいれば、あなたは分かっていない、後で連絡するとされます。学者や弁護士であれば、多くの署名を並べた批判文を作成して公表されたり(キャンセルカルチャー)します。文献を提供しても「読む必要がありません。」と返してきます。
専門書店が様々な本を紹介すれば、これこれは差別本として紹介したことを糾弾します。批判的な本を出した出版社に「差別だ」とし抗議を集中し謝罪を求めます。批判ツイートへの「いいね」さえ糾弾されます。すべては自分たちが正義とする「ポリティカル・コレクトネス」とします。「身体男性」は禁句です。そのくせ、女湯や女性スポーツについては多くの論者は、黙して語らず。
推進論者のオピニオンリーダーに東京大学教授の英文学者清水晶子氏がいます。氏は、2022年7月の「フェミ科研と学問の自由」というシンポジウムで、「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセルカルチャー」の正しさを述べ、それによって学問の自由、表現の自由が一部損なわれても良い、議論は正義のためにするものだとしました。「討議や対話を拒絶することこそが生き延びる戦略になりえる」としています。これらは『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』(有斐閣、2022年8月)にも著わされています。
「今の思想が普遍的に正しいとは言えないかもしれない、自由に情報と意見を交換しなければ、とんでもない間違いを犯してしまう可能性がある」から言論の自由が存在すること、「あなたの言うことには強く反対するが、私はあなたがそれを言う自由は命をかけて守る」ことの重要性をすっかり忘れています。
更に、日本でも「Fuck The TERF」というプラカードが出たパレードが、2022年11月ありました。下劣で暴力的な表現です。米国では同月「女性刑務所に男性を収容するな」との平和的な活動をしていた女性らは白い液体をかけられ、横断幕を奪われました。ドイツでは8月「男はレズビアンになれない」と表示して行進したレズビアン女性が攻撃されてケガをし、9月には攻撃されたレズビアンを守ろうとしたトランス男性(身体は女性)が男に殺されました。
もはや、中国で1966年から10年間続いた文化大革命、ジョージ・オーウェルのSF小説『1984年』、始皇帝が行なった「焚書坑儒」です。
裏付けと論理矛盾のない内容での建設的な議論をすべきなのに、できないのです。
Q32 考えてみれば、現生人類が出現する前から女と男という性別はあるのに、今「性別には多様性がある」とか「性別移行」と言う言葉を聞くが、どういう意味ですか。
A はい、医師という職業が存在し、出産に立ち会って性別を判別し、出生証明書や出生届が存在する社会になるはるか前、現生人類成立の頃から、性別はあります。
出産時には判然としない、胎内での性分化が一般的な形と異なり典型的に進まない状態である「性分化疾患DSD/ Disorder of Sex Development」がありますが、つまりはどちらかの性別でした。「トランスジェンダー」の課題とは関係がありません。性別セックスは、あくまで「女と男」だけでした。
だが、今「性別には多様性がある」「性別移行」という言葉が使われています。現生人類の成立時は、オスメスはあっても性別はなかったという表現もされます。
どうやら、ジェンダーつまり「男らしさ・女らしさ」や社会的役割と、性別セックスとを混同してしまっていると思われます。ジェンダーは地域と時代により大きく異なるのに、「女らしく」「そう認識する」から性別も女性、「男らしく」「そう認識する」から性別も男性とするのですから。本末転倒の考えであり、女と男の「ジェンダー」を固定化して考え、性の多様性に反して「性別」にこだわるという矛盾した態度だと言うほかありません。
ドイツの1995年ノーベル賞受賞の発達生物学者クリスティアン・ニュスライン=フォルハルト氏は2022年8月、「すべての哺乳類の性は二つであり、そして人間は哺乳類」「性に関する生物学の基本原理はトランスジェンダリスムを否定する」と述べました。
簡単明瞭なことです。
Q33 そうは言っても、揶揄・嫌がらせされたり、仕事上の差別があったら困るから、まずは理念法から作るべきでは。
A いえ、職場での禁止法制はできています。2019年改正の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」いわゆるパワハラ防止法の一環として対応できています。
その指針では、性的指向・性自認についても事業者に防止義務が課せられていて、今進められています。民法上の不法行為にもなりましょう。
Q34 たかが理念法ですから、作られてもいいんじゃないの?
A 理念法も、見解の違いや訴訟となったとき、判断指針として使われます。パワハラ防止法に加えて定めると、別の影響があると思われます。
1つは、実質「トランス女性の公衆女子トイレの利用公認」、女子スポーツ選手権等へのトランス女性の参加可能性が拡がりましょう。
2つは、追々に手術なしでの性別変更、つまり性自認だけにて性別変更もあり得ましょう。この「セルフID」つまり性自認至上主義の進展にあると考えられます。
Q35 それでも性的少数者の尊重のためには、必要ではないのですか?
A 性的指向の面での性的少数者「LGB」の人にとって重要なのは、同性婚の法制化です。相続、年金や医療で、同性婚ができた方が助かるものですが、別の議論になります。議論がそう分かれるものではないLGB「性的指向」の尊重・差別解消についてだけの法律にする方法もあります。
Tトランス女性も、尊重することは良いのですが、女性スペースや女子スポーツ等々での、安心安全・公平性の確保といった場合は別の話だと明確にしておかないと、新法は「セルフID」、性自認至上主義に向け確実に独り歩きしていくのでしょう。
Q36 ジョグジャカルタ原則「性的指向と性同一性に関わる国際人権法の適用に関する原則」というのがあり、国連人権畑の動きからしても、日本もトランス女性について「女性として遇せよ」さらに「性別変更を」としないと、まずいのでは。
A 2016年11月のジョグジャカルタ原則は、国際法律家委員会や元国際連合人権委員会構成員および有識者たちの草稿に基いて採択されたものです。2017年にはジェンダーの表現と性別の身体的特性について補完されました。
しかし、これは条約でもなければ、国連の理事会や総会で採択されたものでもありません。性自認との関係で、トランス女性と女性スペースの安心安全、女子スポーツでの公平性の課題との調整につき言及していません。起草者のひとりであるロバート・ウィンテミュート氏(イギリス・人権法教授)は、後に「女性の権利が考慮されておらず、原則のいくつかの側面に異議を唱えるべきだった」と言い、男性器を持ったままのトランス女性が女性専用スペースを利用しようとすることを「考慮していなかった」と認めた上で、「女性の意見に耳を傾けたことが、私の意見を変える重要な要因となりました」と語っています。注意を要します。
Q37 そうは言っても、2015年9月、国連総会で採択のSDGs(エスディージーズ)「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の目標5では「ジェンダー平等」とあるから、「トランス女性は女性」として対応しなければならないのでは。
A それが違うんです。SDGsでは、むしろ性自認を含めて性的少数者への対応は注意深く避けられています。36ページもある外務省日本語訳を読んでも、性的少数者についての単語は1つもありません。
目標5は正確には「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」なのですが、中身の6つ(abcを加えて9つ)あるターゲットも男女平等にかかることばかりで、cに「ジェンダー平等の促進、ならびに」とあるだけです。
むしろ目標6には「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」とあり、そのターゲット6.2では「2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。」とあります。
国連事務総長が「LGBTはSDGsのすべての項目に関わる問題であり、『誰も置き去りにしない』というSDGsのモットーに含まれている」と言ったと指摘されますが、総会で採択されたSDGsの中身が変わるわけでもありません。
2015 年9月25日第70回国連総会で採択のSDGs「我々の世界を変革する: 持続可能な開発のための2030アジェンダ」はこちら全文PDFをこそ参考に。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf
以 上
🏡noteの TOPページへ戻る
→ https://note.com/sws_jp
🏠「女性スペースを守る会」サイトへ戻る
→ https://womens-space.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
