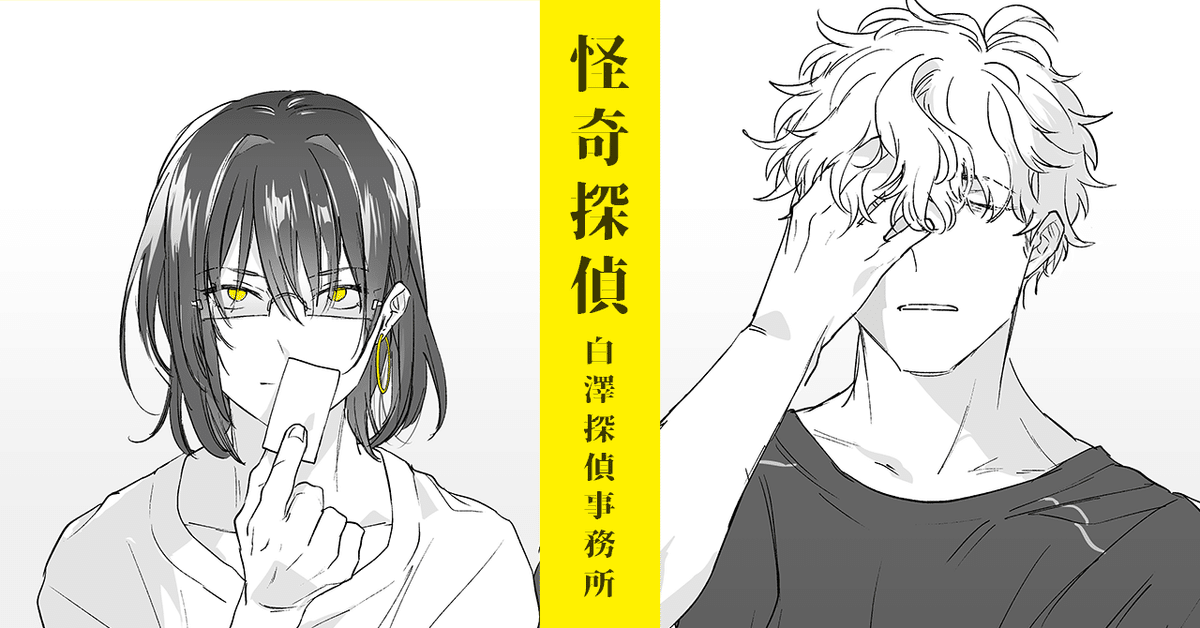
【小説】#10 怪奇探偵 白澤探偵事務所|悪夢を見せる蟲
あらすじ:新宿歌舞伎町の幽霊ビルの案件を解決してからというもの、野田は悪夢に悩まされていた。悪夢に魘された次の朝、右目に激痛が走る。夢ならまだしも痛みの原因がわからず困惑するが、白澤は蟲のせいだと言い――。
シリーズ1話はこちら https://note.mu/suzume_ho/n/nd6bc9680df73
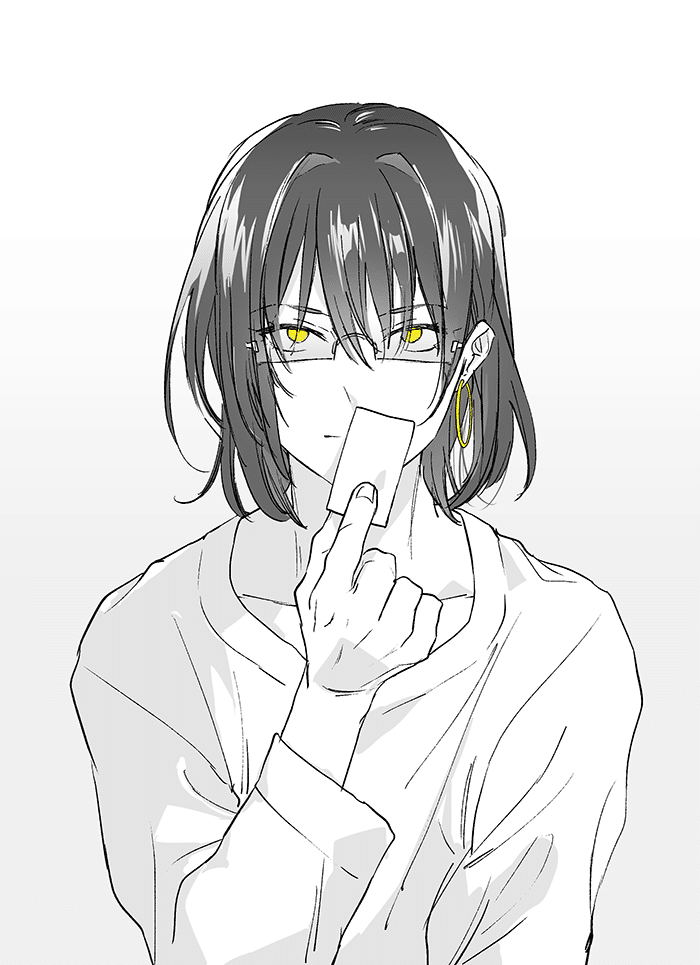
遠くで、ベッドメリーの鳴る音がする。
からん、ころんとオルゴールのメロディには聞き覚えがあるような気がするのだが、どこで聞いたのか思い出せない。音の出どころを探して周りを見渡すが、それらしいものが見えないどころか、暗闇の中にいることに気が付いた。
ここはどこだろう。何でここにいるのか全くわからないし、思い出せない。とにかく明るい場所を探そう。ここがどこかわかれば、帰るとか、人を探すとか、そういうことができるかもしれない。
暗闇の中を恐る恐る歩く。時折、身体にふわふわとした何かが触れる。動物の毛のような、やわらかいタオルのような感触だ。身体に触れるくらいなら気にならないが、歩き続けるうちにそれが身体にまとわりつくようになってきた。歩きづらく、息苦しい。払ってもすぐに取り囲まれてしまう。逃げるように足を速めても息苦しくなるばかりだ。
このまま、ここにいるのはよくない気がする。早く出たほうがいい。このままでは、やわらかい何かに包まれて圧死しそうだ。
思い切って身体にまとわりつくものを体から剥がし、暗闇の中を走り出した瞬間、何かに躓いて転んでしまった。
痛みより先に、何に躓いてしまったのかが気になった。床を手さぐりに辿るうちに温かいものに触れる。その表面はぬるりと濡れているようで、反射的に手を放してしまった。
この感触には覚えがある。目を逸らしたいのに体が動かない。今まで暗かった部屋に突然明かりが射した。オルゴールが頭上で鳴り響いている。頭上で何かが軋む音がする。
視線の先にあるものから目を逸らせなくて、でも見たくはなくて、いやだと叫びかけた時――はっと目が覚めた。
心臓の音がうるさい。全身に汗をかいている。暗闇の中に何かが見えてしまいそうで、枕元のケータイを手繰り寄せた。
スリープを解除して表示される時刻は深夜にほど近く、設定したアラームの時刻は遠い。
夢か、とわかって全身から力が抜けた。まだ耳の奥にベッドメリーの音が残っている。身体にかけていた毛布が床に落ちていて、のろのろとそれを拾って掛けなおした。
自分は、こんなにショックを引きずるタイプの人間だっただろうか。これで同じ夢を見るのは四回目だ。
幽霊ビルの仕事を終えてからしばらく経つが、あの時見た光景を夢に見る。ベッドメリーの音楽、落ちてくる大きなものの影、白澤さんが――ぶるりと背筋が震えて、それ以上思い出すのはやめた。
自分が役に立たなかった後悔からか、それともショッキングな光景が記憶から消えないからかはわからない。いずれ忘れるだろうと思うが、日常から遠くなってきた頃に夢に見ることを繰り返している。
まだ心臓がどきどきとうるさい。全身が冷たくて、身体をぎゅっと丸めた。瞼を瞑る。何も視えない。二度寝で悪夢を見ないことを祈るくらいしか、俺にできることはなかった。
枕元のケータイが鳴らすアラームで目が覚めた。
激しく振動するケータイを止めて体を起こすが、身体がだるい。夜中、悪夢にうなされて飛び起きたせいか寝る前より疲労している気がする。
今日が休みならこのまま二度寝に入るところだが、残念ながら平日である。けれど、起きる気力もない。そのままぼんやりしているうちに再び眠気に襲われ、瞼が重くなってきた。
「痛っ」
瞬きをした瞬間、右目に鋭い痛みが走った。眠気も覚める突然の痛みに驚いて、そろそろと目を開ける。もう一度瞬きをしたら、同じ痛みがあった。目を閉じると痛むらしい。まつ毛が目の中に入ってしまったのかもしれない。痛みの原因を確かめるため、とにかく部屋を出た。
「野田くん、おはよう」
「おはようございます……」
テレビから流れるニュースの音と、コーヒーの匂いはもはや見慣れた朝の風景だ。共に住み始めた頃は声をかけたほうがいいのかどうか悩んだものだけれど、朝の挨拶を交わすのももはや日常の一部になっている。
ただ、白澤さんの視線がいつもと違った。
ひどい寝癖を見ているのか、それとも寝ぼけ顔が気になったのだろうか。あまりにまじまじと見つめられて、少し気まずいくらいだ。他人に傷跡をじろじろと見られる機会は多くあったが、白澤さんからこんなに顔を見つめられるのは初めてかもしれない。
「野田くん、具合悪い? 顔色が悪いけど……」
何を言われるのかと身構えていた分、気が抜けてしまった。俺の顔色が悪いのが気になったらしい。具合が悪そうに見える原因として思いつくのは昨晩の悪夢による寝不足くらいだが、幽霊ビルの夢を見たとは言えなかった。
幽霊ビルでの一件で、白澤さんは俺に悪いものを見せたと気にしているようだった。例の事件から今日までの間、業務に怪奇由来の気配が薄く、何かを視ることもしていない。業務の調整と言えばそれまでだが、俺を気遣ってのことではと思えばこそ悪夢のことは相談できずにいた。それに、話したとして俺の夢見具合を解決できるわけでもない。
「右目が真っ赤だけど、痛くない?」
「それが、瞬きするたび痛くて……」
顔色はわからないが、瞬きするたびに痛みがあるのは確かだ。片目だけを閉じるというのは難しく、なるべくゆっくり瞬きをしようと試みてはいるが、瞬きのたびに痛みを感じている。
「野田くん、ちょっと座って。見てみるよ」
「すんません……まつ毛が刺さってるんだと思うんですけど、多分」
ソファーに座ると、すぐに白澤さんの指が瞼に触れる。傷跡の残る顔を他人に触られるのは苦手なのだが、そうも言っていられない。指先で瞼を上げ、まつ毛の付け根を撫でられる。くすぐったさについ体が逃げてしまうが、なんとか耐えた。
「あー……野田くん、これ、まつ毛じゃないね」
白澤さんの手のひらが頬に触れる。指先の冷たさに思わずびくりと体が跳ねてしまった。前髪を捲られ、瞼やら目元を撫でたり擦ったりされるたびくすぐったくてしょうがない。診てもらっているのだから、と白澤さんの判断をじっと待った。
「蟲がいるかな、これは」
「むし……って、普通の虫ですか?」
思わず息を呑んだ。虫がいる、と言われると好きとか嫌いとかは置いておくとして怖気が立つ。まつ毛とか髪の毛のほうがまだましというものだ。
「人間に寄生して悪さをする蟲だよ、疳の虫の仲間みたいなものかな」
かんのむし、という言葉は聞いたことがある。赤ちゃんの夜泣きや癇癪を引き起こす原因とされ、虫封じのお札や虫出しのおまじないが盛んだったらしい。用途のわからないお札の送付をしていたとき、そもそもどういうことにお札が使われているのか気になって調べたからよく覚えている。
「あ、蟲と言ってもその辺にいるような虫と違うよ」
虫と違うと言われても、もう言葉の響きが悪い。朝からげんなりしてしまう。そのうえ居るだけでこんなに目が痛いのだから相当体に悪いものなのでは、と思ってしまう。
「野田くんの目の中にいるね……最近、よく眠れなかったり、悪い夢を見たりした?」
心当たりがありすぎて、すぐに返事が出来なかった。返事ができないというのはほとんど答えみたいなものだから、白澤さんが少し、ほんの少しだけ、困ったような顔をしたのが見えて、目を逸らす。
「じゃあ蟲出しをしよう、これは簡単だから野田くんでもできる」
「実地訓練みたいな感じすか……?」
「いや、私がお手本を見せるから。次に蟲出しの依頼が来たらやってみようか」
白澤さんが怪奇探偵であることを知ってから、視ることでしか役に立っていないのは俺の気がかりの一つだった。もっとできることがあればと思っていたのも確かで、俺にもできる範囲のことを教えてくれるのであれば、それはありがたいことだ。
道具を取ってくるから、と白澤さんが一度リビングを離れ、自室へ入った。ふと時計を見れば、九時半を過ぎている。あと三十分で処置は終わるのだろうか。目の痛みや蟲が居るという事実に驚いているうちに時間が過ぎていくが、もしかして初めての遅刻になるのではないだろうか。
「お待たせ。野田くん、目を瞑ってくれる?」
「あ、はい」
白澤さんは片手に小さなカードケースを持って戻ってきた。ケースの中には文字のような、図のような、よくわからないものが描かれている。何に使うのかわからないまま、両目を閉じた。
右目の上に、ぺたりと何かが貼られた。シールというか、セロハンテープというか、とにかく何かが固定されたような感じだ。
「蟲がいるところに蟲出しの符を貼って、符に書いてある陣を指で書く」
瞼の上に、図を指先で撫ぞるの感触がある。縦、横、丸、とぼんやり指先の描く形から符に描かれた陣を想像してみるけれど、何も浮かばない。陣を描き終わって指先が離れる一瞬、右目がちりと痛んだ。
「今、ちょっと痛かったかな?」
「……ちりってしました」
「うん、じゃあ蟲は符に移ってるね……剥がすときもちょっと痛いけど、ごめんね」
絆創膏を剥がすときみたいな、ちりちりとした痛みと共に瞼の上にあった符がはがされる。瞬間、糸くず状の光が視えてしまった。うすぼんやりとした光だけれど、妙に長い。これが体の内側にいた蟲かと思うと、背筋がぞっと冷えた。
「あとはこの符を丸めて捨ててしまえばおしまいだよ」
「……案外簡単に出ていくんですね、蟲って……」
「符を新しい宿主だと錯覚させて捕まえてるからね」
蟲だからそんなに賢くないし、案外扱いは難しくないよと言いつつ白澤さんは符であったものを手のひらでくしゃくしゃに丸めている。丸めすぎでは、というくらい丸めている。そのままではただの紙くずになってしまいそうだが、恐らくはそうする必要があるのだろう。
恐る恐る瞬きをしてみる。ついさっきまであった痛みはなく、脱力してソファーに沈み込んだ。二度は勘弁してほしい痛みだった。いや、対処法も教えてもらったのだから二度目はない。あってたまるか、と思う。
それにしても、悪夢も蟲のせいだったとは全く想像もしていなかった。これで今夜の安眠は約束されたのだろうか。白澤さんの言うことを疑っているわけではないが、こればかりは眠ってみないことにはわからない。
「歌舞伎町のビルで拾ってきたのかもね」
「……蟲ってどこにでもいる感じなんですか?」
幽霊ビル――歌舞伎町のビルでは、怪異の原因であるぬいぐるみ以外に何も視えなかった。視えるもの、範囲が広くなってきた自覚はあるのだが見落としてしまったのだろうか。
「珍しくないよ、力が弱すぎて見えなかったんだと思う」
自分の身にも起きたことを考えれば怪異として珍しくないのはわかるのだが、激痛に襲われた後に力が弱いと言われてもぴんとこない。痛みのあった目元へ触れてもいつもとそう変わらない感触があるだけで、さっきの痛みはもう記憶の中だけだ。
「外で生きていくのが困難だから人に寄生しているものだからね、宿主が弱ると外に出ようとするんだ。そこで痛みが出てしまうんだけど」
「ああ、じゃあ出ようとしたところだったんすね」
なるほど、と手を打って顔を上げれば、白澤さんの向こうに十時を指す時計が見えた。遅刻確定である。思わず小さく声を上げれば、白澤さんが小さく首を傾げた。
「すいません、俺、支度してきます。遅刻ですね」
「支度……あ、いいよ野田くん、座ってて」
ソファーから立ち上がろうとした肩を白澤さんに抑えられ、あえなくソファーに戻る。いや、もう勤務時間は始まっているのだから着替えて事務所にいかなくては。目の痛みはもうなくなったのだから働くのに支障はないのに、と今度は俺が首を傾げた。
「蟲が出ていく準備をしていたってことは、野田くんの体は弱ってるってことだよ。体温計とか色々買ってくるから、このまま休んでいていいからね」
事務所は閉めておくから、と言われてようやく白澤さんが外出の支度を整えていることに気が付いた。さらには、俺が使うものを買いに行くのだということに思い至って少し焦る。
「俺、もう大丈夫ですよ」
「顔色が悪いのは蟲と関係がないから、たぶん熱があると思う。私が心配なんだ」
身体が丈夫なのが取柄という身としては、これくらいは怪我のうちにも、体調不良のうちにも入らない。本当に大丈夫だから、と言うより先に白澤さんは財布片手に出て行ってしまった。
事務所を閉めておくということは、今日の勤務はなくなったという意味になる。遅刻ですらない。欠勤というやつだ。勤め始めて五か月、ついに穴をあけてしまったと思うと少し落ち込む。しかも自分の体調不良疑惑で事務所を閉めさせてしまった、と思うと落ち着かない。
手持ち無沙汰を誤魔化すためにテレビの電源をつけると、ニュース番組が流れ出した。気が紛れれば見るものは何でも良かったけれど、内容が全く頭に入ってこない。いつもよりぼんやりしすぎているような気がする。ぼんやりしているというか、眠たい。もう眠っても悪夢は見ないのだと思うと、今はこのまま眠気に体を任せたい気もする。
瞼が重たくなってくるのに負けて、目を瞑る。目を瞑っているだけだ。このまま何か、考え事でもしていれば眠りはしないだろう。
テレビの音声は頭に全然入って来ないのに、ついさっきの白澤さんの言葉ははっきりと思い出せる。心配なんだ、と言われたのが思いの外くすぐったかった。気を遣わせてしまった後ろ暗さから相談しなかったのがいけなかったな、と思う。具合が悪いということを隠す必要もないということに今更気が付いて、つい頬が緩んだ。
白澤さんが帰ってくるまで待っていようと思ったのに、すぐに意識を手放してしまった。ベッドメリーの音は、もう聞こえなかった。
