
RVRコモンカードPauper評価
かなり唐突な発表ではありましたが、本日の午前3時に2024年1月12日発売のリマスター・セット、『ラヴニカリマスター』(RVR)の全カードが公開されました。
前回の『ドミナリアリマスター』のコモン落ちが微妙だったので、あまり期待はしていませんでしたが、それでも「もしかしたら《頭蓋割り》や《舞台照らし》がコモンになるかも」と希望を捨てきれずにいました。
まぁ当然そんなわけもなく、前回に引き続き環境に食い込みそうなカードはなかったものの、8種類のカードが新しくコモンになったので紹介していきます。
ちなみに今さらながら前回の『ドミナリアリマスター』のコモン落ちについてコモン評価を書き忘れていたことに気づきました。
本当に大したカードがないので《魂の絆》だけ覚えていただければOKです。
(それすら元々《絆魂》が存在したので強化らしい強化でもないですが。)
【お知らせ】2024年1月12日発売セット『ラヴニカ・リマスター』のカードイメージギャラリーにて、全収録カードを公開いたしました。https://t.co/OZk8ZAHRlH#mtgjp #MTGRavnica
— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) December 12, 2023
白
《ボロスの精鋭》

正直、殴るだけが取り柄のクリーチャーが1/1/1なのは厳しい。
一瞬で止まるうえに《クォムバッジの魔女》のようなティムや《祭典壊し》のような全体1点除去で簡単にアドバンテージを取られてしまいます。
元々、白いアグロは《戦隊の鷹》や《金切るときの声》といったタフネス1を並べる戦略を取ることが多いので脆弱性を強調することになるのも辛い。
サイズを上げる条件も厳しく、これを含めて3体以上のクリーチャーで攻撃というのは1ターン目からマナを無駄なく使っても大体4ターン目以降になるのではという印象。
相手からの除去もあるし、一緒に殴るクリーチャーがチャンプ・アタックになってしまうと基本的に損なので、十全の性能を引き出すのに結構な手間と運が必要になるのではないでしょうか?
これを使うくらいであれば1/2/1のバニラのほうが、最序盤の通し易さだったりブロックに回ったときにタフネス2と相打ちにできたりと強い要素が多そうです。
青
《悪意ある妨害》
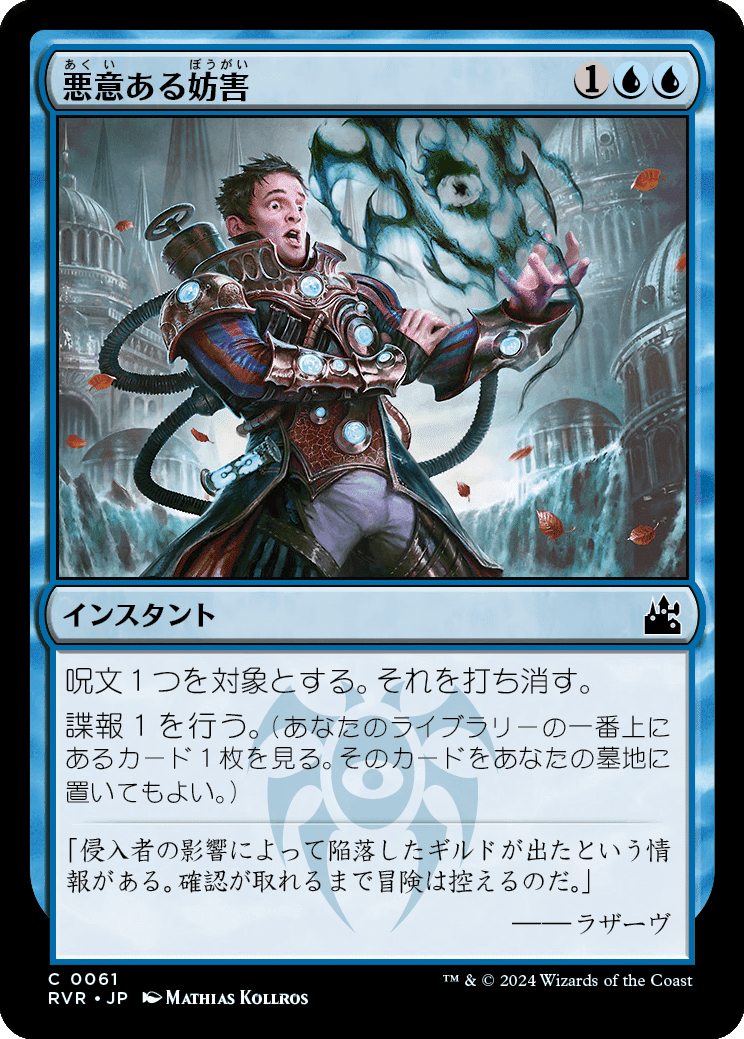
《解消》の占術1が諜報1になり《トレイリアの恐怖》のようなカードとのシナジーを考えると強化ではあるのですが、そもそも《取り消し》(3マナの確定カウンター)に需要のあるフォーマットではないので結局は五十歩百歩。
赤
《大いなる溶鉄の精》

さすがに2005年発売の『ラヴニカ:ギルドの都』のカードだけあって元アンコモンなのに今の基準で考えるとコモンでも弱い。
(なんでダブルシンボル?)
サイズをもう一回り大きくして先制攻撃でも持たせてあげて欲しい。
それでも構築向きの性能でないことに変わりはないですが。
《ブリキ通りの身かわし》
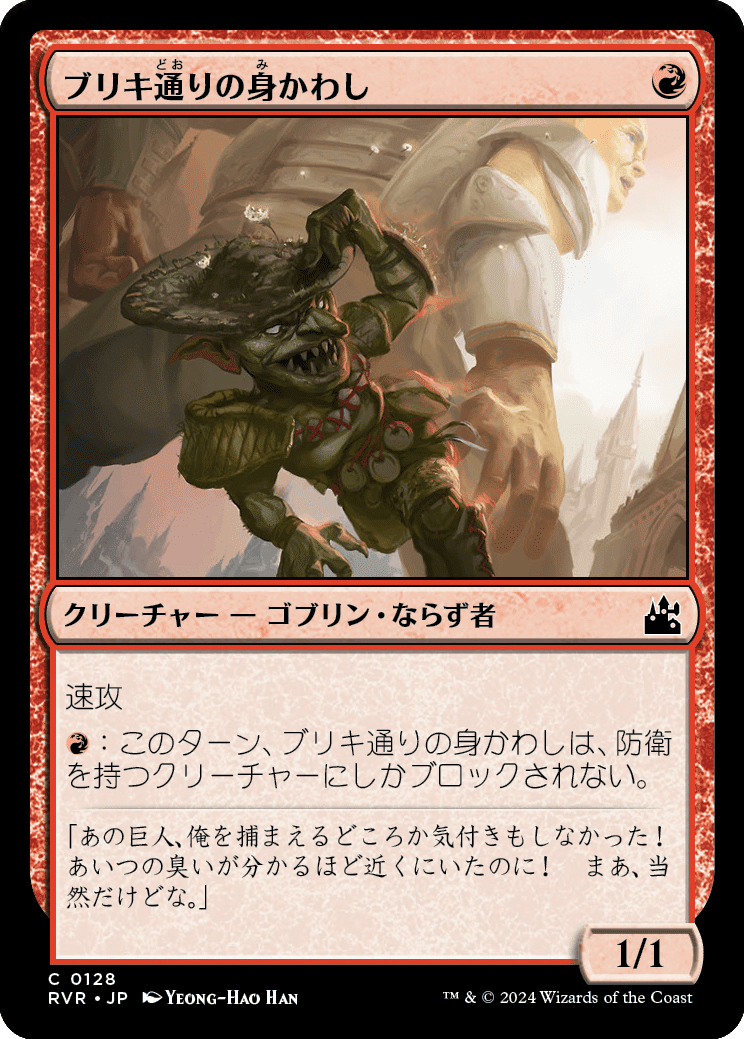
ラヴニカ次元としては最新のセットからの収録ですし、スタンダード時代に赤単で実績もあり《怒り狂うゴブリン》の系統としては普通に使える性能です。
しかしながら《僧院の速槍》が禁止された現在では防衛で止まるこれより《ジンジャーブルート》のほうが通りが良さそうに見えます。
一説によると《僧院の速槍》禁止直前の環境での勝率トップのデッキは《陽景学院の使い魔》採用の白青らしいですし、壁コンボも環境に一定数は存在ので防衛を持ったクリーチャーは割と頻繁に遭遇する印象です。
もっとも《ゴブリンの手投げ弾》や《ゴブリンのそり乗り》のコストにできるという明確なメリットもあるため、デッキをゴブリンに寄せるのであれば優秀そうです。
緑
《芽吹く更生》

メインから採用し易い《帰化》は増加傾向ですが、クリーチャーとの選択ができるので特にアグロデッキで使い易そうです。
3マナのソーサリーですが、召集のおかげで使用感としては思ったより軽そうです。
同じような役割で緑系のデッキで《仮面の蛮人》がメインから採用されたりしていますが、こちらは下準備が不要で使用可能な点が強み。
(もちろん《仮面の番人》にも追放だったりサーチ手段が豊富だったりでメリットが多い。)
2/2警戒というトークンの性能はパウパーでは高めなので居住と相性が良さそうだなとか考えましたが強い居住というと《隔離する成長》とかになるので置物破壊が被って流石に微妙そう。
多色
《審判官の使い魔》

今回のコモン落ちカードの中で恐らく一番実績のあるカード。
晴れる屋のデッキ検索で調べると昔のヴィンテージやレガシーで《石鍛冶の神秘家》を《意思の力》でバックアップするようなハーフ・コントロールにも採用されていたりで驚きます。
パウパーで《石鍛冶の神秘家》と役割が共通するカードとしては《バジリスク門》がありますが(これについては浅原晃さんの記事に詳しく書いてあるので最後にリンクを貼っておきます)、確かに相手への妨害を兼ねながらバジ門で強化した際の攻撃の通し易さなどもあり相性が良さそうです。
とは言え相手の妨害ができるクリーチャー枠としては《黎明運びのクレリック》など完成度の高いカードが他にもありますので、試しで数枚程度採用されることはあっても3~4枚もスロットを割かれるようなことにはならなそう。
そもそも、《神の怒り》のような重いインスタント・ソーサリーが少ないパウパーにおいて《トゲ尾の雛》ってそこまで優秀かという問題もあります。
どちらかというと白単アグロのようなデッキで序盤の打撃力と《悲哀まみれ》のような全体除去へのけん制を兼ねるウイニー用クリーチャーという面が強そう。
また白と青の混成1マナで出せるという面を見ると《きらきらするすべて》を採用した親和デッキで採用するのもアリかなと思います。
使ってみると分かりますが、白青の親和は色マナが割と不自由なデッキで、特に序盤に《バネ葉の太鼓》が手札にあるけど青マナを出せる土地しかなく手札の《スレイベンの検査官》を出して太鼓を叩くことが出来ない……なんて状況がしばしばあります。
1ターン目《バネ葉の太鼓》から2ターン目にクリーチャーを出して太鼓を叩くという動きが《古の居住地》からでも《教議会の座席》からでもできるというのは嬉しい。
さらに太鼓を叩いてタップしても変わらずインスタントやソーサリーをけん制することができるのも良き。
パウパー環境にはメインにはタフネス依存の除去しかないというデッキも多く、そういった相手に対し序盤に《きらきらするすべて》をぶっぱする際、マナの面でも妨害の面でも強力にバックアップしてくれそうです。
《深みのマーフォーク》

知らないカードなので調べてみましたが、当時はアンコモンのくせにリミテッドですら採用圏外という糞カードおぶ糞カードの烙印を押されていた模様。
インスタントのタイミングで進化を誘発させるための瞬速とサイズだとは思いますが、これ自体に進化を付けてもまだ弱そう。
本セットのコモンには青黒の混成で《囁く工作員》がいますけど性能差が酷すぎてリミテッドで比べられてしまうのが可哀想でなりません。
《滑り頭》

0マナで活用というポイントを活かすなら戦場に出してから生け贄にするより手札から捨てたり切削でライブラリから墓地に落とす動きが強そう。
やはりマナを使って1/1を出すという動きが強くはないので。
《拷問生活》を採用したデッキなら《臭い草のインプ》の発掘で落ちてもヨシ、手札に引き込んでしまっても《拷問生活》で捨てて+1/+1カウンターを載せられる《死者再生》として使えばヨシで相性が良さそう。
最も、強化して強いクリーチャーが《墓所のネズミ》くらいしかいなさそうなのが残念ではありますが。
一部の界隈ではステッカーによるサイズ修整が墓地でも有効であることを利用し、これに5/1や4/2のステッカーを貼って攻撃しつつ、墓地に落ちたら0マナで+4/+4や+5/+5分のカウンターを置く動きを狙っているようです。
ちなみに余談ですが、最近Twitter(現:X)で見かけた情報によると、ステッカー・シートはどれを使うのかが明確であればカラーコピーでよく、公式のステッカー・シートは不要とのことです。
需要の高いステッカー・シート(特に母音関連)は一式を揃えるだけで数千円とかするため集めるのが億劫だったのですが、公式のステッカー・シートに拘らなければ本体のカードだけで十分に使えるので興味を持った方は試してみてください。
(詳細はイベント規定を参照。)
参考
浅原晃の「デッキタイムトラベル!」
イベント規定
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
