
スパイファミリーの面白さは「かっこいいうそつき!」にある
スパイファミリーが面白い。
魅力的なキャラクターや、ギャグとアクションが交互に繰り広げられるテンポの良さなど、多くの点で非常に完成度が高く、面白さを語ろうと思えばいくらでも語れるだろう。
その中でも外せない要素が、「お互いに正体を隠しながら疑似家族を築いていく」というコンセプトの面白さだ。
ロイドは任務のために偽の妻と子供を用意して、精神科医の身分と良き父良き夫を演じる。スパイであることがバレないように心を砕きながら、上から降ってくる仕事をこなしていく。
ヨルは裏の仕事を隠すために普通の生活を装う都合から、偽装結婚を受け入れた。殺し屋として長く暮らしたため常識に疎い面があり、周囲に馴染もうと振る舞う。
アーニャはスパイへの興味から養子になり、学校へ入学する。里親を転々とした経験から超能力を隠しながら、ロイドの任務が成功するように奮闘する。
三者それぞれに人には言えない課題や悩みがあり、別々の思惑から家族を装うことになった。秘密を守るために嘘をつきながら自分が抱える課題を解決しようとする、ある意味でお互いを利用し合う関係と言える。
一般論として、人は誰でも多少の秘密を抱えている。そして、秘密を守るためには嘘をつくことになる。
まあ、大抵は些細なものだろう。客観的に見れば「そんなことで嘘をつく必要がある?本当のことを言えばいいじゃん」という程度のものだ。
それでも、小さなプライドや、思い込み、浅はかな考えなどから嘘をつき、大したことのない秘密が積み重なっていく。
スパイファミリーの中で描かれるすれ違いギャグは、そういった誰もが思い当たる嘘を漫画的に誇張したものだ。設定は突飛でも、そこで起こる心の動きは誰でも共感できる。
じゃあ、この漫画は嘘をつく僕ら読者の罪悪感を突くような作品なのだろうかといえば、もちろんそれは違う。
ロイドは、任務のために用意した家族生活の中で、ふとした瞬間にやすらぎを覚えたりする。駄々に手を焼きながらも、アーニャの成長を感じたときには喜びを感じる。
ヨルは、世間の目を欺くために契約をした家族だったが、本物の母に見えるように振る舞いながら、娘のピンチに駆けつけ、本気の感情を見せたりする。
アーニャは超能力で両親の秘密を承知しながらも、両親の仲を取り持とうとする。遊びの延長線の任務でも、自分の興味の範囲を超えて、ロイドの身を案じたりする。
家族は嘘でも、そこで経験することは本物なのだ。こうした本当の経験を繰り返すうちに、次第に本物の家族になっていく過程が丁寧に描かれていく。契約上の一時の関係でも、ちょっとした思いやりを積み重ねていくことで、やがて本物の家族の愛につながっていく。
欲目を見せてポカをやらかすようなギャグや、正体がバレないように手を尽くすサスペンスなどの根底に、この「嘘の上に成り立つ思いやり」から来るハートフルドラマ。これがグッとくる。
これは「嘘はいけないことで、真実に価値がある」という話ではないし、「自分のための嘘は良くないが、相手のために嘘をつくのは許される」という意味でもない。
人間は誰でも自分の損得を考えるし、そのためには嘘をつくこともある。だが、たまにその中に相手への思いやりが混ざることがあるのだ。
例えば、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』でこんな場面がある。
最終話、バーニィが残したビデオレターが再生される。そこで、戦う理由をうまく説明できずに無理やり言葉にした「ガンダムと戦ってみたくなった」と言う時は目をそらして、「逃げるみたいに思った」「仲間の仇ではない」「連邦を憎んだり自分を責めないように」と本心を語る時はカメラをまっすぐ見つめている。
バーニィは、アルが「自分を守るためにバーニィが死んだ」と思い悩まないように「ガンダムと戦ってみたくなった」と嘘をついたのだ。
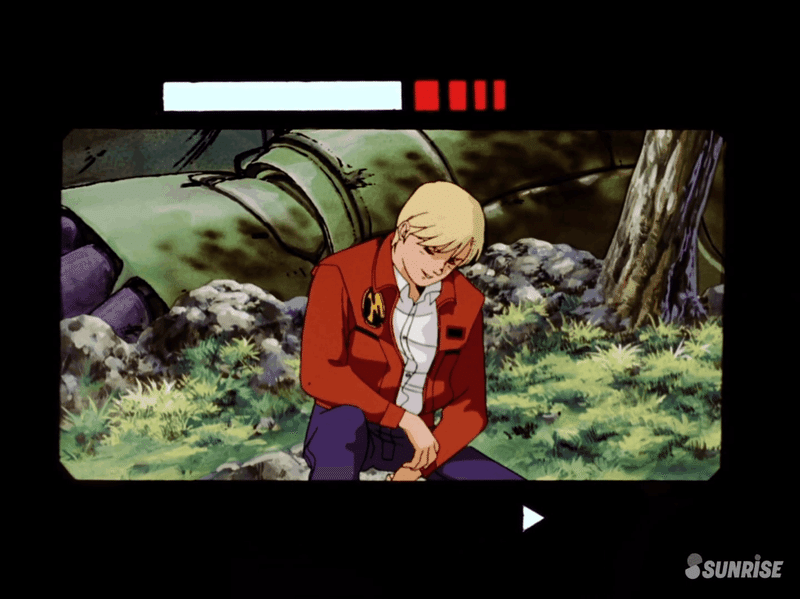
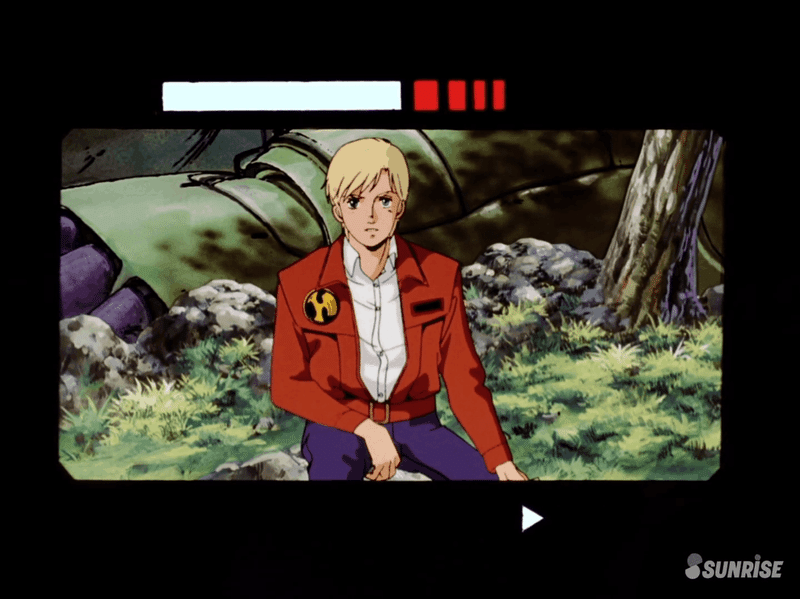
1人だけ逃げようとしたもののアルのために戻ってきたバーニィと、「一人ぼっちになるのが耐えられないから人を守るために戦う」と語ったクリスは、ジオンと連邦、立場が異なるだけで同じ動機で行動している。両者とも、人への思いやりと自分自身のための行動が混じり合い、不可分になっている。
そして、バーニィはアルが責任を感じないように「戦ってみたくなった」と嘘をついたので、アルもクリスが責任を感じないようにバーニィの死を隠すための嘘をつく。
バーニィに会うため、周囲の気を引くため、自分のために嘘をついていたアルが、最後に相手を思いやって嘘をついた。
ロイドは自分のような戦争の被害を受けた子供を作らないためスパイになったと言い、ヨルは殺し屋の仕事を「国家に命を捧げる尊いもの」と語り、アーニャはロイドの任務を成功させるため、ひいては(漠然とした)世界平和のために、それぞれ秘密を守ろうとして嘘をつく。三人とも、大元の動機の部分では自分以外の誰かのために行動している。この点は愛を語りつつも常に自分本位な言動となっているユーリやフィオナたちとの違いとも言えるだろう。
エゴを押し通すのではなく、といって滅私奉公に徹するわけでもない。例えば入試面接でアーニャが泣いた場面で、ロイドは任務を忘れて感情的になってしまい、ヨルは偽装生活が終わって仕事に支障が出ることよりも先に関係が終わることをそのものに思いが至った。自分自身の都合と同じくらい、いつの間にか家族単位でも物事を考えている。
これは、突き詰めれば、自分/他人という区分け、つまりは近代的な自我の認識への問いかけとも言える。
デカルトが発見した自我(我思う故に我あり)は、理論的には成立するが、あくまで観念的なものである。おそらく、実生活上での自我は、他人との関係性の中で生まれてくるものだろう。
例えば、リンゴとはどのようなものだろうか?「赤い果物で、丸くて、甘くて……」と、リンゴが持ついろいろな性質によって説明ができるだろう。つまり、赤くないもの、丸くないもの、甘くないものといった無数の「リンゴ以外のもの」との関係性の中でリンゴが浮かび上がってくる。
人間も同様に言える。独立した自我、魂のようなものは存在せず、「あなたではない、彼ではない、彼女でもない、犬でもない、木でもない……」という他者との関係のネットワークの交点に自己がある。
人は自分のために嘘をつく。だが、自分とは他人との関係の中にあるものだ。だから、自分のための嘘の中に相手のための嘘が混ざることがある。
確固たる自分=相手を排除する二元的な理論ではなく、自分と相手の関係性の融和、つまりは愛が描かれていく。
嘘の仮面をかぶって暮らす人間は、本質的に理解し合えることは無いかもしれない。だが、理解できない他者を理解できないありのままの姿で包摂する姿勢は、多様性に満ちた社会を築いていく。
スパイや殺し屋として任務の成功、自分の都合を優先してきたロイドやヨルは、自然と家族として物事を考えていることに気づくと、「いや、ここで関係が破綻したら任務に支障が出るからだ」などと合理的な説明をつけようとする。それに対してアーニャは、両親の”仕事”の理屈を超えて、二人の間をつなぐ。
これは、近代的な自己認識に慣れた読者にとって、擬似的に愛の姿を見せてくれるものになるだろう。
愛は分断を乗り越える。スパイファミリーで描かれる「愛が形作られていく過程」は、善悪や賛成/反対といった二元論で分断されがちな現代で輝くのではないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
