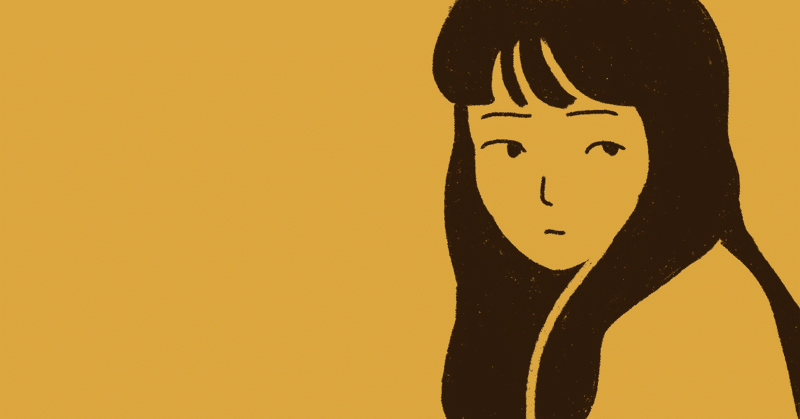
「これは容認されているんですか?」
「私の目を見て。」
彼女は、僕にそう言った。僕はそれに従い、彼女の目を見た。病院の待合室で看護師に名前を呼ばれ、ふと顔をあげてその看護師を見るかのように。
「もっと、よく見て。」
彼女はこう続けた。それは「目を見ること以外の何か」を僕に要求しているかのような言い方だった。しかし、僕はその「目を見ること以外の何か」が分からなかった。だから彼女の言葉通り、しっかりと目を見た。目を見たら彼女の意図が分かるのではないかと思った。その瞳の奥に光が、僕が彼女に求められているもののヒントとなる光が、きっとあるはずだと思った。まるで、目指す島が向こうから現れると信じて疑わない船乗りが水平線を見つめるような目で、僕は彼女の目を見つめていた。
気がつくと、僕は星を見ていた。夜空に放り出されたかのように、視界の外側にぱちぱちと光る星が見えた。僕は、彼女にビンタをされたのだ。左のほほがひりひりと痛い。目の前の彼女は、野球のピッチャーが渾身の一球を投げ込んだ後のような体勢で、右手と僕を交互に見ていた。
近くに、5人ほどの人だかりがあった。彼らは驚いてはいなかった。彼らは待っていた。ビンタされた僕を助けることよりも、僕の口から発せられる一言を待つことのほうが重大任務だと、彼らの顔は語っていた。後ろを見ると、30人ほどの人が僕を見ていた。彼らもまた同じように、僕の一言を待っているようだった。笑いを堪えるような表情の者もいた。僕以外の全員が、僕がビンタされることを予期していたかのようだった。
誰も、何も言わない。僕は、ここに味方がいないことを悟った。ここにいる人々は、皆一様に僕がビンタされることを知っていた。知ったうえで、僕がビンタされることに異議を申し立てる者はいなかったということだ。
世界が、僕の知らないところで、知らないうちに僕をはじき出そうとしている。僕は、深い井戸の中に投げ込まれたような感覚に陥った。僕が言葉を発するまで、僕は深い井戸の奥へと落ち続けていく。人々は、井戸の上の明るい陸地から暗い闇に落ちていく僕を見ている。「早く何か言ってごらん」と、彼らの動かない口から声が聞こえてくる。
何かを言わなければ、この井戸からは出られない。深い井戸に落ち続け、生活用水と共に見知らぬ沼に流れ着いてしまう。何か言わなければ。何か言わなければ。何か言わなければ。
「これは容認されているんですか?」
咄嗟に出た言葉だった。井戸の上にいる彼らに聞こえるように、できるだけ通る声で、僕は言葉を届けようとした。
刹那、彼らはどっと笑った。そして僕の視界が明るくなった。井戸は消え、僕は皆と同じ場所に立っていた。近くにいた5人が、僕を迎えるような朗らかな顔で歩み寄ってきた。
「なるほど!全員不正解!」
ビンタをした彼女がそう言った。近くの5人は残念そうだったが、笑っていた。後ろの30人も、笑っていた。その笑いは、一人の人間を暗い闇に葬る冷たい優越感から生まれるものではなく、そこにいる全員で一つの命題を解いたかのような、開放感に満ちたあたたかな笑いだった。
気がつくと、僕も笑っていた。判然としない意識の中で、皆が笑っていたことが、たったひとつの正解であるような気がした。
あとがき
先日、人力舎同期3組(オールドトム、コガラシガーナ、ハンサム金魚)によるユニットライブ『俺の左手』が開催された。そのライブの中で「クイズ!鈴木ジェロニモのリアクションを当てろ!」という企画が行われた。ハンサム金魚・寺田が僕にビンタをして、そのあとの一言を当てるというものだった。

指を差されている男性は平山で、サスペンダーをしていない女性が寺田である。
この企画は僕には極秘で進められていたため、僕は楽屋から突然呼び出され舞台上に立ち、寺田にビンタされるという理不尽な仕打ちを受けた。上に書いた内容は、寺田にビンタされてから僕が一言を発するまでの一連の流れと僕の頭の中で起きたことの一部始終である。上の文章中に登場する「彼女」とは寺田のことであり、「5人」とは鈴木と寺田を除いた『俺の左手』メンバー、「30人」とはお客様のことである。僕が発した「これは容認されているんですか?」という言葉を的中させた者はなく、クイズは全員不正解に終わった。
この企画はいわゆるドッキリの流れを踏襲して進められたわけだが、ドッキリを受ける者はこれほどの孤独感や精神の浮き沈みを一瞬のうちに経験するのだと、身をもって学んだ。寿命が縮んだような気がした。被験者の寿命と引き換えに笑いを生むのがドッキリである。
ユニットライブ #俺の左手 のライブ映像が発掘されました。以前に更新したこちらのnoteと併せてお楽しみください!
— 鈴木ジェロニモ (コガラシガーナ) (@suzukigeno) October 14, 2019
「これは容認されているんですか?」|鈴木ジェロニモ (コガラシガーナ)|note(ノート) https://t.co/NQnqkO2Hyw pic.twitter.com/lbA0ZB3SAW
ご来場いただきまして誠にありがとうございました。
大きくて安い水
