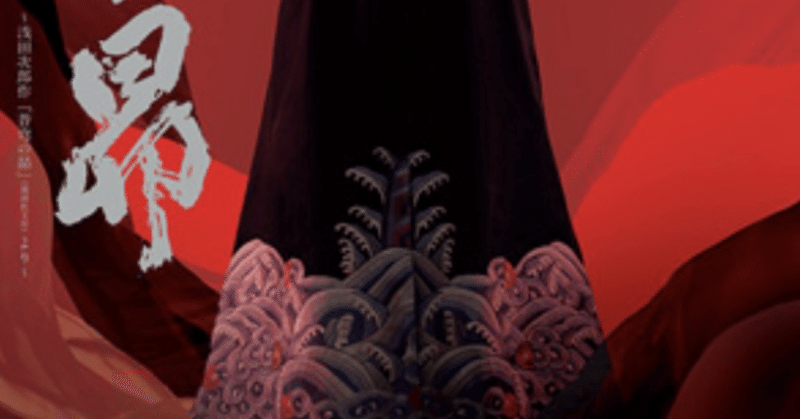
舞台で描かれていないエピソードを補完して観る「蒼穹の昴」②
雪組公演「蒼穹の昴」東京公演千秋楽まで完走!おめでとうございます!!!
なんとか千秋楽までに、ギリギリセーフで間に合った!!
千秋楽ライブ配信のお供にして頂けたら嬉しいです。
無事にメリークリスマス!と言えて嬉しいです。それでは第二幕も長文でお届けしまーす。
第ニ幕
第1場 楊喜楨の死
栄禄(悠真倫)たちが楊喜楨(夏美よう)の死体が消えたことをありえない、本当に殺したのか、と慌てながら話している。
変法派の支柱、楊喜楨(夏美よう)が殺された。復讐だ!行くぞ!と騒いでいる変法派の面々に文秀(彩風咲奈)は冷静に皆を諭す。
「落ち着け。騒ぎ立てるな。」
「君はなぜそんなに冷静でいられるんだ!楊先生が殺されたのだぞ?」
「栄禄(悠真倫)たちは楊先生の死を願っているのではない。我らの騒ぎを待っているのだ。騒げば、西太后さまを亡き者にしようとした大逆の罪で徹底的に潰される。奴らの思うつぼだ。しかも、清国は外国にも狙われているだろう。騒ぎに乗じて外国の軍隊が攻め込んでくる可能性だってある。いいか、楊先生は本日夕刻、密かに杭州の郷里へとお帰りになったのだ。他に何も起きてはいない。」
「西太后(一樹千尋)が黒幕だったとしてもか?」
「ありえない。他ならぬ楊先生が言っていたからだ。そもそも西太后さまは光緒帝陛下を愛しておられる。陛下を悲しませるようなことは決してなさらない。まして楊先生は陛下が信頼されている家庭教師だ。このまま西太后さま御引退に持ち込み、光緒帝陛下の親政を開始するのだ。」
変法派の面々の頭の中に、いろいろな思いが渦巻く中、文秀は楊先生のご遺体を決して露見しない場所…そう、飲み仲間である畢五の家に運ぶのであった。少年を宦官にする場所など、誰も寄り付かないだろうから。
第2場 紫禁城(寧寿花園)
西太后に仕えるようになった春児は瞬く間に西太后のお気に入りとなり、出世していた。西太后はどこへ行くにも西太后は春児を連れていく。西太后付き筆頭宦官として、西太后の悪いイメージを覆すために、トーマスや岡など外国人記者の取材を受けることを許されるほどの信頼ぶりである。その取材の帰り、春児は久しぶりに畢五の家へ向かった。中にはなにやら人がいるようで、畢五は出てこない。
家へ入り居間に上がりこんだとたん、春児は立ちすくんだ。椅子に座り暗い顔を向けたその男…文秀がそこにいたのだ。
「あの、その、これから一杯やろうとしてたところでな。」
畢五が狼狽しながら言う。しばらくの沈黙を破ったのは文秀だった。そして、お互い、職務上の言葉を投げ合う。
「まぁ、座れ。知らぬ仲じゃないんだ。」
「ほどなく大臣になろうというあなたが、こんな所で酒なんて、あまりよいことではありませんね。」
「李春児さん。あの、楊先生暗殺の企てを知らせる手紙を物乞いに預けたのは、あなたでしょう。あなたに読み書きを教えたのは私です。それくらいのことわかります。筆跡が私の手癖そのままですから。」
「はて、何のことでしょうか。」
「李春児さん、こうして酒を飲むのは初めてですね。」
「いえ、お忘れですか。子どもの頃、私はあなたにいたずらに飲まされて、大爺様に怒鳴りつけられたことがあります。河に放り投げられました。」
「あぁ、そうでした。私もろとも突き落とされた。」
畢五が我慢ならず叫んだ。
「あぁ、俺は見たくねぇ。一人ずつここへ来るたびにお互いのことを気遣いあっているお前らが敵同士だなんて。殺し合うなんて。」
畢五が部屋を出て行くのを確認してしばらくたった後、文秀は昔のままの言葉を口にした。
「なぁ春児、俺はお前に秘密を持ちたくない。もしお前とこのまま縁が切れれば俺は一生悔やむだろう。あの時、ひどいことを言って喧嘩別れしちまった。許してくれないか、春児。」
「もういいよ、そんなこと。おいらが勝手にへそ曲げたんだ。玲玲はどうしてるの?」
「元気だよ。何一つ不自由させていない。きれいな娘になったよ。」
「文秀はどうしてそんなに優しいの。文秀がいなけりゃ、おいらも玲玲もとっくにのたれ死んでいた。」
「いいや、お前は立派に出世した。俺は内心鼻高々だ。」
語り合ったあと、文秀は楊先生の遺体を春児に見せる。春児は必死に西太后さまの命令ではない、と訴えるが、それはもちろん文秀も理解していた。
「春児、力を貸してくれ。一日も早く、西太后さまを頤和園へお移ししてくれ。」
文秀はこれ以上、誰の血も流させない方法を考えに考えているのだ。
春児は梁文秀からの手紙を西太后に手渡す。
「楊喜楨(夏美よう)がそこまでの決心をして下野したとあらば、予もためらわずにこの玉座を降りなければなるまい。ただちに頤和園へ向かおう。」
その言葉を聞き、茫然と立ち尽くしていた栄禄(悠真倫)と李蓮英(透真かずき)が西太后に大声をあげて訴える。
「陛下、ただいまの言葉、よもや真意ではございますまいな、頤和園へお下がりになるなど。楊喜楨(夏美よう)がいない変法派など、無力です。叩きつぶしましょうぞ。」
「おだまり、載湉(縣千)がちゃんとやるわ。…あんたたち、まさか楊喜楨を殺したんじゃないでしょうね。」
栄禄と李蓮英は言葉を失う。
「調べるわよ?だって楊みたい常識的な男が私に一言の挨拶もなく里に帰るなんておかしいわ。白状おし。」
「西太后さま、それがしは楊喜楨を手にかけました。どうかご慈悲を。天誅であります。楊喜楨は皇帝陛下をそそのかし、恐れ多くも西太后さまを弑せんとしておったのでございますぞ。奴らは何をしでかすか、わかりません。」
西太后は栄禄の話を聞かず、頤和園へ向かうことを決める。しかし、紫禁城を出るこの機に乗じて西太后を弑せんという噂があることは事実である。春児の機転で、馬家堡駅の工事を見に行くという名目にし、道筋を変えて頤和園へ向かうことに決まる。
一方その頃、日清戦争の責任をとり、すべての職を辞して北京へ戻ってきていた李鴻章(凪七瑠海)と王逸(一禾あお)が清国の未来を憂いている。
「日本は維新の動乱の後に、伊藤と山県という傑物を残すことに成功した。革命では多くの人が死ぬ。どれだけの人材を生き残らせるか、それが問題だ。袁世凱(真那春人)はその器ではない。王逸、君が敗将の汚名を着たのは大きな誤算だ。しかし何としてでもこの時代を生き残らねばならんよ。全てはわしの過ちじゃ。袁世凱が援軍の君を正面に据えたまま兵を引くなど…」
「しかし、私は負けました。袁世凱は万兵を傷つけず率いたのに。私は袁世凱の強さがうらやましい。」
「それはな、将たる器のゆえではない。友を戦場に置き去りにして身を翻すことが真の強さだと思うか。わしが天津の軍をあやつに委ねたのは器量を見切ったからだ。小物ゆえにむしろ安全だと。袁世凱には何もできぬ。」
そこへ李鴻章のもとへ康有為(奏乃はると)からの書状が届く。李鴻章は王逸に、康有為をどう見るか問う。
「現実味に欠けます。孔子さまの教えを都合良く解釈しようとする無理があります。日本が40年かかった維新を我らなら4年で出来ると豪語しております」
「ばかな。日本が40年なら、我らは100年かかるよ。しかしそのようなことを公言しているとなると、穏やかではない。官位はなんじゃ。陛下に拝謁はできるか。」「できません。」
「そうか。しかし光緒帝は若く聡明だ。もし康有為と会ってしまったら。まかり間違えば爆発してしまうぞ。王逸、袁世凱の様子を探ってはくれぬか。康有為がことを急げば、袁世凱は握ってはならぬ鍵を握ってしまう」
王逸は李鴻章の懸念をすぐに理解した。康有為と光緒帝が変法維新を断行しようとすれば、都は大騒ぎになる。騒ぎが大きくなればなるほど、時代の鍵は兵を率いる者の手に転がり込んでしまう。王逸は天津へ急いだ。
王逸を送りだした李鴻章は胸をざわめかせていた。そこへなんと、旧知の白太太(京三紗)が訪ねてくる。
「李鴻章、袁世凱という男を殺せ。袁という男は破軍の星を持っておる。必ずや国を滅ぼし、多くの民を殺す。今ならまだ間に合う。殺すのじゃ。」
李鴻章は首を振って、その予言を拒んだ。
「袁世凱はそれほどの器ではない。いざとなれば恭親王(日和春磨)殿下がいらっしゃる。私が下野した今、あの方が最も力のあるお方だ。天津総督・袁世凱であろうと逆らえぬ。」
「だめじゃ。確かに恭親王はこの国のかすがいじゃ。しかしのう…命運じゃ。まもなく血の病に倒れるであろう。既に袁世凱は、破軍の星に護られておるということじゃの。」
「まことか。誰か、ここへ。駅まで早馬を出せ。王逸に、これを!」
そう言って書簡と愛用の銃を手渡した。書簡には…
『王逸よ、必ずや袁世凱を殺すのだ』
トーマス(壮海はるま)が岡圭之介(久城あす)にスクープを話す。そして、ミセス・チャン(夢白あや)もいる。トーマスの恋人?であり、優秀なスパイ技術をもっている。世界中の言語を話し、変装の名人だ。楊喜楨(夏美よう)の死体が運び出されるところも、変装して見ていたらしい。
「ケイ、聞いたか。袁世凱暗殺未遂が起こったぞ。犯人はわからんというが、李鴻章の銃をもっていたらしいから王逸に間違いない。」
「李鴻章の下野ですべての均衡が崩れた。今や恭親王(日和春磨)くらいしか頼れる者はいない。かつての帝の弟でヌルハチ公の嫡流、政治経験も豊富だし、外国にも顔がきき、栄禄(悠真倫)たち保守派と変法派の二大勢力を制御できるただ一人の人物だ。ところが…もう長くはないらしい。袁世凱と栄禄がもし繋がったら…清国に火がつくぞ」
「和解だ!今のうちに和解させなくちゃ、そうだろ!トム」
「無理だ、ありえない。康有為、こいつがマッチポンプだ。聡明で穢れのない光緒帝はこいつの夢のような思想にイチコロだろうよ」
「康有為を制御できるやつはいないのか?」
「梁文秀。こいつくらいだな。3度会ったがひとかどの人物だ。楊喜楨暗殺の後も、変法派が騒ぎを起こさず冷静を保てたのは梁文秀がいたからだ。敵の作戦を読むことができる。ああいう男を殺してはならん。必ず歴史を作る。しかし、どうなるか。」
「順桂、この人は?満州人の変法派など珍しいじゃないか。」
「会ったことはないが恭親王(日和春磨)に可愛がられているらしい。今のところ、この男に関する情報はまるでない。」
袁世凱暗殺に失敗した王逸は、捕らえられている。苛酷な取り調べに、石のように黙り倒す王逸を見た後、袁世凱は「殺せ」と部下に命じた。しかし、まだ生きている。恐らく袁世凱は、王逸が李鴻章の命で殺しにきたことに気づいている。そして、その理由を知りたいのだろう。
王逸の牢屋には、小梅という盲目の少女が食事を運んできてくれる。何もすることがない牢屋での生活で、王逸はその少女に文字を教えた。貧しい少女にとって文字は希望であり宇宙である。その後、王逸はその少女に助けられ、脱獄する。逃げに逃げ、何日も飲まず食わずで、もはやこれまでかと思ったとき、ある少年に助けられる。そして、王逸はその少年の家庭教師となる。その少年こそが…。こうして、かつて白太太が王逸に伝えた「天に選ばれし者。天下をとるものを護る者。」というお告げがとうとう動きだす。それが実を結ぶのは…もっと先のお話だが。
第3場A 胡同A(菜市口の市場)
譚嗣同(諏訪さき)と玲玲(朝月希和)は市場で買い物をしていた。市場はにぎやかで、手毬で遊んでいる子どもたちもいる。
「君に話があるんだけど、だめかな。」
「なんですか、お話って。」
譚嗣同は答えない。身体を寒そうに丸めて、黒猫を撫でている。そして、何かを練習するようにブツブツとひとりごと。
「つくろい物ですか?お洗濯ですか?遠慮なく仰ってください。」
「玲玲さん、僕と、結婚してください。」
黒猫を抱えたまま言う譚嗣同の言葉を聞いて、玲玲は驚いて跳ねのいた。
「だめですか。僕のこと嫌いですか。光緒帝陛下の親政が始まれば、じきに僕にもお金が入ります。家も整えますから。」
「私、字も書けないし、身寄りもないから、お嫁に行けるなんて思ってもいないから…」
「いいんです、いいんです。ぼくだって身寄りがない。でもだからあなたを選んだんじゃありません。好きなんです。僕は一生、死ぬまであなたを愛し続けます。」
「急に言われても…私、いいことなんてひとつもなかったから」
「僕も同じです。いいことなんてひとつもなかったから、ひとつくらいわがままを言ってもいいかなと思って。だめですか。あなたにとってはいいことじゃないですか。」
「ごめんなさい。私、何が何だか…少し時間をください。」
そこへ胡弓の音が聞こえる。物乞いの安徳海(天月翼)である。
「旦那さま、お恵みを。」
譚嗣同は「すまない、これしかない」とありったけの銭を差し出した。そして、物乞いの身の上を思い、譚嗣同は泣いた。そんな譚嗣同に黒猫がまとわりついている。通りがかった康有為がその様子を見て言った。
「やれやれ、譚嗣同いいかげんにしろ。みっともない。」
「ちっともみっともないことじゃないわ。康先生は時々間違ったことをおっしゃいます。」
あの人と結婚したらきっと苦労するだろう、と玲玲は思った。
第3場B 胡同B(東安市場)
恭親王(日和春磨)は皇族でありながら、変法派に力を貸している。その中でも、同じ満州人である順桂(和希そら)をことさら信頼していた。
「そちはどう思う。」
「謀が栄禄らの独断であるにせよ、おおもとはイエホナラの女にござりまする。殿下がお命じ下されば、この順桂いつでも覚悟ができておりまする。」
「子は、いくつになる。」
突然、私事を訪ねられて、答えをためらったが順桂は答える。
「八歳と六歳は女子、男子はよちよち歩き始めたばかりにござりまする。」
「さようか、可愛いざかりじゃのう。…そちは子らのことを考えておるか。西太后を弑する大罪を犯せば、そちの家は一族郎党、皆殺しぞ。」
「承知いたしておりまする。すべては清国のため。わが家が代々受け継いだ宿命、ヌルハチ公の遺命をゆめゆめおろそかにはいたしませぬ。」
「そちは忠義者よのう。」
そう言いながら恭親王(日和)は涙を流し、病に倒れ亡国の兆しを食い止められなかったわが身の無力さを嘆くのであった。そして、そこから多く時はたたず、恭親王(日和春磨)は末期の床に就く。文秀は「殿下、今少し」と念じ続けていた。西太后はまもなく頤和園へ退く。ようやく新時代が訪れようとしているのだ。栄禄たちの目も光っている今、政治の空白は作ってはならない。新時代の宰相は恭親王以外いないのだ。しかし、恭親王の命は消えようとしている。床の周りに居並ぶ面々を見ながら恭親王は言う。
「あぁ、満州の者が予と順桂、そちだけじゃ。なぜであろうか。」
理由は本人も周りもわかりきっている。満州人官僚はみな、栄禄についているからだ。李鴻章も見舞いにきた。その中で、恭親王はふいに力強い声で叫んだ。
「順桂、近う。………。よいな、順桂。」
恭親王は、誇り高き支配者の言葉…満州語で遺言を伝え、息を引きとる。
「順桂、謹んで恭殿下の御遺言を承りました。」
李鴻章はその遺言を聞いて、体中で怒りをあらわにしながら出て行った。李鴻章は漢人であるが、満州語がわかるのだ。
「勝手にやればよい。わしは知らんぞ。西太后も光緒帝も変法も維新も知らん。このわしが何年かかってもできなかったことがおぬしらにできるわけがない。また清国人同士が血で血を洗うのか。いやだ、もういやだ。」
日頃温和な李鴻章の剣幕に、一同はわけもわからず立ちすくむ。その場を去る順桂の耳には恭親王の末期の声が渦巻く。
『順桂よ、聞け。イエホナラの女を殺せ。』
悪の秩序が形作る無法地帯の東安市場を順桂は、一人歩く。世界中の言葉が入り乱れ、迷路のような阿片窟である。黒づくめの姿で濃い色眼鏡をかけた順桂は、その迷路を少しの惑うそぶりもなく歩き、目的地に着いた。そこは爆弾を密造する場所であった。中の男(蒼波黎也)に話しかける。
「入るよ、よろしいか。」
「おぉ旦那、上々だ。これなら投げ返されて自爆する心配がない。だが、その分あぶねぇ。針を抜いたとたんに爆発しちまう場合だってあるぜ。」
「それはいっこうに構わない。投げつけるつもりはないから。爆弾に抱きついてから、針を抜く。」
「正気か?あんたまで木っ端みじんだぜ。なぁ、旦那は満州じゃねぇのか?皇帝と同族の満人が爆弾なんて…いったい誰を殺るつもりなんだ」
「私は、ここに出入りする客たちが一番殺したい奴を殺す。」
「そりゃあここに出入りする奴らが殺したい奴っていえば、このひでえ時代を作った西太后だが…旦那。冗談だろ。」
「いや、本気だ。私にはできる。」
「誰なんだ、あんた。」
見せられた名刺を男が読む。
「満州正白旗、総理各国事務衙門章京、順桂。おい、章京さまだと?」
「君たちが日の当たらぬ阿片窟で爆弾の密造をしなければならないのも、こんな生活をしているのも、みんな西太后のせいだろう。ちがうかね?私は君たちを裏切らない。だから、君たちも他言は無用だ。」
「いや、旦那、それにしたって…西太后と心中だなんて穏やかじゃねぇ。例えば一服盛るとかピストルとか…」
「おや、私の身を案じてくれるとは有難い。だが、これは私の使命だからね。決心がつかずに今日まで来たことを恥じている。私が尊重するのは結果だけだ。より確実な方法を選ぶだけだよ。あるだけの金を置いていく。」
「こんなに…だって、ご家族とかは…」
「家族も生きてはおれまい。金などいらんよ。」
そう言って順桂は色眼鏡をかけ、爆弾を隠し持ち、黙々と東安市場を横切った。
『わがいさおしは韃靼の風の染めたる旗なるぞ』
まだ見ぬ故郷の風が吹いた気がした。
第4場 馬家堡駅頭
駅の構内は大群衆で埋め尽くされていた。トーマスや岡など記者たちもいる。岡は先ほど飲んだソーダ水が効いたのかトイレへ。そこの鏡の中でちらりと目が合った色眼鏡の男、どこか見覚えがある。岡は何となく不穏な気持ちになり、男の使っていた個室を除くとそこには官服一揃いが脱ぎ捨ててあったのだ。
「トーマス!」
「ケイ、ソーダ水の飲みすぎか?」
「トム、これを見てくれ。」
「なんだ?章京職の官服ではないか」
「章京…そうだ、順桂だ。テロだ、これは変法派のテロだぞ!」
西太后の行列が現れる。西太后たちはヨーロッパに旅行したことのある鎮国公載沢(咲城けい)の説明に興奮していた。天気はあいにく雷であり、雷嫌いの西太后は怖がっていた。
そこへ色眼鏡をかけた男が雨に濡れて黒ずんだ服を着て立った。栄禄が叫ぶ。
「無礼者、西太后さまの御前であるぞ」
すると男は妙にあか抜けたお辞儀をし、よく通るはっきりした声で言った。
「西太后陛下。いや、大清を私せんとするイエホナラの女!ヌルハチ公の命により、お命ちょうだいつかまつる。」
男の袖口から火花があがる。男は飛び降りて春児を突き飛ばし、西太后に迫った。春児は唸り声をあげて突進し、西太后と男の間に入り込む。そのはずみに男の色眼鏡が飛んだ。
「おてまり、おてまり、花火のおてまり」
そこへ群衆の中から幼な児が、火のついた爆弾を追って走り出た。順桂は春児の手を振り払い、何のためらいもなく幼な児を拾い上げて母親に押し付けた。そして、息をのんで見守る民衆をいっぺんに見て叫んだ。
「伏せろー!」
そして自身は爆弾の上に身を伏せたのであった。
皆が避難したあと、事件現場に着いたトーマスと岡。悲惨な爆発の現場だった。トーマスは落ちていた砕けた色眼鏡を拾いあげて言った。
「ケイ、これはとっておけ。順桂のことはよく知らないが、1人の男が命を捨てた。歴史を作るためにな。」
岡は色眼鏡の破片をポケットにしまった。
第5場A 紫禁城(回廊)
夢の中で光緒帝はある歌を聞く。かつて父に教えてもらった韃靼の秘歌。
『わがいさおしは韃靼の風の染めたる旗なるぞ』
光緒帝(縣千)は最も寵愛する側室・珍妃(音彩唯)と共にいた。そして光緒帝の行くところには必ず蘭琴(聖海由侑)が付き従っている。
「西太后さまは雷がお嫌いじゃ、大丈夫であろうか。」
そう言って心配する光緒帝のもとに「西太后暗殺未遂事件」という火急の知らせが届く。
光緒帝は身の潔白を証明するためにも、西太后のいる頤和園へ行こうとした。しかし、それは阻まれた。西太后は光緒帝に会おうとしないのだ。
更に、頤和園から西太后による詔書が出される。政治の実権は未だ西太后にあり、愛する西太后と話もさせてもらえない光緒帝は、もうどうしてよいかわからない。そんな光緒帝がすがったのは、康有為であった。
第5場B 紫禁城(養心殿)
ついに光緒帝は康有為を召見する。二人はこの日の到来を互いに熱望していた。康有為の書いた著書を読み、その思想に心酔しきっていた光緒帝にとって康有為はまだ見ぬ恋人に等しかった。
そしてついに、光緒帝は変法の詔書を出すのであった。
こうして、清国は西太后からの詔、光緒帝からの詔、2重の詔が出されるようになり、大混乱に陥る。
光緒帝の詔は多くの反感を買い、しだいに孤立していく。特に満州人の経済的特権を奪ったことと、科挙廃止で役人たちの怒りを買ったことにより、四面楚歌状態であった。
第6場 頤和園
西太后は湖のほとりで愛する光緒帝載湉を思う。
「春児ごらん。湖が美しい。」
「はい、西太后さま。」
あの子が私を殺すなど、そんなことするはずがない、順桂が勝手にやったんだろう。しかし、いや、まさか。あの親孝行な載湉が私を殺すなんて。駅での事件のあと、取り乱す西太后に皆、載湉が仕組んだことだと言った。春児でさえ、何も言わなかった…載湉の仕業ではない、と言ってくれなかった。
会えぬ、今はあの子に会えぬ。何も話せぬ。
私は何としてでもあの子を守りたかった。国を率いる孤独と苦しみをあの子に味わわせたくなかった。それでも、載湉が私を殺せと命じたなら、それは致し方のないことかもしれぬ。だが、このままでは載湉もこの国も壊れてしまう。
壊れ、破滅していく、この国を亡ぼすという大仕事をやり遂げ、嫌われ者になるのは、私だけで十分だったはずなのに。
第7場 紫禁城(養心殿)
光緒帝が変法の詔を出して3か月。維新政治は進むどころか、収拾のつかぬ大混乱に陥っていた。そして光緒帝の詔は無視され続け、変法派は孤立していた。梁文秀は光緒帝に参内する。
「なにゆえ康有為は予のもとに来ぬのじゃ。」
「恐れながら陛下。この3か月で出された詔は百十余にも及び、みな戸惑うておりまする。協議いたしまして、康有為の参内を止めております。」
「何の権限をもって!」
「康有為はすでに冷静さを欠いておりまする。」
頤和園の西太后さまの詔も出される今、光緒帝が出す詔はもはや紙切れ同然であった。
「なぜ、誰も予の命に従わぬ。なぜ天命を戴く中華皇帝の意思が天下に通じぬ。」
「康の申すところは誤りではありませぬ。しかし、大臣にも我ら同志にも計られずに詔を出されたのは失策でございました。」
「予は康の申すことがそちたちの総意だと思うていた。文秀、我らが目指す立憲君主国家において皇帝はひとつの役職にすぎぬな。予はそのことに気づかずいたから、詔は全能だと信じて難題を押し付けてしまった。その点、西太后さまの詔は現実に則していたのであろう。」
文秀は光緒帝の聡明さに驚いた。そして、なんとしてでもこの聡明な皇帝の世を作りたい、この劣勢を挽回せねばならぬと思った。文秀は伊藤博文(汝鳥伶)と袁世凱(真那春人)を味方につけること、西太后を幽閉する方法なしでは光緒帝自身が殺されてしまうことを進言し、了承をとった。皇帝は追い詰められていた。
第8場 玉河のほとり
文秀は天津の袁世凱のもとへ行く前に、玲玲がいる家へ戻る。
『この小さな命を守るのが、私の使命だ。その日その日を懸命に生きる四億の民を守るのだ。』
懐かしい話をし、玲玲を抱きしめながら決意を固める文秀であった。
第9場 天津総督府の執務室
栄禄の手と文秀の手、その2つを前に袁世凱(真那春人)は笑みをもらした。はっきりと、自分が時代の鍵を握っていると感じたのだ。いずれの手と組むか、袁世凱の肚はまだ決まっていない。変法派は科挙を経て役人になった者ばかりであるから、変法維新がなれば軍人である袁世凱の席はないと思っていた。しかし、光緒帝は袁世凱があれだけ憎んでいた科挙を廃止してくれたのだ。
「私に光緒帝殿下は何を期待しておられるのか。」
「栄禄を逮捕処刑し、頤和園を包囲する。あとは私がやる。国を保つには、西太后を除かねばならぬ。」
「それこそ大逆の罪ではないのか。」
「あなたには選ぶ権利がある。どうぞ自由にお選びなさい。」
「死ぬのは怖くないのですか。君ほどの人物なら望んで手に入らぬものはあるまい。」
「それは私の分を越えている。腹が満たされ、愛する人がいる、その上何を欲する。私はすでに満たされている、ゆえに死を恐れていない。」
袁世凱はその清廉潔白な強さに激しく嫉妬した。俺は決して満たされはしない。天下をとってやる。奴らを殺してやる。
第10場 破軍の星
「こんばんは、春児。おばあちゃまはお目覚め?」
孫の寿安が西太后を訪ねる。実は、寿安は普段はミセスチャン(夢白あや)としてスパイ活動をしている。
「いらっしゃい寿安。相変わらずのお転婆さんだこと。ところで寿安、おまえ載沢(咲城けい)と付き合ってるってほんと?」
「そんなんじゃないわ。載沢が勝手にのぼせ上って付きまとってるだけですわ」
「私はあれがあんまり好きじゃない。留学させたらすっかり西洋かぶれになっちゃって。外国人記者たちに、お城の噂とか、私のこととか、ありもしないことをぺらぺら喋っているのは載沢だろう。」
「確かにおしゃべりですけれど、おばあちゃまの悪口は仰いません。ただちょっとした冗談に尾ひれがついて…書かれちゃうの」
「いいかげんにしないと承知しないよって言っておきなさい。ほら、トーマスとかいうお前のいい人に。お前の正体は知っているの?」
「まさか。トーマスも載沢殿下もご存じないわ。」
「さて、内輪話はこれくらいにして。変法派の動き、どのようであるか。」
「謹んで申し上げます。梁文秀が袁世凱を訪ねました。そして袁世凱は栄禄に寝返りました。変法派の面々は伊藤公に会いに、日本公使館に向かったようです。康有為は同志を捨てて亡命したようです。林旭(紀城ゆりや)や劉光第(華世京)は今は黙して死ぬべしと申しおるそうです。」
「西太后さま。光緒帝陛下のご家族は西太后さまおひとりです。何卒お慈悲を持ちましてお助けを。」
春児は禁じられたことだと知りつつ、口を挟まずにはいられなかった。光緒帝を助けることが西太后の本心であると知っていたからだ。
「言うな、春児。」
西太后は悲しい顔を春児に向けた。あの事件で西太后さまが受けた心の傷は深い。助けたい。しかし、助けられない。寿安は続けた。
「そして、梁文秀は各国にも評判の高い者でございますが、各国の亡命の勧めを断じて拒んでいると。」
「…その者らは病み衰えるこの国を、命惜しまず救おうとした真の志士ぞ。やはり予は亡国の鬼女としてあの者らに殺されるべきだったか。こんな歳になっても、この国のために必死で勉学に励んできたであろう若者らを惑わしている…老いたこの身が憎い。」
「寿安、よく調べてくれた。何か褒美を。」
「では、命をひとつ、頂けますか。梁文秀の命を。トーマスに頼まれたの。きっとお国のためになる人だから、何とか助けられないかって。」
「困ったね。とうの本人が助かろうとはしていないだろうよ。そういえば春児や、おまえも同郷だとか。」
「梁文秀は、幼き頃より様々な恩義を賜った方です。どうか、なにとぞ。」
「おまえたちでなんとかできるの?助けられるものなら助ければよい。それを咎めはしないよ。」
第11場 日本公使館
文秀と譚嗣同(諏訪さき)は日本公使館でかれこれ1時間も伊藤博文(汝鳥伶)を待っていた。岡圭之介(久城あす)も同じ部屋にいるのだが、取材する気にはなれなかった。そこへ柴五郎(叶ゆうり)がやってくる。
「申し訳ありませんが、伊藤公はお二人とお会いになりません。」
「そうですか。ではひとつお尋ねしたいのですが、光緒帝陛下のご消息はおわかりになりますか。」
「南海の瀛台に幽閉されました。本日、西太后陛下が紫禁城に戻られました。」
二人は絶句した。
「実は今朝、光緒帝陛下付きの蘭琴が命からがら我らの隠れ家に駆け込み、伊藤公にご仲介をと陛下のお言葉を持ってきたのです。どうかもう一度…」
「閣下のお立場もお考えください。ただし、あなたたちの勤王の志はよく理解しておいでです。亡命の意思がおありなら保護いたします。清国の未来のために生きてください。」
「私は、科挙第一等状元の矜りにかけて、亡命するわけにはまいりません。」
伊藤博文がその部屋に現れたのはそのときだった。
「まだ肚は決まらんのかね。」
岡が慌てて通訳をする。
「日本の維新では多くの志士が命を落とした。しかし、わしや山県が生きながらえたからこそ国は成ったのだ。康有為は逃げたのではないね。難しい道をあえて選んだのだ。同志は一人でも多い方がよい。わし一人では何もできなかったし、康有為ひとりではおそらくなにもできぬ。」
生きながらえよと伝える伊藤公に文秀は言う。
「しかし閣下、私には宿命があります。」
「そんなもの誰が決めたのだね。ならばわしが生き延びて今があるのも宿命というのかね。この芝(叶)がなぜ君を熱心に説得するのかわかるか?この男はわずか10才で会津の戦に加わり、一族はみな死に、自分も深手を負った。維新のころはわしらと敵であったのだ。本来は死ぬはずであったものが生き延び、今こうしてお国の役に立っている。それは決して宿命などではない。生きようと、尽くそうと、努力したからだ。私はこの男を尊敬している。」
芝は、その言葉を聞きながら拳を握りしめて何も言わなかった。伊藤公の言葉をありがたく受けながらも、尊い家族の命が薩摩長州の維新志士によって奪われたことは変えようのない事実であるのだ。
通訳し終えた岡は自分の言葉で文秀に言った。
「生きてくださいよ、梁文秀さん。」
「君はどうするね。」伊藤は譚嗣同に聞いた。
「私は康先生や文秀さんのように出来がよくないので、この先生き延びても何の力にもなれないでしょう。それならば、血を流して、将来の革命家たちの勇気の源になりたいと思います。」
「さすがのわしも返す言葉が見つからん。」
譚嗣同にかつて命散っていった仲間の姿を重ね、文秀の答えを聞かずに伊藤は去った。死に場所を決めた者に言える言葉などもはやない。
文秀の決意は揺らがない。全ての望みが断たれた今、命生き永らえることに何の意味があるのか。すると日本公使館の前で警備兵と大声でわめき合っている者がいる。春児だ。我らを捕らえにきた栄禄らと共にきて、なんとか先回りしたのか。春児は泣き叫びながら文秀のもとへ走って来た。
「文秀、だめだ、だめだ、行っちゃだめだ。おいらを一人にしないでくれ。なんで死ななきゃならないの。悪いことなんて何一つしてないじゃないか。白太太はおいらに嘘をついた。おいらはちゃんとわかってたんだ。あのとき白太太はおいらに夢を恵んでくれだんた。」
「春児、お前…。良かったな、本当になったじゃないか。」
「運命なんて、頑張りゃいくらだって変えられる。なぁ、だから生きてくれよ。おいらがやったみたいにお告げを変えてみてくれよ。」
膝から崩れ落ちた文秀に譚嗣同が言う。
「文秀さん、なんだかよくわからないが君はここに残って難しいほうをやってください。僕は簡単なことしかできないから。」
公使館の外には、袁世凱や栄禄の兵隊が並んでいた。
「行こう、春児さん。君とは兄弟になり損ねた。心残りと言えばそれくらいだな。」
そう言って、譚嗣同は胸を張って歩いていった。敵兵の海の中へ。二度と振り返らずに。後を追おうとする文秀を公使館員たちが必死で抱きとめた。
第12場 進むべき道は
まだ名前のない黒猫を抱きながら、1人家にいた玲玲をトーマスが迎えにきた。
「君の兄さんにことづかってきた。すぐに日本公使館へ行ってほしい。」
「…兄さん?」「はい、李春児さん。」「うそ、出まかせ言わないで。」
「うそじゃない、梁文秀さんも待っている。」
生き別れた兄の使者を信じられない気持ちで見つめながら、玲玲はトーマスと連れ立って日本公使館へ急ぐ。道すがら、罪人の処刑に遭遇する。
「譚嗣同さん!!!」
「玲玲、行こう。見ちゃだめだ。」
「私見ています!ここでちゃんと見ていますからね!」
玲玲の姿をとらえ、玲玲の勇気に鼓舞されたように譚嗣同は叫ぶ。
「君らに賊を殺す力はあるが、難しい局面を打開する力はあるまい!僕は死に場所を得た!これ痛快!再見!」
玲玲は決して声を出さなかった。唇を噛みしめて見つめた。
『僕は一生、死ぬまであなたを愛し続けます。』
刃が降りる直前、にっこり笑った譚嗣同を見て、あの言葉を守ってくれたのだと気づいた。
トーマスと玲玲は日本公使館へ急ぐ。街は騒然となっていた。袁世凱は変法派に関わった者たちを炙り出して片っ端からとらえていた。2人が取り囲まれそうになったときに陽気な記者仲間ハンスが助けてくれた。
「亡命か。誰だね。」
「助かった。この方は梁文秀の秘書だよ。」
「なんてこった!わかっているのか、袁世凱たちの標的はそれだぞ?」
「ありがとうハンス、恩に着るよ。」
「あぁ、グッドラック」
第13場 紫禁城(太和門前)
譚嗣同の処刑を終えた栄禄と李鴻章が話している。
「閣下が天下をとるおつもりならどうぞ、この袁世凱と軍をお使いください。しかし、その後の天下は速やかに本官にお譲りください。」
袁世凱は明らかに栄禄を脅していた。
「冗談ですよ。では、これより包囲してまいります。」
「頼むぞ、他の雑魚はともかく梁文秀だけは逃がすな。」
そこへ幻だろうか、李鴻章将軍の姿が見えた。死んだはずの王逸までいる。
「なぜ殺した。忠義の若者を、言い分を聞かずなぜ斬ったのだ。」
李鴻章の切っ先を今にも受けんとしながら、栄禄は答える。
「西太后さまを殺そうとした大罪人ゆえ。」
「西太后の意思ではない。西太后は、あやつらの志をよしとすれば喜んで命を差し出すだろう。すべては汝の仕業じゃ。」
袁世凱はすぐさま馬から飛び降りた。
「閣下、お久しゅうございます。」
「どこの国の兵隊だ、わしはお前など知らぬ」
「閣下、ご冗談を…」
そうして将軍はきびすを返して去っていた。…幻だったのかもしれない。
第14場 日本公使館(玄関)
ミセスチャンこと寿安(夢白あや)は何も知らない鎮国公載沢(咲城けい)を連れ出し、馬車に乗り日本公使館へ向かっていた。
日本公使館では、文秀と玲玲が日本人の洋服を着て変装し、亡命の準備をしている。そこへ、文秀が身につけていた官服を着た岡が来た。
「この日本公使館の周りや塀の上にも見張りがいるのです。じきに迎えが来ます。わたしがこの格好で庭の目立つ場所にいればあなた方は疑われません。どうでしょう、名案でしょう。」
「あなたの身に危険はないのですか。公使館と言えど、袁世凱なら狙撃しかねない。」
「そのときはそのときだ。とにかく、ここはあなたの死に場所ではない。」
「私に死ぬ権利はありませんか。」
「あなたの同志は、あなたを生かすためにみな死にました。だからあなたには生きる義務があります。」
そう言って、岡は壊れた色眼鏡を手渡す。順桂の形見である。
「わかってください。みんながあなたにこの国の未来を託したんですよ」
そこへ鎮国公載沢の馬車が到着した。
日本公使館で文秀が演説をしている。袁世凱はイライラと言う。
「国際世論を味方につけたことを我々に見せつけているのか?」
「あれだけ記者がいれば、どこかの国が亡命の補助を申し出るのではないか?いや、梁文秀は大罪人。そんな者を匿う国などないか。」
「ええい、撃て、間違っても記者には当てるなよ。戦争になるぞ。」
「だめです閣下、当たります。」
副官がそう言ったとき、その騒ぎに乗じて鎮国公載沢の馬車が日本公使館から出る。乗っているのは日本人の夫婦だ。そして文秀は記者に取り囲まれながら中へ入ってしまった。さすがの袁世凱も諦めるしかない。
「もうよい、やめい。」
「馬車に乗ったのは外交官の夫婦でしょうか。」
「ふん、載沢殿下にも困ったものだ。大方お忍びで客を集めて舞踏会でもやるつもりなんだろう。まったくどうしようもない道楽者だ。」
天津へと走る馬車の中には、文秀と玲玲、そして載沢とミセスチャンがいた。何も知らない鎮国公載沢は日本人の男に話しかける。
「困りましたねぇ。僕は日本語ができません…やっ!誰かと思ったら文秀じゃないか!こたびのこと難儀であったの。して、なぜそちはそのような身なりで予の馬車に乗っておるのだ?」
「殿下、これから夜通し天津で仮装舞踏会ですわ!」
馬車が少し止まると、窓の外にはトーマスがいた。
「文秀、君を祝福に来た。グッドラック!もう一度、北京へもどってこい。俺は待っているぞ!」
そう言って愛用のウォーターマンを背広の胸に差し込んだ。
あれは誰かと問う鎮国公載沢にミセスチャンは言う。
「私の恋人ですわ」
「ハハハ!あなたという人は美しいだけでなく、機知に富んでいる。まさに才色兼備だ。」
「祖母に似ましたのよ。」
鎮国公載沢はミセスチャンの冗談に手を叩いて笑い、それを見ながらミセスチャンはぺろりと舌を出した。
第15場A 紅牆の道
春児は、西太后の書状を手に、急ぎ港に向走った。ひと目、文秀と玲玲に会いたい。しかし、立場と責任がそれを阻む。
遠いあの日、迷いの中で導かれたこの場所。
漆黒の夜に降り注いだ光…昴よ。
春児は、どうか、2人が無事であるよう祈るしかなかった。
第15場B 天津・大沽埠頭
その夜、港は深い霧に包まれていた。迎えの船は来ているが、波止場の霧に目を凝らすと兵隊がゆっくりとこちらへ近づいてくる。
「昨日のように殿下の御威光でなんとかなりませんの?」
「申し訳ございませぬ、殿下。この文秀、今更どうお詫びをしてよいものか。」
「よいよい。ちっとも良くはないが、仕方がないではないか。どうせ、予の命まで取ろうとは思わんよ。それより文秀そちは気の毒じゃ、万にひとつも助かるまい。」
指揮官らしき将校がやってくる。
「載沢殿下、恐れ多くも西太后陛下よりのお言葉を申し上げる。こちらは側近の李春児大総管さまが自らお運びになられた書状である。」
「あ?……誰も捕らえられぬのか?」
将校は頷き、咳払いをして読み上げる。
「載沢、汝は変法を騙りた主犯、梁文秀を見つけ、自ら天津まで連れてきたこと、ご苦労であった。然れども世界協和の理に鑑み、梁文秀をただちに日本へ引き渡すべし。」
平伏した載沢は我に帰って言った。
「何だかよくわからんが、ともかく僕は罪に問われず、文秀は日本へ行くと、そういうことですな?」
「まことにかたじけのうございます。このご恩はいつか必ずや…」
言葉を詰まらせる文秀に載沢は笑って言う。
「恩返しなどいらぬわ。そうだな、東京に何ぞ珍しいものがあったら送ってくれ。」
「行こう、玲玲。」
船へと急ぐ2人を将校が呼び止め、玲玲にあるものを手渡す。
「ご多忙ですぐに帰られた李春児大総管様より、預かっておりました。これをあなたにと。」
「何だね、玲玲?」
玲玲は溢れ出しそうになる涙を必死に堪えた。それはあの乾隆銭であった。自ら宦官になって、都へ登る兄へ、幼い玲玲が手渡した…せめて何か食べてほしいと手渡した、あの古い乾隆銭。わたし、不幸なんてひとつもないんだ。泣くことなんてない。本当なら父さんや母さんたちのように、死んじゃってたはずなんだから。泣いたら文秀さんが悲しむ。託された乾隆銭を握りしめると、玲玲の胸の中に炎が上がった。
「文秀さん、お兄ちゃんがどこかにいる!」
「春児が!?」
「ずっと前に約束したの。お兄ちゃんはきっと、家来を大勢連れて帰ってくるって。お金をいっぱい持って私の所へ帰ってくるって。約束したんだ。春児にいちゃん!!どこにいるの!!」
玲玲と文秀は確かに見た。堤防の端に、立派な杏色の籠に乗り、大総管という身分の印・孔雀の羽を頭に揺らした春児の姿を。運命は変えられるんだ、そう言っているような輝かしい春児の姿を。
「おおい、春児!!」
両腕を振ったが春児は答えない。しかし、文秀と玲玲が乗った船が遠ざかるのをじっと、見据えていた。おうちも無くなってみんな死んでしまったけれど、お兄ちゃんはちゃんと約束を守ってくれたんだ。泣くのを必死にこらえる玲玲を文秀は抱きしめる。
「春児、俺は必ず帰ってくる。この国の未来を築くために!」
昴よ、我らを導けー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
