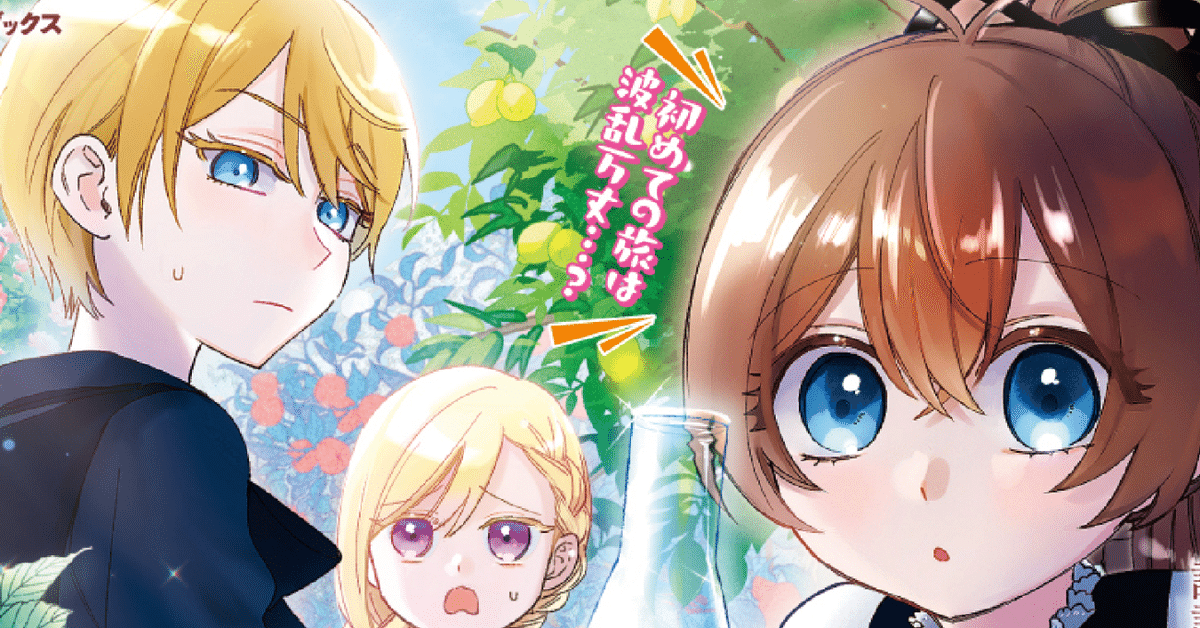
お姫様で、着せ替え――してみませんか? (書籍&コミックス2巻同時発売記念SS)
*コミックス収録描き下ろし漫画ネタバレ注意!!!可愛い描き下ろしを見てから本文を読むことをオススメします*
物持ちの良さ、とは一つの美徳だと思う。
私の名前はアリシア・ファーマン。ファーマン侯爵家の一人娘だ。侯爵家とは王家から別れた公爵家がない中では、王家の次に偉い。つまりヒエラルキーの上位に位置する家だ。
記憶が戻るまでは当然のように享受してきたけれど、前世の記憶が戻った時はそれはもう大変だった。だって今まではしがないOLで、オタ活のために日々節約をして過ごしていた。アレもコレも推しのため。
時には食事も我慢しつつ、推しのために貢いでいたのだ。そんな私に湯水の如く両親は大金を使っていた。
いや、今から考えればそこまですごい金額ではないのだけど……当時の私はこの世界の物価がわからなかったし、侯爵家の位置付けをいまいち理解していなかったからそう感じていたのだ。
だから両親にこれ以上買ってくれるなとストップをかけた。だってそんなに沢山服はいらないし、靴だって毎日出掛けるわけではない。宝飾品は言うに及ばず。子供に身につけさせるには早すぎると。
でも両親からしてみれば、侯爵家の令嬢として当然の扱いなわけで……必要経費なのだと納得させられた。これによって収入を得る人がいる。そして侯爵家の人間として相応しいものを身につける必要があると。
理解はできたが、納得するかと言えば別問題。私はそれでもなるべく、華美でなく物持ちの良い素材で衣服を作ってもらうようにお願いした。宝飾品は落としたら怖いから、もう少し大きくなってからとも。
だから私は他の貴族令嬢に比べれば衣服は少ないかもしれない。
それでも、それでも――――
「私でももっと持っています……ルティア様」
ため息まじりに告げれば、当のご本人はキョトンとした表情を浮かべながら首を傾げた。そんな私の後ろでは側妃であるマリアベル様が「あらあら」と声をあげる。思わずそういってしまうぐらい、ルティア様の部屋のクローゼットには服が少なかったのだ。
ことの始まりは、ロイ様にハンカチを返しに行った日のこと。あまり人目のつかない場所だと噂になっても困るから、とロイ様の配慮で離宮の庭でお茶をしていたのだ。するとたまたま散歩をしていたマリアベル様と鉢合わせた。現在ルティア様の離宮で生活しているのだからそんなこともあるだろう。
偶然とはいえ、側妃であるマリアベル様と出会った私たちはそこから一緒にお茶を飲むことになった。ハンカチを返しにきた、という私の話から最近の流行の話になったのは女性ならではだと思う。
そもそも一度嫁いでしまえば後宮から出ることはないのだ。そうなると王都での流行はわかってもそれ以外の場所のことはまずわからない。領地と王都とを行き来している私はそんなマリアベル様に新しい流行を伝えるには打ってつけの役だったのだ。
楽しくおしゃべりをしていると、不意にロイ様が「ルティアもそうやってお洒落に気を使ってくれると良いんだけどね」と。そこで私とマリアベル様は顔を見合わせた。
「そういえば、ルティア様とはあまりこういった話はしないですね」
「そうね。本を読んだ感想とか、畑のこととかは聞きますけど」
「カフィナも悩んでるみたいなんだよね。ルティアがあまりにも興味を持ってくれなくて。毎月衣服代が余ってるって……」
「衣服代……そんなに買わないってことですか?」
「そうみたい。着れるのだから別にいらないって」
「そういえば、視察の時もそうでしたね。街で見て回っている時もあまり興味がなさそうでした」
「ルティア様なら最近流行の洋服、すごく似合うと思うんですよね。こう、胸の下から切り返しのある服があるんですけど……」
「そうね。あとよく動き回られるから、ペチコートのレースをたくさん使って膨らませたらきっと可愛いわ」
ふわふわと裾が揺れて良いですね!といえば、テーブルの上にササッと紙が用意される。いつの間にきたのか、ロイ様の従者であるロビンさんが用意してくれたのだ。私とマリアベル様はああでもない、こうでもない、と言いながらルティア様に似合いそうな服をピックアップしていく。
「こんなのとかどうでしょうか?」
「こういうのも良いと思うの」
そんな感じで話していたらあっという間に時間は過ぎて……ルティア様に似合う服!と書かれた紙は、ロイ様が回収して侍女長のカフィナさんに届けられることになった。
カフィナさんにはとても感謝されたらしいが、それはそれとしてルティア様の衣装選びに付き合ってほしいとロイ様から依頼が来たのは必然だったかもしれない。だってこのクローゼットじゃ、私程度でも呼びたくはなる。
そんなわけで私とマリアベル様は渋るルティア様に新しい服を買いましょう!と説得している最中だ。その過程でクローゼットを見せてもらった。やはり新しい服を選ぶのなら、既存の服と被らないものやあとはコーディネートできるものが良い。あまり服に興味のないルティア様でも、持ってる服でコーディネートできれば喜ぶと思ったのだ。
今までの物を無駄にしない、ということになるしね。でも根はもっと深いのかもしれない。ルティア様は今までの生活が影響しているのか、ある程度の枚数があれば着まわせるし十分だというのだ。
ほんの少しだけ口を尖らせ、「これだけあれば十分だと思うの。だって先月も買ったのよ?」と。
「先月購入したのは4着だけです。月に7〜8着は作れるんですよ?」
呆れた声で侍女長のカフィナさんが答える。しかしルティア様は「着られるのだから必要ないでしょう?」というのだ。確かに私もそう思う。まだ成長期でもないし、そこまで急激に身長が伸びることはない。ならばそこまで衣服を揃える必要はないのでは?と。
でも高位貴族や王族はそれでは済まないのだ。手本となるべき者が見窄らしい格好をしていたら、民はついてこない。ある程度の見栄えは必要なのだ。もちろん税金をあげてまで湯水の如く使えと言うわけではない。
私はどう説得をしたものかとマリアベル様を見上げた。
「姫殿下、確かに毎月服を買うのは多いなという気持ちはわかります」
「そうなの。だってまだ私はお茶会を開いたり、パーティーに行くような年齢じゃないもの。着られる服があるならそれで良いと思うんです」
「そうですね。確かにそうなのだけど……王族や高位の貴族にはある程度の見栄えが求められるのですよ?」
「見栄え……ですか?」
「ええ。だって王様が見窄らしい格好をしていたらどう思うかしら」
「えっと……お金がないのかな?って思います」
「そしてもしその話が他国に伝われば、その国は危ういのではないか?とも思われるわ。もちろん湯水の如く使いましょう。というわけではないのですよ?品格を維持するための必要経費、というべきかしら?そういうものが私たちにはあるのです」
「ひんかく?」
ルティア様は軽く首を傾げる。するとマリアベル様はわかりやすく品格の意味を教えてくれた。品格とはその人や物に感じられる上品さや気高さ――――そういったものだと。
「上品さや気高さは、その人の内面が一番大事です。ですがそのサポートをしてくれるのが衣服なの。どんなに立派な王様でも品のない服を着ていたら残念に思うでしょう?」
「それは、確かに……じゃあ、私にもその品格が必要だから服を増やすの?」
マリアベル様は小さく頷き、どうしても必要なことなのだとルティア様に伝える。
「無理に毎月決まった枚数を買う必要はないけれど、それでも新しい服は買うべきですね。それに職人たちは常にドレスを作っているわけではないのはご存知ですか?」
「えっと、確か……その年、初めての夜会前が一番忙しいって言ってました。あとは年の終わり。毎月一定量で仕事があれば良いのにって聞いたことがあります」
「そうですね。夜会用のドレスを何着も仕立てる人は王族や、高位貴族くらいだけど……夜会がない時はどうすると思いますか?」
「仕立て屋さんの仕事があまりない?とかですか?」
「でも仕事がないと困りますね?」
「ドレスだけで一年分稼げたりはしないもの……もしかしてその為に、毎月服を買うの?」
マリアベル様によって導き出された答え。その答えにルティア様はカフィナさんを見る。カフィナさんは静かに頷いた。私はもうひと推し、と言わんばかりにルティア様に話しかける。
「定期的に購入できる人がしてあげないと、職人さんだって家族やお弟子さんがいるし生活が困っちゃいますよ?みんながみんな新品のお洋服を買えるわけじゃありませんし。私も決まった額までは買うようにしてます」
「アリシアもなの?」
「それでも普通の貴族令嬢よりは購入している数は少ないと思います。でも贔屓にしているお店が生活に困ったらイヤですし」
「そっか、贔屓にしてるお店も急にお仕事無くなったら困るわよね」
「そうなんです。王侯貴族の衣服を仕立てるということは、名誉なことですけど……逆を言えば、私たちの服を優先して作ってくれているんです。仕入れている布も私たちのための物。一般の人たちには高価すぎて手を出せません」
確かに、とルティア様は呟くと腕を組んで唸り始めた。きっと必要なことだけど、自分にとって本当に必要なことなのか悩んでいるんだと思う。ルティア様はお下がりも平気だし、手直しして着られるならきっとそのまま着続けけるのかもしれない。私だってできればそうしたいけど、それじゃあ需要と供給が見合わないのだ。一般的な人たちもそこまで衣服にお金をかけない。サイズアウトしたものは、古着屋に持って行って買い取ってもらう。そして新しい服もそこで買うのだ。
新品の、質のいい服を買えるのはお金がある人たちだけ。私たちはその「お金のある人」にカテゴライズされている。残念ながら。そして質のいい服は一般に流通しない。買ってくれる人がいないのだから、当然と言えば当然なのだけど。そうなると在庫を抱えることになる。利益が出なければ生活ができない。
もっとも、私たちが買わなくても別の誰かが買うのではない?と思うこともある。でもその場合、何か急ぎで用意したい時にお店は果たして最優先で用意してくれるだろうか?時折しか買わない客と、毎月のように購入してくれる客、同じ家格であればどちらが優先されるか、火を見るよりも明らかだ。
「……わかったわ。買う」
ルティア様は深いため息を吐くと、観念したように仕立て屋さんを呼ぶようにカフィナさんに告げた。ここまでくればあとは私たちの出番だ。ルティア様が飽きないように、それでいて興味を持つように話を誘導していくのみ!
私はマリアベル様と顔を見合わせ、そっと両手を合わせた。これでルティア様で着せ替え放題だ!!
「さ、では姫様の気が変わらぬうちにやりましょう」
カフィナさんがパンパンと手を叩くと、サッと扉が開く。そこには既に待ち構えていた仕立て屋さんたちが並んでいた。その姿を見てルティア様の顔がひきつる。
「――――もしかして、みんなして共謀した?」
「そんなことはありませんよ?」
「ええ、全く。ルティア様に似合いそうな服を色々着せ替えしたいなーってちょっと思ってますけど」
「やっぱりそうじゃない!!」
ハメられた!という表情に私たちは笑だす。でもこの場にルティア様の味方は残念ながらいないのだ。みーんなルティア様の衣装を作りたい!という人たちだけなのだから。
「さ、姫殿下。今のおすすめを一通り見てみましょうか?」
「それと今ある服に合う服もですね!」
「既製品も良いですけど、一から仕立てるのもいいですね。流行り廃りはありますけど、そういったものに左右されないデザインもありますし」
「さ、ルティア様!サイズを計りましょう?」
「なんでそんなみんなして楽しそうなの!!」
ぷくーと頬を膨らませ、いかにも不服です!という表情をつくる。そんな姿も可愛らしいだけなので、私もマリアベル様もとまるわけがない。カフィナさんも、その後ろにいる仕立て屋さんたちも手をワキワキさせながらルティア様をみている。
もう逃げ場はどこにもない。
「これで本当に品格というのが出るのかしら?」
「お姫様なんですから、これぐらいは慣れないとですよルティア様!」
もういやぁーと顔が物語っているけれど、女性がたくさん集まれば衣装を選ぶことに時間がかかるのは当然。ちょっと可哀想な気もしたけど、心ゆくまで堪能させてもらった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
