
目の前にあるということ、目の前にいるということ。
身体の内側がざわめき立つそんな本に出会った。
紙の本に触れながら、文章に触れながら何となく読み進めているときに、突然 心臓が飛び出るかと思うほどドキッとしたり、思わず息を止めてしまうくらいハッとするようなひとつの文章に出会うことがある。
「赤い実はじけた」を思い出した。
特に理由は必要ない。
赤い実がはじけた。
はじき飛ばされた先にある場所に飛び込む。
ただそれだけ。
春は別れと出会い、終わりと始まりの季節。
自分のなかの何かが終わり、新たな芽吹きへと形を変えるのかもしれない。

ただ、そこにいる人たち

みんながそれぞれに、ただ、そこに、いたいようにいた。名札をかけているわけではないし、制服があるわけでもないので、もはやスタッフと利用者の垣根もない。利用者っぽい人がべつの利用者っぽい人をなだめていたり、利用者っぽい人とスタッフに見える人がふざけあっていたりしているので、そのわからなさがさらに大きくなる。ぼくも基本的には放置されている。ぼくは途中から自分の立場なんてどうでもよくなって、だれがスタッフで、だれが利用者なのか考えるのをやめた。存在することが、ただシンプルに許されている、そんな不思議な空間だった。

ページの終わりから始まりに向かって撫でる。
なんとも言えない気持ちよさ。



ここは、重度の知的障害がある人たちが通う施設だ。障害者施設というからには、なにかをつくったり、なにかを学んだり、なにかのカリキュラムをしたりしているはずだと思っていた。ところがちがった。この施設にあるのは「ただ、そこにいる」だけだった。そして、それがあてはまるのは利用者だけではない。スタッフも、ただ、そこにいる(ことを支える)のである。つまりそれで支援が成立するということだ。
けれども、それはもうひとつの、べつの厳しい事実を突きつけていた。ここは支援の場所である。当然なにもしていないわけではない。スタッフは「そこにいられるように」支援しているということだ。つまり、みんな支援されてはじめて「ただ、そこにいる」ことができているのである。逆にいえば、支援がなければ「ただ、そこにいる」ことも難しいということを意味している。
その事実に思い至り、ぼくはハッとした。集団行動を乱すとか、みんなを怖がらせてしまうとか、仕事にならないとか、彼らが排除される理由はいろいろあるだろう。なにかをずっとつぶやいていたら「やかましい、出ていけ」と怒鳴られるだろうし、落ち着かなくソワソワしていたら「仕事をしろ」と怒られる。彼らの行動の多くは「迷惑行動」とされてしまう。おまけに、少なくない利用者が食事やトイレにサポートが必要だ。「ただ、そこにいる」ことは、自宅を一歩出たら、というか自宅ですらとても難しいことなのだ。
その「ただ、そこにいることの困難さ」は、なにも利用者だけに限った話ではあるまい。ぼくたちは、ただそこにいるだけでは価値がないとされる社会に生きているからだ。生産性を問われ、だれかの役に立ったり、売上を上げたりしなければ存在価値を認めてもらえない。男らしさや女らしさ、父親や母親、会社の役職など、果たすべきさまざまな役割を押しつけられたりもする。ぼくたちは、ただそこに突っ立っているだけではダメなのだ。
ただ、そこにいるだけでいい。
この場所に漂うメッセージは、ぼくの中にもある「生きにくさ」も優しく包みこんでくれていた。そして同時に、ぼくがいかに「存在価値」のような概念にまみれているかを鋭く突きつけもした。ぼくは娘に「生まれてきてくれただけでいいんだ」なんていっておきながら、いろいろななにかを期待し、その期待を押しつけている。自分だって、フリーライターとして価値を生み、この社会の中で評価を上げなければ食っていけないと思っている。ぼくたちは、「いるだけでいい」と「いるだけじゃダメ」、その両方を使い分けて暮らさざるをえない。その大きな矛盾がなんだか鈍く痛かった。
けれど、その大前提を忘れてしまうのと、つねに立ち返るべきスタートラインに設定しておくのとでは、人への向き合い方は変化するのではないだろうか。すこし自分に引きつけていえば、娘に、いまよりももっと穏やかに向きあえるのではないかと思ったのだ。「こうしなさい」ではなく「それでもいいか」と穏やかにいまを受け入れる、という感じで。
最初はみんな思う。そこにいてくれるだけでいいと。けれどその「スタートライン」は、いつのまにかかき消され(というか見ないことにして)、ゴールラインばかりが、価値や評価の世界に先延ばしにされていく。ぼくたちは、もっとまえへ、もっとさきへと急き立てられ、ずっとずっと、そのゴールラインだけを追いかけてきた、そんな気がする。ぼくたちは、成果や目的、生産性というゴールラインではなく、いま一度、そもそもの「生存」が許される場所や「ただ、そこにいていい」というスタートラインを取り戻さないといけないのではないか。
ああ、なるほど。たけぶんって、ぼくたちが立ち戻るべきスタートラインのような場所なのかもしれない。ゴールばかりを追い求める社会で、そもそもの出発点に立てる稀有な場所。そんなことを、レッツに関わることになった最初の日に、ぼくはしみじみと感じたのだった。
自分の力で肉を獲る

「ーーーどんなに気性があらくて、人にかみつくような犬でも、つばをつけた食べものをあたえて、それを犬が食べた場合は、つばをつけたその人には、けっしてかみつかないばかりか、その人としたしくなると、言われているのです。」
(椋鳩十全集5「孤島の野犬」)

ぼくはいったん竹林からちょっと離れ、持ってきたおにぎりを取り出した。そして、念入りにつばをつけ直してから、そいつが警戒して立ち上がるかどうかギリギリのところまでじわじわと近づいた。
驚かさないように静かな動作でおにぎりを転がした。おにぎりはボーリングのボールのようにうまい具合に犬のほうに転がっていった。
「あ、このままだとあいつに当たっちゃう!」
と、ぼくが思った瞬間、そいつはパッと飛び起き、すごい勢いでおにぎりをガツガツと食べだした。その光景はぼくが椋鳩十の本で読んだそのままだった。
「やった!これでもうこいつらを飼いならすことができるぞ!」
うれしくて興奮したぼくが思わず身を乗り出したところ、そいつは「ウーッワンワンッ!」とその場でいかくしてきた。
ぼくは焦ってまたダッシュでちょっと離れたところまで逃げたが、犬は追っては来なかった。
「あぶないあぶない、油断は禁物や。三吉だった野犬をさわれるようになるのに1ヶ月はかかったんやしな」
「まあ、今日のところはおれの目の前でおにぎりを食べたんやから十分やろ」
と満足して家に帰った。
こんな感じの「野犬おにぎり作戦」を、ぼくはその後1週間ほど続けていたのだが、それは急に終わりを告げた。
学校が終わって帰り道に竹林をのぞくと、犬たちの気配がない。
しかも、捕獲用のオリがなくなっている!
近所のおばさんに話を聞くと、野犬狩りの人たちに連れていかれてしまったという。
「野犬狩り」とは保健所などによる捕獲事業で、野良犬の多かった当時は狂犬病対策のため積極的におこなわれていた。
針金の輪っかが先端についた長い棒を使って、専門の職員さんたちが犬の首をくくって捕まえていくのをたまに目にしたことがあったが、この空き地の野犬たちがやられるとは思っていなかった。
「せっかくだいぶなついてきたのに……」
と残念に思いながら、ぼくは家に帰った。
「かあさん、空き地に住みついとった野犬たち、保健所に連れて行かれたみたいやねん」
「まあしかたないかもしれへんね。近所の人もこわい言うてたし。別に悪いことはなにもしてへんかったけどなあ」

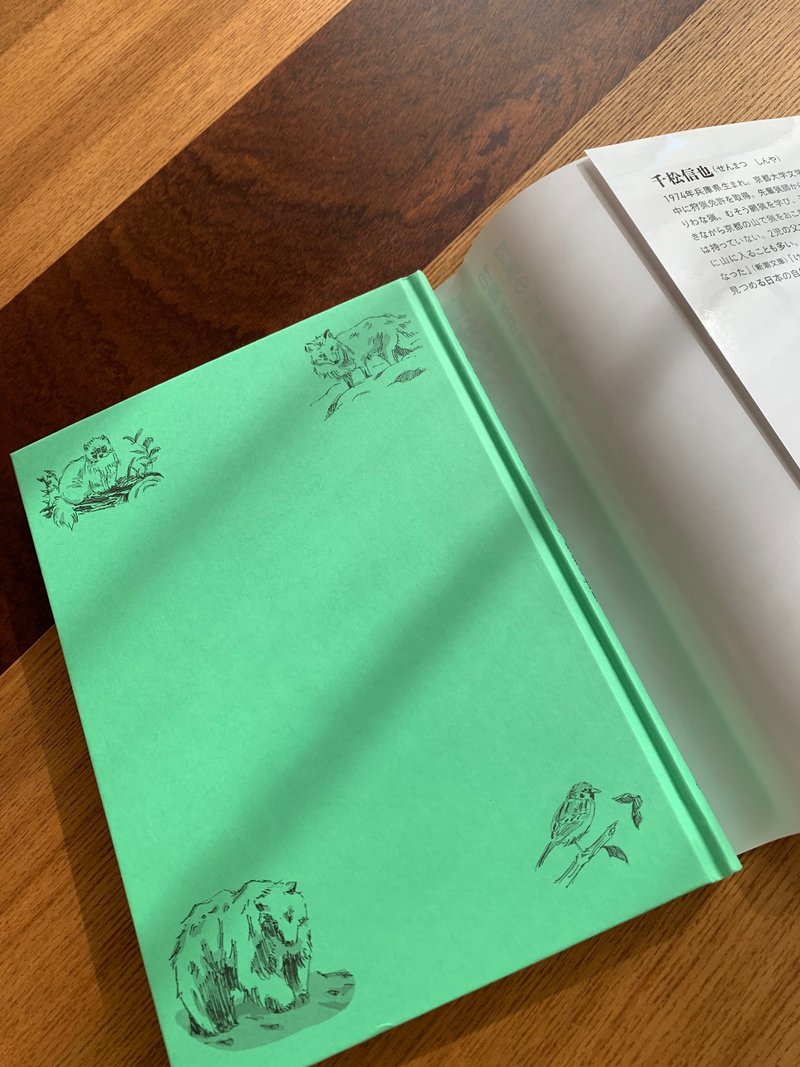

食べ物さえなんとかなれば、あとはどうとでもなるだろうと思っていた。
いつのころからか、漂流するかどうかに関係なく、自分が無人島や山奥でひとりぼっちで暮らしていくには何が必要なのかということに興味を持つようになった。
「かあさん、おれがひとりで1年間食べるんやったら、どんぐらいの田んぼがあったらええの?」
「せやなあ、うちの大きいほうの田がだいたい一反あって、あれでウチの7人家族分くらいあるし、あの5分の1もあったらじゅうぶんちゃうかな。畑もそれとおんなじくらいあったら、野菜もしっかり作れるわ」
一反はだいたい1000平方メートルなので、その5分の1だから200平方メートル。畑も200平方メートル必要なので、合計400平方メートル。つまり縦横20メートルずつの土地があって半分でお米、半分で野菜を作ればいいというわけだ。
意外とせまい土地で行けるんやなあとそのときは思った。
ぼくは狩猟を通して、自然環境や山の動物たちのこと、自分の食べ物のこと、ほかの生命をいただいて生きるということ、山村で引き継がれてきた歴史や文化などたくさんのことを学んだ。この本では、そんなことも伝えられたらいいなと思っている。

「モモ肉10キロください」
「追加で肩肉5キロお願いします」
こんな連絡が毎週のようにお店からくるようになった。
ぼくも大忙しだ。これまでよりもわなの数を増やし、イノシシねらいからシカねらいにシフトし、シカの気配の濃い猟場を中心に回った。
シカは順調に獲れていった。唯一の問題は、お店で使いやすいのは大きなブロックが取れるロースやモモ肉なので、自分の手元にスネ肉やクビ肉などの扱いにくい肉がたくさん残ることだ。いろいろと工夫してそういう肉を使ってくれるお店もあったけど、それくらいではなかなか使いきれない。その結果、我が家の食卓にモモ肉やロースが並ぶことはなくなり、スネ肉の煮込み料理や、切れ端部分の肉をミンチにして作ったハンバーグなんかが定番となった。「たまにはモモ肉も食べたいなあ」なんて冗談を言いながら……。
ひたすらシカをねらいながら何度かの猟期をすごした。
「あー、週末までにあとモモ肉10キロ欲しいって言われてたし、追加でわなを仕掛けるか……」
「あの山のイノシシねらいたいけど、シカ優先でいかないと、注文に間に合わへんやろなあ」
こんなことを考えながら毎日山に入っていた。
いつのころからだろうか。そんなぼくの中に、ある違和感が生まれていた。好きではじめた狩猟のはずなのに、いつのまにかシカを獲るのが義務や仕事のように思える。なんだか狩猟していても楽しくない……。
山の中に朝の光が差し込み、小鳥たちもさえずりはじめた。そんな山の中で何だかぼくは疎外感を感じていた。自分だけが自然の中に侵入した異物のように思えた。
「ああ、こんなことやってちゃダメなんかもな……」
ぼくは子どものころから動物が好きだった。動物の仲間になりたかった。山の中に分け入って、自分が食うための獲物を狩ることに憧れたのも、それが理由だった。はじめて獲ったシカの肉を友人たちと分け合って食べたとき、彼らが「うまいうまい」と言って喜んでくれたことがなによりうれしかった。自分や仲間たちの血肉となってくれる獲物を、知恵を絞り自分の力で獲ってこれたことは、自分も動物であることを実感できた瞬間だった。
それがいまは、誰だか知らない他人が食べるためのシカ肉を得るためにたくさんのシカを獲っている。そして、その肉が売り物になるかどうかばかりを気にしている。自然界の肉食動物だって家族や仲間が食べる分以上の獲物を獲ることはない。ぼくは知らないうちに、山の動物ではなくなってしまっていたようだ。
「もうやめよう。これは自分がやりたかった猟じゃない」
こういう暮らしをしていると、本当に山にはいろんな動物がいて、それぞれがつながりあって生きているということがよくわかる。狩猟という動物の命をうばう営みは、その部分だけ見ると残酷に映るかもしれない。でも、猟を続け、山の動物たちの血肉を食らうことは、彼らとつながることでもあり、自分もその大きな自然の一部だと実感させられる。ぼくの暮らしには、動物たちが元気に暮らしている豊かな山が必要不可欠だ。

ページの連なりが作り出す:模様
螺旋
🫀The Helical Heart ⑤
— purplepearl (@purplep76858690) March 8, 2023
At first I couldn't believe it, but when I saw his dissection, I felt the expression "the heart is a rope" was very appropriate.
心臓はらせん状🌪️
非常に驚き、最初は信じられなかったが、実際に彼の解剖を見て、「心臓はロープ」と言う表現がピッタリだと腑に落ちた https://t.co/uGJla9fAjT pic.twitter.com/HpzmKNQipu
赤い実と赤い鳥
陽のなかにも陰はあって
陰のなかにも陽がある
ただそこに居て、味わうこと
優しいなかにも残酷さがあるように
絶望のなかにも希望はあって
自然は優しさだけではないこと
厳しさだけではないことを教えてくれる。
それらはそのように見ている視点があるだけで、ただ起こるべくして起きているできごとに過ぎない。
「目の前のできごと」をどう捉えるのか。
みんな自由に思い思いの視点でそれを見ている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
