
小林さんとドラゴンたちから学ぶイシュカン・コミュニケーション
※『小林さんのメイドラゴン』はクール教信者による漫画だが、ここではアニメ化された作品を扱う
概要
人間がコミュニケーションを行う目的はさまざまだ。有用な情報の取得といった面や、巨大な社会を形成するためといった側面、あるいは、単にそれ自体が楽しいからといった意見もあるだろう。
『小林さんのメイドラゴン』からは、コミュニケーションを行う以下のふたつの目的を垣間見ることができる。
情報の共有
異なる人や文化と交わることによるアイデンティティの確立
1では、逆説的に、他民族との関わり合いに失敗し、情報の共有がなされなかったために文明が崩壊した例を示す。また、その失敗を避けるためになにができたかを作品から考察する。
2では、他者と深いコミュニケーションをつづけた結果、自己におよぼす影響について考える。
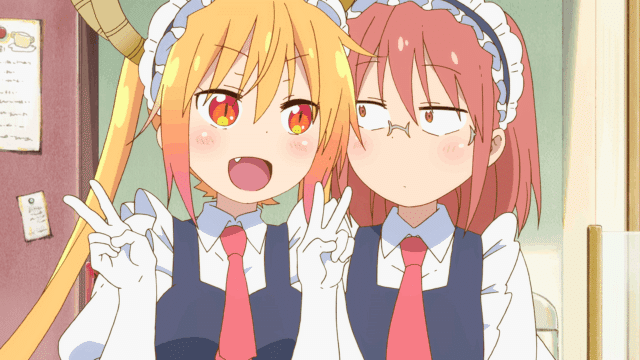
1.情報の共有
コミュニケーションの原義は、ラテン語 communis(共有される、同化する)である。(注1)
人間という種族は、価値ある情報を共有し、ここまで発展したといっても過言ではない。この見解に異議を唱える者は少数だろう。
だからここでは、異種間での対話を拒み、失敗した例を挙げる。
なるべく極端な、規模の大きいケースのほうが納得感が得られると思うので、ノルウェー領時代のグリーンランドの崩壊を紹介する。
時代は遡り10世紀、グリーンランドにヴァイキングが移住してきた。
ヴァイキングは恐ろしい海賊であると同時に、植民地の開拓者としての側面を持ち合わせていた。彼らはヨーロッパ大陸各地に進出し、やがて地元の人々に同化していった。
グリーンランド植民地は、13世紀にノルウェー王国の支配下に入り、約450年のあいだ存続していたが、最終的には崩壊し、西洋の歴史から一時姿を消した。
UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の教授であるジャレド・ダイヤモンドによると、ノルウェー領グリーンランド崩壊の理由は、中世ノルウェー人たちによる環境侵害、気候変動、ノルウェー本国との友好的な接触の減少、イヌイットとの敵対的な接触の増大、中世ノルウェー人の保守的な世界観の5つの要素から成るとしたが、ここではイヌイットの敵対的な接触の増大と中世ノルウェー人の保守的な世界観に焦点を当てたい。中世ノルウェー人がグリーンランドから姿を消したとき、極北の厳しい環境でもイヌイットが生き延びていた事実がわかっているからだ。イヌイットの生存は、当時のグリーンランドでも人間の生存が不可能でなかった証左である。
イヌイットたちは、ノルウェー人たちと異なり、極北の状況を知り尽くしていた。グリーンランドでは建材と燃料に使える樹木の入手が困難だったが、彼らにとってそれは問題ではなかった。雪を建材にすればイグルー(注2)を建てることができ、クジラとアザラシの脂肪を燃やせば燃料にも照明にもできた。彼らは、船をつくるための樹木がなくとも、骨組みにアザラシの革を張る工法によって、カヤックはもちろん、クジラ漁ができるウミアクと呼ばれる船もつくることができた。
また、イヌイットは、捕らえにくいワモンアザラシ猟に関しても特殊な技術を保持していた。そのため、ほかの種類のアザラシが減った時期に、イヌイットが猟の対象をワモンアザラシに切り替えたときも、ノルウェー人はこの方針を採用できず、餓死の危機に見舞われた。

イヌイットに支援を求めたり、彼らの知恵や技術を取り入れていれば、未来は変わっていたかもしれない。
しかし、中世のノルウェー人たちはそうしなかった。
1721年にデンマーク人が再入植したときには、スカンディナヴィア(注3)人とイヌイットの交易関係はスムーズに確立されている。
なぜ中世にはそれができなかったのか。
数世紀のあいだ、同じ土地に住んでいながら、中世のノルウェー人がイヌイットについて触れている記録は、ほんの2、3度だけだ。そのなかで彼らはイヌイットをスクレーリングと呼んでいる。スクレーリングは、ノルウェー人がヴィンランドとグリーンランドで接した3つの種族(イヌイット、ドーセット人、アメリカ先住民)に対し用いた言葉で、「愚劣な民」というようなニュアンスを持つ。このような態度で接していては、良好な関係を築くのは難しかっただろう。
さらに、イヌイットとの共存を阻んだ障壁に、ヨーロッパ人としての、キリスト教徒としての自己認識がある。
グリーンランドの人々がキリスト教に改宗したのは1000年ごろで、アイスランドをはじめとした北大西洋の各ヴァイキング社会とノルウェー本国も同時期に改宗している。
当時、グリーンランドには常駐の司教が不在だったため、ノルウェーから数人の司教が派遣された。その全員がヨーロッパで教育を受け、初めてグリーンランドに訪れた者たちばかりだった。当然ながら、この司教たちはヨーロッパを範と仰ぎ、アザラシの肉より牛肉を好んでいた。
司教たちが現地を訪れ、ヨーロッパの教会を模した教会が、1300年ごろまで建設されつづけた。教会には、壁や屋根を支える建材として希少な木材が大量に消費された。青銅製の鐘や聖体拝領用の葡萄酒など輸入された教会の備品にしても、積載能力の限られた船上では貴重な鉄の輸入量を減らす原因になった。
現代人は、この事実に触れ、「青銅の鐘を減らし、道具の材料となる鉄を増やし(注4)、またイヌイットから身を守るための武具、あるいはイヌイットから肉を入手するための交換品を増やせば、文明崩壊を避けられたのではないか」と考えるかもしれない。だがそれは、我々が後知恵を授かっているからであり、グリーンランド人の文化的伝統、ヨーロッパへの帰属意識に目を向けていないからだ。
ヘルヨルフスネス教会墓地に広がる永久凍土からグリーンランド植民地最後の数十年間に葬られた遺体が、良好な保存状態の衣服とともに発見された。
その衣服から、グリーンランド人が、ヨーロッパの優雅なファッションを取り入れていたようすが窺える。
寒冷な気候には、ぴっしりとした袖とフードのついたイヌイットの一体型の上着のほうが適しているはずだが、遺体が身に纏っていたのは、それとはかけ離れた衣服だった。具体的には、丈が長くて襟ぐりが深く、ウェストを絞った女性用の上衣や、男性用ではフープランドと呼ばれる華やかな上着があった。これは丈の長いゆったりとした外衣をウェストの位置でベルト留めするもので、袖は風通しのよいつくりになっている。ほかにも、前をボタンで留める上着、丈の高い円筒形の帽子などが見つかった。
以上のようにヨーロッパの様式を取り入れ、習慣に格別の注意を払っていた点から汲み取れるのは、「我々はヨーロッパ人でキリスト教徒だ。我々とイヌイットを混同してはならない」といった無意識の訴えだ。
長々と述べたが、上記のように、異種族間のコミュニケーションの拒否は、ひとつの文明の行方までも左右する。
他者との初接触
私たち現代人は、いくつかの例外を除けば、地球上のほとんどの種族と接触したあとの世界に住んでいるので、初めてほかの種族と接触することの難しさに想像がおよばない。
異民族間の初接触は、我々が想像するよりはるかに危険で緊張感を伴う。
そのような状況下では、先住民はまずこちらを侵入者と見做し、自分たちの健康や土地の所有権を脅かしかねない存在として認知する。どちらの側も、相手の出かたを予測できず、緊張と不安が場を支配し、逃げ出すべきか攻撃すべきか決めかね、相手が恐慌をきたしたり先に攻めてきたりしないかと神経を尖らせる。この状況を切り抜けるのはもちろんとして、友好的な関係に転じるためには、極度の細心さと忍耐が必要になる。
後年のヨーロッパ人たちは、経験により対処の仕方を学んでいったが、中世の人々は、その術をまだ手にしていなかった。イヌイットと友好的な関係を築けなかった中世グリーンランド人たちを、現代の我々が冷笑すべきではない。そもそも現代人ですら、異種族間でのコミュニケーションの齟齬が原因の争いが絶えないのだから。
異種族との初接触がいかに難しいかは理解できたと思う。では、小林さんとトールのファースト・コンタクトはなぜ成功したのか。
小林さんがトールと初めて邂逅した際の幸運が3つある。
ドラゴンが人語を理解できたこと
小林さんが酔っていたこと
小林さんの異種族と接するときの態度
1.ドラゴンが人語を理解できたこと
言語によるコミュニケーションの障壁は、人間どうしでも大きい。ドラゴンが人語を理解できたのは幸いだった。
トールをはじめ、カンナカムイ、ケツァルコアトル、ファフニール、エルマ、イルルといったドラゴンの面々は皆、日本語を話す。だが、彼らの言語体系が日本語に準ずるものだったと断ずるのは早計だ。彼らが住んでいたのは日本とはまったくことなる異世界だ。
ドラゴンが人語を理解し、流暢に話せるのは彼らの能力に起因している。
カンナカムイ(以下カンナ)が小林さんと喧嘩した回(注5)に注目してみる。家出したカンナは、ドラゴンの姿となってニューヨークまで飛び、そこで現地の人々の会話を数秒間見聞きしただけで、言語体系を理解し、会話していた。
おそらくトールも、小林さんと初対面する前に(街を飛翔しているときにでも)、この能力を駆使して日本語を習得したと思われる。

2.小林さんが酔っていたこと
トールと初対面したとき、小林さんは泥酔していた。そのときトールは巨大なドラゴンの姿だったが、小林さんは動じなかった。
小林さんは肝が据わっているので、酔っていなくとも物怖じしなかった可能性はあるが、大抵の一般人は未知の巨大生物を目の前にすれば逃げ出すか気を失うものである。

加えて、アルコールが人間どうしの絆を深めるのに役立っているのは周知の事実だ。(逆の場合も往々にしてあるが)
1600年初頭、オランダ東インド会社に雇われた航海士のヘンリー・ハドソンは、香辛料が多く採取される東インド諸島への新規貿易ルートを開拓するため大海原で舵をとっていた。その道中、ハドソンはマンハッタンに上陸し、原住民と接触しているのだが、円滑なコミュニケーションのためにワインなどの酒類を譲渡している。
欧州側の視点しか得られないのは、情報として偏っているので、2世紀が経過したのちマンハッタンで布教活動をしていた宣教師のジョン・ヘッケウェルダーが友人に宛てた手紙を参照してみる。
彼は手紙のなかで、ハドソンが上陸したときのようすが部族の口頭伝承になっていると知り、文字に起こしている。
「昔々、白い肌をもった人間のことなど原住民が知らなかったころ、漁に出ただれかが……はるか向こうの波間に、これまでに見たことのない何か大きなものが、泳いでいるのか浮かんでいるのだけなのか……」。各部族の長が集まり、議論した結果、この見慣れないものは巨大なカヌーで、なかに超越的存在《マニトウ》が乗っているということになった。
やがて、2人の部下を連れたハドソンが陸に上がってきて、族長たちと呪術師に挨拶した。それから彼は、透き通ったアルコールの瓶を開けグラスに注ぎ、飲み干した。彼はそばにいた族長に瓶とコップを渡し、呑めと身振りで伝えた。
族長はコップを受け取ったが匂いを嗅いだだけで隣の男に回し、その男も同じようにした。こうしてコップは輪になった一同のなかを一巡した。
コップがハドソンまで戻ったところで、原住民の1人が立ち上がって「中身が入ったままコップを返すのは失礼である」と熱弁をふるった。「だれも飲もうとしないのならば、自分が飲もう、結果がどうなろうと知ったことじゃない、と言って、コップを手にし、みんなに別れを告げてからグイッと飲んだ。結果がどう出るだろうみなの見つめるなか、勇気ある男はやがてフラフラしはじめ、地面に倒れた。一同、嘆き悲しんだ。彼は眠ったまま動かなくなった。みなは、息絶えたものと思った」
だが、数分経つと男は飛び起き、一同に、生まれてからこんなにいい気持ちになったことはないと口にし、もう一杯所望した。「彼はもう一杯貰い、みんなもそれに倣った。そして酔っぱらった」
このようにアルコールはコミュニケーションを円滑にする作用がある。
3.小林さんの異種族と接するときの態度
これがもっとも大きな要因である。
コミュニケーションを円滑に行うには、相手に対する敬意を忘れないことや、相手の考え方を否定せず受け入れたりする姿勢が重要であり、小林さんは丁寧にそれらを実行している。
では、なぜ、小林さんがそのような姿勢を貫けるかというと、コミュニケートする難しさを誰よりわかっているからではないかと考える。
カンナとの初対面で、彼女から信用できないと言われたときには、「知らない世界で誰も信じられない。当たりまえだと思う。私だって信じない。誰かを信じるなんてさ、友だちになったり、恋人になったりしたあとのことなんだよ」(注6)と発言している。この発言はネガティブにも思えるが、それでも小林さんはコミュニケーションを放棄せずカンナに手を差し伸べた。対話の煩雑さを知っているからこそ、他者の感情に機敏で、どういう言葉を相手にかければよいのかがわかるのだ。
また、トールと彼女の父親(終焉帝)の喧嘩を止めに入ったときには、「違いを知ることは単なるスタートだ。それを確認しながら近づいたり、離れたりを繰り返す。そしたら、ちょいちょい好きなところもできて尊敬だってできる。信頼も絆もできる」(注7)とコミュニケーションの本質を突いたようなセリフを口にしている。
他者とのコミュニケーションに対するロバストな姿勢こそが小林さんの強みであり、そんな彼女の魅力に多くのドラゴンたちは惹かれるのだろう。(注8)

そして、それはまたドラゴン側も同様である。トールは近所づきあいを楽しみ、商店街の人たちと仲良くする。カンナは小学校に通い、人間の子と同じように学び、遊ぶ。(注9)ドラゴンたちもまた、柔軟な思考を持って、人間社会に参画している。
以上のように、両サイドの他者に対する正しい姿勢こそが、人とドラゴンとの相互理解につながった。
2.異なる人や文化と交わることによるアイデンティティの確立
人間は内省によってのみ自己を認識するのではない。外部からの、他者からのレスポンスによって初めて自己を認識し、己がどういう存在であるかを知覚する。
とくに異文化コミュニケーションは、自分探しの旅であると言われる。自分と異なる人や文化と交わり、自分が何者なのかに気づき、発見されるアイデンティティは新鮮なものだ。
小学校、中学校、高校、大学、社会人とコミュニティが変わるたびに自身に求められる役割が変わり、それに伴い性格や価値観も変わったという経験はないだろうか。そして、その変動は、国内から国外へ移ったときのほうが大きい。留学経験、海外勤務の経験のある者ならば、日本にいたときの自分と海外での自分が、まるで別人のような感覚を抱いた者もいるのではないか。
トールもまた例外ではない。彼女は日本を訪れ、小林さんと出会い、新しい自己を開拓した。アニメ2期11話で彼女が日本にやって来た経緯が明かされるが、小林さんと共同生活する前の彼女は、己の居場所に苦悩し、自由を求めながらも自由を恐れていた。だが、小林さんと出会い、トールいわく、小林さんが「自由を怖がる私の手を、そっと引いてくれた」おかげで、彼女は居場所を、本当の自分を見出した。「私はメイドになりたかった」のだと気づけたのだ。

結び
以上、『小林さんのメイドラゴン』から抽出できる他文化と交流する意義について、情報の共有と異なる人や文化と交わることによるアイデンティティの確立を論じた。
もちろん、コミュニケーションは、上記で語った目的だけによって行われるのではない。概要でも少し触れたが、コミュニケーションには、それ自体が楽しいといった側面がある。その点に関していえば、ドラゴンと人間は近い存在だと解釈できる。小林さんの世界の人間たちとドラゴンたちは、自覚しているにせよ無自覚にせよ、コミュニケーションを楽しんでいるように映る。彼らの将来は、この先衝突もあれど、基本的には明るい未来が待っているはずだ。さて、我々の世界はどうか。
注釈
1.コミュニケーション学への招待 橋元良明 大修館書店
2.石や雪でつくる簡易的なシェルター。イヌイットたちは革製のテントを使っていたが、冬のアザラシ漁の際には、イグルーをつくりながら移動を繰り返していた
3.ノルウェー、スウェーデン、デンマークを含む地域の総称。 元来はノルマン人の国の古称で、フィンランドとアイスランドも含める場合もある
4.グリーンランドの鉄不足は尋常ではなかった。遺跡の地層の最下層からはいくつかの釘が発見されているものの、その後の地層からはほとんど出土していない。このことから、釘が貴重となり、廃棄できなくなったと推測されている。また、刀剣や兜といった類もほとんど見つかっていない。鉄器は摩耗して小さくなるまで研ぎ直され、再利用された。ほかにも、グリーンランドで鉄が欠乏状態であった事実は、遺跡から回収されたほかの品物からも見て取れる。欧州では鉄でつくられているものが、グリーンランドでは、ほかの材料で代替されていた。たとえば木を削ってつくられた釘、シンリントナカイの角でつくられた矢尻などだ
5.アニメ2期10話
6.アニメ1期2話
7.アニメ1期13話
8.小林さんの魅力に惹かれているのはドラゴンたちだけではない。彼女の職場の人間たちも、彼女を頼り、尊敬している。バレンタインデーにはたくさんのチョコレートをもらっていた
9.今回はトールと小林さんの関係にスポットを当てたが、作中、ほかにも人とドラゴンで良好な関係を築いているケースは多い。カンナと才川、ファフニールと滝谷、ケツァルコアトルと翔太など
参考
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
