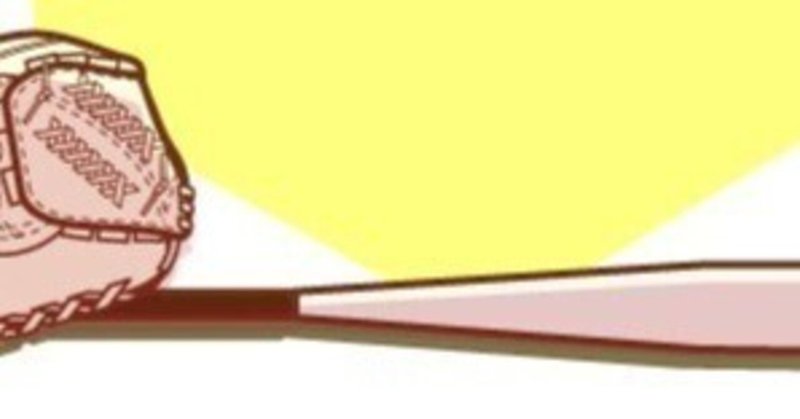
「小説 雨と水玉(仮題)(5)」/美智子さんの近代 ”夏の思い出”
(5)夏の思い出
次の夏、啓一の修士二年時の夏合宿には、学生責任者のY君らが活動を盛り上げようと女子を誘って彼女も初めて泊りがけの活動にくることになったらしい。さすがに一人ではということであと二人の女子大生を誘い、一週間の合宿が行われた。
啓一は大学院に進学してから、同級生であり親友でもあるOと二人して毎年夏一週間の合宿はいくことにしていた。その頃の国立大学の化学系の大学院の、夜中まで続く月月火水木金金の毎日は大変厳しいもので年に一回でもそのような楽しみがなければとてもやっていけなかった。体力系の啓一とOでそこは全く波長が合っていた。後期課程いわゆる博士課程への進学はしないことに決めていた二人にとってそれは最後の夏合宿だった。
その夏は、岡山の高原で実施され、気候やロケーション的にも申し分なかった。四年先輩で文学部の独文で学生を続けていたNさんに同行参加を嗾け、往復の運転者代わりになってもらった。
確かに同じ年頃の女性が一緒にいるというのは、ただただ体力系のサークルの合宿にとっていつもと違う華やかさがあった。
そういう雰囲気の中、あまり気を使う必要がないOBとしてただただ走りスポーツを楽しむという気楽な時間が啓一とOにはとても心地よかった。
毎日の運動を終えると疲れ切った身体から心地よく火照るものが感じられた。
風呂で汗を流した後、宿舎の外のベンチで沈みゆく夕日を見ながらOと二人で飲んだ瓶ビールの味は忘れがたい。あのような時間をその後の人生で持てたことが有っただろうか?
三日目の水曜日だっただろうか、美智子がふいにベンチの方にやってきたなり、今にも落ちていく夕日を見つめ、一瞬目をしばたたかせ、
「わあ、綺麗!、こんな夕日ってあるんですね、、、、、
こんなところで二人で黄昏てたんですね(笑)」
「うん、いいでしょ。あなたも一緒に一杯やる?(笑)」
「佐藤さん、飲んだらさっき頼まれたユニフォームつくろえませんよ!
いいんですか!」
「ちょっとぐらい大丈夫でしょ」
「わたし、お酒弱いんだから何もできなくなってしまうじゃないですか」
「それもいいんじゃない?(笑)」
「酔ってますね、全く、そんなこと言ってえ、能天気なんやから、、、、」
美智子は笑顔でそう言って足早に戻っていった。
啓一は、今さっき一瞬目をぱちくりして夕日を見つめていた美智子の美しい瞳を脳裏に描きながら、つい一時間ほどの前の会話を思い出した。
その日の午後終了近くに、六年間使っていたユニフォームが膝に力を入れたとたん、10cm以上ほつれてしまい、仕方なく三人いる女性の中で年長の二年生の美智子のところへ行った。
洗濯場に行くと、忙しそうに洗い物を洗濯機に放り込んでいる美智子の姿が見えた。
ほほとうなじの線ぐらいで切りそろえ、黒髪を向かって少し左から分けたショートのストレートヘアが少し下ぶくれの白い顔を際立たせ、きびきびとした動きと相俟って一層清楚な趣を醸していた。そして、黒ジャージのズボンに黄色クリームのTシャツはスポーツウーマンの彼女にぴったり寄り添い、清潔感を演出した。
啓一が近づいていくと、ちょうど汗と土で汚れた幾つもの着衣を上半身を折って取ろうとしていた。その一瞬間、彼女の首元の隙間から白い下着の一部とほどよい二つの小さなふくらみが、啓一の目に飛び込んできた。そこに少女から大人へと成長する女性特有のぞくぞくっとするコケティッシュな姿態があった。
啓一は、ドキドキっとしたが気を取り直して、
「忙しくしているとこ済まないけど、それで汚くて申し訳ないんやけど、このほつれたところ縫ってくれませんか?」
「はい分かりました。うーん、ちょっと難しそうね、どうしようかなあ、きれいにできないかもしれないけど、、、」
「そんなのかまへんよ。」
「我慢してくださいね。」
「いや全然問題ないよ。ありがとう。」
といって頼んだ。
一週間でほんの数回だけれど美智子と直接話す機会があったが、それとなくみていると美智子は誰とでも隔てなく普通に、多くは楽しそうに会話していた。その明るい爽やかな姿が心地よく感じられた。
それより後、秋か冬からは胸が疼くような感じを受ける嫉妬の感情をその時はまだ感じていなかった。
天候にも恵まれ、一日も活動休止することなく、存分にトレイニングにいそしむことができた合宿だった。啓一やOにとっても学生生活最後の活動が充実したものとなったのだが、一つには、彼女が皆のためにいつも甲斐甲斐しく動いてくれていたことがこの一週間をチーム活動としての中身を濃いものに仕上げていったように思われた。
そのことが啓一をして美智子への傾斜を強めさせていくことにもなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
