
深夜バスの話③温度との戦い
深夜バスでの移動中は外の景色も見るでもなく、スマホ等の明かりが使えるでもなく…友達とおしゃべりなど、問題外。基本的には全員一斉就寝RTAといった展開になる。たとえ寝付けない場合でも、「どれだけ体力を温存できるか」が翌朝以降の運命を分けることになる。深夜バスの移動は、旅の初日が始まる前のロケットスタート行為だからだ。お前はまだここで倒れるさだめではない。
1-5 あなたはなぜ死ぬか

水曜どうでしょうの企画でもお馴染みの深夜バス移動…腰へのダメージが最大の警戒ポイントと判断する人が多いと思う。何度も深夜バスに乗ってわかってきたのだが、バス内の気温条件がかなり重要な体力消費ポイントとなっている。シートと腰の相性、その日の腰の状態はコントロールできない要素なので甘んじるしかない。しかし、温度の問題だけは、確実にユーが対策することで問題に対抗できる。大体の問題は、「暑い」か、「寒い」かだ。準備し、確認し、対応しよう。
![]()
まず、準備作業。
バスに乗る少し前の時間に、自販機でお茶を購入する。具体的に言うと「キャップがはめなおせるタイプの275ml、缶入りの冷たいお茶」。これがあればベストの条件だね。このお茶の役割は、喉を潤す事と、夜行バスの車内が『暑モード』だった際に手のひら等経由で熱交換し、体温を逃がすためのものだ。家屋倒壊かなんかで生き埋めになったじいさんが、近くのひんやりした石を順番に握ってヒートシンク代わりに体温を逃し、一定の体温と体力を保って救助まで生きながらえた、みたいな話を参考にしました。命がけだね。
![]()
ユーが主要バスターミナルを出発地点にしたならば、現地の電光掲示板で60分くらい前から自分の乗るバスの情報が掲載されるはずだ。ネット予約したチケットはメールで便名や出発地・到着地の確認が取れるようになっており、電光掲示板で「そのバスが何番乗り場につくか」が確認できるケースが大半だ。(ローソンチケット払い等だと実際の券が発行されるかも)
乗車前は余裕を持って行動しよう…なぜかというと、「バスに乗る直前or休憩ポイントに着いた直後にやっておいたほうがいい作業」があるからだ。それは、「乗車予定のバスのナンバープレートを撮影しておくこと」。実は、深夜バスの運行ルートや休憩ポイントは複数のバスでほぼ共通している事が多いのだ。出る時間帯と到着時間帯が一緒なのだから当然といえば当然なのだ。これがどういう事かというと、「サービスエリアで休憩のためにバスを降りたあと、いざバスに乗ろうとすると駐車場に似たようなバスが4~5台並んでるのに初めて気付き、どれがどれかよくわかんねえ」という事実に直面して、死にます。なんとなれば、同じ会社が運行してるバスが複数いて見た目だって一緒ってこともあります。地獄です。だれだって死ぬのはまっぴらごめんです。ターミナルにいるときと違って、バスの外見からは便名がわかりにくいことも多いです。なので、乗る時、もしくは休憩ポイントでバスを降りた直後に、ナンバープレートを控えておきましょう。まじでわかんねえぞ。おれだけかな、こんなの。
![]()
話がそれました。温度です。バスに乗ったとき、すぐに「室内がむわっとして空気がこもってるか」「室内がひんやりとして寒いか」を感じ取ってください。コロナ状況下の場合、しっかり換気をしたり、4列シートも極力隣通しに客を配置しないようにしたりしているため、夏でも冬でもひんやりコースの場合がやや多くなるかもしれません。
『冷モード』の場合は比較的話が簡単。バックパックを棚に仕舞う前に一枚パーカーかカーディガンのようなものを出しておきましょう。えっバックパックじゃない?荷物預けちゃった?そういうのはしたことないのでわかりません。耐久訓練を開始してください。ちなみに、暑いと寒いの中間くらいだったら、出したうすべりは着込まずにひざ掛け、肩掛けのように体にかけておくと気温の変動に応じてよけておくこともできて過ごしやすいです。
問題は『暑モード』です。腰が痛い、寒いはコントロールしやすいのですが、「冷たさ」を作り出す機能は人体にないからです。というわけで、缶入りのお茶の出番となるわけです。熱伝導性のいいスチール缶やアルミ缶で体にこもった熱を逃がしつつ、必要に応じてちびちびと飲み喉の乾燥を防ぎます。喉の乾燥は大敵です…深夜バスの中で、誰かの咳なんて聞きたくないでしょう?

ほどなく、バスは一回目の休憩ポイントに到着します。東京発ならば、西ルートは海老名、東ルートは佐野あたりが初回の休憩ポイントとなることでしょう。時間は12時ちょうど、まだ起きていてもそれほどダメージがないくらいの時間でしょうか。ここでお手洗いと同時に、ここまでの移動を踏まえて飲み物を再調達するかを決定します。
バスが『寒モード』だったら、ここで熱源として缶のお茶を買ったり、カイロを買うのも一つの手です。『暑モード』の場合は、休憩ポイントで深呼吸&体温下げを行うと同時に缶飲料を再調達するのが最優先事項となります。ここでのポイントは、缶飲料は飲み物としての機能はあくまで副次であり、主目的は安価に「冷たさ」を調達するということです。つまり、喉かわいてなければ、飲まないでいいです。懐に置いて常温になるまでゆっくり体温を逃していきましょう。暑いと確定したあとなら、大きい500mlボトルを買うのも一つの手です。
ちなみに、座席の配置によっては、バスの窓側壁面にふれることでバスをヒートシンクにできる場合もありますが、衛生的にも特におすすめはしません。ガラス面のほうが効率的に熱を逃せると思いますが、カーテンに漏れると光漏れで周りのお客さんに迷惑がかかるので静かに煮えましょう。
![]()
二回目以降の休憩ポイントは、関東圏の気配が薄れ、いよいよ旅の気配が漂いはじめます。ただ、本当の深夜での休憩となるため、寝れる状況なら寝ておいたほうがいいとは思いますが、それでも眠れなかったら…仙台便だと、二回目の休憩は安達太良SAあたりになると思います。ここのSAは、自販機のところにウルトラセブンの立像がおっ立てられており、飲み物を買うとジョワ!みたいな声が出たりというギミックも仕込んであります。密かな観光スポットなので、見ておくのも一興です。円谷英二さんの出身地らしいっすよ。
※大阪以西、仙台以北だと日が登ったあとにも休憩ポイントがあるかもしれないぞ。やったね。
※買う飲み物、お水やお茶はいいけれど、コーヒーはおすすめしない。覚醒作用や利尿作用もあるんだけど、暗い中で手元におく飲み物は万一服にこぼしたときに染みにならない淡い色のほうが好ましいからです。

深夜バスの話はこれでおわりだよ。どっとはらい。
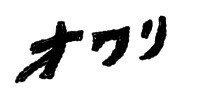
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
