
スタオケの期間限定イベント「The Nightmare Of Halloween」のストーリーを読む
ここでは、iPhone/Android向けソーシャルアプリゲーム「金色のコルダ スターライトオーケストラ」(スタオケ)にて配信された期間限定イベント「The Nightmare Of Halloween」(2022年10月24日~11月2日)のイベントストーリー感想を書いてみる。
例によってイベントストーリーのテキスト引用やスクリーンショットなどを交えての感想記事となる。範囲は「The Nightmare Of Haloween」に限らず、グランツ交響楽団のメンバーが関わった過去の期間限定イベントやSecondo viaggioシリーズの内容に及ぶので、ネタバレには十分ご注意いただきたい。
「天使の歌声」ルカ・ミュラー
これまでのイベントストーリーでも、いわゆるクセの強いゲストキャラクターは何人もいたが、今回のルカほど成長と変容を描写されたキャラクターはいなかった。前回グランツメンバーが勢揃いしたイベント「Music and the Fatal Ring」で、朝日奈本人がもがきながらもコンサートミストレスとして新たな力を獲得する中でのグランツメンバーとの交流を描いたのとは異なり、ルカを主役とすることで、グランツキャラクターの普段と違った側面が見えたと言える。メインキャラクターではないのに主役に据える都合もあって、他のゲストキャラクターよりも遥かに気を遣って(ユーザーが違和感なく受け入れられるよう)作成されたように見える。
少年合唱団のエース
ルカ少年の両親が「オーストリア音楽界の重鎮」というから、彼の所属している「海外の有名少年合唱団」はウィーン少年合唱団を想定していると見てよいだろう。
実際のウィーン少年合唱団は私立の全寮制学校(ギムナジウム下級校)として運営され、ソプラノとアルトのパートを務める10~14歳の少年が約100人在籍している。4つの団に分かれて音楽教育を施された彼らは、公演のために世界各地へ出張するという。そのようなバックグラウンドを持つからだろうか、ルカの口からは親についての話は出ない。
が、ストーリー中で指摘されているように、「天使の歌声」は期限付きである。モデルと思われるウィーン少年合唱団はギムナジウムの卒業年齢(14歳)に達するか、それ以前に変声するかすれば退団し、一般の普通校に転入することになる。年齢を重ねるごとに個人の歌唱技術は磨かれるが、声変わりがその独特の美しさを奪うという無情さを兼ね備える。少年合唱団はまさしく団員ひとりひとりの一期一会の美で成り立つ音楽芸術とも言える。
家柄・美貌・歌の才能に恵まれたルカは、それにふさわしい自信を併せ持っている。月城も「ルカの才能は本物だ」と認めるほどで、ストーリー中ではその月城と同質の存在として扱われる場面がある(第4話)。
自らの歌声を“もてなし”の対価、つまり他者に施すものとして扱いながら、ソリストの交替を示唆されると「ソロは誰にも譲らない」「僕が一番上手く歌えるんだから」と激しく拒絶する(第2話)。つまり、彼は歌うことそのものは好きで、譲れないこと、つまりアイデンティティーであるのだが、この時点で自覚しているようには見えない。
アポロン
ルカの幼少期から側仕えする執事ロボット。ルカは「僕の一番の友達」(第1話)、「僕の相棒」(第3話)と紹介している。ロボットではあるが決して無機質な機械ではなく、ストーリー内では人間味のある一人格として扱われる。こう書くとドラえもんを髣髴とさせると思いきや、ルカ様全肯定のスタイルを崩さないロボットであるため、グランツメンバーとしてはなんとも癇に障る存在として登場した。
ロボットということもあり融通の利かないアポロンだが、第5話では、故障して動けなくなる直前までルカの体調を案じていたことが示されている。

アポロンという名だけ聞けば、ギリシャ・ローマ神話の太陽神を思い出す人が多いだろう。人気があるゆえに光明の神、医術の神、予言の神など様々な側面を持つようになった神であるが、今回登場したロボットには「美少年を愛する芸術の神」の名を冠されたものと捉えることができる(アポロン神の“美少年を愛する”というのは文字通り少年愛嗜好を指すが、もちろん今回ロボットとして登場したアポロンにそのような要素はない)。アポロンに傅かれて登場したルカは、神の眷属(天使)であると同時に、音楽の神の加護を得た存在なのである。
黒橡との相克関係
序盤からルカに振り回されまくることで、コメディリリーフとしての役割を果たしている御門と大我。普段は最もコメディから縁遠いコンビであるだけに、意外な一面を垣間見ることができた。「天使の歌声」を持つルカは、概念的には天からやってきた神の遣いであるので、“地獄の釜の底”で喪の音楽を奏でるユニット・黒橡とは相性が悪いのもある種当然であろう。
そもそも御門と大我には、親を失ったために少年時代を強制終了させられ、精神的に大人になることを余儀なくされたという共通項がある。第3話と第5話で本人たちが話していた通り、“普通の子ども”とは縁遠い人生を送ってきているのだ。
ただ、ルカと黒橡の関係は単なる相克にとどまらない。それが明確に示されていたのは、イベントストーリー第6話でアポロンの故障をルカが知った場面である。“生まれた頃から一緒だった親友(=ほぼ家族のようなもの)”が動かなくなり、さまざまに手を尽くそうとしたり涙を流したりするルカを前にした御門・大我の反応は、明らかに共感を示すものだった。ルカが生まれて初めて知った大きな喪失を、このふたりはわがことのように感じるわけだ。後半のふたりのルカへの対応の軟化には、ルカの喪失体験が確実に影響している。

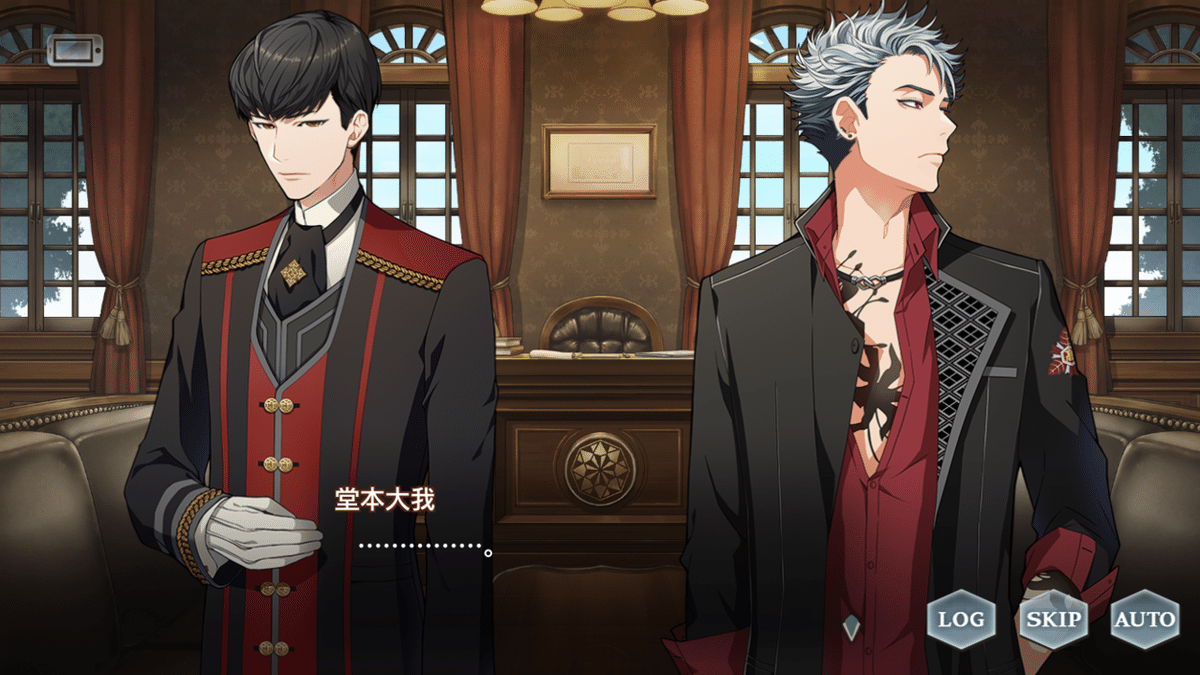
ストーリー構成
グランツ交響楽団のキャラクター4名がピックアップされた今回のイベント。花響学園がハロウィンウィークと称して敷地を一般開放するのに合わせ、グランツ交響楽団も海外の有名少年合唱団とコラボレーションコンサートを行うことになる。今回の朝日奈は一般人としてハロウィンイベントを楽しむために花響学園を訪れ、ひょんなことからゲストキャラクターであるルカ少年の話し相手を任される――という導入になっている。
そのようなわけで、今回の朝日奈は主役というよりはルカの見守り役として控えめな立ち位置にいる。ストーリーの主眼となるのはルカの変化の物語と、それに対するグランツサイドの四者四様のリアクションだ。
ルカの挫折と再生
アポロンの故障と声変わりの予兆というふたつの事件に見舞われたイベントストーリー第7話。ルカと大我の間で次のやりとりが交わされる。
ルカ「……世界中、いろんな教会に行ったことあるよ。合唱団として呼ばれて、歌って」
ルカ「みんな、すごい誉めてくれるの。感動したって、泣いてる人もいた。きっといいことある気がするって」
ルカ「喜んでもらえて嬉しかった。なんか、ほんとに神様の遣いになった気分だった」
ルカ「でも……」
ルカ「……違ったんだ」
ルカ「…僕ね、この一年ですごく背が伸びたんだ」
ルカ「たぶん、成長期が来たんだと思う。これから、もっと背が伸びる。体がどんどん大きくなって……」
ルカ「どんどん大人に近づいて。声も大人の声になって、大好きな歌が歌えなくなる」
堂本大我「声変わりが始まりかけてるの自覚してたのか」
ルカ「当たり前じゃん。自分のことなんだから、わからないわけない」
ルカ「でも、知らないフリしてた」
ルカ「……怖いよ。しかも、僕は替えがきくんだ」
ルカ「大事な歌声も歌える場所も失ったらいったい、どうしたらいい?」
ルカが歌うのはなぜか。ルカは「天使の歌声」を持っており、多くいる団員の中で一番うまく歌えるからだ。ではなぜ「天使の歌声」を持っているのか。神様に特別愛されているから――というのがルカの考えだ。だが神の恩寵として与えられた美声を失い、自分が特別な存在ではないと知ったとき、ルカは神の遣いどころかなにも持たないただの人間となる。加えて、合唱団の他の少年がルカのソロパートを歌うこともできることもわかった。このときルカを襲ったのは、アイデンティティーの崩壊である。
大我が「お前の替えはいない」「お前がお前であることを守れ」と激励したことで、ルカは再び歌の練習を始める。彼が再びアイデンティティーを取り戻す=歌えるようになるためには、「なぜ歌うことが好きなのか」を振り返る必要があった。神の恩寵としての歌声から離れ、少年合唱団以前の記憶を遡って思い出の童謡を歌うよう朝日奈と巽が勧めた(第8話)のは、そのためだ。
おそらくルカを想って歌われたであろうアポロンの歌をルカが歌い、さらに朝日奈がヴァイオリンの音色を合わせると、ファータの光が辺りを包む。ファータの光は、金色のコルダシリーズにおける美しい音楽の証のようなものだ。「天使の歌声」がもはや取り戻せないものだとしても、ファータの光が宿ったルカの歌は、巽の求める至高の音楽そのものであった。
唯一性
ストーリー中、巽とルカの間で「唯一無二のものは存在するか」という問いが投じられる。「唯一無二のものは存在しない」と考えていた巽の考えが変わるきっかけとなったのは、アポロンの代替品として巽が手配した新品のロボットが届いたときのルカとのやりとりだ。アポロンの代替品を手配した巽に激しく反発するルカに対し、「唯一無二のものなどない」と言い聞かせる巽。だが月城慧の名を出したルカは、巽に例外の存在を気付かせる。
ルカ「ロボットだから、世話してくれるから友達なんじゃない。あの子だから友達だったんだよ?」
ルカ「代わりを用意したよ、だから解決だねって? 無理に決まってる!!」
巽 瑛一「落ち着いてください、ルカ様。少し冷静に考えてごらんになっては?」
巽 瑛一「この世に唯一無二の存在などありはしないのです」
巽 瑛一「壊れたロボットだって、翌日にはこうして同じ役割の新品が用意されてしまう」
巽 瑛一「どんなものにも、替えはきく。落ちこむ必要などないのですよ」
ルカ「……じゃあ、ケイの代わりも?」
巽 瑛一「………………」
巽 瑛一「……おそらくは」
巽 瑛一(……いや。あの音の代わりは、きっと……)
己にとって月城(の音楽)は唯一無二かもしれないということに気付く巽。「あの音」と表現していることから、巽は人間を人格ではなく音楽そのもので認識していることがうかがえるのも、彼の独特な認知感覚を示していておもしろい。
巽 瑛一「そこにある新型ロボットはルカ様の『ご友人』と同じ型。見た目も変わりません」
巽 瑛一「同じ外見に、同じ機能を備え、同じ役割をこなすことができる。以前のロボットとどこが違うのです?」
(中略)
巽 瑛一「確かに、共に過ごした時間を書き換えることは不可能です」
巽 瑛一「ルカ様にとっての『友達』が思い出を共有する相手を指すのなら…なるほど」
巽 瑛一「あのロボットでなければならない。あなたもルカ様もそうおっしゃるのですね」
巽 瑛一「見た目や役割が同じであっても大切だと信じる要素が欠ければ代わりにはなり得ない、と」
ルカが大我に連れていかれた後、巽が朝日奈に諭される場面。人間関係の唯一性は「時間や体験を共有すること」によって裏打ちされるものだと知った巽は、「納得、とはいきませんが。勉強させていただきました」と答える。
さらに巽は、ルカの歌声の美しさに執着している自身に気付き、「この感情こそが、唯一無二のものが存在する証左に他ならないかもしれませんね」と苦笑する。彼自身が価値を感じるものの唯一性についても考えを改めることになったのだ。
ルカとアポロンの友情は、アポロンの故障(=天寿を全うしたことによる死)によって一度終わりを迎えた。最終的にアポロンは巽が修理を手配したことで復活することになるが、あくまでも延命措置であり、「彼が大人になる頃には再び故障する」ことを巽は想定している。そこで彼は、自らが取り寄せた新型ロボットのスイッチを入れる。これは、アポロンが再び寿命を迎えるときまでに、新型ロボットをルカとともに過ごさせ共有体験を増やすことで、新型ロボットをルカにとってのふたりめの「唯一無二の友達」にするための措置であろう。アポロンがふたりいる必要はない。アポロンとは別個の「友達」を作ることが重要なのである。当初巽がルカに提案した通り、「故障したら取り換える」ことに変わりはないが、取り換えるまでの時間を“奇術”によって延ばす――朝日奈に諭されて学んだ巽が出した解答だ。
一方、自分自身を「唯一無二で替えのきかない存在」「自分が一番上手に歌える」と考えていたルカの方も、他の団員の歌声を聴くことで、その傲慢な考えを改めることになる(こちらはあくまでも技術的な唯一性であり、大我が第7話で諭すアイデンティティーとしての唯一性ではない)。正反対の考えの持つふたりが、同じ体験を通じて、互いの持論を変化させる構成がおもしろい。
Secondo viaggioシリーズとの連動
ルカの立ち直りに一役買った以外は朝日奈の立ち位置は控えめだったと書いたが、これはメタ的な前フリに過ぎない。というのも、「The Nightmare Of Halloween」は「Secondo viaggio 第2章 暗礁のゲネラルパウゼ」の直前に公開されたイベントストーリーだからである。
9月に配信された「間奏曲 金のリンゴは天に実る」のイベントストーリーは、その次に配信された「春嵐出来フェルマータ」と類似した主題が扱われていた。であれば、「The Nightmare Of Halloween」も「暗礁のゲネラルパウゼ」と近しい主題が扱われていると考える方が自然だ。すなわち、ルカの挫折と再生はSecondo viaggioシリーズで朝日奈の挫折と再生を描くための前フリなのである。
今回のイベントストーリーでは、「ルカは月城に、アポロンは巽に似ている」という話題が出た。現代日本にそぐわない君臣関係に見えながらもお互いをリスペクトしている無二の親友である点において、これは真である。しかしルカとアポロンの関係を真に踏襲しているのは朝日奈と銀河だ。
ルカにとって幼少期から人生を共にしてきたアポロンは、精神的な支えであり、音楽を楽しむきっかけとなる存在でもあった。かつてのアポロンが歌っていた思い出の童謡を歌うことで、ルカは音楽への愛を取り戻し、近い将来「天使の歌声」を失っても歌い続けることを決意する。Secondo viaggioシリーズで描かれる朝日奈と銀河の関係も同様のものだ。「暗礁のゲネラルパウゼ」では、音楽の愛し方を忘れヴァイオリンから離れた朝日奈が、初めて銀河と出会った幼い頃に「ガヴォット」の連弾をして他者とハーモニーを作り出すことの楽しさに目覚めたことを思い出すくだりがあった。ルカの物語は、朝日奈の物語の相似形なのである。
銀河は無機的なロボットではないから、故障はしない。その代わり、朝日奈・スタオケ、そして自分にとってよりよい未来を選ぶため、自ら彼女らに別れを告げることができる。だからその別れは苦くはあっても、永遠ではないし、悲しいものでもないのだ。
各キャラクター雑感
月城 慧
グランツのメンバーたちが少年のわがままに翻弄される中、普段は専制君主のような辣腕ぶりを見せる月城が、ルカのいたずらにつきあうのをおおらかに楽しんでいる様子は新鮮である。巽は「少年の心」を持っていると形容している。名家で育った彼は病弱ながら冒険心が強く、しばしばベッドを抜け出しては使用人たちを困らせていたことが、SSR「セレネの輝かしき愛し子」等で描かれていたが、今回のかくれんぼのシーンでもそのときのことを思い出すような言動が見られる。
そんなほのぼのとした様子も垣間見える一方、月城 慧の本質は「至高の音楽のために限りある命を燃やす星」である。彼がルカに対して兄のように寛容にふるまうのは、彼が月城と同質の存在だからだろう(月城自身は一人っ子のようなので、もしかすると年の離れた弟ができたようで楽しかったのかもしれない)。
イベントストーリー第9話のコンサート終了後、グランツ交響楽団のコンマスとしてというよりも、ひとりの音楽家として年若いルカを激励するシーンもよい。最高の音楽を作り上げるために努力を惜しまない月城の姿を、朝日奈(=月城の最大の好敵手)からではなくひとりの後輩の視点から見るのは実に頼もしい。最後にハロウィンの菓子としてチョコレートを登場させるのも、彼らしい遊び心に満ちていると言えるだろう。

スタオケメンバーの登場はイベントストーリーの最序盤のみだったが、月城と朝日奈がルカの声変わりの予兆について会話する場面(第6話)で、朝日奈がスタオケメンバーたちに思いを馳せる場面がある。ここで「失う不幸を呪うより、この瞬間の幸福を見つめるべきだ」と語る月城の言葉は、現実的でありながらも前向きだ。「暗礁のゲネラルパウゼ」での展開を暗示しているようにも見えるのと同時に、なにかに取り組みながら生きるユーザーたちにとっての強い激励でもある。
巽 瑛一
イベントストーリーのキーマン。「組曲 遙けき蒼天のマドリガル」でも触れられていたが、彼は至高の美しい音楽に執着している。ゆえにルカの「天使の歌声」に強く惹かれ、ルカを大切にもてなすのは彼を“「天使の歌声」を奏でる楽器”とみなしていたためだと明かされる(第4話)。
そして美しい音楽のために執念を燃やす一方、過度に合理的な考えの持ち主であることから、人間の情の機微に疎いことも露見した。故障したアポロンの代わりに同じシリーズの最新モデルのロボットを用意して(励ますつもりで!)ルカにプレゼントした巽の言動は、本物のロボットであるアポロンよりも遙かに機械的である。ルカと体験を共有した時間こそがアポロンを唯一無二の存在たらしめるのだと朝日奈が説明すると、「人の感情とは、実に複雑怪奇…。だからこそ、面白いのでしょう」と話す。人間の感情に対する理解が欠落した巽という男は、人間についてどこか突き放したようなものの言い方をする。
ストーリー中、「ルカと月城は似ている」という話題が出るのと並行して、「アポロンと巽は似ている」という話題が出る場面がある(第4話)。後者については本人たちから「心外ですね」と否定されているが、主人に忠実な執事という点では確かに類似している。ただし、アポロン故障後の第6~7話での巽の思考や行動は、ルカの感情を考慮しない過度に合理的なものである。ロボットのアポロンよりも遥かにロボットらしい言動をしているのが興味深い。
「Music and the Fatal Ring」のアドリブ演技でも、「私はあなたとも王子たちとも異なる生き物なのですよ。ご理解いただけないでしょうがね」というセリフがあったことから、本質的に人間と異なる生き物であることが暗示されている。シリーズ過去作に前例があるので不思議はないが、巽の正体については今後の展開を見守っていきたい。
堂本大我
ルカの遊び相手として最も振り回されたキャラクター。“天使”のルカと、“地獄”の眷属に相当する大我が真逆の存在であることは、イベントストーリー第7話でのルカの「(教会が)僕にはよく似合う。タイガはなんか浮いてるね」の発言から示唆されている。大我本人は鬱陶しがっていたが、子どもに対して面倒見のいい兄貴分であることが十二分にうかがえるストーリーであった。
今回、大我はイベントストーリー冒頭のセリフと最後のセリフを発しており、「悪夢」の開幕と終幕を告げる役割を持っていた。また、第5話で「……天使の歌声、ねぇ」「だったら、さっさと神様が迎えに来てくれないもんかね。俗人の俺の手には余るぜ」と話していることにも注目したい。この後まもなくアポロンの故障という転換点が生じたことから、ルカの“天使の歌声”が神の手に返還される(=神様が迎えに来る)時の予兆になっていると言える。
ストーリー上の大我の一番の見どころは第7話、教会でルカに胸中を吐露させた場面。大我はルカの「ずっと子どもでいたい」という願いを「甘ったれた祈り文句」と評するが、突き放さないどころか抱き締めてやっていた。メインストーリー7章、御門邸の門前で朝日奈と顔を合わせた大我が彼女に「青臭い理想論」「あんたたちとは生きる世界が違う」と小馬鹿にしたような態度を取っていたことを考えると、堂本大我の価値観の変化に「おや」となったユーザーは少なくなかっただろう。
堂本大我「世界はお前が思うよりずっと広いんだよ、坊ちゃん」
堂本大我「今日という日を生き抜くので精一杯で歌なんて忘れちまうような世界だってある」
堂本大我「それに比べて、ずいぶんとお気楽な悩みだと思わないでもないが…」
堂本大我「まぁ、幸福も不幸も環境によって物差しは違う。お前には、十分深刻な悩みか」
御門と大我がクラシック音楽ユニット「黒橡」を結成しデビューするまでについて語られた「組曲 彼方を染めゆくリチェルカーレ」のイベントストーリーを踏まえた内容である。当初、御門は大我を「他人の矜持を踏みにじり、平気で食い物にする腐った野良犬」、大我は御門を「ぬるま湯で甘やかされながら、平気で退廃を口にする坊ちゃん」としてお互いに嫌悪し合っていた。しかしお互いの背景にある苦しみと譲れないものについて知ることで、ようやく協同(互いを利用し合って自己の目的を達成する、という意味での協同である)して音楽を作り上げていくことができるようになったのだ。
今回の大我が、ルカの悩みをお気楽と評しながらも「幸福も不幸も環境によって物差しは違う」として理解を示しているのは、御門と人生観をぶつけ合った経験があるからだろう。違う人生を生きていればその人生なりの喪失体験がある。だから「俺よりマシだろう」と相手を軽んじたり嘲笑したりするのをやめよう、と彼は学んだに違いない。
見ようによっては一番かっこいい役どころを充てられた大我だったが、今回登場したSRカードのイラストに描かれている仮装姿(イベントストーリーでは「虎の仮装」とされていた)については多少物申したくもなる。着ぐるみやかぶりものではなく演奏用礼服+仮面で仮装として押し通すのは……なんというか、その……拘束具をつけさせたかっただけなのか…………!?(大変よろしいと思いますありがとうございます)

御門浮葉
ルカは大我に相手をしてもらいたがる一方、御門に対しては「会話が弾まない」「眉を下げてシュンってされると僕が悪いことしてる気分になる」と話して敬遠している(第2話)。御門は他人の憐れみを誘って自らに降りかかる面倒ごとを回避するのが得意なことが彼のキャラクターストーリーで語られているが、ルカに対してもその態度を発揮していることがわかる。子どもが嫌いなのではないと御門は話しているが、ルカと御門は、大我とはまた別の意味で相容れない者同士であることが知れよう。
箱入り育ちで世間知らずなため、一人で電車に乗ることもできないことがわかったのも印象深かった。どこまでも他人に世話を焼かれる側の人間である。リーガルレコードと契約して上京すると告げられた使用人たちは倒れなかっただろうか。
第8話、歌の練習を再開したルカに、御門は「あなたも抗うことを選んだのですね」と話す。“あなたも”ということは当然御門もルカと同じ境遇であったことを示しており(メインストーリー7章および「組曲 彼方を染めゆくリチェルカーレ」参照)、その先達としてものを言っているのだが、言葉遣いが回りくどいためかいまいちルカには伝わらない。
そこで彼が述べたアドバイスは、「声を絞り出すのはおやめなさい(=死期を早めてはいけない)」というもの。ストーリー内では詳しくは触れられていないが、男性の変声期に負荷のかかるボイストレーニングを行うと声帯が傷つく(=喉を潰す)ことを指していると思われる。ロックや演歌などでは喉を潰して歌うことが推奨されることがあるが、ルカの場合は本人がそれを望まないだろう。
余談ながら今回登場した仮装姿(Rカードの調教師)が最高でテンションが爆上がった。10回に1回くらいの割合であんな感じのカードイラストが来るといいと個人的には思う。
舞台設定
サーカス
2021年ハロウィンシーズンの期間限定イベント「音速のハロウィンキング」では、ピックアップされた4名はいわゆるハロウィン定番の仮装をしていた(桐ケ谷はドラキュラ、凛は小悪魔、銀河は狼男、刑部はフランケンシュタイン)。2022年ハロウィンシーズンの「The Nightmare Of Halloween」では、月城・巽・御門・大我がそれぞれサーカス団に扮することになる。わかりやすい“仮装”のテーマではあるが、一見ハロウィンらしさに欠ける題材のように思われる。
サーカスが題材となった要因として、サーカスがひとときの夢を観客に見せる舞台装置として機能していることが考えられる。「Music and the Fatal Ring」でグランツが朝日奈と共演・交流するには演劇という舞台装置が必要だった。演劇にしろサーカスにしろ、「活動期間が限られるが、異世界を生み出すショービジネス」であるという点で共通している。
サーカス団は本来、町から町へと移り、その場その場でテントを張って短期間の興行を行う、非定住団体である。そういった意味では、イベントストーリー第2話でルカがグランツ交響楽団を一時的にサーカス団に見立てる話をするのも不自然ではない。イベントストーリーの最後が大我の「こんなサーカス団、即刻解散だ、解散!」というセリフで締めくくられるのも、今回の“グランツサーカス団”がひとときの夢であったことを強調するためのセリフである。


サウィン(ハロウィン)
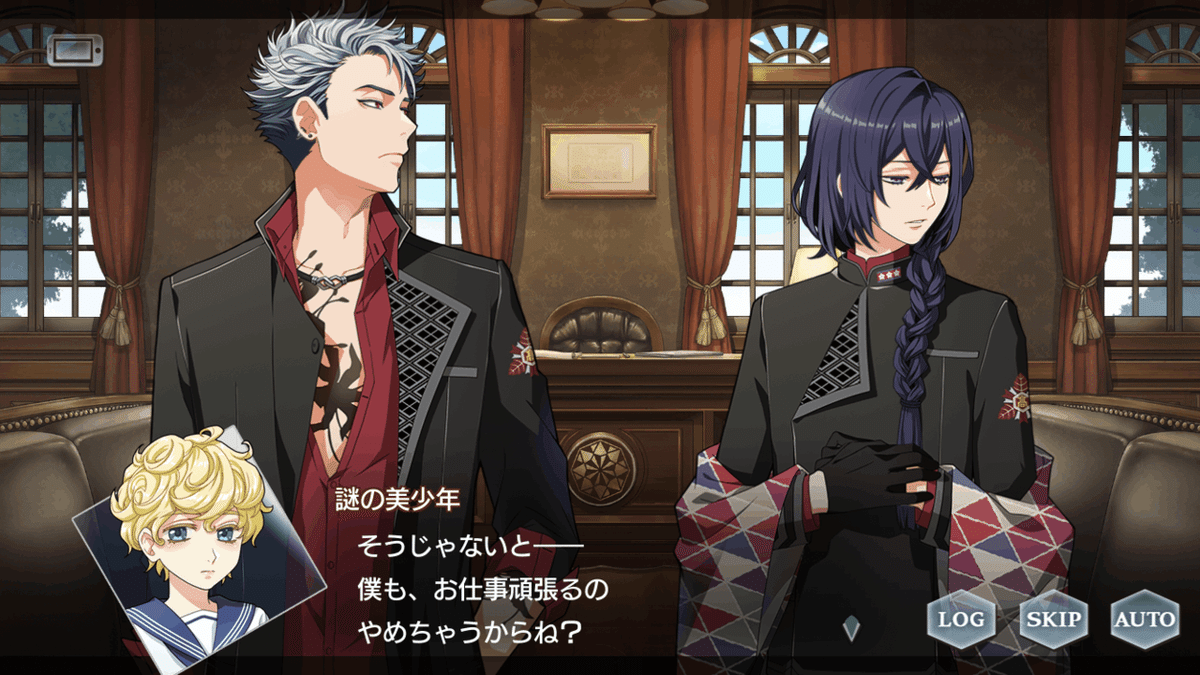
序盤、ルカは御門と大我のふたりに「僕はゲスト、君たちはホスト」「僕の満足のいくようにもてなしてくれないと、歌ってあげない」と言い出す。これはイベントテーマすなわちハロウィンに合わせたセリフで、「お菓子をくれなきゃいたずらするぞ!(Trick or treat?)」の代替表現である。
さらに、今回のイベントストーリーでは、巽がこんなことを言う場面がある。

「生者と死者の魂が行き交う」というのはなんとも穏やかではないが、現代のハロウィンの原型にあたる古代ケルトの行事サウィン祭(Samhain)を念頭に置いたセリフと思われる。
サウィン祭は10月31日(光の季節である夏の終わり)を前夜祭、11月1日(闇の季節である冬の始まり)を祝祭当日とみなし、夏の収穫を祝って余剰分の作物や家畜が共食に供される。同時に、生者の世界と死者の世界を結ぶ「門」が開かれ、死者の霊魂が生者の世界に帰ってくる日なので、彼らをもてなすために飲食物(ソウル・フード)を用意する必要があった。死者の霊魂が饗応に満足すれば、厳しい冬を生き抜けるよう祝福を生者に与えてくれるという(仮装して「Trick or treat?」と唱える子どもに菓子を提供する風習の起源である)。日本でいうお盆と似たようなものと考えてよい。
今回のイベントストーリーにおいて、ハロウィンウィークと称して一般開放されている花響学園は、サウィン祭の場として見立てられている。花響の関係者以外にも近隣の住民たちが訪れており、敷地内は通常より雑然とした空気が漂っていることだろう。ではその隙に入り込む「死者の魂」は何者かというと、異国からやってきた少年合唱団、もっと言ってしまえばルカである。
傍若無人にふるまっていたルカは、グランツサーカス団でのできごとを経て成長し、最後にはごちそう(=ソウル・フード)をふるまってもらい、メンバーと打ち解ける。彼らの饗応に満足し、チケットの半券を大切な思い出として異国へ持ち帰っていく彼は、あの世からやってきて生者たちに祝福を与える死者の霊魂に似ている。
さらにもうひとつ。古代ケルトにはドルイドと呼ばれる祭司がおり、彼らは森や木々を利用した呪術・占い・人身御供の儀式を行う、ケルト人社会最高位の知識層であった。彼らはサウィン祭においてかがり火を焚いて儀式を主導した。
ここで思い出されるのが、巽の存在である。彼は奇術で人々を驚嘆させる奇術師の仮装で人々をもてなしていたが、今回のイベントで特効が付与されたSSR「夢幻のステージ」のイラストでは炎を操る様子が描かれている。今回のイベントで、巽は魔術を扱うドルイドの役を充てられているのである。グランツ交響楽団のコンサートマスターでありサーカス団の長を務めるのはもちろん月城慧であるのは確かだが、ルカをもてなすにあたり、朝日奈を招いたことを含め、最も重要な役割を果たしたのは巽と言えるだろう。ルカとの交流の結果、彼は価値についての学びというよきもの、そして求めていたファータの光を目の当たりにすることができた。
おわりに
「金色のコルダ スターライトオーケストラ」は、若者たちが一度失った生きる力を再び取り戻して音楽を作り上げていく物語だ。今回のルカの物語は、そのテーマを10話完結にまとめたミニチュア版でもあったと言える。
グランツ交響楽団メンバーのみで構成された今回のイベントストーリーでは、Secondo viaggioシリーズと近しいテーマを感じ取りつつ、丁寧に作りこまれたゲストキャラクターが投入されることで新鮮な物語運びを見ることができた。ゲストキャラクターに接しなければ見えない魅力がふんだんに盛り込まれていたと言えるだろう。心揺さぶるシリアスな場面と、思わず口角が上がるギャグシーンもあったが、配分もよかった。個人的には、特効カードで構築したデッキで路上ライブでリンクスキル「漆黒の覇者」を発動させられたのも嬉しかった(初期観客数大UP効果がある)。
Secondo viaggioシリーズではグランツ交響楽団も人員面での動きがあり、そちらの今後の展開も楽しみではある。だが期間限定イベントでは引き続きこのハイコンテクストな会話を交わすメンバーたちでの「グランツ交響楽団」としての姿が見られることを願いたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
