
【ショート・サーブ】が、こんなに増えているのはなぜなのか?(その1)
(photo by FIVB)
コロナという強大な逆境の中で、何とか無事に開催されたTOKYO 2020。
日本の男子ナショナル・チームが13年ぶりに、オリンピックのコートという晴れ舞台で躍動する姿を見て、やっぱりバレーボールは面白い! と再発見した方もいらっしゃることでしょう。
中には、久しぶりに決勝戦はじめ、海外勢同士の試合を見たくなった方もいらっしゃったのでは?
そして久しぶりに、海外勢の、五輪での頂点を争う舞台での本気モードの対戦を目の当たりした皆さん。どのような感想を覚えたでしょうか?
なんだか、緩いサーブが多いなぁ …
正直、そう感じたあなた。
その感覚は、あながち間違いではありません。
2010年代以降の、バレーボールの「サーブ戦術のトレンド」が何か? と問われれば、その答えの1つが
「ショート・サーブ "戦術" の多用」
にあることは、もはや疑問の余地もないでしょう。
ショート・サーブ "戦術" が効果的である理由は、上の動画で解説されているとおりです。難しい理屈など、何もありません。
ですが、YouTubeのコメント欄にあるような「こんな当たり前のこと」が
なぜ今頃、世界トップ・レベルの舞台で頻用されるようになったのか?
あるいは逆に言えば、技術的に難しいサーブではない「アタック・ライン付近にボールを緩く着弾させる」ショート・サーブが、
今まであまり用いられてこなかったのは、一体なぜなのか?
おそらく、こうした疑問に回答するには、
サーブ戦術の変遷そのもの
を整理していくことが、おそらく必要なんだろう、と思い始めました。
バレーボールの戦術の中で、アタック戦術とブロック戦術の変遷については、これまで様々な形で文字に残してきたので、明示されるかどうかは別にして、実際引用されていることも多いです。
手前味噌ですが、一番最近ではつい先日開かれた、日本バレーボール学会 第27回大会(JSVR 27th Scientific Congress for Volleyball, 2022)。
#バレー学会27 初日、恐らく日本 #バレーボール 史上初めて、 @JVA_Volleyball の テクニカルレポートが公開されました。
— 渡辺 寿規(Toshiki WATANABE) (@suis_vb) March 5, 2022
そこにもあった各国の TOKYO 2020 出場各国の身長比較で、日本と遜色なく低かったアルゼンチンが、果たしてどのようなブロック戦術をしていたのか?!
明日の発表、乞うご期待! https://t.co/krxzhQZc0r
執筆だと直近のものはこちら。
引用されているものとしては、これとか。

バレーボール研究, 17(1), 06-11, 2016
正直、あまり得意な分野ではありませんが、ディグ戦術の最近のトレンドについても、2017年にバレー学会 第22回大会で発表しています。
しかし、ことサーブ戦術の変遷となると、私自身きちんと文字にしたこともなかったし、過去の文献等を漁っても、あるいは『セリンジャーのパワーバレーボール』等の王道の教科書を開いても、実は、きちんと体系化された記載はほとんど存在しない、ということに、最近気づきました。
そこで本記事では、過去に通説や先行研究といったものが、ほとんど存在しないバレーボールの「サーブ戦術の変遷」について、紐解いていきたいと思います。
◎ 1950年代〜1964年東京五輪頃まで 【9人制からの移行期】
1973年生まれの私には、流石に、この時代のサーブ戦術がどのようなものだったかは、全く見当もつきませんでした。
参考とした文献は、『中国バレーボール理論と実践』(李 安格・黄 輔周 著、武井 克己 翻訳 | ベースボール・マガジン社)『セリンジャーのパワーバレーボール』(アリー・セリンジャー, ジョーンアッカーマン・ブルント 著、都澤 凡夫 翻訳 | ベースボール・マガジン社)、さらには慶応大学研究紀要「ナショナルルールが日本のバレーボールに及ぼした影響について」(木村 正一, 体育研究所紀要 (Bulletin of the institute of physical education, Keio university). Vol.16(1), 51- 61, 1976)、等です。
当時はまだ日本では、バレーと言えば9人制が主流でした。9人制は6人制に比べてオーバーハンド・パスでのキャッチの適用が緩く、レセプションはオーバーハンド・パスで行うのが当たり前だったようです。
さらには9人制のルールはテニス同様、サーブを2回打つことが可能で、1本目はミスを恐れず強く打てるため、当時は1本目にはドライブ・サーブ( → スタンディング・ラウンドハウス・オーバーハンド・トップスピン・サーブ)が主に選択されていました。
その理由は、強いトップスピンをかけることで「ボールの挙動を変化させること」を狙ったサーブ(=変化サーブ)ゆえに、アンダーハンド・パスではコート外へ弾かれやすく、それに対抗するため9人制ではレセプションは(多少、キャッチしても許容される)オーバーハンド・パスが、主に用いられていたという絡繰りです。
しかし6人制の場合、上述のとおり9人制に比べてキャッチの適用が厳しいため、必然的にレセプションはアンダーハンド・パスを用いるのが、必須の技術となっていきました。
下の映像は、1956年にパリで開催された世界選手権男子大会のものですが、
当時は世界も9人制からの移行過渡期であり、ドライブ・サーブが高頻度で用いられていたことが、ご確認いただけるかと思います。
日本も、世界のトレンドに追随すべく(のちに1964年東京五輪で正式競技として採用される)6人制への移行を急いだのですが、その過程において
9人制の主流であったドライブサーブは馬力を主とすれば打率は低く、打率を主とすれば球道は単調となりレシーブチャンスとなる。これがドライブサーブが6人制に使用されなくなった原因で
Bulletin of the institute of physical education, Keio university, Vol.16(1), 51-61, 1976
ドライブ・サーブは、次第に使用されなくなっていったようです。
6人制でドライブ・サーブに代わって主流となったのは、「ボールの挙動を変化させること」を意図した同じ変化サーブではあっても、その狙いを、むしろ「ボールに回転をかけないこと」で達成する、無回転サーブでした。
無回転サーブと言われて、皆さんがまず思い浮かべるのは、フローター・サーブ( → スタンディング・ハーフスパイク・オーバーハンド・フロート・サーブ)でしょう。
先ほど紹介したパリでの世界選手権から8年後の、東京五輪女子決勝戦の映像を見ると、ソ連の選手のほぼ全員が、フローター・サーブを打っていますね。
一方、日本の選手もやはり全員が無回転サーブを打っていますが、サーブの打ち方がソ連の選手とは大きく異なります。
いわゆるフローター・サーブとは異なり、コートに向かって体を横向きにして立ち、ラウンドハウス・スイングによってサーブを打っています。
このように打ち方には違いがあるのですが、注目して頂きたいのはそこではなくて、「各サーバーが『どの付近から』サーブを打っているのか?」 という部分です。
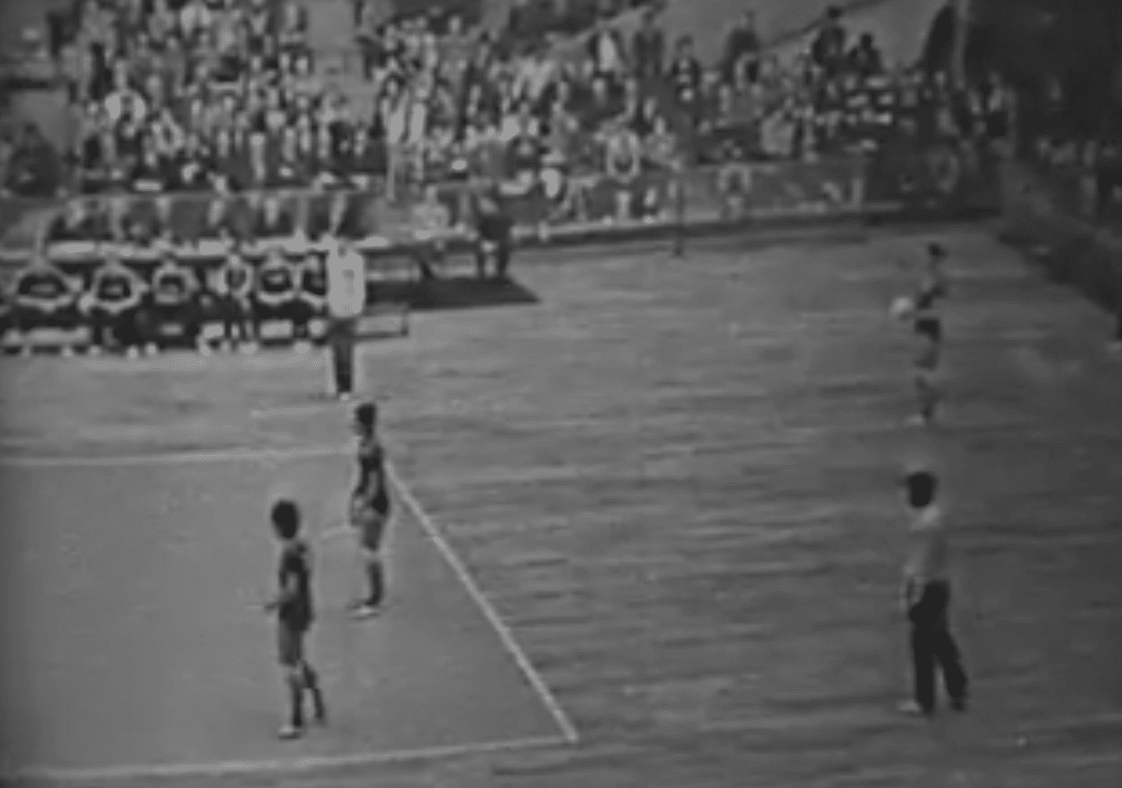

エンド・ライン近くで打っている選手もいますが、多くの選手がエンド・ライン遙か後方まで下がって、サーブを打っていませんか?
当時のこうした日本選手のサーブは「木の葉落とし」と呼ばれ、諸外国から恐れられたそうです。

無回転サーブ自体は、緩い(スピードのない)サーブでもボールの挙動が多少なりとも変化する特徴があるため、相手コート上の特定の場所に着弾させるよう狙いを定めて、ミスを避けるように打っても、相手のレセプションが乱れる可能性が見込める堅実なサーブと言えます。
しかし、両チームとも敢えてこうして、エンド・ラインから距離を取って無回転サーブを打っていることから、この無回転サーブに当時の選手たちがどういう意図を込めて打っていたのか? という点に思いを巡らせれば、
飛行距離を伸ばすことによって、挙動の変化を最大化しよう
としていたことが見えてきます。
一見すると、緩いサーブに見えるかもしれませんが、エンド・ラインより遙か後方からネットを越えるようにサーブを打つには、それなりの高い軌道を描くため「相手コートにボールが到達するまでの、経過時間が長い」から緩く見えるだけで、実際には20m以上も飛行するサーブを打つには、ボールにそれなりの初速を与えなければなりません。
実はこうした、無回転サーブにおけるボールの挙動については昔から多くの研究がなされており、挙動の変化には臨界速度(*1)が関係していると考えられています。その理論に基づくと、投射角20°〜30°で飛距離が21mの無回転サーブを打てば、挙動の変化が最大になります。
そうした理論背景からも無回転サーブでは「打撃位置をエンドラインの後方にとらせ、打球距離の長いサーブを打たせる」指導が、実際に現場で行われていたようです。
フローターサーブの特徴は、変化球サーブであるから、技術指導における最も重要なポイントは、ボールが空中で臨界速度に達して打球方向の変化を生じるように、サーバーの打撃位置をエンドラインの後方にとらせ、打球距離の長いサーブを打たせることである。・・・(中略)・・・本研究で明らかにされた、サーバーの打撃位置をエンドラインの後方にとらせ、打球距離の長いサーブを打たせることは、フローターサーブを指導する際の技術資料として役立つと考えられる。
日本教科教育学会誌 27(1), 35-41, 2004
こうした、サーブの「飛行距離をできるだけ長くする」ことに主眼を置いたサーブ戦術のことを、「ロング・サーブ "戦術"」と呼びたいと思います。
変化が大きく、予測しづらい変化をするだけに留まらず、スピードもあるためアンダーハンド・パスでレセプションをし損なうと、ボールがコート外へ大きくはじき飛ばされてしまう可能性の高いサーブであり、1本しか打てない6人制のルールの下でも、ミス率を高めずにサービス・エースが狙える攻撃的なサーブ(パワー・サーブ)だったと言えます。
それゆえ、東京五輪後には男子の世界でも、日本の女子選手たちが魅せた「木の葉落とし」が、サーブのトレンドになっていきました。
1966年にプラハで開催された世界選手権男子大会における、Technical Evaluation(サッカーで言えば「テクニカル・レポート」に相当するもの)で、サーブについて以下のようなナレーションとともに、スタンディング・ラウンドハウス・オーバーハンド・フロート・サーブを打つ男子選手の映像が収められています。
De serveerder staat 5m van de achterlijn.
Deze afastnd heeft invloed op de vlucht van de bal.
Na’t passeren van het net aarzelt de bal.
Hij wijkt, valt snel en de tegenpartij reageert hierop te laat.
(日本語訳)
サーバーはエンドラインから5mの地点に立つ。
これがボールの飛行を左右する。
ネットを通過した後、ボールの挙動が変化する。
軌道が逸れたり、早く落ちたりして、相手の反応が間に合わない。
https://www.youtube.com/watch?v=ejZ-037vpwE
(↑クリックすると、別ウインドウでYouTube動画がみられます)

このTechnical Evaluationを見る限り、9人制からの移行期と言えるこの時期のサーブ戦術のトレンドが、男女ともにロング・サーブ "戦術"であったというのは、間違いないと断言していいでしょう。
◎ 東京五輪以降、1980年頃まで 【ロング・サーブ "戦術" に対抗するアンダーハンド・パスによるレセプション技術の開発過程】
ロング・サーブ "戦術" により、ミス率を高めず攻撃的なサーブが打たれるようになったことで、レセプション側チームにとっては、アンダーハンド・パスを用いて、いかに失点しないでレセプションできるか? が、まず最重要課題となってきます。
たとえば、1979年(昭和54年)の岩手県高校総体を分析対象とした研究(*2)によると、男子が計71セット全3,498本のサーブのうちサービス・エースが221本(6.3%)、女子は計68セット全2,754本中サービス・エースが373本(13.5%)出現していたと報告されており、特に女子では1セットあたりサービス・エースが平均で(もちろん、サイドアウト15点制だったという側面はあるにせよ)約6本近くも出現していたという計算になります。
ラリーポイント25点制に改正後、2002年における中国大学バレーボール1部リーグ女子その他(いずれも女子大学生)を分析対象とした同様の研究(*3)では、計71セット全1,251本のサーブのうちでサービス・エースは6%(75本)を占めたと報告されており、高校生と大学生の違いがあるとは言え、やはり1979年当時のサービス・エースの出現率の「異常な高さ」が、うかがい知れます。
ロング・サーブ "戦術" がトレンドとなり始めた1960〜1970年代は、上述の通り、オーバーハンドからアンダーハンド(「組み手パス(レシーブ)」と当時は呼ばれていたようです)へと、レセプション動作の転換が迫られた時期だったわけですが、中でも「速攻(クイック)を繰り出すリズムを崩さない」という要件が特に、アンダーハンドでのレセプションを技術的に難しくしていた、と考えられます。
9人制におけるクイックプレイのパスは、リズム的に上手で直線パスを送るのが一般的であった。東京オリンピック以来速攻に自信を持った全日本がこのプレイの常用化を計ったのであるが、これを妨げたのは上手パスに対する厳しい反則と、組手パス乱用によるコントロール難とリズムの相違であった。これらの障害を取除き速攻の多用を可能にしたのが組手ヒットによる直線パスの考案である。・・・(中略)・・・トスとの連係プレイの点から考えてこのパスは些かのコントロールの乱れも許されない極めて高度な技術を要求されるものであり・・・(中略)・・・サーブレシーブに定評のあった日本、韓国女子チームがこのパスを使用したためにソ連、ハンガリーよりもサーブレシーブ成功率が劣ると言う結果が記録されているのである。
Bulletin of the institute of physical education, Keio university, Vol.16(1), 51-61, 1976
当時中国では組手レシーブを取り入れるかどうかで意見が分れ、論争があった。反対者の主張は速攻に影響が出るというものであったが、時間が経つにつれて組手レシーブが必然的な発展方向であることがわかり、これを積極的に学ぶようになった。
(李 安格・黄 輔周 著、武井 克己 翻訳 | ベースボール・マガジン社)
ロング・サーブ "戦術" に対抗して、サービス・エースを取られずに、なおかつ、常に速攻が繰り出しやすいようなリズムで、ボールをセッターに供給する・・・そういった「ゲーム・モデル」を達成するため、当時の世界各国の選手たちに求められたプレーが、いわゆる
「ボールの下に早く移動して、正面で受ける」
「セッターに直線的な軌道で、レセプションを返す」
という、日本の(特に育成カテゴリの)指導現場で長年、変わらずに行われてきた、レセプションにおける「1つの」プレー指針であったんだろう、と思います。
このプレー指針により、日本の男子ナショナル・チームはミュンヘン五輪で見事な速攻コンビネーション・バレーを確立し、世界を席捲しました。
それを契機に、世界が日本のバレーボール、技術論を学んでいきます。
(↑クリックすると、別ウインドウでYouTube動画がみられます)
こうした「ボールの下に早く移動して、正面で受ける」「セッターに直線的な軌道で、レセプションを返す」いう、日本の育成カテゴリで今でも変わらず指導されているレセプションのプレー方法には、
ロング・サーブ "戦術" が当時のトレンドであったからこそ理に適っていた
別のメリットも、実はありました。
「ボールの飛行距離をできるだけ長くすること」に主眼が置かれたサーブが主に打たれていたお陰で、レセプション側のチームにはサーブが自コートに飛んでくるまでの「時間的猶予」が確保される一方、サーブ側のチームはサーバーがエンド・ライン遙か後方から自コートまで戻るのに時間を要するため、相手に直線的な軌道でレセプションを返して速攻を繰り出されると、「フロア・ディフェンスが整わないうちにスパイクを打ち込まれる」という危険性があったのです。
サーバーの打撃位置が、エンドラインから最も遠かったのはフローターの 11.5mであった・・・(中略)・・・サーブ後は、サーバーも相手チームのアタックをレシーブしなければならない。エンドライン後方からサーブを打てば打つほど、打撃後は走って早くレシーブ位置に戻らなければならない。
日本教科教育学会誌 27(1), 35-41, 2004
レセプションで失点せず、なおかつ、速攻を高い確率で繰り出せるようにと考え出された「正面で受ける」「直線的な軌道でボールを返す」という、アンダーハンドでのプレー指針がこうして、世界各国へと広まっていくわけですが、その前提条件として、あくまで当時は
「ロング・サーブ "戦術" が主流だったから」
という点は、意識しておかなければなりません。
本記事ですでに、何度も引用している『中国バレーボール理論と実践』の
中にある、レセプション技術の記載を以下に記すと、
サーバーからの距離がかなりあり、ボールの速さも限界があるから移動判断力を高めれば、大部分は移動してボールに正対し、正面組手パスで処理できるはずである。
(李 安格・黄 輔周 著、武井 克己 翻訳 | ベースボール・マガジン社)
となっており、「ロング・サーブ "戦術" が主流だったから」という前提条件を意識した記載がなされているのがおわかり頂けるでしょう。
もちろん、当時の日本の指導教本(1977年初版)においても、
ボールがとんでくるときに時間的なゆとりがあるのだから、早くボールの正面にすばやく移動し、できるだけ身体の正面で、セッターに正対してレシーブすること。
((財)日本バレーボール協会指導普及委員会 | 大修館書店)
と、きちんと書かれています。
従って、東京五輪以降、1980年頃までの戦術トレンドのまとめとしては、当時主流であったロング・サーブ "戦術" に対抗できる、アンダーハンドでの「1つの」プレー指針を日本が確立し、それが世界に普及していった過程、とまとめることができると思います。
◎ 以下、蛇足・・・
上述のサーブ戦術の変遷を頭に入れて頂ければ、サーブ戦術のトレンドに変化が生じれば、「正面で受ける」「直線的な軌道でボールを返す」というレセプションのプレー指針にも、変化が起きて当然だということが、ご理解頂けるだろうと思います。
ですが、東京五輪以降男子にも採り入れられ、男女を問わず主流となったロング・サーブ "戦術" は、この後実に30年近くもの間の長きにわたって、世界のトップ・レベルのサーブ戦術の主流であり続けたのです。
1992年のバルセロナ五輪男子決勝戦でも、ブラジル・オランダ両チームの選手がかなりの頻度で、エンド・ラインからかなり距離を取って打つ無回転サーブを使用しているのが、下の映像から見て取れます。
「ロング・サーブ "戦術" が主流だから」という前提条件は、この長い長い30年の間に、日本の指導現場でいつの間にか忘れ去られ、バレーを始めた日から「そう教わった」「そうやってプレーしてきた」という理由だけで、それがレセプションの『基本』『基礎』であると勘違いした指導が、なされてはいないでしょうか?
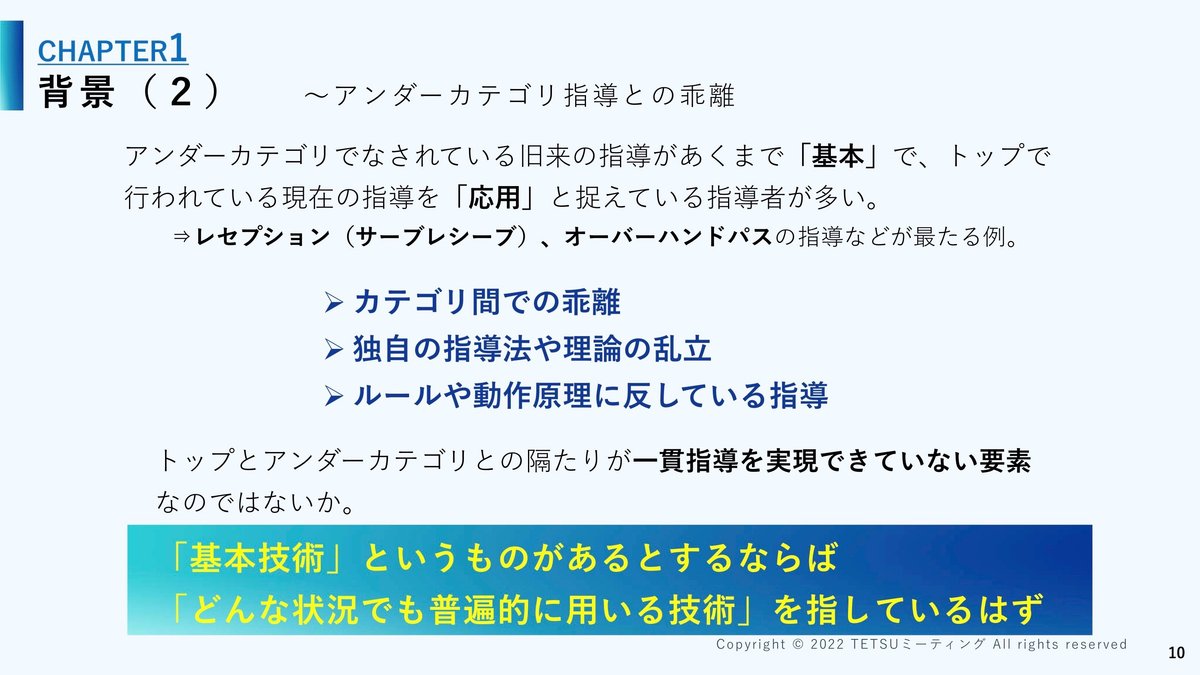
『バレーボールの一貫指導実現のための階層構造の検討』より
JSVR 27th Scientific Congress for Volleyball, 2022
あるいは、相手に直線的な軌道でレセプションを返して速攻を繰り出されると、「フロア・ディフェンスが整わないうちにスパイクを打ち込まれる」という、ロング・サーブ "戦術" が主流だからこそ成り立つ弱点についても、
いつの間にか、
中田ジャパンが掲げるテーマ「ワンフレームバレー(サーブレシーブを高く上げすぎずにセッターに返し、トスも速くして相手ブロックが完成する前に攻撃を仕掛けること)」
『web Sportiva』
レセプションを「高く上げすぎずに、リズムよくセッターに返球」し、そこから攻撃を繰り出せば、相手のサーブ戦術がどうあれ、相手のディフェンス(→ ブロック?)が整わない??
という謎の論理へと、すり替わってしまったのではないでしょうか?
少し脱線しましたが、こうして1970年代に日本が、ロング・サーブ "戦術" に対抗できるアンダーハンド・パスでのレセプション技術を開発し、それが世界各国へと浸透していきましたが、それだけでは、サーブ戦術のトレンド自体に新たな変化をもたらすものには至りませんでした。
次なるサーブ戦術のトレンド変化に寄与したのは、ロング・サーブ "戦術" の抱える、レセプション側のチームに「時間的猶予」を与えてしまうという弱点を、逆手に取った画期的なレセプション戦術だったのですが、
それについては、次回(その2)でじっくり、解説したいと思います。
(*1)篠村 朋樹・杤堀 申二・吉田 清司
「バレーボールのサーブ軌道に関する一考察 〜無回転サーブの軌道解析(第2報)〜」
日本体育学会大会号, 38A(0), 300, 1987
(*2)小笠原 義文
「バレーボールにおけるサーブについての一考察」
岩手大学人文社会科学部紀要, 27(1), 239-261, 1980
(*3)橋原 孝博
「バレーボールのフローターサーブに関する運動学的研究」
日本教科教育学会誌 27(1), 35-41, 2004
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
