
『命懸けの虚構〜聞書・百瀬博教一代』#1
永久に陽の目を浴びないであろう原稿がある。
作者が未刊のまま封印する作品もある。
出版を前提としていないながら書き続ける物語もある。
ノンフィクションの定義に躊躇い、迷宮に入り込むものもあるだろう。
棺桶まで持って行きたくないはずの事実や、己の主観でしかない虚構もあるはずだ。
それでも、そこには厳然と活字がある。そして途中経過そのものを遺しておきたい。
この作品をnoteに置いておく。
誰かがその存在を意識してくれればそれで良いのだから。
--------------------------------------
プロローグ「石原慎太郎の電話」
この物語は事実(ノンフィクション)ではない。
本来なら百瀬博教が自ら綴った自叙伝であり、そこに私こと水道橋博士が取材し要約し考察を加えた評伝のようなものでもある。
言わば、故人との共著だ。
そう。百瀬博教はもうこの世にはいない。
鬼籍に入ったのは2008年1月27日のことである。
この日、午前2時40分ごろ自宅を訪れた知人が風呂場の湯船の中で意識を失っている百瀬の姿を発見し救急搬送されたが、同日午後3時半ごろ死亡が確認された。
警察の調べでは死因は熱傷死したとみられている。
後に正式に事故死と処理されたが、その死を巡りさまざまな憶測が流れ、謀殺説他、数々の陰謀論が囁かれた。
しかし、死後12年、多くの関係者は口を噤んだ。
「百瀬博教とは何者か?」
その事実は封印されたのだ。
百瀬博教は自他共に認める「怪人」であった。
自らの職業を「不良」と称した。
『不良』とは曖昧な表現、それはどういう意味を持ちどういう人生を過ごしたのか?
まず、その概要を知ってもらうために私はこの物語の「はじまり」を「あとがき」の引用から始めようと思う。
以下は、私が書いた百瀬博教著『プライドの怪人』の幻冬舎文庫版(平成15年上梓)の「あとがき」(解説)である。
…………………………
2003年7月──。
我々、浅草キッドは『お笑い男の星座2・私情最強編』を文芸春秋より上梓した。
その本に於いて最終章のさらに番外編として「男のホモッ気・百瀬博教」と題して一章を書き下ろし、この文章のなかで我々は「俺たち自身が、未だに世間に知られざるこの希代の怪人を世に知らしめる最初の語り部になりたいのだ」と書いた。
当初、この本の草稿中には、確かに百瀬博教氏は世間にも我々にも「正体不明の怪人」であったのだ。
しかし、その後、百瀬氏の世間の認知は急速に広まり我々との交流は急速に深まった。

そんなある日、僕が「百瀬さんの言う“不良”とは何ですか?」と尋ねると百瀬氏は言葉を選ぶこと無く「命懸けの虚構だ」と即答した。
その意味では百瀬博教本を読むことは「この話が実話なのか!」と嘆息し「こんな人が実在するんだ!」と驚嘆する、物語の中に浸り虚構に身を置く興奮だけで読者は「命懸けの虚構」を共有することになる。
さてこの文庫本は単行本時『プライドの怪人』と題され、かのアントニオ猪木との遭遇から始まるわけだが、常日頃より「出会いに照れない」と公言する百瀬氏は人生を強烈に彩る数々の人物との邂逅を自らの意志で呼び込んでいるのである。
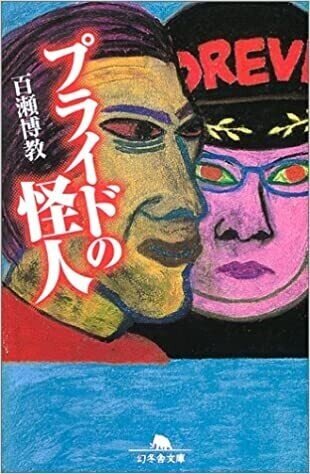
例えば、私の体験を語れば2003年7月8日のことである──。
この日、四谷で文化放送のラジオ番組『百瀬博教の柳橋キッド』の収録を終えた百瀬氏が慰労を兼ねてラジオのスタッフを西麻布のレストラン『キャンティ』に招待した。
このラジオ番組を時間のある限り自主見学している私も百瀬さんに誘われ此処にに同席していた。
一同が店の奥まった席につくなり、先乗りした百瀬さんが抱えきれない程の大きなユリの花束をラジオでパートナーを務める藤木千穂アナウンサーにプレゼントした。
「何事も照れちゃあ駄目なんだよ!」
と言い続ける百瀬さんらしいサプライズと気配りに勿論、藤木アナも「頂いてもよろしいのですか!」声を張り上げ喜び宴は盛り上がった。
しばらくして、店の入り口から歓声が聞こえると明らかにショービジネス系だとわかる出で立ちの外人さん一行がドカドカと店の中に入ってきた。
それは丁度、来日公演中のマライア・キャリーご一行であった。
スタッフ数名に親しい友人と思われる人。そして、超特大サイズの屈強な黒人ボティーガードが2人。
百瀬さんが騒ぎを聞きつけて「誰?」と聞くと「マライアです」と声を潜めてラジオスタッフが告げる。
「ああ、そう!あのデッカイ、ボブ・サップみたいな黒人がマライアなの? アイツ、強そうだな!」とトンチンカンな百瀬さん。
「違います、もう奥に座ってしまった派手な金髪の女の方がマライア・キャリーです。ちなみにあの娘は7オクターブの声域を誇る世界一の歌手ですよ」と慌てて訂正するスタッフ。
しかし我々の席からは死角に入っているので、この歌姫を一目だけでも見たいと順番で一人一人トイレに行くふりをしてマライアを覗き込むようにして眺めた。
そんなラジオスタッフの姑息な行動に百瀬氏が口を開いた。
「おい、コソコソするな!そんなに彼女を見たいなら、そのユリの花束をマライアに持っていけよ!」
「いや、これは……折角、今日、百瀬さんから頂いた物なので……」
「そんなの、また何時でも買ってやるよ!」
それでも藤木さんが物怖じしていると、
「いいかい。六本木でマライアを見たって位じゃあチンケじゃない。でもマライアに会った時に自分がユリの花束を渡したんだって言ったら、一生、誰にでも話せる想い出になるでしょ。出会いは自分から作り運命は自分で引き寄せるもんなんだよ!人生は全て演出なんですよ!」
と店中に響き渡る声で叱責した。
そこまで言われて、意を決して藤木アナもマライアのもとへユリの花を抱えて持って行ったのだが同席していたマネージャーらしき女性がぞんざいな手振りでシャットアウトした。
そしてマライアのお付きは「大変光栄だがマライアはユリの花のアレルギーなの」とその場しのぎの言い訳をした。
このやりとりの事情説明を聞いた途端、百瀬さんは、
「何をしみったれたことを抜かしてんだ! おい!帰ろうぜ!」
と席を立つと帰り際、出口にそびえる屈強なボディーガードに向かい合い何か一言、二言、捨て台詞を残し出て行った。
そして我々も続いて席を立って店を出ようとする時、その黒人の用心棒が我々を呼び止め、奥座のマライアを手招きすると藤木アナより花束を貰い受けマライアに手渡した。
世界が愛するセレブ様は大きな花束に囲まれると大仰に匂いを嗅ぎながら満面の笑顔で「サンキュー!」を繰り返したのである。
《どこがユリの花アレルギーなんだよ!》
と全員が心のなかで毒づきながら(いったい百瀬氏は何をあの黒人に言い含めたのであろう?)とも思いつつ、さらにあの不躾なマネージャーの振舞いを呪いつつ、この日、我々に最高の想い出が出来たことを確信したのである。
以上が2008年7月8日、一日のことだ。
この逸話が私にはことに面白いのは我々が『お笑い男の星座2』にも書いた百瀬氏とエリック・クラプトンとの出会いにも相通じるからである。
PRIDEの会場のリングサイドへ自費で観戦に現われた世界的アーティストであるクラプトンが後にPRIDEのテーマ曲を書くこととなる。
──その百瀬氏との巡り合いの珍エピソードは……我々の本「お笑い 男の星座2」で確かめて欲しい。
さて長らく知る人ぞ知る存在だった、この作家の状況が、ここのところ多くの人々に認識され世間との親和力を増していくようになった。
例えば、それは、ラジオのパーソナリティーも、その一つであり、また2003年8月11日のPRIDE会場での“出現”も一つの事件であった。
この日、大会ごとにその規模を拡大するPRIDEがミドル級GPを開催し、その会場となったさいたまスーパーアリーナには大観衆が詰め掛けた。
そして、この大会は初の地上波同日放送としてフジテレビで中継されたが全試合終了後、猪木の横に座る怪人はすくっと立ち上がるとリングに登り大会主催者として初めてマイクを持って観客に挨拶し多くの人にとって正体不明の怪人の姿がお茶の間に放送されたのである。
さらには、この4月よりテレビ東京系日曜22時、ゴールデン枠のバラエティー番組『プラチナ・チケット』ではシロートの諍いごとの調停役、雷親父として百瀬氏がレギュラー出演するらしい。
さて、今やテレビタレントにまで転進しつつある百瀬氏だが、その以前より、その出自、強面、不良のイメージからさまざまな風説を語られている。
その昔、『週刊朝日』の対談で林真理子さんが曽野綾子さんに対し、
「私、前に曽野さんにごちそうになりましたときに、その筋っぽい方も同席して写真パチパチ撮ってましたでしょ。私、こういう方と一緒の写真をどこかに使われたらどうしようとか、そんなことしか考えなかったんですけど」と語ると、曽野さんは「あの方は百瀬博教さんといって、いい詩人です。博学ですよ」と言下に答えた。
この話は、チンケな世間に対し背を向けて屹立している百瀬氏の存在、そして世間の偏見と実像の差を表して象徴的だと思う。
今、百瀬氏と接していると、外部よりいつも良識めいた雑音が耳に入る。
その度に百瀬氏が幼少時、父親と銭湯に行くと刺青を見て怯む人達を見て「弱いものいじめなど死んでも出来ない優しい父も彫り物を見せた瞬間から邪悪なものと後ろ指を差されるのだ」と感慨した、その幼き純情に思わず想いを馳せてしまう。
その父・梅太郎のことを百瀬氏は「幼い時から単純勁烈なる男の世界で生長し、常に自分を何かに賭け、駆り立てて生きねばならぬ稼業の人だった。そのなにかが虚構であると知りつつも、なお虚勢を張って生きる世界の人だった。侠気を装う気風。そうした精神風土の中へ、どっぷりと己を埋没させ自らを育み磨き上げよう努力してきた人」(『不良ノート』より)
と描いているが------
私から見れば、この猛き父の姿こそが今の百瀬氏と二重映しになって見えるのである。
とは言え、この種のエピソードすらも当の本人は「全然へっちゃらだね! 悪名こそ我が評判!」と面白がっていて、自らの噂、偏見、よからぬ伝説、風評さえ、人に語られることを楽しんでいる節がある。
で、あるならば圧倒的な多数の世の先入観に対し、少数派の熱烈な百瀬本マニアの俺は誤解を怖れず、あくまで曽野さんの側で語りたいところだ。
例え、百瀬氏の無軌道が将来、新たな地雷を踏むことが仮にあったとしても、その窮地に於いて、この類希なる作家の言動、振る舞いに対し私は強い関心を持つであろうと思うのだ。
そういう予感に対し自分が無視、黙殺の態度でいられないのは、私の生来の性(さが)であり、世の良識ある「保険だらけの現実」が「命懸けの虚構」を回避し「安全」な場所へ居続けようとする、その「退屈さ」に私は耐えられないからであろう。
さて、今回は文庫『プライドの怪人』の解説ではあるが、百瀬本全体の読後感を一言で言えば「純情の地下水と、溢れ出る過激」とレイモンド・チャンドラー風の言葉が思い浮かぶ。
そして百瀬本の地下水脈に流れる純情の血が「詩人」のものなら、その溢れ出る過激とは過剰すぎる「私」である。
なにしろ「百瀬さんは、頻出する『私』で世界を所有しようとする」(詩人・高橋睦郎)と書かれるように、数多(あまた)ある百瀬本の1大特徴は百瀬さん本人「私」の視点でしか書かれないことである。
しかし百瀬さんの書く物語に「私」だらけなのはそれだけ「私」の実人生が小説家の創作以上に過激すぎるからであり日々があまりに尋常ならざる劇的であることなのだ。
そして「想い出に節度がない」と自称するように自らの思い出語りに臆面なく果てしない。
「過去偏執狂と言ってもいいくらいの異常な記憶力に驚嘆する」(文芸評論家・松田修)と言うほど読者の誰しもが驚愕する、その郷愁の洪水のなかで時世は飛び交い、人名が入り乱れ、話しのディティルはどこまでも瑣末な横道に迷い込み、圧倒的な薀蓄が溢れかえる。
読書馴れしていない若者にはとっつき難いかもしれないが、その対処法としては、その百瀬博教の個人史を時間軸で捉え、俯瞰しながら人名の出入りを整理して読み解くことである。
例えば何点か抑えるべきエポックを生い立ちから列挙するならば、侠客の家に生まれ千葉県市川で過ごした幼年期、相撲取りを目指す高校時代、立教大学入学後のニューラテンクオーターの用心棒時代、拳銃不法所持事件、6年半の服役生活とその間、獄中での驚異的な読書への耽溺、乱読。出所後の詩人・作家デビュー、やがて大金持ちとなってしまう狂乱バブル時代、そして現在のPRIDE後見人(プロデューサー)期と大きく分けられるであろう。
さて、この本では、他の百瀬本では触れられていなかったバブル期の総資産九六〇億円(百瀬氏本人だけの額ではないが……)まで膨れ上がった錬金術ついても詳細に語られてある。
その顛末は本のなかでは「飛鳥銀行不正融資事件」と書き改められたが、実際にはバブルを象徴する史上最大規模の銀行犯罪として知られる「富士銀行不正融資事件」のことである。
金に堕ちて行く人間の狂乱を、その渦中に居ながら振り返り冷徹に客観的に描くのもまた百瀬本の醍醐味の一つであろう。
そして、この本では深く触れられることはなかったが百瀬本の読者としては一つの軸として、日本で有数なロイヤルファミリーとももくされる石原兄弟との係わり合いも肝要である。
戦後の日本を代表する日本一のピッカピッカの兄弟。
青年期に百瀬氏が私淑し「あにき」と慕った「裕次郎」、そして今や都知事、将来には日本の総理にも成らんとする「慎太郎」、その出会い、そしてこの兄弟への追慕、蜜月、そして誤解、さらには確執まで、時に擦れ違い、時に密に絡む、互いに“人生の時の時の人”である物語に注視することだ。
この本を担当した幻冬舎の見城徹氏が、長年、石原慎太郎氏の最側近編集者の存在であったことを考えれば読者はまた新たな興味が湧くことだろう。
文字通り「太陽」のごとくデビューし、小説家だけでなく政治家として
表舞台を輝き続けた石原氏を「恒星」だとすれば、その周囲を裏方としてあるいは裏街道を「惑星」の如く軌道した見城、百瀬の両氏は互いに意識しつつ共通の人脈も数限りない。
しかし今まで見城氏の方が、この怪人のブラックホールの如き人を引き寄せる強力な引力から逃げ続けていたらしい。

その見城氏は、今回、百瀬氏とコンビを組むに当たって、
「二十年以上も何度もすれ違っていたけど、この人と付き合うと面倒なことが次々起こるなと思って避けていた。親しく喋り合って二十年来たわけじゃないけど風の立ち方がどんどん成長しているのがわかる。それと、この人は小手先で誤魔化さない、まっとうに行く。突破する時にもまっとうに突破する。私、5年前の百瀬さんとは、きっと仕事が出来なかったと思う。この人とは生半可なことでは一緒にやれないって思いが常にあったから。百瀬さんと付き合えば掠り傷や返り血は浴びるでしょう。その覚悟がなければ道行きは出来ませんよ。道行きっていうのは絶対に地獄へ行くに決まっているんだから。天国に行く道行きなんて面白くもなんともない。一緒に死ぬ覚悟が決まるまで二十年かかったんです」
と語っている。
ならば見城社長にはこれから次々と起こる面倒の一つとして地獄ならぬ冥土の土産として「幻冬舎アウトロー文庫」に正真正銘のアウトロー百瀬博教の全著作を文庫化することに取り組んで頂きたい。
これだけ、そのパーソナリティーに関心が寄せられても多くの読者にとって今なお百瀬本を収集、網羅するのは困難な状況のままなのである、これを機会に幻冬社で文庫化を果たして頂きたい。
そして、この膨大な著作を一望にし、一つの視点を持って読めば「百瀬物語」とは実に多面的に豊饒に捉えられるのが実感できるであろう。
それは文芸の薫り高い多感な少年期からの成長小説でありピカレスク小説であり獄中記でもあり教養小説でもあり詩集でもあり、なおかつ同時代を生きる稀有な怪人の類まれな一生(ノンフィクション)でもある。
その読書の行為はまるで万華鏡を覗き込むように記憶は刻まれ、言葉は響きキラ星のように煌く男の世界へ誘われるはずだ。
そして、それは一人の漢が人生に描く「命懸けの虚構」である。
さて、ここまで書いてきたが実は中盤の曽野綾子さんの記事の引用には俺の意図的な省略、いや「虚構」がある。
正確には曽野さんの台詞は「あの方は百瀬博教といって、いい詩人です。文章を書くと有名人好きが目立って、私と少し趣味が会わないんですけど博学ですよ」と書かれていたのである。
あえて、ここでは私の判断で「有名人好き」以下のくだりを省略していたのである。
てっきり「私は有名人好きだけど、たまたまめぐり合えた有名人の方と話をして、その人の気分や気合が良いから好きになる。一人よがりで思いやりのない、単に有名な奴なんか、こちらかも相手もしない」
(「不良少年入門」)
と語る百瀬氏だから、曽野さんの苦言をも軽く聞き流しているのものだと思っていたからだ。
ある日、百瀬氏の執筆部屋に通された私は机の上に張られた手書きの文字を見つけた。そこには、
「『人のこと』は書かないでまっしぐらに自分の内面を書け。その思い込み方が作家の本当の姿である(曽野綾子さんのテガミより)」と百瀬氏特有の太字のマジックの楷書で書かれていた。
それを読んだとき、(正確には盗み読みしてしまったとき)わざわざこの言葉を自ら文字に書き起こし日々肝に銘じている百瀬氏を思い起こした。
そのとき、多くの人生の困難を己の剛毅と腕力で片付けてきた“不良”で“プライドの塊”の百瀬氏の人知れぬ一面を見つけたようであり、63歳になっても今もなお思春期の少年のような素直さを持ち合わせ、人生を前向きに生きようとする、その心意気と可愛らしさに私の男のホモっ気が胸の奥でキュンと音を立てた。
--------------------------------------------------------
この解説を書き終えた2003年10月1日──。
私は、この文庫本の出版元である、幻冬舎の見城徹社長と密かに会談を持った。
我々の著作である『お笑い男の星座2・私情最強編』の出版元の文芸春秋が書評は出揃い高評価であったにも関わらず販促に力を入れてくれないのが不満だった私は、この「お笑い男の星座シリーズ」の上梓後「不覚だった。この本は私のところで出版したかった」と高く評価してくれた見城社長率いる幻冬舎に移籍する話を直談判したのだった。
模様替えしたばかりの瀟洒な社長室で向かい合うと、見城氏は業界の大立者である貫禄を漂わせ、ふんふんと頷きながら話しを聞き終えると私の提案の大筋をOKし一点だけ条件をつけた。
「今回の『お笑い男の星座』の最終章で予告している百瀬さんと慎太郎さんとの絡みを今後、あなたが作品のなかで描くのなら私は他の出版社を紹介することは出来るけど幻冬舎からは本は出せない。なぜなら私は石原さんとは昔から特別に懇意であるし誰よりも恩義がある。百瀬さんとも仕事を始めたばかり……。二人共、現在の立ち居地もあるし緊張感のある関係もあるだろう。もし二人が事実の解釈を巡って齟齬が生じた時に自分が仲介に立つこともあるだろう。長く慎太郎さんの側近編集者としてやってきた私がそれじゃあ慎太郎さんに対して筋が立たない」
とのことであった。
そして、この私の解説を掲載した文庫本が出版された直後の2003年11月25日──。
MXテレビの番組収録で石原慎太郎知事にお会いした。
この日、知事はSPを引き連れた物々しさはいつもどおりであったが、丁度、おりからの第43回衆議院選挙も終わり東京5区から立候補した三男、宏高氏への度重なる知事自らの応援も空しく落選の憂き目に合ったところだった。
しかし、その表情は柔和で、祭りが終わった一段落の安堵感に包まれた様子であった。
私は、このMXテレビで東京都の広報番組『Tokyo Boy』のレギュラーをつとめて丸4年目に突入していた。
東京ローカルの番組なので全国的には知らない人も多いが、この番組、テリー伊藤の総合演出であり毎回、石原都知事が出演し他の民放番組に決して見劣りしない。
さて、我々が、この番組で司会を担当して久しいが、開始より2年目の時、都知事の著書『国家なる幻影』にサインを求めたところ、サインペンをもったまま「名前はなんだっけ?」と言われたほどであるから都知事は我々浅草キッドのことはまるで知らないのだろうなと思っていた。
そして、今年最後の収録になった、この日、空き時間に幻冬舎より出版されたばかりの『プライドの怪人』の文庫版を知事に進呈した。
しかし、見城氏の忠告もあって石原都知事にこの本を渡すことは躊躇していたのも確かだった。
知事は私が手渡した文庫を眺めると、
「ほーーぉ……。この本は、前に見城のところから百瀬の単行本で出たものだよね」と言った。
「はい。それで今回、文庫版になるに当たって解説を僕が書きました」
「へー、君が!?そう言えばこの間、百瀬に前に会ったら『俺は一晩で3億円用意できる』なんて吹いていたけどホントかね? 金貸しってそんなに儲かるの?」
「知事、それが、何時の話かわかりませんが3億どころかバブル時には、27億円を現金で当時レイトンハウスのオーナーだった赤木明社長に貸したこともありますよ、それに一時は間接的にですけど、百瀬さん、株の投資で総資産960億円まで膨れ上がったわけですから」
「おいおい言うねー、そりゃあハッタリ、嘘だろ! 」
「額は正確ではないかもしれませんが……嘘ではないと思います」
「ふーん。ところで今、百瀬は何をやってるの?」
「今、PRIDEって格闘技イベントのプロデューサーですね」
会話を続けながら都知事は恍(とぼ)けて知らない振りをしているのかな……と思った。
「僕は調べているからわかりますが、百瀬さんと知事とはお付き合いも長いはずですし、かなり昔のことになりますが知事が遊説で秋田に行かれた時、全国指名手配で逃亡中だった百瀬さんと偶然、お会いして平野政吉美術館で藤田嗣治の絵をご一緒に見たこともありますよね」
知事は遠い目をしながら、
「……ああ、確かに秋田で藤田嗣治の絵は見たことあるよ」
(ホントに憶えていないのだろうか?)
そして知事はまばたきを繰り返し、
「しかし、君はなんでそんなこと知っているんだ?」
「知事と百瀬さんが秋田の美術館で一緒に撮った写真も見せていただきましたし、その話は百瀬さんの著書のなかに出てきますよ」
「いやいや、あれを信じるかねー?あの本はあることないこと嘘ばっかり書いてるんだよ!」と知事。
途中から、知事の様子から、この話を続けるのはいかにも迷惑気な雰囲気になったきた。
スタッフから「本番です」の声が掛かり話はここで途切れた。
不穏な雰囲気のまま中座した。
やはり本を渡すべきではなかったし、調子に乗って余計な話をすべきではなかったと半分後悔していた。

その夜、ロケが終わって帰宅して自室で寝転がって本を読んでいたところに突如、私の携帯電話が鳴った。
非通知の番号であったので仕事柄、頻繁にかかってくる、悪戯電話かと思って出た。
第一声が──。
「誰だ?」
電話をかけてきて「誰だ?」は、いたずらでも珍しい。
沈黙で答えていると続いて、
「キッドぉ?」
聞いたことのない声で居丈高であった。
案の定のイタ電だと思った。
「はい、そうですけど」と私はぶっきら棒に答えた。
「すいどう?」
「水道橋ですけど、そちらはどたな様ですか?」
私は完全に迷惑気に怒った口調で問うた。
「石原です!」
「いしはら?」
「石原慎太郎です!」
と言われて事を察するまで数秒の沈黙、そして慌てふためき、立ち上がると直立不動で「はい!」と答えた。
それから時間としては15分だろうか──。
私は、あの石原慎太郎都知事と電話でお話したのだ。
知事は帰りの車の中で一読、そして帰宅後、食卓で二回目、この私が書いた文庫の解説の文章を読み直したと言われる。
「二度読んで確かめたけど、いや、あの解説はなかなかのものだよ……」
そして、長々と私には身に余る激賞を頂いたのである。
しかし、何を言われても「いえいえもう滅相もない!」と答える私に対して知事はこう言った──。
「君は知らないだろうけど、俺はけっこう芸術には見巧者でね、いろいろ、文学賞の審査員もやっているし新しい文章を見る目があるんだぜ!」
<そんなことは知ってます!>と思わず声を出しそうになった。
「君は、今まで何か本を書いたことあるの?」
「知事、大変申し訳なく、お言葉を返すようですが……実は文藝春秋から『お笑い 男の星座』と言うシリーズを書いてまして、今、2冊目が出たところです」
「あ、そうなの?」
「しかも、一冊目の単行本は知事の担当編集者から知事にお願いして本の帯に知事と一緒に撮った写真と推薦文をいただきました」
「……あぁ……そうかい……。いやいや、そういうことは僕の場合、なんというか、多々あるんで失敬というと申し訳ないんだけどね。……正直に言うけど、実は全くその本のことは知らない。でもまあ後で必ず読みますよ!」
多忙すぎる知事には、いかにも、ありそうな不測な事態であり互いにバツが悪い話なので思わず二人して笑った。
「で、君は今、何か書きたいものがあるのか?」
知事の質問に私は、
「はい、今は百瀬さん、百瀬博教さんの評伝が書きたいです」と答えた。
「そう……僕はひろ坊はねー。昔から知ってるんだよ」
(やはり、ひろ坊って呼ぶのか!)内心、声を挙げる。
「ひろ坊は、弟の裕次郎の兄弟分みたいなもんでね、まぁいろいろと彼には家族一同迷惑もかけられてきたんだけど、僕は彼の感性を認めていて、かねがね奴に『小説を書いてみろ!』と言ってるんだけど、しかも、タイトルはプルーストの『失われた時を求めて』って引用の題名で書けって言っても奴は何時も『わかりました』って言うだけで一向に書かないんだよ。」
「知事、百瀬さんが書かれる話は全部、自分が体験した事実しか書かないですから」
私は百瀬さんの文章のスタイルについて言及した。
「いやいや、事実とか言っても僕に関してはいろいろあることないことを彼は書いてるんだよ」
「知事、お言葉ですが『全ての告白は誇張を免れません』から……」
「おぅー、言うねぇ!」
「実は『お笑い男の星座』シリーズを幻冬舎に移したいって話があったんですが、そのときの見城さんの条件が“石原慎太郎には触れるな”ってことだったんです」
「……そう。僕はそんなの一向にかまわねぇよ。でも君はそんな評伝なんかより小説書けよ!そのほうがいいよ!……とにかく今度じっくり話をしようよ!」
と言って知事は電話を切った。
携帯電話を持ったまま私はしばらく呆然と立ち尽くした。
が、内心は小躍りしたいほど興奮して舞い上がっていた。
私の「百瀬博教の評伝を書きたい」の申し出に知事は了解なのか了解ではないのか答えは要領を得なかった。
しかし、文庫本の解説で自分が書いたように「百瀬博教の個人史を時間軸で捉え俯瞰しながら、人名の出入りを整理して読み解くことである」
——この言葉通りに実際に自ら俯瞰し整理し読み解き、この「命掛けの虚構」の全貌書いてみたいと本気で思った。
つまり-------------------。
石原慎太郎の電話がなければ、この文章を書くことはなかったのだ。
そして物語ははじまる。
『命懸けの虚構〜聞き書き・百瀬博教伝』(2)へつづく。
サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!
