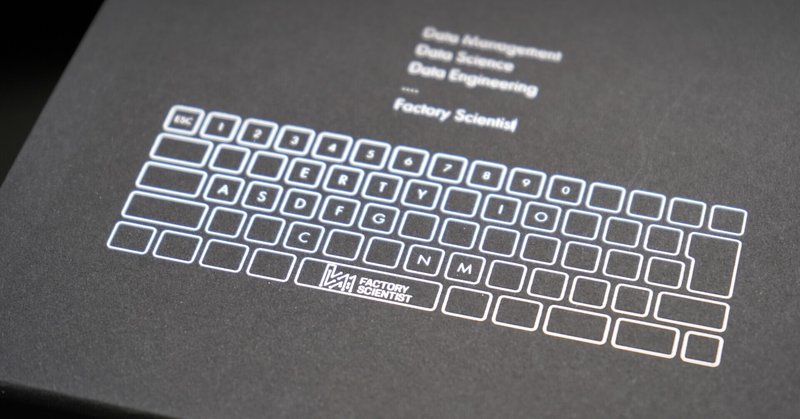
ファクトリーサイエンティストの受講を終えて
きかっけ
2021年年明け、ファクトリーサイエンティスト(FS)協会が主催する「ファクトリーサイエンティスト講座」を受講しました。
ファクトリーサイエンティスト協会は、「現場起点のデジタル人材を養成する」教育機関なのです。講座では、工場の現場を科学して、経営陣を巻き込み、工場の稼ぐ力を向上させる。見える化を起点にして会社を変えていく存在、そうした人材を育成することを行っています。
講座は、週1回5回、オンラインによる座学と10人位のグループに分かれて実際に自身でも手を動かす実習で構成されています。さらに、オフィスアワーという補講時間もありクラスで分からなかったことを質問したり、最終プレゼンテーションにむけての課題の相談などもできるようになっています。
講座は以下のように進みます。
1日目:IoTの基礎を座学で学び、実際にIoTデバイスを組み立てる
2日目:IoTハブの立ち上げ、Stream Analystics を開設する
3日目:Power BI を使いデータを加工する
4日目:MS Power Automate などをつかって見える化する
5日目:最終プレゼンテーション (受講生1人づつ)
さて、
今回の冬講座は、約40名の参加。全員で参加しての座学と実習が交互にあります。座学では、いままで言葉で聞いたことは合っても結びついていなかったIoTの基礎を学ぶことができました。
1日目のセンサーをつないで、マイコン(Wionode)にノンコードのプログラムデータをグラフに表示する。言葉にすると簡単なのですが、私は実はここに至るまで大変苦労しました。マイコンに初めて触る。ノーコードだから簡単というけれど、プログラムを知らないので、そもそもの敷居がとっても高い。プログラムってワード1文字間違っているとerror を起こす。アルファベット1文字違いを最後に発見してもらい、データが動き始めたときの感動といったらありません。
動画を学習しながら、分からないときにはいつでも画面の向こう側にいるTAに質問をできる。パソコンに向き合って一人で動画を見るというのは一見孤独に思えるけれど、動画はとても便利なのです。何度も繰り返し見ることができます。オフラインだったら恥ずかしくて黙って通り過ぎたかもしれないところをとことん見ることができます。
家からの受講だったので、部屋の身の回りにあるIoT化できること、に着目しました。講座で実際に使った「温湿度センサー」を使って、温度と湿度の変化をみました。部屋を見回してみると、温度と湿度の差がある場所は、結構あるものです。たとえば、冷蔵庫、風呂場、冬場なので加湿器、エアコン、などなど。

昔から、マニュアルを読まない、読むのが面倒だと思っている人です。感覚人間なのでとにかくそれもあって苦労しました。動画を見た回数は誰よりも多いと思います。毎回、講座が進む3回目までは、水曜の講座の後は深夜まで、その後の平日は仕事を終えてから夜になると動画を見入っていました。。 というわけで苦労しましたが、苦手なものに向き合い、投げ出さないで最後までたどり着けたことが自分にとって小さな自信になりました。
グループの仲間と時間中に話をする余裕もなかったのは残念でした。その代わりに、Facebookでつながっている方々に助けていただきました。こちらは、つながらないWionode をFB上にアップした写真です。何人もの方が即返でアドバイスをしてくれました。コネクタに正しい方向がある、なんて知りませんでした。 コミュニティはいたるところにあることを、支えられていることを再認識しました。

これからのこと:
データを取り、整理し、見える化し、周囲を巻き込んでいく。この流れは、工場の現場に限ることではないです。実は、最終課題に向けて、「課題を設定する」して、どうわかりやすくしていくか、といういことはIoTデバイスを触ることと同じくらい、大変ながら大きな学びでした。
どんなデータが必要か、データが取れたらわかりやすく見える化し、周囲を動かし説得できるように、意思決定を進められるように動かしていく。日々の私自身の仕事の中でも生かしていけたら、と思いました。
部屋の身の回りでいえば、コロナ禍で部屋で仕事をする時間が増えた中、温度と室温の快適性をもっと追及してみるつもりです。もっとも快適で、生産のあがるバランスはどんな時だろう?と。 ちょっとづつ身の回りを意識してみていく、発見があってたのしいですよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
