
[2020年初頭インタビュー] Dスタ/ホストアーティストから見たその魅力とは?
初回開催から2年、通算50回を目前にした「The D-Studio.-kanda」――。
その立ち上げから当初理念、そして現在にいたる“継続する意義”を踏まえ、松本誠治は何を伝えたいのか…。佐藤ケンケンが望むDスタの姿とは…。的場は何を実現したいのか…。
これまで語られてこなかったホスト側から見る「Dスタの魅力」について、彼らホストアーティストたちに存分に語ってもらった。(敬称略)
各ホスト紹介
松本誠治

the telephones、Migimimi sleep tightのドラマーであり、「We Come One」のオーガナイザー。
さらにはDJとして「大宮Base」というマンスリーのレギュラーパーティーの開催や、Rolling Stone Japanでのコラムの連載、ラジオ番組「松本誠治のWe Come One」のパーソナリティーとしても活動中。
サトウケンタロウ
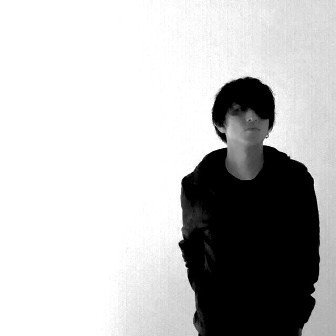
PlasticTree/泡/silly/PublicBath/infill
各バンドで活動中。
他ライブサポートなども務める。
synergyをテーマに、自主イベントのvol.1、vol.2を開催。
使用機材。SONOR/小出シンバル/VATER/EVANS/ZOOM/Roland
http://instagram.com/pla_kenken
http://twitter.com/pla_kenken
http://twitter.com/drums_kentaro
的場誠也

1989年、有機生命体としてUKプロジェクトよりCDデビュー。解散後、フリードラマー&ドラムチューナーとなる。メンテナンスやセミナーの開催にも着手。 参加アーティスト
Cari#gari TheTelephones PlasticTree NICO Touches the Walls LUNKHEAD Despairs`Rey 9GOATSBLACKOUT DuelJewel Sugar ヴィドール FAKE? La'crymaChristi Laputa Pierrot Psycho le cemu 河村隆一 goatbed Waive SHAZNA Hush AUTOMOD FANATIC◇CRISIS DIP Pre-School RAVE SIREN 宮本コウジ 杏子 Leyona いしのだなつよ 谷村詩織 もりきこ Halation etc・・・ https://twitter.com/matobaseiya
ーーーーーーーー
Dスタ立ち上げの経緯
ドラマーたちの座談会The D-Studio.-kanda(以下、Dスタ)は、東京・神田でリハスタStudioBpmがオープンする際、その柱となる企画として立ち上げられ、2018年5月に第1回目が開催されている。
もともと同スタジオスタッフの的場氏が、東京・平井にあるリハスタ「オトキチ」で1人ホストの座談会として開催されていたものだが、これを神田でもやってみようというのがスタートだった。その立ち上げおよび、ホストを増やして実施するにいたった経緯を当の的場氏に聞いてみた。
「そもそもこのおふたりと僕は、アーティストとドラムテックという関係性のなかで知り合って長年一緒に仕事させてもらってきた。そんななかで近年は、僕がふたりにたいして『そろそろセミナーとかやったらいいんじゃないの?』という話をそれぞれ別々にふっていたんです」(的場氏)
先輩アーティストが、ミュージシャンの活動のもう一つの柱となるセミナー・講義・講演という方面でのムーブメントを起こすよう勧めた、ということだ。的場氏が続ける。
「やがてこのおふたりの距離が近くなったこともあって、僕の中で二人を組み合わせたら面白いかも、って思うようになった。世代も近いし、お互いアイコン的な意味でも“持ってる”バンドにいる。直接『二人で回ってみたら面白いんじゃないの?』とも話していました。そこへ、このスタジオの話が舞い込んできた。今後のおふたりには悪い話じゃないと。それが企画立ち上げの、ごくごく初期の衝動でしたね。」(的場氏)
その話を受けた際の二人の反応はどうだったのか。まずはケンケンさんがこう話す。
「セミナー的なものをやったらいい、というアドバイスをいただいていたころって、ちょうど的場さんにドラムのレッスンを受けていた時期だった。そこでこのDスタの話をいただいたので、僕にとってはこのDスタは、そのドラムを教わっていたときの延長なんです。いまも勉強しにきている、という感覚というべきでしょうか」(ケンケンさん)
その反応はいささか意外だ。セミナー形式のイベントでは、ホストはあくまでも講師役であり、その持てる技術や知識を披露することで、集まった参加者が何かを得る。そんな形で進んでいたと考えてきたが、その講師役が勉強にきていたとは…。
「勉強といってもいろいろありますよね。単純にドラムの知識を知りたいというだけでなく、参加するすべての人たちそれぞれの音楽に対する観点や価値観を知ることも大事だと思うんです。来てくれる人が何を感じているのか、それを知るのは僕にとって勉強になっている。だからオレ、黙っちゃうことが多いんですよね…。みんなの話を聞いてしまうんです…」(ケンケンさん)
たしかに、これまでのDスタでケンケンさんは寡黙でいることが多い。総監督としての的場氏、現場を回す誠治さん。ケンケンさんは、長い沈黙のすえの鋭い意見が参加者をうならせる、という役どころだ。
誠治さんいわく、「ケンケンさんって、いつもロダンとおんなじですもんね…(笑)」。つまり、考える人ーー。そんなポーズでいることが少なくないというわけだ。

参加動機は『知る』こと
では、誠治さんはどうなのだろう。いつもDスタでは司会役を務めることが多い誠治さんだが、発言頻度がもっとも高く、かつその発言は知識や経験に裏支えされた熱い内容であることが特徴的だ。
その誠治さんも、Dスタを始める大きな動機のひとつが“知りたいから”なのだという。何を知りたいのか。
「目指すべきスキルアップのための方法論といったテーマは、多くのセミナーでとりあげられていて、正直、“もうお腹いっぱい”なんです。そういう方法論は、知らないより知っていたいとは思うけど、せっかく自分たちでやるなら、それだけじゃないところ目指したかった」(誠治さん)
具体的にはどんなことなのか、重ねて誠治さんに聴いてみた。
「方法論ではなく音楽そのもの。知りたいのはそこですよね。どうやって音楽と接していくべきなのか、どうやって音というものを制作していくのか、どういう音の歴史・リズムの歴史があるのか…。そういうことを知っていくことのほうが意味があると思っていたし、いまも思ってます。だから座学的な、かといって肩肘張らないイベントがいいなと。的場さんから話をもらって、まず考えたのはそこでしたね」(誠治さん)
座談会形式のイベントは、誠治さんの希望にもマッチしていた、ということなのだろう。では、はたして、その当初の想いは実現できているのか。
「実現できているかはともかく、続けていて思うようになったのは、少なくともDスタがドラムの“駆け込み寺”にはなっているかな、と…。見に来てくれる人が割と気軽に相談とか提案を投げかけてくれる。それに僕らが、肩肘張らずに応えている。もちろんお客さんがいる以上はひとつの演し物、エンターテインメントであるってことは承知のうえで、『ここでの距離感がいいんだよな』っていう楽しさがあるんです」(誠治さん)
その距離感は、聴衆としての参加者の側も濃厚に感じているようだ。ドラムを始めたばかりだという女性がいう。
「最初はもっと技術的なこと。スネアの叩き方とか、フィルインの入れ方を教えてほしいと思っていました。でも、そういうことよりさらに深い音楽の楽しさ、ドラムの難しさや楽しさがテーマになることが多いので、自然と音楽全般にたいする知識が増えたし、向き合い方も変わってきました」(30代・女性参加者)
参加者の意識が変わる――。それは主催するホスト陣の当初の狙いが実現されつつあることに間違いないだろう。

“座談会”であることの意味
その参加者の意識の変化は、質問内容にも表れてきているように感じられる。例えばDスタ第30回「世界のリズム」の際の一コマだ。
世界のリズムがホストから紹介され、コメントが入り、実際にそのリズムの特徴的な楽曲を聴くといった内容が展開されていたさなか、参加者のひとりから突如「じゃ、日本のリズムってなんですか?」との問いが発せられた。
たしかに聞いてみたい素朴な問いかけではあるが、音楽を知る人ほど尋ねるのに躊躇されてしまう質問ともいえる。予定されていたテーマだったとみえて、ホスト陣はもちろん課題をクリアしていくのだが、質問があった瞬間、3人のホストが絶句したのが印象的だった。
直球過ぎる質問に面食らったというべきかもしれないが、参加者の意識が変わるにつれて、質問がより遠慮のないものになっていく、という側面はありそうだ。
的場氏は、その状況を「そういう突飛な質問を待っているんです」とひとことで評していた。
誠治さんは、こう補足する。
「大前提として、われわれも学びの途中にある。だからお客さんの質問に『あれ、それってどうなんだろうな』って考えてしまうことは、今後も大いにあると思っています」(誠治さん)
その問いに対するベストな回答や解決方法をホストが必死に考える。そして、その姿を参加者が見守る。
「それがDスタのいいところなんです。困ってしまう質問っていうのは、われわれに考えるきっかけをくれる“いい質問”なんだと、そう受け止めていきたいですね」(誠治さん)
どんな初歩的でバカらしい質問であっても、あるいはどれだけ専門的な質問でも構わない、ということなのなのだろうか。
「僕らは上からものを教えるというスタンスは取りたくない。一緒に学んでいきたいと思っているので、誰が来てくれてもうれしいですね。初歩的な質問はもちろんだし、逆にプロでやってる方、理論をお持ちの方が来てくれるのであれば、ぜひいろいろ聞いてみたいこともあります」(誠治さん)

あくまでも、自身の学びの場であることにこだわるのは、ケンケンさんも同じだ。
「どんなに初歩的な質問であっても、あるいは音楽経験がないひとの見当違いな質問であっても、それを楽しむことが一番だと思うんです。そこにも僕らの勉強になる要素は必ずあるはずだし、要素を見つけようとすることが僕らにとっての勉強でもある。勉強しつつ楽しむという、そういうスタンスでいたいと思うんです。勉強はさておいて楽しみたいというお客さんがきても、そういうスタンスでいれば退屈させないで済むんじゃいかと…」(ケンケンさん)
さらに的場氏も「イベントとして開催している以上は、全世界にむけて門戸を開いているわけで、誰が来てももちろんOKです」と前置きした上で、こう続ける。
「そのなかで僕らよりもずっと深いヴァイブ(※vibration=雰囲気、フィーリング)を持っている人が来れば、その人に壇上に立ってもらいたいし、こちらから質問をぶつけてみたい、と思います。その人と僕らのやりとりをみて、参加者の方が『そういう考え方もあるんだね』と感じてもらえるような、そういう場になれば、Dスタはより深い意味を持っていくんだと思います。その意味でも、この会は講義でもセミナーでも討論会でもない。やはり“座談会”なんだと思います」(的場氏)
このイベント「The D-Studio.-kanda」が、副題「ドラマーたちの座談会」と銘打たれている意味は、そこにあったわけだ。
殴り込みもバトルも大歓迎!?
しかし一方で、主催者側である同スタジオスタッフはこうも考える。
「プロ同士、『ここはこう叩かないとダメだ』とか『オレなら絶対ここはこう叩く』といった方法論の違いはあるはず。当然、主義主張のぶつかり合いだって生まれてくる。そういうぶつかり合いを、参加者は見てみたいのではないでしょうか」(スタジオスタッフK)
いわばバトルの推奨、または誘導とも思える発言だが、誠治さんはいう。
「Dスタにバトルが似合うかどうか…。もちろん意見の不一致はなくはない。でもここが難しいところで、楽器の演奏って、人間に個体差があるようにそれぞれ違うんです。どれが正解かと聞かれても、それは分からない、というしかない」(誠治さん)
利き手が違う、体の向きが違う、視界が違う…。そういったわずかな条件が重なりあうことで、楽器の演奏方法には大きな個人差があるというのだ。
「そのうちの一つを正解と決めつけてしまうのは、もったいないなぁ、と思ってしまいますね。だから演奏法とか技術論としては、バトルになりにくいと思います」(誠治)
さらに誠治さんがこう続ける。
「それに、Dスタのような集まりでは、何かを排除してしまうことが最もバカらしいと思うんです。どんな考え方でも、どんな練習方法でも、どんな音楽でも、それを好む人がよりよく表現できるのが大事なのであって、よりよくするためにみんなで考えよう、という会でありたいんですよね」(誠治さん)
このDスタでのバトル推奨論には、ケンケンさんも熱く反応する。
「方法論や価値観の違いは間違いなくある。それが自然です。でも、たとえ異なる意見であったとしても、それについて“対立”しようとは思いません。そもそも僕らが話している内容は『ドラムはこうあるべき』というものではなく、あくまでも『自分たちはこういう気持ちでやってますよ』というに過ぎない。だから、われわれとの対立は起こりにくいと思いますね」(ケンケンさん)
まさかとは思うが、ものすごいテクニック自慢が殴り込んできて、『これ、できるか!』などと技術を披露する、などということがあればどうするのか。
「おぉすごいな…って、単純に感心しちゃうでしょうね。そもそも高度なテクニックを持っているアーティストより、若干技術は劣るけどこっちのアーティストのほうが好きだ、ってケースは往々にしてあるわけです。アーティストにとって、テクニックというのは表現のための手段の一つではあるけど、それがすべてではないと思うんです」(ケンケンさん)
煽ろうとする質問者が恥じ入るばかりの冷静な分析だが、やはり同じ立場から総括してくれたのは的場氏だ。
「このおふたりはどちらも大きなバンドにいて、長年そのバンドを回してきた。そこはやはりテクニックだけでは乗り切れない場合が多々あったはずです。テクニックなどではなく、より人としての大事な要素、総合的な人間力が試される場所にいて、絶えず揉まれてきたのでしょう。そんな彼らには、単純にドラムが速く叩けるから『オレすごいだろ』という価値観はないし、他者と対立する意見がでてきても、“なぜそう言ってるんだろう”と考えて自分の糧にしてきたから、ケンカになりようがない」(的場氏)
そういえる的場氏も含め、かれらホスト陣の落ち着きぶりは堂にいったものなのだ。かえって殴り込みやバトルを、彼らがどう捌くのかが楽しみにさえなってくる。
ここはひとまず『Dスタでは殴り込みやバトル、大歓迎!』と謳っておくのはどうだろうか…。

ドラマーだけじゃない!
Dスタについて、誠治さんは「ドラムの駆け込み寺」と評し、的場氏は「世界中に向けて門戸を広げている」という。また、Dスタには“ドラマーのための座談会”というサブタイトルがついている。
あくまでもドラマーのため、という点にこだわるのか。これについて誠治さんには持論がある。
「じつをいえば、ドラムに限らず全パートの“お悩み相談所”になればいいかな、と思っています。例えば、作曲家に『ここのスネア、音を作ってみたけど、どうもミックスすると消えちゃうな。音が弱くなるな』なんて悩みがあるとすれば、それを一緒に考えて提案できる場所でもいいなと。ギタリストやベーシストからは『なんかドラムとハマらないんだよな。なんでこういうことが起きるんだろ?』って疑問を投げかけて欲しい」(誠治さん)
それに対してドラマーが答えを持っているということなのか。
「もちろん的確に答えることはできないかもしれない。でも、われわれドラマーの悩みを聞いてもらうだけでも、『そうか、パートが違うからなかなか同じ言語がないけれども、彼らもこういうことを考えているのか』と発見があるかもしれない。ひとつ歩み寄ることができるわけです。そうなればバンドの流れが変わることもあり得るわけです」(誠治さん)
バンドの流れ…。そういえば過去のDスタで「他のパートとの意思疎通」がテーマとして取り上げられることがたびたびあった。バンド内にもパート同士の葛藤があるということか。
「バンドをやっている以上、摩擦がない、ということは考えられません。そもそもバンドって、エゴの押し付け合いなんです。みな自分が正解だと思ってるし、そうでないとやって行かれない、ともいえる。その、“それぞれの正解”をすり合わせていったところにバンドの音があると思うんです」(ケンケンさん)
同じことは誠治さんも、「メンバーがそれぞれ色のついた円を持っていて、その円が重なり合った一番色の濃いところがバンド」だと話している。意思の疎通を図ることで、その色の濃い部分、つまり“共通言語”がふえていくというのだ。
「Dスタは、たしかにドラマー主導でやっていますが、そもそもドラムは合奏してはじめて生きてくる楽器。ドラムだけの世界で楽しむのではなく、他のパートとの共通項を作っていくことのほうが僕らっぽい。だから、すべてのパートの人に来て欲しいんです」(誠治さん)

最後に的場氏がこう締めくくる。
「難しいことをいうつもりはないんです。ただ、Dスタに参加するとドラムの世界がちょっと広がりますよ、と言いたい。一人よりも二人、二人よりも三人、さらに仲間がいる。そうなってくると、参加すれば何かがちょっとだけ広がるじゃないですか。音楽への理解とか、情報とか…。そこが目指しているところですかね」(的場氏)
Dスタが志すのは、“ドラマーたちの座談会”の枠をこえ、いまや“バンドマンたちの座談会”へと脱皮しつつあるのかもしれない。
想いは熱く、スタンスは冷静かつしなやかで…。Dスタの魅力は、3名のホスト陣の魅力に他ならない。
○
インタビュー後も、3人のおしゃべりは続いていく。
「インタビューなんだから、もっと紳士的な受け答えをすべきでしたかね…」(誠治さん)
「そうね。すべて“かっこいいセリフ”で返したかったね。テレビのドキュメンタリー番組みたいなノリで…。『ドラムチューナーってどんな仕事ですか』って質問には、『チューナー? いや、おれはマトバセイヤって仕事をしてんだよ』とかね…(笑)」(的場氏)
「うわ、メチャクチャかっこいいですね。ただ、そっちにばっかり意識がいっちゃって、中身のない記事になりそうですけど…(笑)」(誠治さん)
「でも、それ、面白いですよ…。次のDスタのテーマにしません?」(ケンケンさん)
冗談からテーマが生まれるのは彼らにとって日常茶飯事だ。
Dスタとは何なのか――。
この笑いの絶えない光景にこそ、答えがあるのかもしれない。
(インタビュー構成:小板橋三郎)
もし気に入っていただけたらサポートよろしくお願いします。今後のBpmのnoteの運営に役立たせていただきます。
