
なんどわかっても、わからない
「実家の不可思議について悩み続けてもう飽きてのちの話」として継続して書いていきたいと思い、noteを始めました。
今後はこのテーマの他、現在の脳内やら過去の雑記帳やらから取り出していく予定。
書くことは心を整えること。
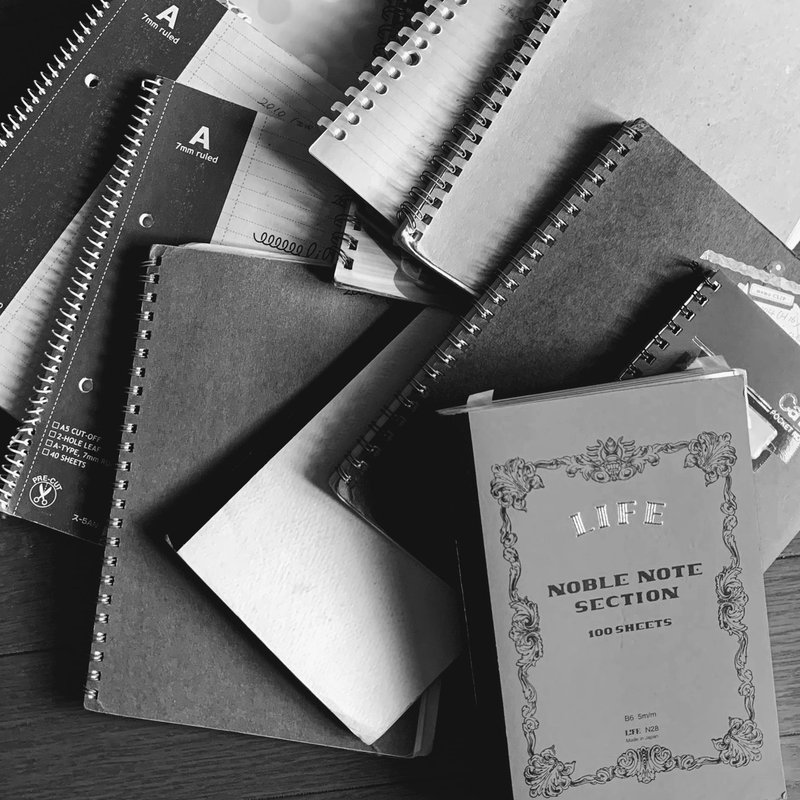
1. わかった、今度こそ。きっとこれが正解だ。
――この言葉をこれまで幾度、脳内で叫んだことか。文字に刻んできたことか。 「なんで ?」的なもやもやした悩み。「もうかんべんして」的に脳内の一部を常に占めているストレス。そんなマイナスでしかないもの、いつか解決するはず、消えてなくなるはず、そうでない人生なんてありえない ! と信じてた。
悩みから解放されたい一心で解決の道を探り探り生きてきて、でもつまり、わからないのが正解なのかもと、半世紀を経た今やっと気づいた。でもああしかしこれもまた「わかった」の誤解かもしんないヘルプミー。
なにせ「実家のこと」なんである。
実家暮らしをしていたとき、とにかく不可解だったのは、「自分(たち家族)は不幸であるべき」とする刷り込みだった。テレビ画面の向こうではしゃぐ人たちの存在が信じられなかった。「あのひとたちはなぜあんなにほがらかでいられるんだろう」と不思議でならなかった。つまり「ねたみ・そねみ・うらみ」の三拍子に凝り固まった心地で生きていたのでしょう。ああヤダヤダそんな人。
目の前に現れる事象に素直に反応すること。心の底から笑うこと。涙を流して感動すること。あるいはまた、人と人との親しい言葉のやりとりや、豊かで気持ちの良い愛情表現。これらすべてが自分とはかけ離れた世界にある架空のものに思われた。
けれどもしも、これらこそが本来「人」としての在り方であるなら、わたし(たち)はいったい何なんだろう。なぜ楽しい気持ちになることが許されないんだろう。いつもいつも、そんな心境で過ごしていた。息苦しかった。
家を出、土地から離れてつくづく思い知った。あれは、少なくともわたしにとってあの暮らしは生き地獄だったと。
実家の居心地は最悪だった。家の中のどこにいても、外に放り出され風雨にさらされているような外気との一体感があったし、360度方向から人目にさらされているような衆人環視の感覚がつきまとった。
国道と旧国道が交わる三差路の角に位置している上、真後ろにも突き刺さるようにまっすぐ道路が伸びる家。
たとえば小中学校時代、同級生などから家の場所を訊かれたとき、口頭で簡単に説明するだけで「ああ、あの家ね」と言われた家。
のちに占いの方からも、
浮いて見える
もともと三本けやきが立っており道祖神が祀られていた
平安時代にはすでに存在した、誰もが目印にした場所
ですよとはっきり告げられた、そりゃあーた、およそ落ち着いて暮らせるはずはなかろうと確信させられた家。
当時のわたしは強く強く憧れていた。
ドアを閉めカギを掛けたら裸になれるくらい安らげる家(部屋)に一度でいいから住んでみたい、と。
今日はココマデ。読んでくださった方ありがとうございます。
実家が実家がと言い続け悩み続けて、いつかどのようにかして、きちんと吐き出さないことには身が、心が保たない ! と感じていたわたしにきっかけをくれたのは、話題になった「キナリ杯」から熱く伝わってきた「書くワクワク感」と、そのおかげで知った「note」の利便性と、家族の悩みに共感し救われた『兄の終い』(村井理子)という本でした。岸田奈美さんと村井理子さん、そしてnoteは救世主 ! 感謝です !
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
