
セクシー本堂における仏教的モチーフから読み解く「怨みのレヴュー」についての考察
John
Discord:soprano John#8958
https://twitter.com/Jack_O_H_Nielse
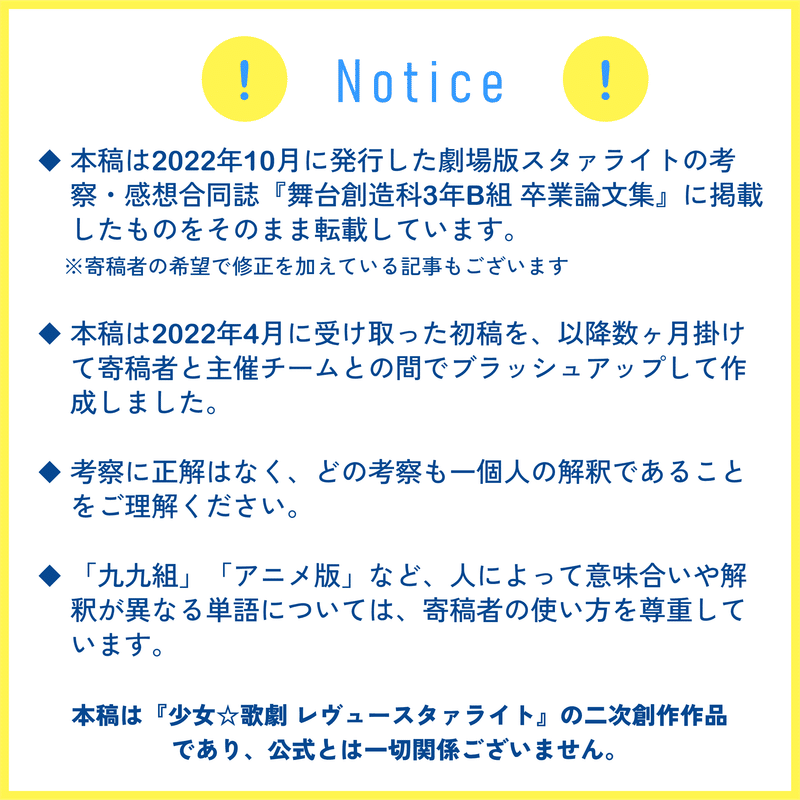
序文
「セクシー本堂とは何だったのか」
本研究は、この疑問を発端とする「怨みのレヴュー」についての考察である。
アニメーション映画『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下、劇場版と記す)には電車が移動式の舞台に変形するシーンをはじめとした超現実的で荒唐無稽な表現が多く見られた。しかし筆者は『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のTVシリーズ(以下、TVシリーズと記す)が暗喩を多用した作風を特徴としていた(*1)ことから、劇場版も同様の手法が用いられていると推察し(*2)、それらの描写に込められた意図を読み取るべく考察を行った。
特に注目したのは劇場版の後半部分である。この部分はレヴューシーンで超現実的描写が頻出することもあり、怒涛の展開と形容しうるものであったが、石動双葉と花柳香子の二人が主演の「怨みのレヴュー」もまた一番手(*3)に相応しいインパクトの描写が含まれていた。
その描写の中でも最も荒唐無稽に感じたのがセクシー本堂であり、本研究はその意図の解明に高い意欲を抱いたことが発端である。筆者は該当シーンに描かれた仏教的モチーフを糸口とし、SNS上で本作のファンと意見交換を行うなどして考察を深めた結果、本研究は「怨みのレヴュー」は香子(*4)による「双葉をトップスタァを目指す者として確立させるため、わがままを言えるようにするため香子が設けた儀式である」という結論に至った。本稿はその論拠を提示するものである。
本研究では「怨みのレヴュー」を扱うにあたり、劇中の描写を参考に以下の4節に分割した。
・第1節 導入部
賭場のシーンから参道の階段を上り切るまでの部分
・第2節 セクシー本堂
キャバレークラブ風の仏堂内のシーン
・第3節 清水の舞台
清水の舞台を模した場所にトラックが並び、香子のトラックが崖下に落下するまでの部分
・第4節 終結部
崩れた舞台に香子と双葉が宙吊りになっているシーンから、香子の上掛けの紐が切られるまでの部分
本稿はまず各節の概要を整理しながら特に注目した箇所を挙げ、それらの意図について考察を述べていく。
*1 TVシリーズ第1話を例に挙げると、「神楽ひかりによって東京タワーから突き落とされる愛城華恋」のカットにより戯曲スタァライトのクレールとフローラと同等の関係性であることを暗示する、劇中曲の主旋律が星見純那から愛城華恋に変わることで戦況の変化を表す、などの表現が挙げられる。筆者は地下劇場で行われるレヴュー自体を登場人物たちの学校生活における衝突の暗喩であると考えているが、本論の趣旨とは外れるためその論拠については割愛する。
*2 劇場版キャッチコピーの「列車は必ず次の駅へ、では舞台は? 私たちは?」という一文においても列車の性質を登場人物の成長に例えた表現が用いられている。また注釈1 の繰り返しになるが、テレビシリーズ同様その場面のイニシアチブをとった人物が劇中歌の主旋律を歌う演出が用いられている。
*3 便宜上一番手と述べたが、正確には劇中劇「ワイルドスクリーンバロック」は「皆殺しのレヴュー」を序幕とし、次に第一幕「怨みのレヴュー」が続くという構成になっている。
*4 一般に学術論文の基本的な様式において人物名の略称は名字が用いられるが、本稿では筆者の個人的信条から花柳香子を名字呼びすることが憚られるため略称に名前を用いる。石動双葉についても同様である。
「怨みのレヴュー」の前提
本論に入る前に「怨みのレヴュー」の前提となるポイントを挙げておく。最も重要なのは、双葉が幼馴染である香子へ相談せず、卒業後の進路に新国立第一歌劇団(以下、劇中の略称に倣い新国立と記す)を志望した点である。
香子の進路は実家の日本舞踊の家元を襲名するというものであり、それぞれの進路に進んだ場合二人の距離は物理的にも離れてしまう(*5)。
これは一見するとTVシリーズ第6 話の「約束のレヴュー」で、双葉が香子に対して宣言した「香子がトップスタァとして花開くさまを一番近くで見届ける」という約束に反し、双葉が香子を捨て去ろうとしているかのように見える。
本研究の結論から言えばそれは誤解であり、双葉が別れを選んだのは再会を見越しての判断であった。香子もそれを理解していたことは第4節の「わかってますんや、そんなこと」というセリフなどから察せられる。本稿ではそれを踏まえ、各節を検討していきたい。
*5 香子の実家、日本舞踊千華流は京都にある。双葉が志望した新国立第一歌劇団は劇中で描かれた劇場などから宝塚劇団をモデルにしたものと推察される。その活動拠点も同様に東京と兵庫の劇場と仮定すると、二人の生活圏は最短でも県を一つ隔てることになる。
第1節 導入部
第1節は賭場のシーンから清水寺を模した舞台の本堂へ向かう階段を上り、双葉が香子へ手を差し伸べるまでの部分である。『わがままハイウェイ』の前奏開始前も含むが、歌詞では以下の部分が対応する。点線で示した部分が香子のパートであり、双葉のパートについては波線で示した。下線がない部分は斉唱である。

この範囲の歌詞は香子と双葉のどちらの主張にも偏っておらず、舞台の上でも大きく形勢が傾く描写はなかった。
冒頭では丁半と思わしき小道具(*6)の配置された賭場を舞台に、壺振りの「香太夫」に扮した香子と博徒「鉄火場のクロ」に扮した西條クロディーヌが登場。それぞれの役を演じながら、香子はクロディーヌの影響で双葉が自分と異なる進路を志望したことについての非難と解釈できるセリフ(*7)を述べながら、寸劇を繰り広げる。
睨み合う両者へ「さぁ、張った張った」と囃し立てる声が上がるなか、壁を突き破り電飾を施されたトラック(以下、デコトラと記す)と共に双葉が登場。ここでレヴュー曲の『わがままハイウェイ』が流れはじめる。
スカジャン姿の双葉(*8)が名乗りを上げると、TVシリーズと同様のレヴュー衣装へと変わる。それに応じ二台目のデコトラが一台目と反対方向の壁を破って現れ、香子の衣装も名乗りと共に壺振りの装いからレヴュー衣装に変わる。そして香子は賭場の外へ飛び出し、それを追う双葉と武器を交えながら清水寺を模した舞台(*9)の参道を進んでゆく。
その道中、香子は双葉へ以下のセリフで「約束のレヴュー」の内容を再提示し、双葉の志望した進路がその約束を違えたものであると主張し、双葉を非難した。
“うちは世界一の踊り手になる。
それをあんたが一番近い場所で一緒に目指す。全部嘘やった”
“うちが進むその隣に、あんたがずっと居てくれるはずやった”
これに対し双葉は以下の通り反論し、進路が別れることは否定しないものの、それは「約束のレヴュー」での誓いを果たすための選択であると主張した。
“お前と並んで後ろから見つめてるだけじゃダメなんだよ。
自分の足で舞台に立たなくちゃいけないんだ”
“行きたいんだもっと高い場所に。立ちたいんだてっぺんの舞台に。
成りたいんだお前に相応しいあたしに”
そして最後に手を差し伸べながら付け加えたのが以下のセリフである。
“変わらなくちゃいけないんだよ。あたしのためにも、お前のためにも”
筆者はこの一言が香子の逆鱗に触れたと考えるが、それについては後述するものとする。
さて、この第1節でまず筆者が注目したのは賭場に組まれていた丁半のセットである。丁半の詳細なルールについては割愛するが、要点としてこの賭博ではサイコロの目の合計が偶数であるか奇数であるかを予想し、それが的中すれば勝利となる。つまり丁半の参加者はサイコロの目が2で割り切れる数字か否かを宣言するのである。
先述の通り、双葉は自分の進路について、あくまで「約束のレヴュー」での約束を果たすための一時的な別れだと主張した。それに対する香子の反応はいくつかに分かれるが、後述の第2節で描かれるのは双葉の主張を嘘と断じた糾弾である。
筆者はこの二人の描写を丁半のルールと重ね合わせて「約束は反故になった。絶交する」と宣言した香子を気持ちを割り切った「半」に見立て、「約束は継続しており、いつかまた再会する」と主張した双葉を割り切らない「丁」に見立てていると考えた。
賭場のセットが登場したのはこの暗喩のためではないかというのが筆者の意見であるが、しかしこの説を裏付ける論拠は本稿執筆時点で発見できなかった。よってこの考察はあくまで個人的な推論にとどめ、今後の研究に期待したい。
*6 博徒風の顔ハメ看板が周囲に並び、中央に敷かれた盆茣蓙 の上には掛け金を換金に用いる木札、星摘みの塔を模した壺などがあり、レヴュー衣装の上掛けを留める星柄のボタン2個がサイコロに見立てられていた。
*7 このシーンのセリフは「許しまへんえ。うちの大事なお菓子箱、食って、荒らして、毒盛った」「あんたのせいで、うちらは……」というものであった。「お菓子箱」は石動双葉の暗喩と考えられる。
*8 私服のトラック運転手、あるいは賭場に出入りする若いヤクザなどをイメージした服装であろうか。
*9 清水寺の特徴である本堂の舞台から推測した。また香子と双葉の出身地の寺院であるという縁もある。
第2節 セクシー本堂
第2節は「セクシー本堂」の字が書かれた看板が表示され、仏像が置かれたキャバレークラブ(以下、キャバクラと記す)と思わしき接待飲食店風のセットへと場面が転換した箇所から、香子が「表出ろや」と発言するまでの部分である。歌詞では以下の部分が対応する。歌い分けについての表記は第1節と同様に示した。

これらの歌詞は3つに分けられるが、初めの部分は香子の主張であり、次の部分はそれに対する双葉の返答になっている。3つ目の部分は雨のせいで顔を寄せ合うような描写である。斉唱であることから両者の心情表現と考えられるが、筆者は別れ話の最中に寂しさを覚え、雨の寒さのせいにして寄り添うような情景を思い浮かべた。口にこそしていないが、互いに内心では別れを惜しんでいることの暗喩であろう。
歌詞の上では香子の主張に対し双葉も言い返しているように見える。だがこの節での二人のやり取りを考慮すると、実態としては苦し紛れの言い訳に過ぎないと言えるだろう。
第2節における会話は香子の「うっと……。鬱陶しい」というセリフから始まる。直後に「何やそのお前のため感」と続くことからわかるが、これらのセリフは先述した双葉の、進路が別れるのは自分だけでなく香子のためでもあるのだ、という主張を一蹴するものである。
戸惑い絶句する双葉に対して、香子は「新国立、なんでひとりで決めた」と自分に相談せず進路を決めた理由を問う。しかし双葉は目をそらし答えず、香子に凄まれて(*10)ようやく語った理由は、相談すれば反対を受けるからというものであった。これに対し香子は肯定も否定もせずため息をつく。
その後双葉はクラスメイトと比較して自分の実力不足を主張した。これは香子の元を離れて自己研鑽する必要性を再び主張する前振りらしき発言だったが、香子は仏像の掌上のピアノを苛立たし気に鳴らし(*11)てそれを遮る。
そして香子は「約束のレヴュー」で双葉の発した「一番近くでお前と一緒にキラめきが見たいんだ、香子」というセリフを引用し「大嘘つき」と双葉を詰った。
続くカットでは鉢を重ねてシャンパンタワーに見立てたと思わしき大道具が登場する。香子はその最上部で酒で満ちた湯船程の大きさの鉢に浴しながら「どうでもええわ、 他の女なんて」と、先ほどのクラスメイトを引き合いに出した双葉の発言を切り捨てた。
さらに香子は「うっといねん、大人の理屈なんて」と発言。後の「本音、晒せや」という言葉を考慮すると、この場合の「大人の理屈」は本音と対になる建前を指すと考えられる。双葉の発言をすべて建前として一蹴した香子は、双葉が自分と違う進路を選んだ理由について「自分が鬱陶しくなり別れたくなったからだ」と指摘。そして絶句する双葉へ「表出ろや」と凄み、第3節へ続く。
この時の香子の「双葉は本音では自分のことを鬱陶しく思っている」という主張は、続く第3節で絶交を切り出す前振りと考えられる。筆者はこの絶交について香子の本心からの望みではないと考えており、この主張も同じく本音とは異なるものであろう。その論拠については第3節の考察で述べるものとする。
次にセクシー本堂の各モチーフについて考察を述べていきたい。筆者はキャバクラと仏堂を組み合わせた画作りが、前述した怨みのレヴューの荒唐無稽さに寄与していると考えている。大胆に背中側が開いたドレスを纏いホステスに扮した香子と、客らしきサラリーマン風のスーツ姿の双葉といった衣装変えによる驚きもあったが、薄暗いムーディなセットの中に金色の光を放つ大仏が鎮座しているという画は、単純にライティングの面でも強烈なものであった。
まずキャバクラというモチーフが用いられた理由について、監督の古川知宏が以下のように述べている。
“京都の有名な某お寺の本堂が、キャバレーになっていたら面白いかなと。(石動双葉と花柳香子の)二人には昭和歌謡のような雰囲気を感じていて。実際に『仕事と私、どっちが大切なの』って、怒られたことがあるんですけど、二人のレヴューではその雰囲気を出したいって、ずっと言ってたんです”
「1回目より2 回目のほうが泣ける」』(2021 年6 月4 日) より引用(https://natalie.mu/comic/news/431021) 2022 年4 月20 日閲覧
“TVアニメでの双葉は、当初、もっとヤンキーっぽいキャラにしたいなと考えていたんです。結果的には今の形に落ち着きましたが、劇場版でどうしようかとなったときに、結局はこの二人って何をしてもどっちつかずになるというか、決着がつかないんですよね。香子がセリフとして言っていますが、この二人ってまさに「しょうもない」んです(笑)。もともとがそれくらいにグダグダな関係性なので、いっそのことそれを昭和歌謡的な男女の関係に見立てようかなと思いました。”
“これまでワガママを言えなかった男が初めてワガママを言うっていう痴話喧嘩を現代劇で語るには尺が足りないなと思ったんですよね。情報が圧縮されたウェットな会話って、完全に昭和の「演歌の様式美」の世界なので、だったらビジュアルも昭和で覆わないといけない。もともとイメージしていた「ヤンキー」と「昭和」は相性も抜群ですし、これはいいなと。”
監督・古川知宏インタビュー②』(2021 年6 月16 日) より引用(https://febri.jp/topics/starlight_director_interwiew_2/) 2022 年4 月20 日閲覧
筆者はこのコメント内で言及されている「昭和歌謡のような雰囲気」に、「清水の舞台から飛び降りる」という諺にちなんだ演出を合わせた結果、キャバクラと仏堂が融合したセクシー本堂が生まれたと考えている。
さて、ここからは本研究の根幹であるセクシー本堂内の仏教的モチーフの考察を述べる。まず初めに取り上げたいのは仏像の種類だ。
仏像のモデルとなる仏にはいくつものバリエーションがあるが、いくつかの象徴的な意匠から判別が可能である。本研究では印相、つまり仏像の手の形に着目した。
セクシー本堂に置かれている仏像の手は、両手の甲を下に向け親指はまっすぐ伸ばし、へその前で合わせている。左人差し指から小指は緩く丸められ、右手の人差し指から小指は垂直に伸ばされた形状(図1) である。なお香子がピアノを弾くシーンでは両手の位置が画面左側にずれていたが、印相は同様であったため単に左掌に乗った香子の身体が仏像の中央にくる構図に
するためであろう。

やや形状が異なるが、この形は「九品印」の一つ「上品上生」(*12)を表すもの(図2) に近い。この印相は阿弥陀如来(*13)を象徴するものであるから、セクシー本堂の仏像は阿弥陀如来をモデルにしたものであると考える。

阿弥陀如来の性質については多くを語ることができる。だが今回の考察において注目すべきは、阿弥陀仏が死を迎えた仏教信者を極楽へいざなうという性質を持つ点であろう。これは劇場版でたびたび扱われる「舞台少女の死」というフレーズとも合致するものである。
つまりあのシーンでは建前ばかり語り、進路についての相談を尻込みしていた双葉に対して「その体たらくでは役者として死人も同然」というメッセージが投げかけられていると解釈できる。
TVシリーズを通して描かれてきた香子の性格を考慮すると、双葉の「(相談しても)反対するだろ」という推測は恐らく正しい。実際、香子はそれを否定も肯定もしなかった。しかし反対を恐れて相談をしないようでは、劇中で世界最高峰と評された劇団への加入を目指すにふさわしい心構えだとは言えないだろう。その卑屈な態度を糾弾し、双葉自身の言葉を引用すれば「叩きなおしてやる」(*14)というのが香子の意図であろうと筆者は考えた。
第3節の中で香子が双葉に対して告げた「絶交」もそのためのアプローチであろうが、第2節には他にも双葉を奮い立たす意図を感じる表現がある。その一つが鉢で作られたシャンパンタワーの場面だ。
シャンパンタワーのイメージはカップ部分が浅く平たいグラスで組まれたものが一般に知られているが、セクシー本堂に登場したものは仏具である鉢で組まれたものであった。さらに最上段に積まれた大鉢には香子自身が入り、自身が注ぐシャンパンを風呂に見立て身を浴している。
筆者はこの場面の強烈な胡乱さに衝撃をうけたが、この大鉢シャンパンタワー風呂とでもいうべき光景は、仏教的観点から解釈を行えばたいへん明快な暗喩なのである。
仏教における鉢とは応量器または応器とも呼ばれ、単なる食器ではない。街を行脚し食物の寄進を乞う修行である托鉢に用いる仏具なのだ。その起源には物欲を断ち殺生を禁じるといった思想に基づいたものであるが、ここでの要点はこの修行において鉢が供物を入れる容器として用いられている点である。つまりこのシャンパンタワーにおいて、香子は自分自身を双葉への供物に見立てているのだ。
劇場版の劇中において舞台少女を奮い立たせる「糧」としてトマトが登場する。香子のこの振る舞いも同様の表現と言える。自身を飲み干して見せろと突き付ける挑発的な激励。より具体的に言い換えれば、もし自分と別れて新国立での武者修行に励むならば、たとえ反対を受けても説得ないし押し通る気概を見せろという叱咤なのである。
また、香子が仏像の掌の中でピアノを叩く場面は第4節での「わかってますんや、そんなの」というセリフ同様、双葉の本心を把握しているさまを表したシーンだと考えられる。
この場面での香子はTVシリーズ第6話のセリフを発していることから、双葉を演じていると言える。その状態の香子が仏像の掌の中にいるのは、双葉の本心を把握しているさまを指して「掌の中」という慣用句をそのまま表したものであろう。
仏像の掌との関連から『西遊記』における孫悟空が仏の掌の上から脱出できなかったエピソードとの関連も考えられる。しかし、このエピソードに登場する仏は釈迦牟尼であり、阿弥陀如来とは別の存在である(*15)。そのため単に「掌の中」という慣用句の暗喩と解釈するのが妥当であろう。
*10 香子は「なぁ」と促しても双葉から返答がなかったため「おい」と語気を強めていた。TVシリーズでもここまで荒い口調のセリフはなく、相当な怒りを覚えていると察せられる。
*11 一般にピアノは7オクターブのものが主流であるが、仏像の掌上にあったピアノは5オクターブの鍵盤を備えたものであった。音域を減らしたのは鍵盤をたたくシーンの構図を考慮したためであろうか。映像から判断すると叩いたのは最高音から1オクターブ下のレ・ミ・ファ・ソと、見切れているが最低音から1オクターブ上のソ・ラ・シのようである。
*12 「九品印」は『観経』で説かれた仏教信者の階位である「九品」に対応する九つの印相を指す。「上品上生」はその最上位にあたる。
*13 なお実際の清水寺本堂にあるのは秘仏十一面千手観音像である。敷地内には阿弥陀仏像も存在するが、置かれているのは別の仏堂である。
*14 「約束のレヴュー」での発言である。該当シーンでは香子が逃げに走りそれを双葉が糾弾していたことを踏まえると、「怨みのレヴュー」では二人の立場が逆転していると言えるだろう。
*15 参考文献3に記したウェブサイトに掲載された西遊記の原文から孫悟空へ「我是西方極樂世界釋迦牟尼尊者」と名乗る場面が確認できる。
第3節 清水の舞台
第3節はキャバクラ風の仏堂から清水の大舞台を思わせる開けた板張りの空間へと移り、デコトラを並べて言葉を交わしたのち香子のデコトラが崖下へ落ちるまでの場面である。『わがままハイウェイ』では以下のサビ付近が対応する。

このシーンでは導入部に登場したデコトラが3台に増え、電飾をいくつかのパターンに灯らせるなどしているのが印象的である。デコトラを登場させた理由については引用したインタビューにおいて古川監督が以下のように説明している。
“デコトラのディテールをしっかりと描写したアニメーション作品って、これまでに少ないじゃないですか。少なくとも僕は見たことがないので、やってみたいと思っていたんです。「昭和」や「ヤンキー」というアイコンとも親和性が高いですし、なによりデコトラなら歌詞をそのまま画面に入れられる。これは『レヴュースタァライト』向きだなと思いまして。つまり、「舞台セット」として機能しやすい素材だからです。”
“わかりやすく3Dマテリアルを使った情報量のある高密度なシーンをやっておきたかったというのもあります。最初に3DCG による高密度な画面を用意しておけば、そのあとがほぼ手描きだとしても、なにかすごい情報量のある映画を見た錯覚に陥るんじゃないかと思って(笑)。最初のレヴューシーンなので、ハッタリを利かせたいという打算もありましたね。結果として、わかりやすいレヴューになったのかなと思います。”
監督・古川知宏インタビュー②』(2021 年6 月16 日) より引用(https://febri.jp/topics/starlight_director_interwiew_2/) 2022 年4 月20 日閲覧
ここで語られているデコトラの「情報量」だが、それを生かしたと思わしきシーンの一つに香子が「これにて縁切りや」と発したシーンがある。
この時画面に映る香子のトラックには「ただいま熱演中」と書かれたランプが灯っていた。
第2節についての考察で「双葉は本音では自分のことを鬱陶しく思っている」という主張が香子の本心によるものではないという意見を述べたが、筆者は「熱演中」のランプはここで歌った歌詞の「飽きた」「絶交」「私の知らないあなたになった」という言葉にかかるものであり、同じく香子の本心ではないと考えた。
言葉だけを見れば双葉が本音を語る気がないのであれば縁を切り、新国立へ進めるよう関係を解消する覚悟の挑発という解釈も可能である。しかし仮に本音を言えないまま絶交で別れたならば、そのことが双葉の道行きを妨げる禍根になるであろうことは想像に難くない。我を通せないようでは聖翔音楽学園以上に厳しい新国立での競争を生き抜くのは厳しいと言えるだろう。香子がその状況を看過するとは考えにくい。
また「約束のレヴュー」で「双葉が自分を止める」という状況を作り出すため己の上掛けを留めるボタンに手をかけた香子の性格を考えると、どんな手を使ってでも双葉に本音を語らせるという決意で発したハッタリだと考えるのが妥当であろう。
それに対し双葉は「やだ」「ずるい」「もう一緒にはいけない」とようやく本音を叫ぶ。そして二人は各々のデコトラの上で武器を構え、騎兵の一騎打ちのような形で舞台中央へ突貫。しかし激突の寸前で香子は「うちら、ほんまにしょうもないな」とつぶやくと、本堂と反対方向の崖下へ己のデコトラを突っ込ませる。
香子のデコトラは崖下に落下するまで破損した様子はなく、またぶつかった効果音も入っていなかったため、この落下は双葉のデコトラに敗れた結果ではなく香子の意思によるものだ。
これは新国立という荒波に自ら揉まれようとする双葉に最後の一押しをすべく、文字通り「清水の舞台から飛び降りる」さまを実演して見せたのだろう、というのが筆者の考えだ。
第4節 終結部
第4 節は舞台の残骸に辛うじて掴まり宙吊りになる双葉と香子の会話から、香子の上掛けの紐が切れるまでの部分である。
双葉はここで香子に対し「今度は私がわがまま言う番」と告げる。そして香子に先に言われてしまうものの「私が待たせる番」と宣言。
これは「約束のレヴュー」で双葉が口にした「約束しただろ。お前が世界で一番キラめくところを一番初めに見せてくれるって。だからずっとお前を追いかけてきたんだ」というセリフなどから示されていた二人の関係性を改めるものだ。
双葉が新たに提示したのは香子を目標とするのではなく、香子を待たずにトップスタァとなって、やがて世界一の踊り手になった香子を迎えに行くというものだった。
二人で最高の舞台に立つという最終目標を変えず、実現のために道を分かつ。『花咲か唄』に一部引用されていた崇徳院の和歌(*16)を思わせるものだが、ここに加えて「自分が先にトップスタァになる」という野心、言い換えれば情熱が加わったものである。
バイクとその鍵を香子に預けた(*17)のも、香子の送迎のために免許を取り調達したバイク(*18)に他の誰も乗せる気はないと示し、約束を果たす日まで操を立てる意思の表れと解釈できるだろう。
対する香子は「わかってますんや、そんなこと」と返す。このセリフが負け惜しみなどではなく言葉通りのものであることは、本稿で繰り返し述べたとおりである。またこの節では香子のデコトラのコンテナに桜の花びらが満載されていることがわかる。第1節から登場していたデコトラに二人の思い出の象徴めいた桜が詰め込まれていたのは、やはりはじめから縁を切るつもりがなかったことの暗喩であろう。
劇中の雰囲気から、香子が双葉の真意を理解していたことは本人にも伝わっていたようだが、以下に引用した第4節に対応する劇中歌の歌詞からもそれは確かなようである。

そして最後に、香子の上掛けを留める紐がバックミラーの破片で切られてレヴューは幕を閉じる。一見すると背後を見るための道具であるバックミラーが砕けているのは過去との決別の暗喩と解釈できるだろう。しかしその解釈はこれまでに提示した「香子の言う絶交はハッタリである」等の考察と合致しない。
そこで筆者はバックミラーが過去、つまり幼馴染としての関係の暗喩だとしても、決別すべきものとしては示されていないのではないかと仮説を立てた。それを裏付けるのが、一つは千切れたバックミラーの亀裂を隠すように、桜の花びらが舞い落ちる描写である。その後の「狩りのレヴュー」にあった星見純那と大場ななの写真の裂け目が埋まるような描写と同様に、崩壊しかけた関係が修復されたことの暗喩だと考えられる。
もう一つはこの場面に描かれる幼少期の香子と双葉が両手と額を合わせているイメージに、二人の「ほんましょうもないで、うちらは」「ほんとしょうもないな、あたしたち」というセリフが重なる描写である。このセリフは互いに呆れながらも肯定的なニュアンスであり、幼少期のイメージも目を閉じて微笑んだ表情である。これを決別すべき過去の描写だと判断するのは不適当であろう。
つまり「怨みのレヴュー」での激突は「約束のレヴュー」のように、双葉と香子が何度も繰り返しその度に和解してきた衝突の一つだったのではないだろうか。二人はお互いに成長した部分があって、進路が別れてしまっても、やはり心根は変わらなかった。そのことへの安堵と呆れから、「私たちはしょうもない」と笑ったのだ。そして双葉は、砕けても変わらない約束の暗喩たるバックミラーの破片で今回の決着をつけたのだ。
*16 「瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ」
*17 この時鍵のついたキーホルダーは香子の左手の薬指にかかっており、婚約指輪を彷彿とさせる演出がされていた。
*18 「約束のレヴュー」において双葉が「歩きがしんどいって言うからバイクの免許も取った」と発言している。
結論
以上の考察を以て、本研究は「怨みのレヴュー」は香子による「双葉をトップスタァを目指す者として確立させるため、わがままを言えるようにするため香子が設けた儀式である」という結論に至った。このレヴューは香子による激励であり、双葉が突破すべき通過儀礼であり、同時に二人が繰り返す衝突の一つに過ぎないのである。
「セクシー本堂とはなんだったのか」という疑問から始まった本研究は、その答えを探るうちに当初の予想よりも広く「怨みのレヴュー」全体を包括するものへと発展したが、数々の超現実的な描写についてある程度の意図を解明できたであろう。
本研究が『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』という奥深いコンテンツを楽しむ上での一助となれば幸いである。
参考文献
1.コミックナタリー編集部(2021/6/4) 『劇場版「スタァライト」初日舞台挨拶で三森すずこ「1回目より2回目のほうが泣ける」』コミックナタリー (https://natalie.mu/comic/news/431021) 閲覧日:2022/4/20
2.岡本大介(2021/6/16) 『『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』監督・古川知宏インタビュー②』Febri (https://febri.jp/topics/starlight_director_interwiew_2/) 閲覧日:2022/4/20
3.吳承恩『西遊記 第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿』開放文學(http://open-lit.com/html/lit/14/305.html) 閲覧日:2022/4/20
4.ヤマハ『ピアノのマメ知識 ピアノの鍵盤数が88 鍵から増えないわけは?』楽器解体全書(https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/piano/trivia/trivia007.html) 閲覧日:2022/4/20
5.音羽山 清水寺『秘仏十一面千手観音立像』清水寺を読む音
羽山と観音信仰、人々の物語(https://www.kiyomizudera.or.jp/read/%E7%A7%98%E4%BB%8F-%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%8D%83%E6%89%8B%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E7%AB%8B%E5%83%8F) 閲覧日:2022/4/20
6.法然上人二十五霊場事務局『第13番清水寺阿弥陀堂』法然上人二十五霊場 霊場のご案内(https://www.25reijo.jp/reijo/13.php) 閲覧日:2022/4/20
7.【WEB 版新纂浄土宗大辞典】(http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8)
以下の項目の閲覧日はすべて2022/4/20 である。
7.1) 工藤美和子(2018) 『托鉢』
7.2) 藤田直信(2018) 『九品印』
7.3) 岸一英(2018) 『九品』
7.4) 西村実則(2018) 『三衣一鉢』
8.【コトバンク】(https://kotobank.jp)
以下の項目の閲覧日はすべて2022/4/20である。
8.1) 小学館『掌の中』精選版 日本国語大辞典
8.2) 小学館『丁半』日本大百科全書( ニッポニカ)
8.3) 小学館『清水の舞台から飛ぶ』精選版 日本国語大辞典
8.4) 講談社『応量器』食器・調理器具がわかる辞典
著者コメント(2022/10/10)
セクシー本堂の考察をお送りしました、John でございます。めまいがするほど強烈な映画、劇場版少女☆歌劇スタァライトの一番くらくらした部分ことセクシー本堂。強烈という言葉でも足りないほどのインパクトに満ちたこ
のシーンを見つめ続けた結果、ゼンめいた真理に至り全ての演出を理解した...... と思いきや、同時に見えてきたのはこのやりとりもまた石動双葉と花柳香子の幾度となく繰り返す衝突の一つだったという真実でした。達成感と充足感。それと共にしょうもない痴話喧嘩に付き合わされていたことに気づいたような不思議な気分です。これが行きて帰る物語ってやつですか……
また、最後になりますが本研究の基礎理論の構築にあたり協力いただいたナグーチカ氏(TwitterID:Qed495Scarlet)・かにたま氏(TwitterID:ChowhanRock1869)、そして著しく締め切りを超過した原稿を寛大に受け取ってくださった企画主催のさぼてんぐ氏、および編集班の皆様へ、この場を借りて深謝の意を表します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
