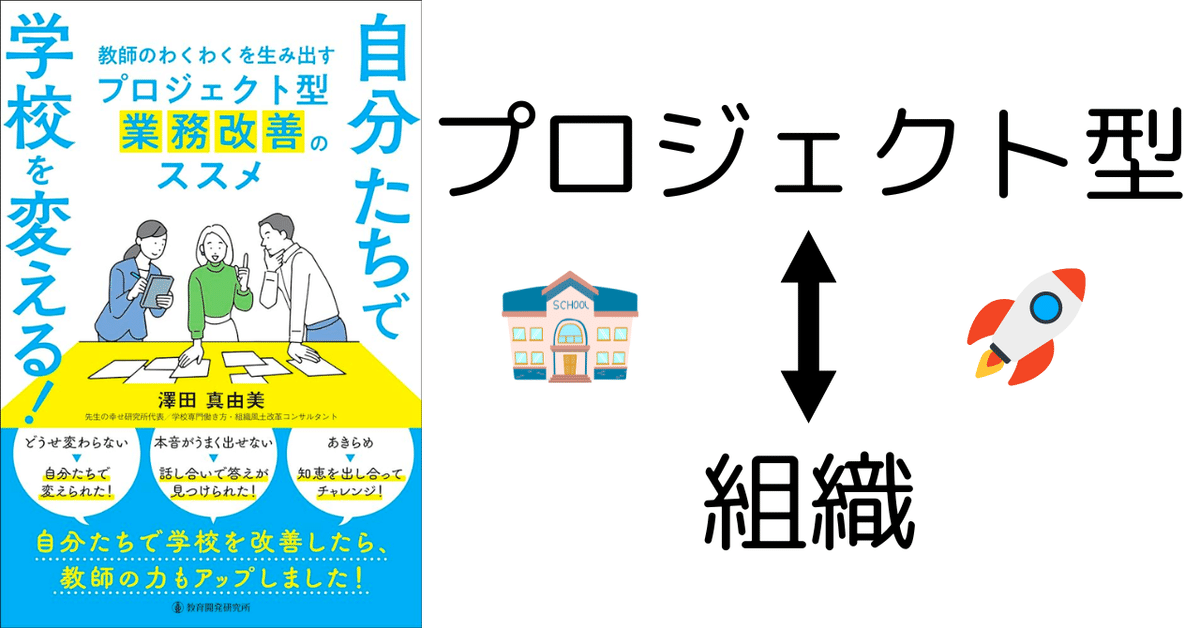
【🚀紹介】プロジェクト型業務改善のススメ
こんにちは!タノ🦒です。
今大阪にいます。
中等学校のカフェテリアで書いてます。
#学校にカフェテリア !
#おしゃれな響き
1月20日(土)にイベントでグラレコ・グラログをさせていただきました。
ゲストは先生の幸せ研究所の澤田真由美さん。
いつもお世話になっております!
記録を載せるとともに、
一度真由美さんの著書を時分なりにアウトプットさせていただきたいと思いました。
それがこちらの本。
今自治体で業務改善のための意見交換会で、ファシリテーターなどをさせていただいています。
「自分たちで学校を変える」ために、もう一度学び直してみたいと思います。
記事にまとめるにあたり、
少し言葉を変えて綴る部分があると思いますので、
ぜひ実際の著書を手に取ってください。
この紹介で、さらに多くの方に、
「プロジェクト型の業務改善」が届きますように!
はじめに
1章.プロジェクト型業務改善の目指すところ
(1)3つの「助」
学校改革は3つの観点があります。
それが「自助・共助・公助」です。
個人裁量の「自助」。
チームや組織で家以前する「共助」
国や自治体レベルでしかできない「公助。」
今回のプロジェクト型は「共助」。
学校の中でできる「共助」には
たくさんの可能性があります。
(2)学校の自由と可能性
「自分たちでつくるなんてできるの?」
「社会を変えることなんてできるの?」
そんな声が多い学校や日本。
ある種の閉塞感がそこには漂います。
ですが「変える可能性が自分たちにある」。
そう実感できるのが「業務改善」。
(3)時間の投資と見えにくいところ
とはいえ、考える時間がない。
積もり積もった悪循環から好循環に変えるためには、
時間の投資が必要。
一度授業を止めてでも考える時間をつくる。
余剰時数は0にしていい。
不安はあるかもしれません。
でもゼロにして時間を作ることで、始まるものがあるはずです。
(4)行動と変化
その時、行動や変化を起こすためには、
「見えにくい部分」こそが重要です。
小手先の直線的な改善は歪みを生みます。
そうではなく、本音で納得解を生み出す。
多様すぎる価値観の中で、じっくりと時間をかける。
そのためには何より「やってみる」こと。
実際に魚をとった経験に勝るものはない。
「机上の空論」ではなく、行動して変化を生み出していく。
(5)業務改善と教室の資質向上
この業務改善は、何よりも「人材育成」になります。
経済産業省が提唱する新しい専門性、
・チェンジメーカー
・アクティブラーナー
・ファリシテーター
のような資質が向上していきます。
組織が、教員が変化していく。
働き方改革と資質向上が一石二鳥で叶う。
そんな自由と可能性を秘めています。
2章.桜丘小学校の実践-
(1)プロジェクト
まずプロジェクトが始まる前は、
「具体的にどうしたらいいか分からない」
「不安」「人を増やすしかない」という意見もありました。
多くの学校で見られる姿です。
その中でキックオフをし、本音やアイデアを出し合い、
今後の具体的な素材とします。
手上げ方式で推進メンバーを募ると、
「人を増やすしかない」と言っていた方々も動き出しました。
ワークショップの中で、本音を共有し、すぐできるアイデアを共有すると、希望を見出し改革は進んでいきます。
そしてプロジェクトを立ち上げ改革に進みます。
(2)動きと変化
と、言っても、
多忙の中でのプロジェクトです。
停滞してしまうこともあります。
半歩・一歩を進めるために、
忙しくてもできそうなことを考え、
アイデアを出し、タスクを決めていく。
目標・やりたいこと・必要なこと・メリット・デメリット、
優先順位、1歩目、アクション。
プロジェクトで必要なことを考え【行動】する。
一方で、ゆるく、ゆとりを生むプロジェクトもあります。
手を止めて、みんなで考え、仕掛けをつくる時間が大切です。
こうしたプロジェクトの中で二項対立が起こることもあります。
ですが、対立でも一択でもない、納得解をつくる。
それには対話が必要です。
何を目指しているのか、共通していることは何か。
そしていくと、新しいアイデアが生まれ、その中で先生が成長していきます。
そして、学校が生まれ変わっていきます。
3章.セントヨゼフ学園の実践-
4章.枚方市教育委員会の実践-
この著書では、さらにもう一校の実践
そして教育委員会の実践を紹介しています。
こちらも要約を書くと、文章が長過ぎてしまうことと、
本書の内容を書き過ぎてしまうため、割愛いたします。
ただ、どちらも大切なのは、
「まず話し合う」
「目的を言語化する」
「アイデアを出し、実行する」
という主軸があります。
そのために、さらに具体に、具体に落としていく。
1つの方法で劇的にはいきません。
でも、話し合いアイデアを出した1つ1つが、
彩を持った「私たちの業務改善」になっています。
そんな色を持った、アイデアがたくさん描かれています。
1つ1つの取り組みの裏側に、それを創った人たちの思いや考えがあり、心を打たれます。
5.章プロジェクト型業務改善のススメ
この章では、さらにプロジェクト型業務改善を、
図式にし、構造的に説明しています。
どんなアプローチで進むのか。
どんなサイクルで進むのか。
当事者をどのように増やせばいいのか。
そして、どのように伴走をするべきか。
研究所のスタンスは。
1:現場を知っているのは現場!一緒に考える
2:楽しい対話の場をつくる
3:対等なパートナーとして一緒に組織変革を
4:豊富な事例で新しい視点をもたらす
5:わくわくする気持ちを原動力に、対話と体験で心から感じる変化を重視
「行きたい向こう岸に渡れるように支援する人」であるように。
タノのまとめ
改めて本書を読んで、考えました。
これまでコンサルタントや現場で実践してきたことは、
間違っていなかったし、さらに先があると感じました。
軸は同じ。
目的を言語化し、ありたい姿へ進む。
進むためのメンバーが対話し、
推進力を得て進めるように伴走していく。
全てのことは「できる」。
人がつくったものは人が変えられる。
「〇〇がやってくれないと・・・」
という言葉は、ともすると口から漏れてくる。
でも、実は裁量はある、変えることはできる。
その変化の向こう岸に行くには勇気がいる。
橋がかかっていても「大丈夫?」ときっと思う。
けれど、向こう岸に渡れたら、新しい景色を見れたら。
それは、自由と可能性を得て、
学校や社会が変わることになる。
私の武器は見える化。
日本中で起こりつつあるこの流れをもっと加速させたい。
できること全部やって、向こう岸に一緒に渡りたい。
「向こう岸の地図や形式があれば、もっと渡りやすいんじゃない?」
すでにある好事例に対し、私ができることを考えたい。
まだまだ止まらず、行けるところまで進んでいきます。
今日は、たくさんの方々に出会えました。
この機会をくださった大泉さん、そして関わった方々に感謝いたします。
若輩ですが、全国に仲間ができることを心強く感じます。
がんばります(*^▽^*)
タノ🦒でした!またね!
↓いろんな活動はこちらからご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
