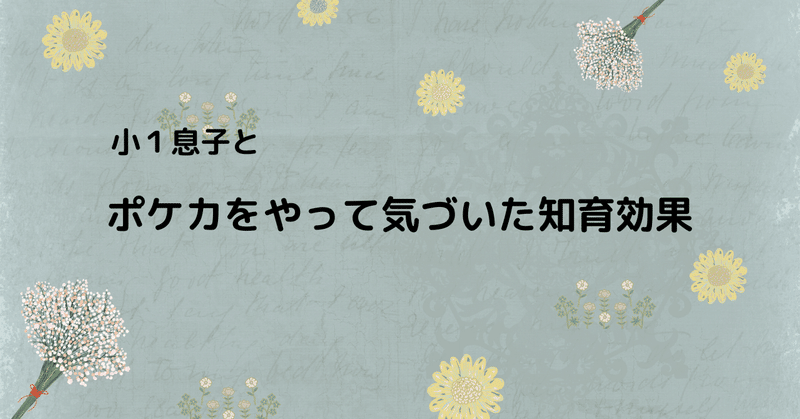
小1息子とポケカをやって気づいた知育効果
ポケカとの出会い
ポケモンカードゲーム、縮めてポケカ。
良くも悪くも巷を賑わす魅惑のおもちゃに出会ったのは、2023年のゴールデンウィークでした。
子どもが祖父に買ってもらったスターターキットで行儀良くルールを覚えて遊び始めたのが遠い昔のように感じます。
そして当時は転売騒ぎのど真ん中だったにも関わらず、過疎地の玩具屋で出会ってしまった拡張パック。毎月コンスタントに出る新作。家の近くにあるカードショップたち。
気づけばカードの枚数は信じられないスピードで増え(たぶん1000枚は超えた)、デッキは盤石なものへと進化していっております。そのスピードが本当に怖い。
何がそんなにおもしろいのか。そう思っていた時期が私にもありました。
しかし、子どもの遊びと侮るなかれ。これがまあ、ものすごく楽しい。
ルールは単純明快なのに、戦法は幅広く、深いのですわ。
家族で夜な夜な対戦する日々が始まり、旦那の帰りが早くなった。そして、子ども(小一)も凄まじい進化を遂げることとなる。
ポケカで知育を狙う
高尚な知育に手を出すつもりはないけど、効果があるならぜひとも狙いたい。
そんな思いで子どもとポケカをする中で気づいた知育効果はいくつかありました。
まずは国語。
カード名、すなわちポケモンの名前はイラストを見れば一目瞭然ですが、わざの効果はテキストを読まなければわからないのです。
当時、入学したてでひらがなを読むのも億劫だったはずの子どもが、たどたどしくカードテキストを読み上げながらドヤって攻撃を仕掛けてくる。
さすがポケモン、ちゃんとルビがふってあって素晴らしい。教える手間なしです、ありがとう。
気づけばカタカナもすっかり読めるようになり、ポケモンの難解な名前を書かせることによって書くこともマスターしつつある。
ピカチュウ、ギャラドス、こくばバドレックス…濁音半濁音と鬼門「ッ」に伸ばし棒(ー)の入り混じったポケモンの名前をすらすら書ければもうカタカナマスターと言っても過言ではない。ちなみに息子のカタカナはまだ怪しい。あと「ッ」の入る場所。しょっちゅう間違えてます。
わざの効果の説明文の読み取りもかなり難解だと感じる。カードの種類はものすごくたくさんあるので、最初のうちはとにかく読んでいくしかない。次第によく使うカードに関しては覚えていくが、新弾が出ればまた読まなければならない。これが短文を読み解くちょうどいい訓練となった気がします。
AのときにBが使える、のような条件付きの文章って小さいうちはなかなか出会わないので助かる。でもたまに難解すぎて親も迷うんだなこれが。
次に算数。
ポケモンカードではわざをうつのに指定の枚数分のエネルギーが必要なので、基礎中の基礎、数を数えることが自然と身についていく。
また、ポケモンがダメージを受けるとダメカン(ダメージカウンター)をカードにのせる必要がある。これが10と50と100の3種類なので、繰り上がり繰り下がり(回復もできる)であれこれと計算する必要も出てくるのです。
息子は10~300までの10ごとの繰り上がり繰り下がりや掛け算の概念(サイドの枚数×〇ダメージ、のような攻撃があるため)まで感じとることが出来ているようで、いつの間にか楽々とこなすようになっています。
何より楽しいのが嬉しい
教科に当てはめて考えた知育効果は以上の通りですが、その他にも
・対戦する楽しさ
・買ったり負けたりしながら戦略を練る力
・負けたときのアンガーマネジメント
・家族であーだこーだ言いながらデッキを組む時間
など、プライスレスなことが盛りだくさんです。
父(夫)と母(私)はちょうどポケモン初代をリアルタイムでやっていた年代なので、新しいポケモンの名前を憶えてボケ防止…といった嬉しい効果もついてくるので、興味を持った方はぜひ子どもと一緒にポケカを楽しんでみてはいかがでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
