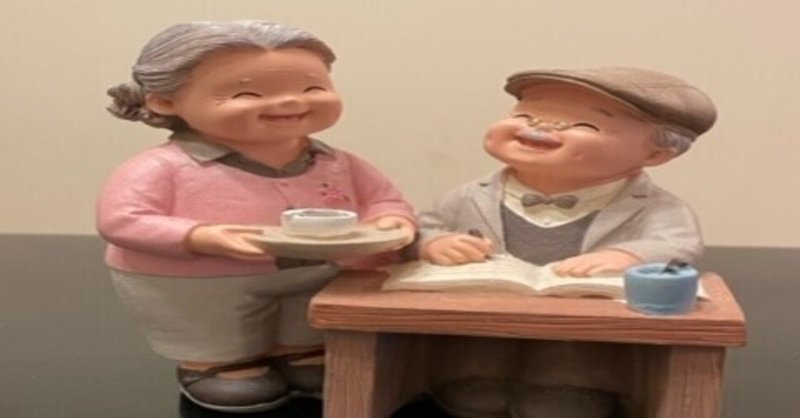
559国会議員の文通費 本務を顧みて議員・議会に自浄意識はあるか
国会議員に月100万円も条件に支給される「文書交通費」。昨年の総選挙で当選した議員の任期開始が10月31日。わずか1日の在職に対して、10月分の文書交通費100万円が全額支給された。「もらい過ぎではないか」と新人議員の一人がブログでつぶやいたことから、「そんなことが議員のお手盛りで行われていたのか」と国民の知るところとなった。
それから5か月何を議員や政党間で話していたのか。「与野党6党は24日、国会議員に支払われる文書通信滞在費(文通費)の見直しに向けた協議を国会内で行い、日割り支給を導入することで大筋合意した」(読売新聞2020年3月25日)。
この問題については関係者3人の声をまとめた報道がある。少々古いが産経新聞の「論点整理」(2021年12月5日)。その要旨は次の通り。
小野泰輔さん。問題提起した新人衆院議員。ブログに「おかしい」と書いたら、これが拡散して国民世論に火が点いた。ところが議員のインナーサークルからは「政治の世界の慣例を壊すな」と猛烈な圧力をうけたらしい。市民とかけ離れた議員の特権意識の改革が必要という。
松井孝治さん。官僚出身、国会議員の経歴を持つ大学教授。与党は政策決定の過程を示さず、野党は政策とは無関係事項での政府追及に終始。国家的課題解に国会議員が取り組んでいる姿勢を国民は感じられていない、国民はもはや国会を見放していると指摘する。
向大野新治さん。国会事務官僚のトップ衆院事務総長を務めた経歴を持つ。安易な評論は議員活動を制約すると国民に冷静さを求める。国会の位置づけは国ごとに違うのだから、事象ごとの各国比較ではなく、総体として機能しているかの観点での判断と評価が必要と説く。

共通するのはこれを機に国会が本来の機能を果たすよう自浄能力を発揮してほしいという期待だった。
国会議員はなぜ存在するのか。それは日本が民主主義国だからである。憲法前文はこう書く。「日本国民は、われらとわれらの子孫のために、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する」。なぜならば「主権は国民に存する。その権力を国民の代表者(=国会議員)が行使し、その福利は国民が享受する。これは人類普遍の原理である」からだ。
この基本に常に立ち返る必要がある。そうすると文通費問題など些末な問題である。月100万円、年額1200万円に議員総数750人ほどを乗じると90億円。有権者一人当たりではスーパーの安売りペットボトル1本分だ。これで国家の安全と繁栄のために国民を糾合する政策を進めてもらえるならばありがたい。
逆に国家のことには無頓着で、自身の個人利益に没頭して本来の任務をないがしろにする者が国会議員の役職に就くようでは国民と子孫の先行きは危うい。
国会議員は国民の代表である。その意味するところは、道義や道徳の面で恥ずかしくない人であることが最低条件。個人の経済生活の面では国民の平均像であることが望ましい。
この観点で議員への手当を考えるならば、政治活動にかかる費用は惜しげなく支給すべきだろう。企業幹部の交際費においても、使った後で領収書を経理に出すと、組織のかじ取りにあたる行為者ほど裁量の余地が広く、ほぼ無条件に払い戻しがあるはずだ。国会議員もそれにあたると考えていいはずだ。後々の検証のために領収書等は保存するが、請求額をほぼノーチェックで支給する。ただし「ロシアのオルガリヒと交際するために豪華ヨットを買いました」などの非常識にならないよう、任期を通じての金額上限を設けることにする。それを1億円とすると、任期6年の参議院議員は年間ならして1600万円強。任期4年の衆議院議員では2500万円になる。衆議院解散があっても、払い済み金額の返還を求めない。
問題は歳費の方だ。月額129万4000円に賞与がつく。政府財政を大赤字にしておきながらボーナスをもらうのはかしいと思うが、それは別にしても、この歳費は高すぎる。国民の代表者なのであるから国民の稼ぎの平均像をもって歳費の額とすべきである。
議員としての活動費はいわゆる文通費でほぼ無条件に使用できる。そうすると他に必要なのは衣食住と遊興費となるが、国民一般の例では月に50万円も60万円もかかるはずがないではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
