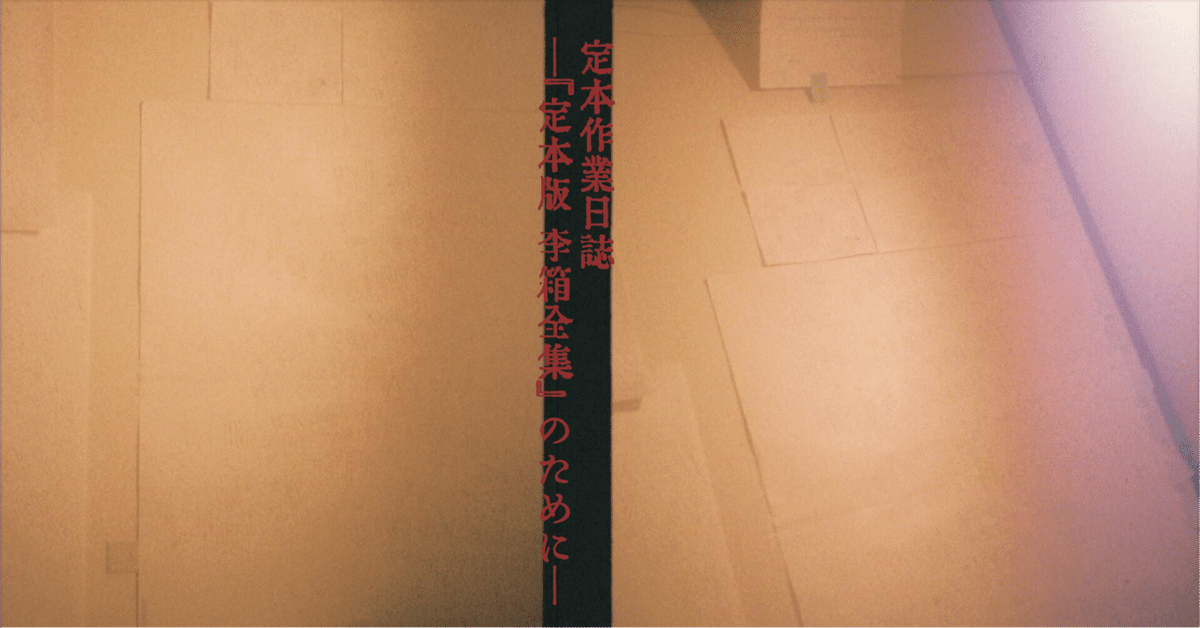
定本作業日誌 —『定本版 李箱全集』のために—〈第三回〉
翻訳作業を頑張っていたら、一ヶ月も更新が空いてしまった。何事もなかったかのように更新する。
2023年現在、日本語で読める李箱の全集は『李箱作品集成』(崔真碩編、作品社、2006年)しかない。しかも絶版。作品社はいったい何してるんだよ何でだよと沸々怒りが湧かないでもない。絶版でない作品集の中に李箱のテキストが1作、2作ほど含まれている場合はあるものの、小説や随筆、詩をまとめて、ある程度のテキストを一遍に見られるのはこの書籍だけだ。一方、李箱の出身国である韓国国内では、李箱全集なんてもう、山ほどある。ここ数年の間に出版された書籍もあれば、1900年代に出版されていた書籍もあり、韓国国内での李箱の知名度と需要度、テキスト編集の供給スピードは日本と比べものにならない熱をもってすすんできた。それだけ、韓国国内における李箱は、韓国にルーツをもつものにとって避けて通れない何かがあるのだろう。
まず日本語で読める貴重な書籍『李箱作品集成』(崔真碩編、作品社、2006年)について、少しでも評価を述べる必要がある。
本作は以下の構成からなる。
・李箱本人や彼にまつわる写真群 6枚
・原文朝鮮語テキストの訳文 小説 11作
・原文朝鮮語テキストの訳文 小説 19作
・原文日本語テキスト 42作
・李箱年譜
・李箱作品年譜
・訳者・崔真碩によるテキスト(別冊付録に論考テキスト)
・訳者あとがき
内容としては潤っている。研究で必要だった大学生当時みつけた頃には大興奮したし、「ありがとうございますありがとうございます」と遠くどこかにいるであろう編者に度々感謝を呟いていた。当時韓国語のハングルから勉強して、「私はロッテ百貨店に行きたいです」レベルの文法習得段階だった私にとって、この訳書ほど有難いものなどこの世になかった。


一日みていられる。格好良い。
韓国語がわからないながらに、李箱のテキストの数量を調べてみると、まあざっと100はあるなと感じた。もしかすると、崔真碩の書籍は非常に有難いものでありながら、まだまだ潤沢な全集とは言い難いのかもしれないと思いはじめた。
時が流れて、韓国語も辿々しいながらに読めるようになり、とんでもない定本全集に出会った。それが『정본 이상문학 전집 (定本李箱文学全集)』(김주현 주해,소명출판,2009)(以下、定本李文学全集)だった。図書館で取り寄せて確認した書籍だった。装丁が何だかイマイチだなと思いつつ、ページをめくってみるとぽろっと溢れた。「これ、やばいな」。目次の時点で「やばい」と。
まず3巻にわたって発刊されているのだが、各巻の収録テキストには、李箱のテキストすべてをほとんど網羅していた。そんなこと、目次をみれば一発でわかった。テキストをみても凄い。
各テキストが他全集ではどう位置づけられているか、この語は他全集でどう修正されているか、難解な古語の意味、漢文の意味、ある語の意味、著者名が李箱でない場合は以下に著者を李箱として同定されてきたか、未発表や遺稿の場合は発掘までの過程を記し、読者が李箱のテキスト定本作業の苦労や複雑さを超えて、”ある程度の”納得に辿り着けるよう情報が惜しみなく記述されている。その量と質の高さといったら、もう途方もないものだ。
また、序文ではあらかじめ「わからなかったところは注釈をつけられなかった」と告白もした。過去の全集の功績を振り返りながら、批判的視座でも見つめなおし、李箱文学の研究全体を見渡すようなテキストも前置きした。 それは読者に伝わる平易な文章で書かれており、平易なところにも根気が感じられて私は恐れ慄いた。
この註解者の方がどんなふうに調査し、資料を集め、定本作業を行い、何に頭を抱え、決め難いこともどうやって決めてきたか、ドキュメンタリー映像でもないかと探しかけるほどだった(いやあるわけがない)。それほど、途方もない作業を一時的に終えられたのだろうと想像する。発行されたのは2009年だが、この書物の複写物や写真に触れるだけでも、(お疲れ様です、本当にお疲れ様です、ありがとうございます)という気持ちが溢れる。いつかお会いしたいものだ(日本語では註解者と仲介者が同じ発音なのも味わい深い)。
ただ、『定本李箱文学全集』にも批判点がある。
まず私が一番問題だと捉えたのは、テキストの形が注釈の量によって崩れていることだ。
例を挙げてみよう。詩のテキストには、かたちがある。二字下げで改行する…三角は下向き▽…空白は全て全角だがこの箇所は半角…誰かの台詞は全て二字下げ…など作家それぞれではなく、テキストごとにそれぞれのかたちがある。当然それは李箱にもある。
そもそも注釈が入る時点で、テキストに何らかの崩壊を与えているのだが、文法のルールに従い連続して書かれている小説におけるその崩壊の度合いはまだしも、詩のテキストとなれば、文法のルールや連続性はそのテキストによるし、かたちの特性もより強い。つまり、詩のテキストは何が書かれているかだけではない。どう書かれているか、も詩の重要要素なのだ。それを注釈の都合で崩してしまうのは、改善に値すると思う。
またそれに関連して、テキストの分類に関わらず縦書きのテキストが横書きにすべて修正されているのある種問題だ。印刷の都合なのだろうか。しかし縦書きと横書きでは視線の流し方も違えば、改行位置も違う、第一印象も違う。書かれている文字は同じでも、感触がかけ離れていくのだ。ここにも改善の余地はありそうだ。
ここまで書いて、批判の可能性として「かたちにこだわって再現したところで、それは表面的な再現でしかない」という声もどこかから聞こえるような気がする。
その声に私はこう返答する。
「そうだよ、表面的な再現だよ」
「でも考えてみてください。表面的な再現がさもいけないことかのように語っておられますが、表面的な再現がどうして馬鹿にされるんでしょう?それが私にはわかりません。小説も詩も何が書かれているかがそのテキストをテキストたらしめているのではないと思います。小説においては文体で、何をどう書いたか。そして詩のテキストはどう書かれているか、が問題だと思います。」
「はあ、でも結局私たちは書かれていることを読むじゃないですか、すると書かれている内容や意味も重要なのではないですか?」
「私は何も、書かれている内容がどうでもいいとは一言も言ってないです」
「む」
「書かれている内容は、どう書かれているかに支えられていてこそ在る。簡単に言えば、内容はかたちにささえられているんだ、内容が読まれ、それとしてあるには、誰しも必ず、かたちも同時にみているんですよ。だから、かたちを無視しようなんてできない。って話をしているんです。もし無視しようとするなら、内容どころか、もう何もみえないと思います」
「でもとりあえずこの『定本 李箱文学全集』?ってのはさ、テキストの再現はもう凄いわけでしょ、じゃあ、もうそれはそれでいいんじゃないの?多くの読者はそう思っているでしょう。だってみんな李箱のテキストが読みたくて豊富にテキストが収録されている書籍を求めるわけだし」
「はい、おっしゃる通り『定本 李箱文学全集』は凄いです。李箱のテキストを読みたい人にとっては十分すぎる内容です。しかしみんなって誰なんですか、どこにいるんですか、そのみんなは。そして今私は、読者にとって良いか悪いかの話はしていません、テキストの話をしているんです。ですよね。読者が最優先にされる編集作業なら、テキストは疎かにされていいわけじゃないですよね」
「そこまでは言ってません」
「確かに。でもね、注釈によってかたちが変わってしまったテキストがあるでしょう。すると、それがずっと後世にまで伝わる可能性がありますよね。読者や編者の都合を優先し、テキスト固有のかたちを軽んじるということは、絵画作品でいうところの、修復作業段階で油画が水彩に変わってしまうくらいの重みがあると、私は思います」
「言い過ぎでしょ」
「今はね。そして今までならね」
こういう会話が頭の中で繰り広げられてしまう。『蜘蛛の巣上の無明 インターネット時代の身心知の刷新にむけて』(稲賀繁美 編、花鳥社、2023年)という書籍があり、その中の「異種のタイポグラフィー──宮沢賢治「蠕蟲舞手」(平倉圭)を一ヶ月くらい前に読んだ。ずっと読まねばと思っていたのだが、ある一節を読んだとき、涙が出るほど勇気をもらったのである。その話はまたのちにできたらするとして、以上の会話は、平倉圭著の『かたちは思考する—芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019年)とこの論考を的確に引用すると、さらに深化できると思う。いつかまた平倉さんには力を借りるのだろう。
話を戻そう。次の批判点からは好みの範疇にも踏み入ってるので書き流していく。
『定本李箱文学全集』は第一巻は詩、第二巻は小説、第三巻は随筆とその他に分かれて掲載されている。そして各巻の中でのテキストは発表年代順に並べられている。読者にとってはこの上なく見やすい構成で、申し分ないと思う。
だが、一方で私は読者よりもテキストの再現に重きを置く考え方をしてしまう。なので、詩、小説、随筆などと分ける必要性も、分けることによって年代順が一・二・三巻で前後してしまうことも気がかりだ。さらに言えば、初期テキストである原文日本語のテキスト群が、発表年代順を無視して巻末に並んでいるのもどうにかしたくなる。印刷の事情や何かがあるのかと思いつつ、テキストそれぞれの再現にここまで心血注いだならテキストの年代順なども読者など無視して再現すればよかったのではないか、再現に身を捧げていたのならたった一人でも再現をやり切ってはいけなかったのかと思ってしまう。ただ何度もいっておくが、これはこれで圧倒的に読みやすいのだ。私一人だけが多分こんな批判を挙げている。
だからといって、『定本李箱文学全集』や『李箱作品集成』の功績は私にとって、李箱文学研究において変わらない。李箱のテキストを韓国語もままならない私に間接的につたえてくれた神様みたいな本であり、全集の作り方やこだわりどころ、粘りどころ、そして何より李箱のテキストに出会わせてくれた本であることは、揺るがない。『定本李箱文学全集』に関しては、もう半分自信をなくすような凄みと、やり尽くされた感があるほど偉大である。でも触れ得ぬ神様でも謎のXでもない。大丈夫(と言い聞かすしかない)。
どちらの編者・註解者も、毎日急くような気持ちでこの書籍を編んでいったのだろう。一刻も早く、日本語に訳し、日本語圏にとどけなくては。一刻も早く完璧な全集をこの世にのこさなくては。そう想像するとやはりそれぞれの本に出会ったときのように、全く似た熱量の有り難さが込み上げてくる。先人がいてこそ、先人の功績とその僅かな綻びを後世の人がみとめてこそ、学問も文学も歴史も、またすすんでいく。批判は批判としてあるべきだが、感謝もまた感謝としてあるのだ。だが批判もする。それでいい。
二〇二三、八月、二二日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
