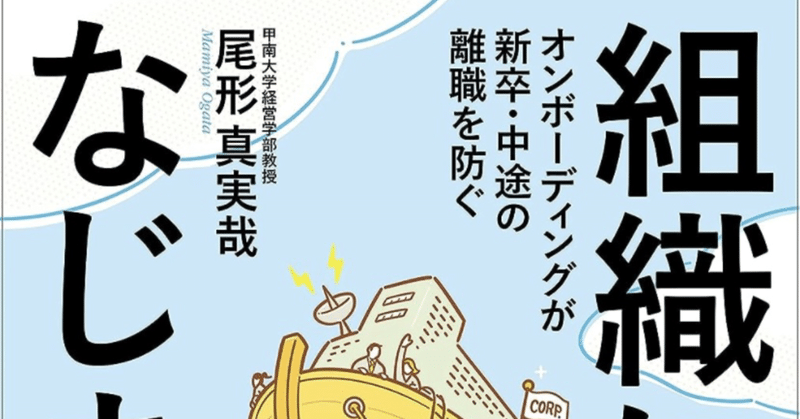
今週のリフレクション【組織になじませる力(尾形真実哉氏)】
今週は、尾形真実哉さん著「組織になじませる力」を振り返ります。ざっくり4点でまとめると・・
1.転職が当たり前の社会では、常に新しい人が職場に入ってくる。採用コストを下げ、新入社員の満足度や幸福感を上げるために、オンボーディング=新しく組織に参加した個人の円滑な適応をサポートする全てのこと、が必要。オンボーディングには、①有益な情報を与えるインフォーム行動(コミュニケーション/リソースの提供/研修)、②感情や人間関係にフォーカスした、迎え入れるウェルカム行動、③導くガイド行動(相談できるガイド役)がある。トップ/上司/職場/人事の協育体制をつくることが重要。
2.新卒社員は、リアリティ・ショック=高い期待と実際の職務での失望させるような経験との衝突、の軽減が重要。①既存型(楽観的な期待)、②肩透かし(ねるい現実)、③専門職型(予想以上)。自分で解決できるか、正当化が可能か、将来展望に結びつくか、が重要。①選考段階での正確で広範な情報提供(敢えて伝えない白い嘘もNG)、②内定後はトランジション・スロープ、③入社後は相談窓口/メンター/教育/再動機づけ/ショック療法が必要。同期との繋がり(短期的には相談相手/中長期にはライバル)はオフラインが効果的。
3.中途社員は、早急なパフォーマンス発揮と、時間を要する組織再適応のジレンマがある。①新しいスキル/知識習得、②暗黙のルールを観察理解、③固執せずアンラーニング、④中途意識による遠慮の排除、⑤既存社員との信頼関係(know who)が必要。まずは、アンラーニングと中途意識の排除から。中途採用者を即戦力と捉えず、新卒採用者よりは多少早めに成果を出す人材と捉える。教育で脱色→染色を行い、同質の中途ネットワーク、異質の人的ネットワークをつくる。配属後は、適応エージェント/コネクターを設定し、上司と人事の定期面談を行うと効果的。
4.本人が組織になじむためには、プロアクティブ行動が重要。①自己志向型行動=革新、積極的問題解決、学習。②他者志向型行動=ネットワーク構築/活用、フィードバック探索、援助要求。③仕事志向型行動=ジョブ・クラフティング(タスク次元/他者次元/認知次元)。職場特性(コミュニケーションの活発さ/革新への積極性/支援風土/学習への積極性)と職務特性(職務自律性/タスク重要性/他者フィードバック)が影響する。
新卒採用においては「リアリティ・ショックにつながりやすい情報の開示」、中途採用においては「成果を求めない育成期間の設定」が重要だと感じました。
新卒採用では、マーケティング観点から「メッセージを絞る」必要があり、結果として伝えない情報ができてしまい、リアリティ・ショックにつながる構造があると思います。だからこそ、入社後のリアリティ・ショックの内容を人事がしっかり把握し、選考段階で「わざわざ」伝える必要があるのだと思います。
中途採用では、即戦力として入社直後からの成果を期待すると、中途入社者は短期で成果を出すために成功体験にフォーカスします。そうすると、結果としてアンラーニングが進まない構造になります。だからこそ、入社直後から成果を求めないソフトランディングできる育成期間を充分な期間、設定する必要があるのだと思います。
どちらも、時間軸を中長期に定めてこそできる対応だと思います。短期的な採用成果を求められる圧力とどうバランスするかが、採用担当者の腕の見せどころなのかもしれないと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
