
今週のリフレクション【起業のすすめ(佐々木紀彦氏)】
今週は佐々木紀彦さん著「起業のすすめ」を振り返ります。ザックリ要点をまとめると・・
1.起業家になるべき5つの理由。①サラリーマン思考から卒業できる。不確実な状況下で成功する能力=圧倒的な当事者意識、他人を説得できるスキル。②キャリアアップにつながる。シードラウンドは競り市のマグロ状態。最後は自分で判断することが成長につながる。③金銭的な報酬が大きい。クリエイティビティ・インプット・チャレンジの自由。④人生の自由を得られる。自由も大きく、責任も大きい。⑤社会を変えられる。政治家もメディアも社会を変えられない。
2.起業に対する5つの誤解。①若くないといけない。起業の成功率が高いのは40代。ミドルエイジの強みは人脈・経験(実践知、交渉、マネジメント、組織構築)・利他心(欲望コントロール)。②お金持ちでないといけない。資金調達の手段は増え、投資家がスタートアップに投資する手段も増えている。③失敗すると借金地獄になる。資金調達はエクイティ。グッドルーザーになればプラスに評価。④エリートしかなれない。学業<ストリートスマート。エリートは採用すればいい。⑤チャラくて尊敬されない。起業家とはプロアスリート。
3.起業型キャリア5つのタイプ。①成長志向スタートアップ型。上場すれば短期的な利益を求められる。ブランド、信用は向上するが、スタートアップらしい文化は失われる。世界を目指すのか?いつ打って出るのか?。②プロフェッショナル独立型。一定期間、副業でやっていく手もある。③スモール&ミディアムビジネス型。事業継承×ローカル、ソーシャルアントレプレナーが旬。④スタートアップ幹部型。創業者はいるか、創業者は好きか嫌いか、ビジネスモデルは強靭か、センスがあるか、報酬制度がフェアか/SOはもらえるか。⑤大企業イントレプレナー型。大企業の社会的インパクトは大きい。社内新規事業、ジョイントベンチャー、スタートアップ買収、既存子会社のトップに抜擢。
4.起業を成功させる5つのステップ。①自己分析。WHY=ビジョナリー型には自己ガバナンス。HOW+WHAT=技術者・アナリスト型にはビジネスの相棒。WHO=デザイナー・営業型はWHY型と組む。ストレングスファインダー、リフレクション(価値観ソート)、FFS理論(保全/拡散/凝縮/受容/弁別)。保全は大企業イントレプレナー型やスタートアップ幹部型が向く。②ミッション・ビジョン・バリュー。創業時がぐちゃぐちゃだと後で直せない。思想・哲学・歴史の教養がモノを言う。ミッションの抽象度が高い時、ビジョンが必要。ビジョンは変わっていい。バリューはルールを作る時の基準。③事業づくり、プロダクトづくり。得意分野に集中する、徹底したリサーチ、ニッチ一本勝負。④パートナー探し・チームづくり。複数での企業がベター。優秀人材をリクルート担当。スタートアップの外からも、異文化・外資系の経験、ビジョン/スキル/カルチャーフィット、ワークライフバランス重視はNG、若さを過大評価しない。⑤資本政策・ファイナンス。自分で勉強。キーマンな60%以上の資本構成。最初の資金調達は外部を最低限に。価格だけでなく、相性の良いベンチャーキャピタルを厳選。ストックオプションをフル活用、創業時に丁寧に組み立てる。
起業することが自分の成長につながることは容易にイメージできます。自分が最終意思決定者になるので、自由も責任も大きくなり、圧倒的な当事者意識で動きます。そして、アテンションを配る先が上司ではなく社会や市場になるため、社会へのインパクトも大きくなります。そんな経験を積んだ結果、労働市場からの評価が高くなるのは必然だと思います。
では、なぜ起業しないのか?それは書籍にもある通り、体力不足/経験不足/お金不足を理由にしたり、失敗した時の経済的/キャリア的なリスクを心配したりするからだと思います。書籍では、全て誤解だと切り捨てていますが(笑)
起業と聞くと、社長になって→資金調達をして→事業を大きくして→IPOして・・とイメージしますが、それは5つあるうちの1つだと書かれています。スタートアップに幹部としてジョインしたり、大企業の中でイントレプレナーとして活動することも「起業」です。個人的には、起業をキャリアとして捉えた時、様々な形があるということが妙に腹落ちしました。
企業に雇われて与えられた役割期待に応えていくことを前提にするのではなく、「起業」という概念を広く捉えて、自分のキャリアのプロセスとして柔軟に組み込んでいく。これからはそんなキャリア観も必要なのかもしれないと感じました。
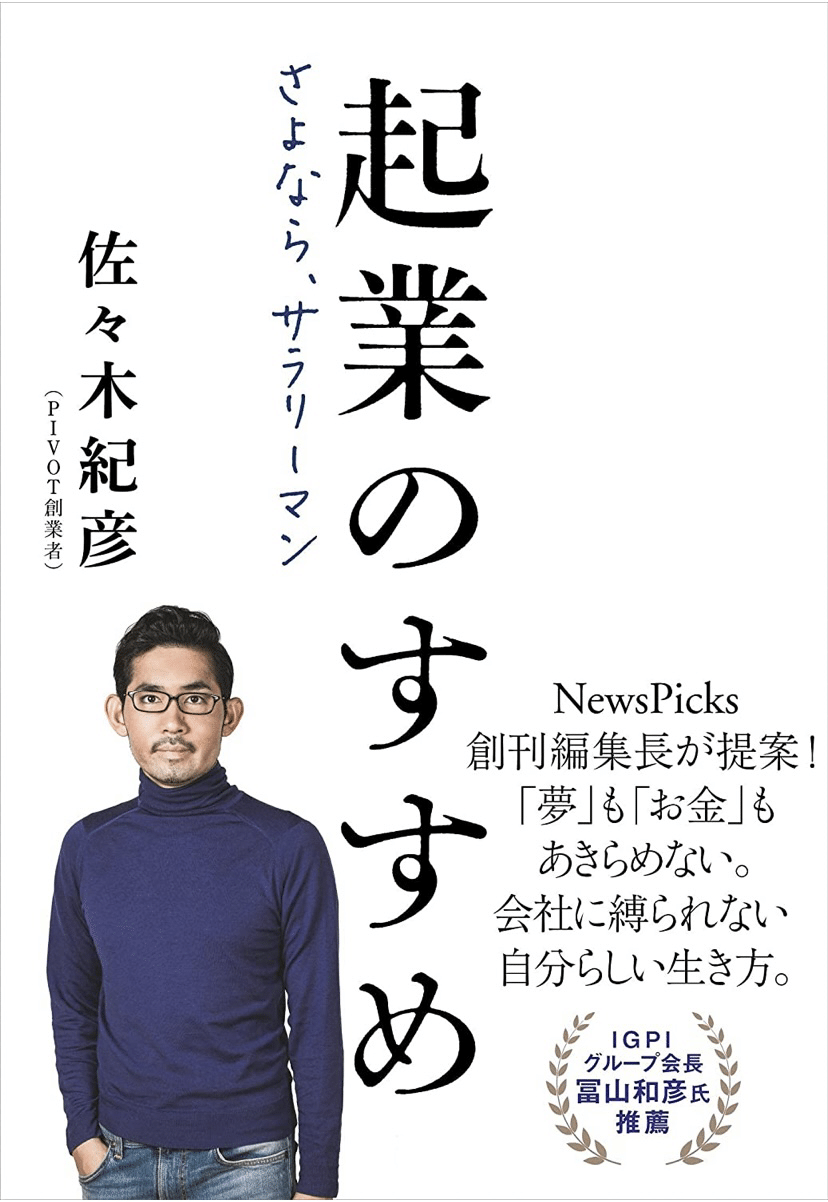
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
