
常に既にあるデモクラシー
1.システム・共同性・連帯
『後期資本主義における正統化の諸問題』においてユルゲン・ハーバーマスは、国家(政治システム)と市場(経済システム)の分離が建前である自由主義的資本主義から、市場の失敗を回避すべく国家が積極的に市場に関わることが期待される後期資本主義への変遷を主張する。国家と市場は一体となって複雑なシステムを形成し、それに大きな影響力を持つ権力者や資本家、あるいはその部下であるテクノクラートがシステムを運用する一方、市民は政治から疎外され、脱政治化されていく。

その後、福祉国家体制が批判され、新自由主義的な改革が各国で進んだが、デイヴィッド・グレーバーが『官僚制のユートピア』で指摘するように、このシステムの複雑性は「縮減」されるどころか、ますます増大している。
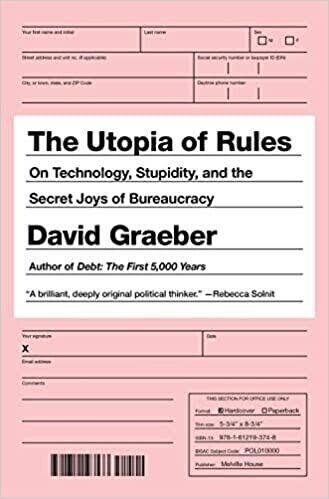
このようなシステムの肥大化に対し、市民の政治参加を取り戻そうとする(民主化する)理論の形成が試みられた。これらの理論は、いずれも市民の連帯をその基礎に据えている。何かしらの形で市民を共同的な政治行動-必ずしもデモに限定されない-に動員することで、システムを運用し政治を独占(無化)するテクノクラートの支配を揺るがし、意思決定過程に何かしらの形で参与しようとする。そして、その連帯をいかなる形で実現するかという点、すなわち、市民が連帯するための共同性の内容に差異が見られる。コミュニケーションを基礎に据えるハーバーマス、可傷性を基礎に据えるジュディス・バトラー、対立を基礎に据えるシャンタル・ムフなど、様々なパターンが存在する。
連帯の重要性を否定するつもりはない。一方で、連帯は人々にプラスアルファのコミットメントを要求する。何かしらの形で、政治的な行為に参与するよう要請する。つまり、連帯はあくまで運動的なものである。そして運動的なものは、制度の前で脆弱である。なぜなら、運動を続けていくことは、生活に割くべきリソースを侵食することでもあるからだ。リソースは有限である。どれほど強靭な意志に支えられたコミットメントであったとしても、運動はいつか終わる。一方システムは終わらない。もちろん連帯が何かしらの形でシステムに働きかけ、何かを変えることができることもあるだろう。だが、それはあくまでも幸運な場合のみである。
また、共同性が必ずしも連帯につながるとは限らない。共同性は新たな差異の入り口にもなりうる。むしろある面において共同性があるからこそ、差異がより際立って見えてしまい、内部分裂に至る可能性もある。何かしらの共同性を見出せれば、それが即連帯に繋がるというわけではない。
では、結局我々はシステムの前に屈するしかないのか。我々は非民主的なシステム全体の忠実な部分として組み込まれていくしかないのか。そんなことはない。我々には共同性はないかもしれない。しかし我々は常に既に民主的であり、共同性なき共同体-それはまだ生まれていないが、しかし現在に関わってしまっている-に開かれている。
2.感性・政治・胚胎
ジャック・ランシエールは『プロレタリアの夜』において、1830年の革命時期における労働者の新聞、手紙、日記、詩などに焦点を当てつつ、それまでただの労働力と見做されていた当時の労働者が、夜に行う芸術的・創造的な活動を通じて自己を解放していたことを明らかにする。そしてランシエールは、それ自体がまさに政治的な営みであるとする。なぜなら、「芸術的な活動を通じて自己を解放する労働者」という労働者像は、我々の感性の体制を揺るがすものだからである。
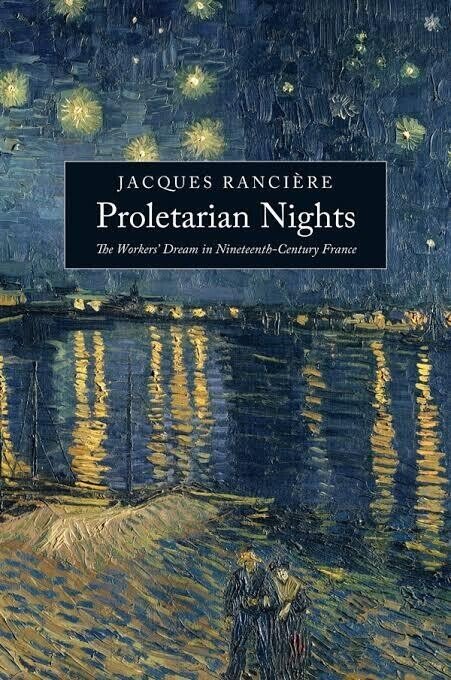
統治が成立するためには、民衆と統治者がそれぞれの声を聞き、理解することができなければならない。ランシエールはこれを政治の感性的基盤と呼ぶ。すなわち、それぞれの人間に政治的な資格があるかどうかは、感性的なものによって決まっている。バルバロイとみなされたものは、どれだけ必死に叫んでも、その声は聞くに値しない「叫び声」としてあらかじめ除外されてしまう。どの声を声と感じるか、その感性的な体制によって、誰が政治に参加するかが決定してしまっている。
ランシエールは『不和あるいは了解なき了解』において、この感性的体制、すなわち「当事者を決め分け前があるかないかを決める感性的なものの布置」を「ポリス」と呼び、それに対比する形で、「定義上その布置のなかに場所をもたぬ前提、つまり分け前なき者の分け前という前提によって切断する活動」として「政治」を定義する。
政治をこのように定義した時、先程の労働者はまさに、資本家の下で労働するという「ポリス」秩序から逸脱し、彼らもまた一人の人間であるということを夜の活動を通じて表現している。バルバロイをデモスへと変容させるという点において、このような営みはまさに「政治」であると言える。
ここでの労働者の活動は、必ずしも資本家の打倒などの直接的な行動を意図したものではない。夜に詩を書く労働者は、朝になれば工場に出かけ、定時まで働く。しかし夜の営みは、その労働者に様々な効果をもたらす。文学の世界は、工場組織の部分であることから自己を逸脱させ、システムの範疇に収まりきらない領域を生み出す。それだけでなく、そのような属性を保持しつつ労働者でいることは、まだ世界には到来していない共同体の実現可能性を胚胎する。いつか何かにつながるかもしれない。全体に回収されない部分としてのあり方を保持することは、たとえそれが何かしらの行動に結びついていなくても、未来の共同体につながりうる、共同性なき共同体としてあることを意味する。故にそれ自体が政治的であり、民主的である。
3.未来・固有性・オルタナティヴ
この労働者のあり方を再評価することにどのような意義があるのか。なぜ共同性なき共同体であるために、部分に回収されない何かを保持し続ける必要があるのか。端的に言えば、「未来」を簒奪しようとする権力に抵抗するためである。
ジョン・アーリは『<未来像>の未来』で、複雑性を増しますます未来が予測不可能になっていく世界において、権力(システム)にとって都合の良い未来を設定し、あたかもそれが自明の未来であるかのように謳って、世界をその方向に誘導しようとする「未来を作る権力」が到来していることを指摘する。権力にとって都合のいい未来とは、本来は誰か(多くの場合一部の人々)に負担を押し付けるものであるにもかかわらず、政治的的な対立が無化され、万人にとって良き未来のように見える未来である。
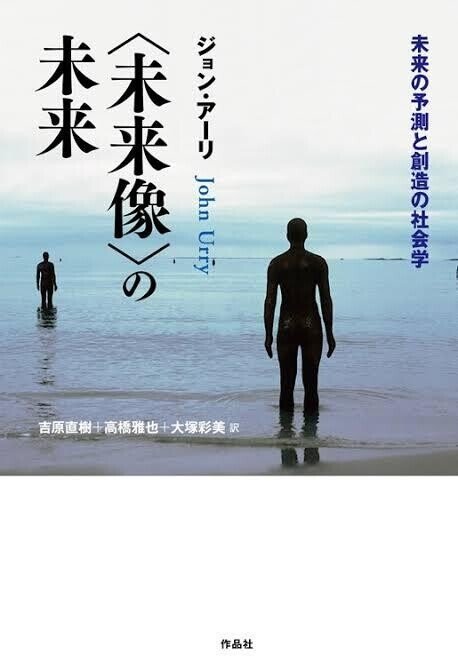
権力が提示する未来に対してオルタナティヴを提示するのは容易ではない。権力が持つ未来を誘導する力は強力である。しかし、権力も万能ではない。未来をいくら誘導しようとしても、予想通りにいかない面が必ず発生する。むしろ、だからこそ権力は未来の独占に躍起になっているとも言えよう。
では未来のオルタナティヴはどのように発生するのか。ここで重要なのが、先ほど言及した、全体に回収されない部分としてのあり方を保持することである。ある人が全体の一部分として(しか)存在し得ない時、その人は権力(システム)にとって予測可能・動員可能な存在でしかない。しかし、部分に回収されない何かしらを保持していること、そしてそれによって何かしらの共同体への可能性を胚胎していることは、権力の予測可能性を裏切り、別様の未来へと世界を導く土壌となる。複雑な現代社会において感性的な体制もまた日々変化しているが、日々の小さな変化を新たな体制への変化まで大きくしていけるかどうかは、部分ではないその人自身の固有性の保持にかかっている。
固有性の保持は何も大袈裟なことではない。誰しもが生きている中で、部分に回収されない何かを保持している。その固有性は、システムにとっては予測可能性を減少させるものであるため、システムは人々を単一の部分に回収しようとしてくる。しかしそれに抗い、固有性を保持し続けなければならない。夜の時間を労働力の再生産のための睡眠ではなく詩に充てた労働者のように、全体一色に染まるのではなく、部分に回収されない何かを常に保持し続けること。それ自体が民主的であり、社会はそのようなあり方をそれ自体として肯定しなければならない。
逆に言えば、人々が自らの固有性ととともに、部分として雌伏しつつ生きることは、それだけで民主的と言える。連帯や動員は必ずしも必要ではない。何かしら政治的なものに参与する必要はない。もちろんそれにつながれば素晴らしいが、固有性の擁護はそのための手段ではない。各人が様々な固有性を保持し続けることは、共同性なき共同体を到来させることであり、それは権力が想像していない未来を受け入れる土壌を生み出すことにつながっていく。
確かに我々は歯車かもしれない。しかし歯車であることに我々は回収されない。歯車として見える我々の背後に、固有の豊かな世界が広がっている。個々の歯車においてそれが実現されているとき、世界は権力の想像のつかない姿に変容する準備が完了する。デモクラシーとは、声を持たなかった新たな存在がデモスとして現れることであると同時に、その存在がまさに現れようとするときに、それに応じて変容できる準備を人々が保持していることを意味する。デモクラシーは、生活と別に政治参与のリソースを切り出すことを必要条件とするものではない。生活の実践を通じて、権力の作る都合のいい未来ではない未来、感性の体制への変容を準備することである。デモクラシーは常に既に、我々の生活の中にある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
