
マシュー・サイド著「失敗の科学」を読み解く - ②失敗は調査されなければ失敗と認識されない
ここから先は
2,316字
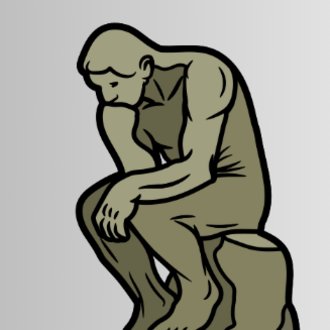
マシュー・サイドはイギリス『タイムズ』紙の第1級コラムニストでライター。オックスフォード大学哲学政治経済学部(PPE)を首席で卒業後、卓球選手としても活躍した。ライターとしての仕事だけでなく、BBCやCNNでリポーターやコメンテーターなども務める人物です。本書では、彼が医療・航空・スポーツなど様々な分野における失敗の事例を取り上げ、失敗からどのような教訓を得ることができるのかを分析しています。
ボクが毎週木曜日に書いていた「マシュー・サイドの失敗の科学を読み解く」シリーズの全10週分をマガジンに収めました。ご興味おありの方はぜひご…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
